医療機関の領収書はインボイス制度への対応が必要?様式や注意点も解説
更新日:2025.12.24
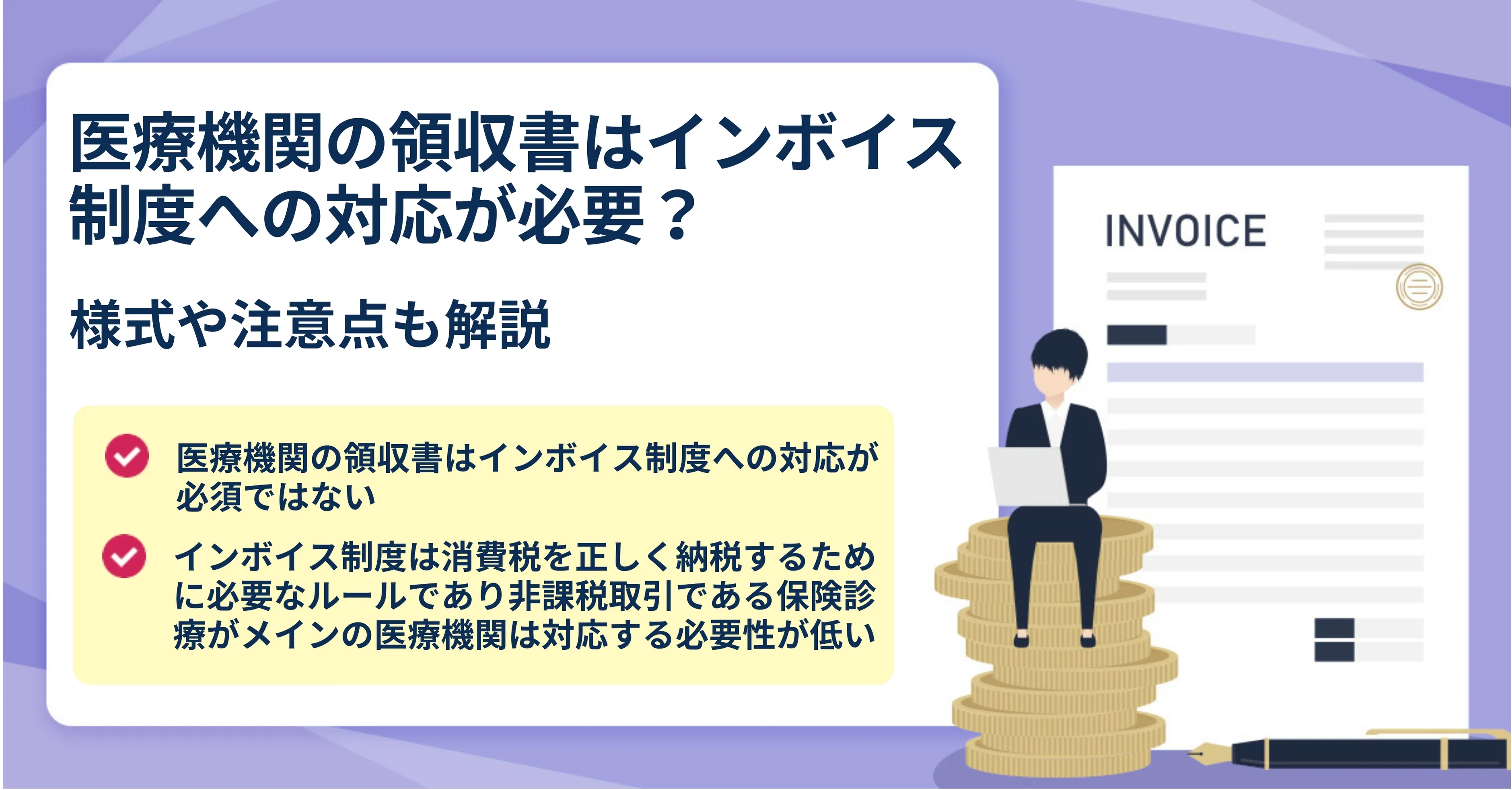
ー 目次 ー
2023年に施行された「インボイス制度」とは、事業者が消費税を正しく納めることを目的として定められた制度です。インボイス制度は消費税に関するルールであり、基本的には事業者との取引を対象としています。
医療機関では基本的な個人が利用する一方で、一部のケースで事業者も利用する機会があります。このようなケースでインボイス制度の影響を受けるため、基本的なルールを把握して慎重に判断しなければなりません。
とくに、医療機関が発行する領収書は、要件を満たせばインボイス(適格請求書)として扱えます。そのため、基本的な記載事項や扱い方のルールを把握しておくことが大切です。
本記事では、医療機関の領収書がインボイス制度に対応する必要があるのかを解説します。
【結論】医療機関の領収書はインボイス制度への対応が必要ではない
医療機関の領収書は、インボイス制度への対応が必須ではありません。
インボイス制度は事業者が消費税を正しく納税するために施行された制度であり、非課税取引である保険診療がメインの医療機関は対応する必要性が低くなります。なお、医療機関における取引のなかで、非課税取引にあてはまるケースは以下の内容です。
- 個人の患者への保険診療
- 個人の患者への自費診療
- 個人の患者へ渡す文書料
ただ、領収書の発行先が事業者の場合は、インボイス(適格請求書)の対応が必要です。
インボイス制度では適格請求書発行事業者同士であれば、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引ける仕入税額控除の利用が可能です。このことから、患者が自費診療や文書料で仕入税額控除を利用する際は、インボイス(適格請求書)が求められる可能性があります。
医療機関の領収書でインボイス制度への対応が必要な場面とは?
医療機関の領収書でインボイス制度への対応が必要な場面は、企業への健康診断・予防接種の実施や自由診療に使用する針・薬剤の購入が考えられます。適格請求書発行事業者への申請を悩んでいる際は、自社に当てはまる取引があるかを確認しましょう。
ここでは、医療機関の領収書でインボイス制度への対応が必要な場面を解説します。
①企業への健康診断・予防接種
企業への健康診断・予防接種は取引先が雇用している従業員のためにおこなうものであり、企業が一括で健康診断や予防接種の料金を支払います。取引先が仕入税額控除を利用したいと考える場合、インボイス(適格請求書)の発行が必要です。
仮に、自社が免税事業者の場合、取引先は仕入税額控除を利用できません。そのため、インボイスが発行可能な医療機関に契約を変更するおそれがあります。
②自由診療に使用する針や薬剤の購入
インボイス制度で仕入税額控除の適用をしてもらうためには、適格請求書発行事業者同士の取引でなければなりません。
医療機関の場合、とくに自由診療は課税取引となるため、使用する針や薬剤を購入する料金を仕入税額控除の対象にできます。このようなことから、医療機関が針や薬剤の購入時に仕入税額控除を利用する場合、適格請求書発行事業者に登録しておかなければ、ほかの医療機関に取引を変えられるおそれがあります。
【見本】医療機関の領収書をインボイス制度に対応させる際の書き方
医療機関でインボイス(適格請求書)を発行する際は、保険診療の領収書とは異なる記載項目を記載しなければなりません。記載事項を満たしていないと、取引先が仕入税額控除を受けられないような問題が生じてしまいます。
このようなトラブルを避けるためにも、事前に消費税の記載方法や必要な項目を確認しておき、自社にあわせたインボイスのテンプレートを用意しておきましょう。
ここからは、インボイス制度に対応した医療機関の領収書の書き方や見本を解説します。
- 医療機関の名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書を受け取る事業者の氏名や名称
|
領収書 取引先企業名 自社の企業名 合計 ¥11,000-(税込)
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||
①医療機関の名称
インボイス(適格請求書)を発行する際は、税務署に申請した自社の正式名称を記載しましょう。医療法人として登録している場合は、クリニック名ではなく法人名を記載します。
②登録番号
適格請求書発行事業者として登録すると、事業者ごとに異なる登録番号が発行されます。登録番号は「T」から始まる13桁の数字から構成されており、医療法人の場合は「T」以降が法人番号になっています。
③取引年月日
インボイス(適格請求書)には、取引をおこなった日を記載します。健康診断・予防接種の日程が複数あるときは、実際に従業員へ実施した日ごとに日付を分けましょう。
④取引内容
取引内容は「健康診断料」「予防接種料」など、取引先に提供したサービスや商品の内容を記載しましょう。自由診療の際は、実際におこなった施術内容を記載します。
⑤取引金額
インボイス(適格請求書)には、商品やサービスの対価として受け取る金額を取引金額として記載します。記載時は商品・サービスの金額以外にも、税率や税率ごとに合計した合計金額、消費税額も記載しましょう。
⑥請求書を受け取る事業者の氏名や名称
インボイス(適格請求書)には、書類を受け取る事業者名の正式名称も記載しましょう。発行前に取引先へ正式名称を確認しておくことで、内容を誤る心配を減らせます。
医療機関の領収書をインボイス制度に対応させる際の注意点
医療機関でインボイス(適格請求書)を発行する際は、事前の申請や納税義務の発生などの注意点があります。ほかにも経理業務が煩雑になるおそれがあるため、事前にデメリットを理解したうえで、インボイス制度の登録を検討しましょう。
ここでは、医療機関の領収書をインボイス制度に対応させる際の注意点を解説します。
①インボイス(適格請求書)の発行には事前の申請が必要
医療機関がインボイス制度に対応した領収書を発行するためには、事前に税務署・登録センターへ適格請求書発行事業者として申請する必要があります。申請後もすぐにインボイス(適格請求書)が発行できるわけではなく、登録番号が付与されるまでは対応できません。
登録番号が手元に届くのは申請方法によって、約1か月〜1か月半かかるため注意が必要です。
②適格請求書発行事業者に登録する場合は納税義務が生じる
適格請求書発行事業者に登録することで、消費税の申告・納付義務が生じます。とくに、インボイス制度の登録以前が免税事業者であった場合には、消費税の申告・納付が必要なかったため注意が必要です。
医療機関においても同様で、インボイス制度の登録以前が免税事業者であった場合でインボイス制度へ登録した場合には売上に大きな差が生じたり、事務負担が大幅に増えたりする可能性があります。
③経理作業の煩雑化が考えられる
医療機関は保険診療と自費診療があるため、適格請求書発行事業者になった場合にも、消費税の納付が不要な取引を判断しなければなりません。
とくに、消費税の申告の際には、課税取引・非課税取引の書類や対応を分けなければならず、経理業務が煩雑になるでしょう。また、インボイス(適格請求書)の発行にともないテンプレートの作成や業務フローの見直しをおこなうため、経理担当者の負担が増加します。
まとめ|インボイス制度のルールを理解し、必要に応じて対応しよう!
本記事では、医療機関の領収書がインボイス制度に対応する必要があるのかを解説しました。
医療機関は課税取引・非課税取引のどちらの取引もおこなわれるため、インボイス(適格請求書)が必要な場面を理解しておかなければなりません。とくに、インボイス制度に対応する場合には書類のフォーマット変更や保存できる環境の整備などの事務負担も増えるため、登録すべきかの判断を慎重に検討しなければなりません。
インボイス制度に対応するか悩んだ際は本記事を参考に、適格請求書発行事業者への申請を検討してください。










