インボイス制度は請求書と納品書を組み合わせてもOK!記載項目やパターンも解説
更新日:2026.01.13
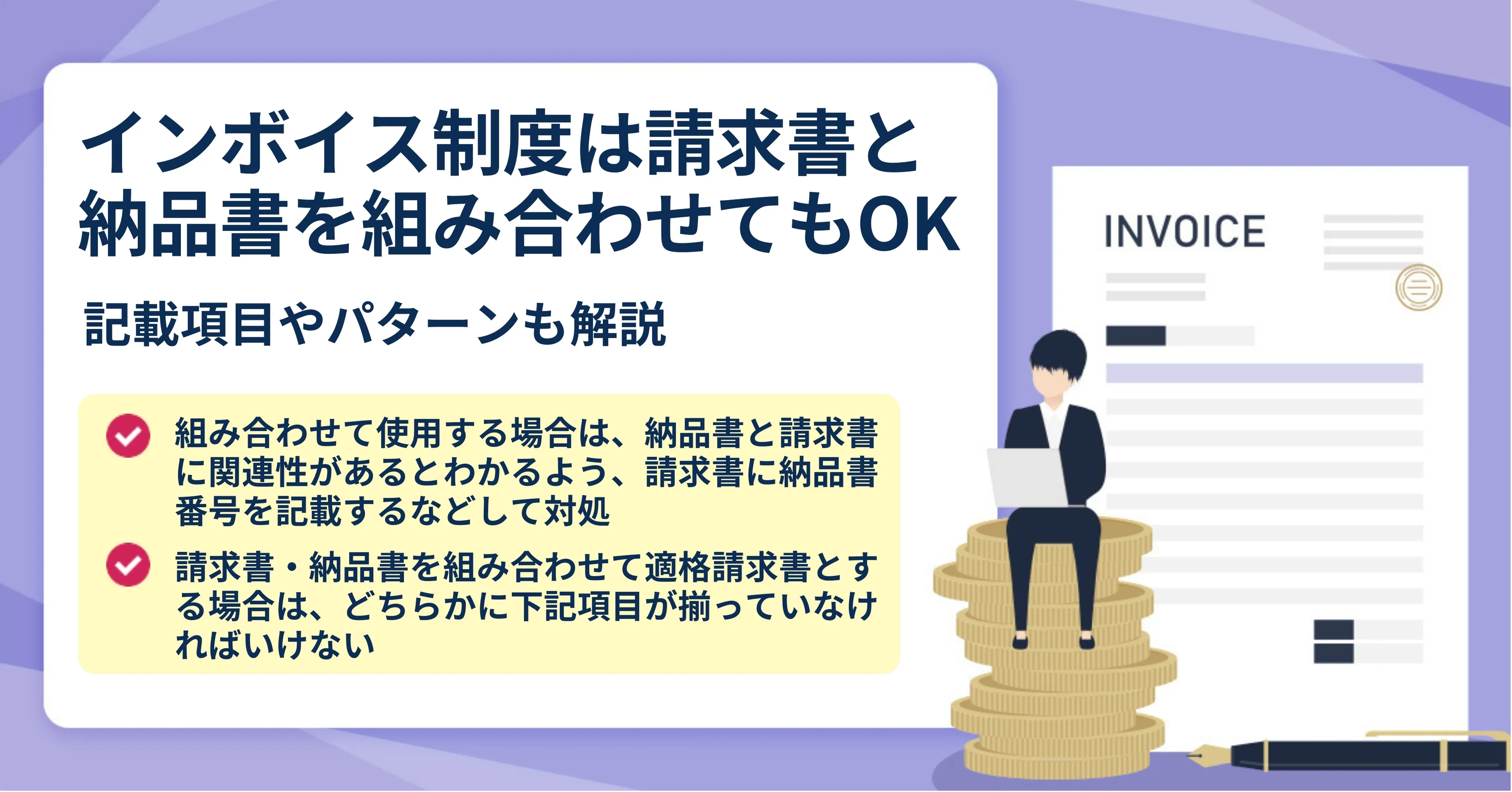
ー 目次 ー
インボイス制度の施行にともない、2024年10月より適格請求書の使用が開始されました。
適格請求書は請求書単体で要件が揃えられない場合に、納品書や領収書を併用して発行することが可能です。ただし、納品書や請求書を併用する場合は注意点もあるため、作成前に理解しておきましょう。
本記事では、請求書・納品書を組み合わせて適格請求書(インボイス)を発行する方法と注意点を解説します。
【結論】請求書や納品書を組み合わせてインボイスの交付が可能
インボイス制度では、請求書と納品書を併用して1つの適格請求書として扱うことが可能です。併用する場合は記載する項目を書類ごとにわけ、通し番号を記載しておくことで関連性がわかりやすくなります。
さらに、請求書・納品書を併用する場合は、取引先に請求書・納品書をあわせて保管するよう伝えましょう。片方しか保管されていない場合は、インボイス制度の条件を満たさなくなるため、取引先が消費税の控除を受けられなくなります。
インボイスを交付するための適格請求書の記載項目
請求書・納品書を併用してインボイスを交付する場合は、記載項目が揃っていなければ取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。作成時は記載項目を理解して、請求書・納品書それぞれに何を記載するか決めましょう。
ここでは、インボイスを交付するための適格請求書の記載項目を解説します。
- 書類の作成者の氏名や名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 支払期日
- 取引内容
- 取引金額
- 書類を受け取る事業者の氏名や名称
①書類の作成者の氏名や名称
請求書・納品書ともに、作成者には税務署に申請した正式名称を記載しましょう。企業であれば法人名や担当者名、個人事業主であれば本名が一般的です。個人事業主が屋号を決めている場合は、あわせて記載しても問題ありません。
個人事業主の場合は、インターネットの取引でもハンドルネームやペンネームではインボイスの交付はできません。
②登録番号
インボイス制度の申請をした場合、事業者ごとの登録番号が発行されます。適格請求書には、自社の登録番号を作成者の近くに記載しておきましょう。
登録番号はTから記載しておくことで、取引先が登録番号と判断しやすくなります。
③取引年月日
取引年月日には、商品やサービスを提供した日を記載することが一般的です。ただし、商品を郵送した場合は取引先の手元に届いた日が明確にならない可能性もあるため、出荷日を記載しましょう。
なお、1か月間に複数の取引がある企業は、まとめて請求する場合は取引ごとの日付を記載します。
④支払期日
納品書を併用する場合は、請求書に支払期日を記載しましょう。支払期日は事前に取引先と相談しておくことで、請求遅れをはじめとしたトラブルが避けられます。
その際は、合計金額の付近に振込先を明記しておき、取引先が探す際に悩まないように配慮することがおすすめです。
⑤取引内容
取引内容は、取引先に提供したサービスや商品の正式名称を記載しましょう。正式名称で記載しておくことで、取引先が内容の誤りを確認しやすくなります。
軽減税率対象の品目があれば「※」といった記号を記載しておき、備考欄に「※は軽減税率の対象品目」と明記しておけばわかりやすくなります。
⑥取引金額
取引金額は、商品やサービスの対価として取引先から受け取る金額を記載しましょう。
取引金額には、商品の単価や合計金額以外にも商品ごとの適用税率や、税率ごとに合計した取引金額と消費税額も記載が必要です。
⑦書類を受け取る事業者の氏名や名称
適格請求書を受け取る側の事業者名も、正式名称で記載しましょう。
記載する前に、正式名称を取引先に確認することで、誤った内容で発行する可能性を抑えられます。
【パターン別】インボイス制度での納品書・請求書の組み合わせ例
インボイスを交付する際は、1つの書類で要件を満たす場合と、記載項目をわけて発行する方法があります。納品書や請求書を組み合わせるパターンを理解して、自社にあった方法を選びましょう。
ここでは、インボイス制度での納品書・請求書の組み合わせ例を解説します。
①納品書と請求書を組み合わせて適格請求書とする場合
納品書・請求書を組み合わせて使用する場合は、必要な項目をそれぞれにわけて作成しましょう。なお、記載項目を分けて発行する場合は、関係性がわかるように、備考欄に通し番号を記載することがおすすめです。
さらに、取引先に送付する際は、どのような方法でインボイスを交付しているかを伝えておくことで、相手が混乱してしまう心配を減らせます。
②納品書のみを適格請求書とする場合
納品書のみを使用する場合は、取引先が受け取った際に適格請求書と理解できるよう、送付時に伝えておくと安心です。さらに、納品日を記載しておくことで、いつ納品された商品・サービスの書類なのか判断しやすくなります。
納品書を適格請求書にする場合の注意点は、下記の記事で解説しているため、参考にしてください。
関連リンク:インボイスの交付は納品書のみで可能!適用条件や注意点を解説
③請求書のみを適格請求書とする場合
請求書のみを使用する際は、項目とあわせて支払期日や支払方法を記載しましょう。請求書でインボイスを交付する事業者は多いため、フォーマット変更に負担がなければ、この方法を選ぶと取引先が混乱する可能性を抑えられます。
④請求書・納品書を両方とも適格請求書にする場合
記載項目が揃っていれば、請求書・納品書をどちらも適格請求書にすることが可能です。
本来はひとつの取引に対して、複数の適格請求書を発行する必要はありません。ただ、請求書以外でインボイスを交付することで、取引先が管理しやすいものを選ぶことが可能です。
一方で、自社のフォーマットを変更する手間が増えるため、経理担当者の負担になる可能性があります。
納品書と請求書を組み合わせても端数処理は一回まで
インボイス制度では、1つの適格請求書に対して端数処理が税率ごとに1回までと決まっています。併用して発行する場合は、納品書・請求書の片方のみで端数処理をおこないましょう。
両方とも端数処理をおこなう場合は、納品書・請求書の記載項目を揃える必要があります。
請求書・納品書を適格請求書にする場合のテンプレート
適格請求書を作成するために、記載項目を満たした請求書・納品書のテンプレートを作成しておくと、請求業務がスムーズになるでしょう。テンプレートを用意していないと、請求業務のたびに1から作成する必要があり、手間が増えてしまいます。
ここからは、請求書・納品書を適格請求書にする場合のテンプレートを紹介します。
①請求書のテンプレート
請求書を作成する際は、下記を参考に自社のフォーマットを作成しましょう。
|
請求書 〇年〇月〇日 取引先企業名 取引先担当者名 自社の企業名 自社の郵便番号・住所 自社の電話番号 自社の担当者名 自社の登録番号 ご請求金額 ¥〇,〇〇〇-(税込) 支払期日 〇年〇月〇日 振込先 〇〇銀行〇〇支店 普通〇〇〇〇〇〇 振込先名称
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②納品書のテンプレート
納品書を作成する際は、下記を参考に自社のフォーマットを作成しましょう。
|
納品書 〇年〇月〇日 納品書番号:〇〇〇〇 取引先企業名 取引先担当者名 自社の企業名 自社の郵便番号・住所 自社の電話番号 自社の担当者名 自社の登録番号 合計金額 ¥〇,〇〇〇-(税込) 納品日 〇年〇月〇日
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本来であれば、納品書に日付を記載する義務はありません。しかし、納品書を適格請求書にする場合は取引した日が必要になるため、記載しておきましょう。
納品書と請求書を組み合わせてインボイスを交付する際によくある質問
ここからは、納品書と請求書を組み合わせてインボイスを交付する際によくある質問について、解説します。
①インボイスを交付するのは納品書・請求書どちらかだけで問題ない?
インボイスを交付するのは、納品書・請求書の片方だけで問題ありません。
ただし、請求書のみを使用する企業が多いため、自社が納品書・領収書などで対応する場合は取引先に伝えておくことで混乱を防げます。
②インボイスを交付する際は納品書と請求書の両方に登録番号が必要か?
インボイスを交付する際は、適格請求書にする書類にのみ登録番号が記載されていれば問題ありません。
納品書と請求書を併用する場合でも、片方に登録番号が載っていれば適格請求書の要件を満たせます。
まとめ|インボイスの交付時に納品書と請求書を組み合わせる場合は取引先に伝えよう
本記事では、請求書・納品書を組み合わせて適格請求書(インボイス)を発行する方法と注意点を解説しました。
インボイス制度では、ひとつの書類で適格請求書の記載項目を満たすことが難しい場合は、請求書・納品書を併用しての発行が可能です。ただし、本来は片方でも交付が可能なため、請求書単体以外で対応する場合は取引先に伝えておくと安心です。
請求書や納品書を組み合わせてインボイスを交付する際は、本記事を参考に書類を作成しましょう。










