インボイス制度が法人に与える影響は?登録方法や作業効率化のポイントも解説
更新日:2025.03.27
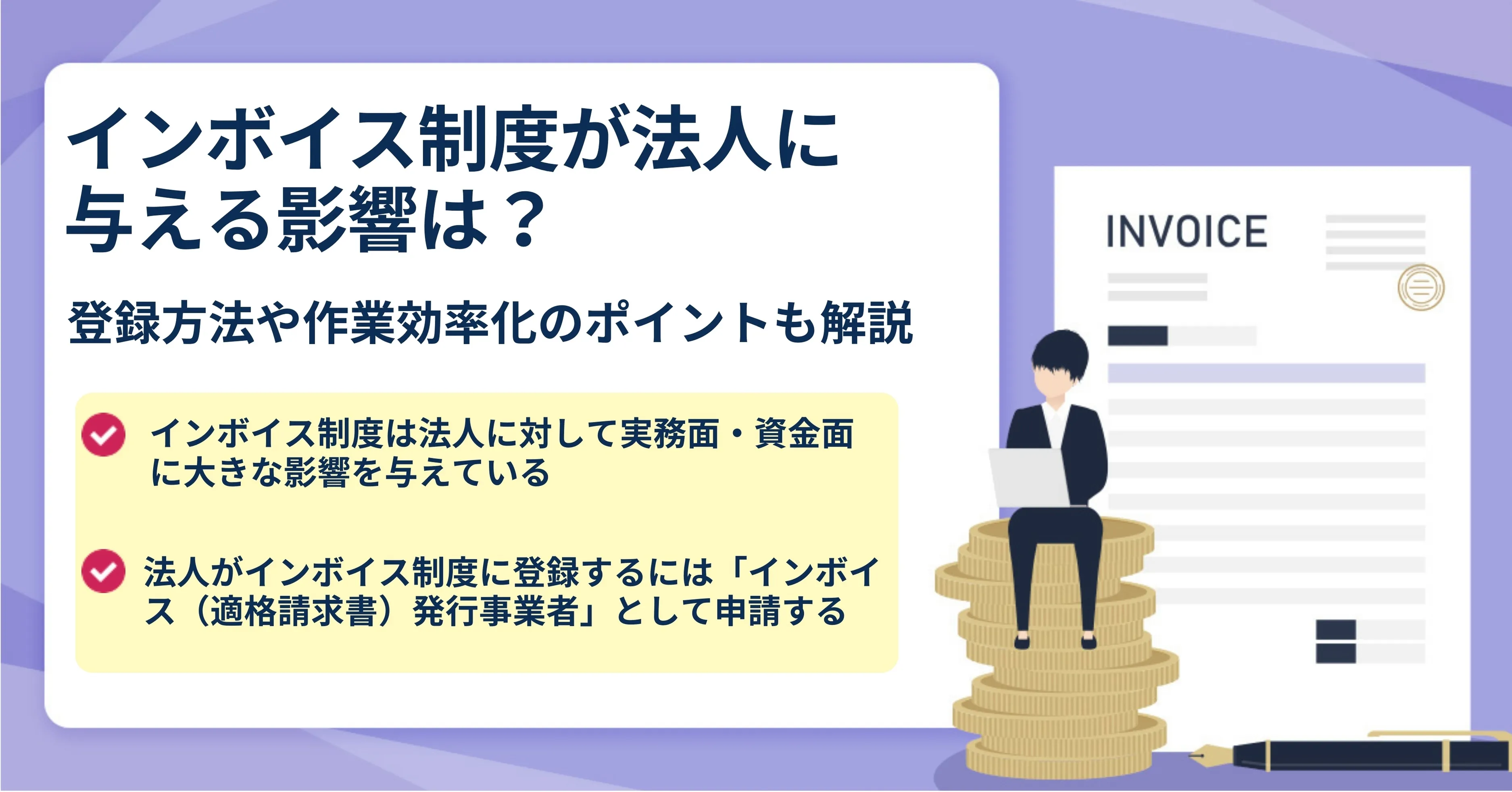
ー 目次 ー
インボイス制度の導入は、法人の経営や業務に大きな影響を与えています。2023年10月から開始されたこの制度で、インボイス(適格請求書)の発行・管理の新たな業務が加わり、経理処理の負担増加や取引先との関係見直しなど、さまざまな変化が生じています。
とくに、企業間の取引で消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス発行事業者から発行された適格請求書の保存が必須です。したがって、これまでの事務処理フローを見直さなければならない企業も少なくありません。
しかし、この制度への対応は単なる負担ではなく、経理業務の効率化や取引の透明性向上といった前向きな変化をもたらす機会にもなりえます。
本記事では、インボイス制度が法人に与える影響や登録方法、作業効率化のポイントについて解説します。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する新しい制度
インボイス制度は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率に対応して、消費税の透明性を高めることを目的とした制度です。この制度では、インボイス(適格請求書)を保存した事業者に対して、仕入れに支払った消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引ける「仕入税額控除」の適用を認めています。
インボイスの発行は「インボイス(適格請求書)発行事業者」に登録した事業者のみが可能であり、免税事業者は発行できません。インボイスには、従来の請求書にくわえて以下の記載が必要です。
- 登録番号
- 税率ごとに区分した消費税額
- 適用税率
なお、免税事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外です。ただし、インボイス制度への移行にともなう影響を緩和するため、免税事業者からの仕入れも一定割合の仕入税額控除を認める経過措置や、免税事業者が課税事業者になる際の特例などが設けられています。
インボイス制度が法人に与える3つの影響とは?
インボイス制度は法人に対して実務面・資金面に大きな影響を与えています。適切な対応策を講じることで、影響を最小限に抑えることが可能です。
法人は個人事業主とは異なり、簡易課税制度の適用判断や法人住民税への影響なども考慮する必要があります。インボイス制度の影響は法人の規模や取引先の状況ごとに異なるため、個々の企業に応じた対応が重要です。
ここでは、インボイス制度が法人に与える3つの影響について、それぞれ解説します。
①法人税申告と消費税申告の整合性がより厳しく問われる
インボイス制度の導入にともなって、税務調査としておこなわれる確認作業が増加するおそれがあります。これまでよりも法人税と消費税の申告内容との整合性を厳しく問われるおそれがあり、正確な申告対応が求められるようになります。
なお、この点に関しての考えられる対応策は、以下のとおりです。
- インボイスと帳簿を連動させる会計システムの導入
- 税率区分ごとの取引管理を徹底するためのコード体系の整備
- 月次での消費税集計・確認作業の導入 など
これらの対応により、作業時間の短縮や税理士費用の削減などの効果が期待できます。
②経理部門の体制強化が必要になる
インボイス制度の導入で、新たにインボイスの確認作業が加わり、1つの請求書の処理にかかる時間が増加しました。取引先の登録番号確認や保存書類の管理などの新たな業務も発生しており、経理担当者の業務負担が増大しています。
このような問題に対しては、請求書管理システムやOCRツールの導入による自動化や、経理担当者の専門研修・教育プログラムの実施などの手段が有効です。
③取引先との関係を見直す必要がある
インボイス制度の導入で、新規の取引先を選定する際に「インボイス(適格請求書)発行事業者であるか」の確認プロセスが加わりました。また、既存の免税事業者である取引先との取引条件の見直しが必要になり、場合によっては取引先との再交渉が発生する可能性もあります。
これらの課題には、以下のように対応することで、無効な登録番号による仕入税額控除漏れのリスクを排除できます。
- 取引先マスターへの「インボイス発行事業者」情報の追加
- 定期的な取引先登録番号の有効性確認の仕組み構築
- 取引約款へのインボイス関連条項の追加 など
法人がインボイス制度に登録する2つの方法
法人がインボイス制度に登録するには「インボイス(適格請求書)発行事業者」への登録申請が必要です。インボイス発行事業者への登録後はインボイスの発行義務が生じるため、請求書様式の変更などの準備が求められます。また、登録完了までには時間を要するため、余裕をもった申請手続きがおすすめです。
ここでは、法人がインボイス制度に登録する2つの方法について、それぞれ解説します。
関連記事:インボイス制度の登録方法とは?申請のやり方や注意点を解説
①電子申請(e-Tax)での登録手順
電子申請(e-Tax)での登録手順は以下のとおりです。
- e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)にアクセスする
- 「申請・届出手続」から「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を選択し、必要事項を入力する
- 申請データを送信する
- 登録が完了すると登録番号(T+法人番号の13桁)が通知される
e-Taxの利用には、法人用マイナンバーカードなどの法人の電子証明書を用意する必要があるため、利用者識別番号が未取得の場合は事前に取得しておかなければなりません。
②書面での登録手順
書面での登録手順は以下のとおりです。
- 国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードする
- 申請書に法人情報や代表者情報などを記入する
- 管轄の税務署・インボイス登録センターに郵送する
- 通常1.5か月程度で「登録通知書」が法人所在地に郵送される
なお、登録番号が記載された通知書は再発行が困難なため、大切に保管する必要があります。
インボイス対応のツールやサービスを導入すれば作業が効率化できる
インボイス制度への対応は、適切なツールやサービスの導入で作業の効率化を図れます。それぞれのツールやサービスは導入コストや機能に差があるため、自社の取引量や業務フローに合わせて選定するとよいでしょう。
おもなインボイス(適格請求書)対応ツールやサービスの概要とメリットは、以下のとおりです。
|
ツール・サービス |
概要 |
メリット |
|
電子インボイス発行・管理システム |
インボイス制度に完全対応したインボイスの作成や発行、管理に特化したシステム |
インボイスの記載要件を完全に満たした書類を自動生成できる |
|
インボイス対応会計システム |
請求書発行から会計処理、消費税申告までをトータルで管理できるシステム |
インボイスと帳簿の連動による整合性を確保できる |
|
インボイス保存・管理サービス |
取引先から受領したインボイスを電子保存して、法定保存期間(7年間)管理するためのクラウドサービス |
紙の請求書のスキャンからデータ化までを自動化できる |
インボイス制度対応のツールやサービスを導入する際は、インボイスの記載要件を正確に満たしているかや、電子帳簿保存法の要件も満たしているかだけではなく、既存の業務フローへの組み込みやすさの確認も重要です。
システムの導入による業務効率化は、長期的なコスト削減につながる可能性があります。
まとめ|インボイス制度の影響を理解して効率的な対応策を講じよう
本記事では、インボイス制度が法人に与える影響や登録方法、作業効率化のポイントについて解説しました。
インボイス制度への対応は、自社の状況を正確に分析して、業種や取引状況に適した対応策の選択が重要です。インボイス対応対応策の実行で、インボイス(適格請求書)の発行・管理や登録番号の検証などの業務を大幅に効率化できます。
また、制度対応をきっかけに経理システムを見直すことで、長期的な業務効率化や経営の透明性向上にもつなげられます。本記事で紹介した内容を参考に、自社に最適なインボイス制度対応を検討してみましょう。










