インボイス制度で消費税はいつ払う?期限や支払方法をやさしく解説
更新日:2025.12.21
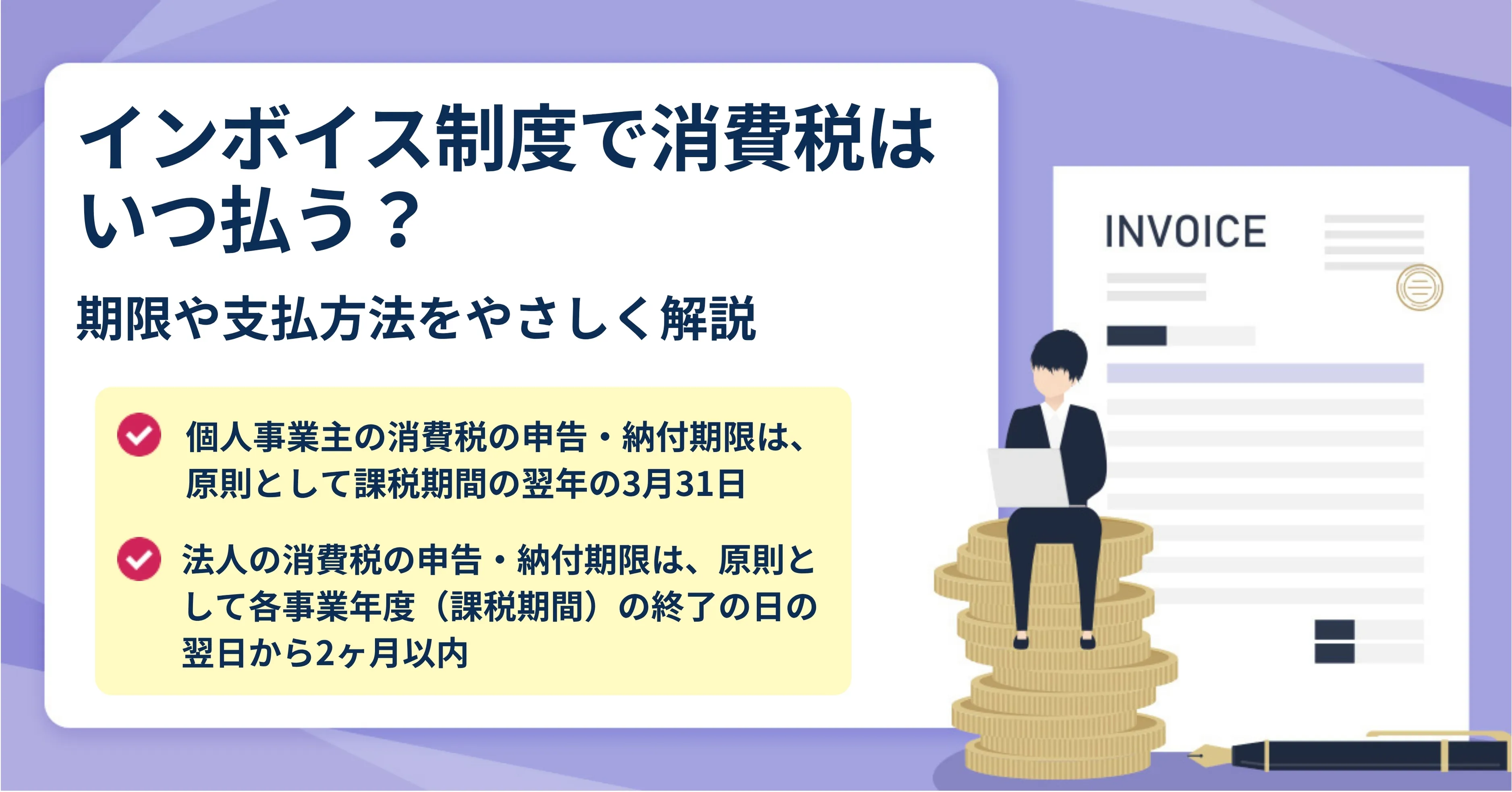
ー 目次 ー
インボイス制度が始まってから、「消費税って、いつ払えばいいの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、個人事業主や法人の方に向けて、消費税の納付スケジュールや支払い方法、遅れた場合のリスクまでをやさしく解説します。制度が変わって不安に感じている方も、この記事を読めば「いつ、どうやって支払うのか」が明確になります。
インボイス制度と消費税の基本的な関係!
2023年10月1日から始まったインボイス制度は、消費税の仕入税額控除の仕組みに関わる新しい制度です。この制度の導入により、特に事業者の方々にとって、消費税の納税額や支払い時期に影響が出る可能性があります。まずは、インボイス制度と消費税の基本的な関係性について理解を深めましょう。
インボイス制度とは何かをやさしく解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。この制度のもとでは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額などが正確に記載された「インボイス(適格請求書)」を交付し、双方がそのインボイスを保存することが求められます。
インボイスを発行できるのは、税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。この登録を受けると、登録番号が通知されます。インボイスには、この登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などを記載する必要があります。
この制度の主な目的は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の適正化です。買い手は、原則として適格請求書発行事業者から交付されたインボイスを保存しなければ、仕入税額控除(支払った消費税額を売上にかかる消費税額から差し引くこと)の適用を受けることができません。
消費税を納める義務があるのは誰か?
消費税を納める義務があるのは、原則として「課税事業者」です。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として「免税事業者」となり、消費税の納税義務が免除されます。ただし、免税事業者であっても、インボイス発行事業者になるためには課税事業者を選択する必要があります。
|
区分 |
納税義務 |
インボイス発行 |
|
課税事業者 |
あり |
可能(登録が必要) |
|
免税事業者 |
原則なし |
不可(課税事業者となり登録すれば可能) |
インボイス制度が消費税の支払いにどう影響するのか
インボイス制度の導入は、消費税の納税額、ひいては支払い時期にも影響を与える可能性があります。具体的には以下のような影響が考えられます。
買い手側の影響(主に課税事業者):
仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要になります。もし取引先が免税事業者でインボイスを発行できない場合や、受け取った請求書がインボイスの要件を満たしていない場合、その取引にかかる消費税額を仕入税額控除できず、結果として納付する消費税額が増加する可能性があります。
売り手側の影響:
- すでに課税事業者の場合:
取引先(買い手)が課税事業者である場合、インボイスの発行を求められることが一般的になります。インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。適切にインボイスを発行・保存し、消費税を申告・納付する流れは基本的に変わりませんが、インボイスの管理業務が増えることになります。 - 免税事業者の場合:
免税事業者はインボイスを発行できません。そのため、課税事業者の取引先から、インボイスを発行できる事業者との取引を優先されたり、消費税相当額の値引きを要求されたりする可能性があります。取引を維持するために、あえて免税事業者のメリットを放棄し、適格請求書発行事業者(つまり課税事業者)になることを選択するケースがあります。この場合、これまで免除されていた消費税の申告・納付義務が発生し、「いつ消費税を払うのか」という点が新たに重要になります。
このように、インボイス制度は特に免税事業者であった方が課税事業者になるきっかけとなり得るため、消費税の支払い時期や方法について正しく理解しておくことが非常に重要です。
消費税はいつ払う?知っておきたい納付スケジュールの基本
インボイス制度の開始に伴い、消費税の納税義務が生じる事業者の方や、すでに納税している事業者の方も、改めて消費税の納付スケジュールを正確に把握しておくことが重要です。ここでは、事業形態別に消費税をいつまでに支払う必要があるのか、基本的な納付スケジュールについて解説します。
個人事業主が消費税をいつ払うか
個人事業主の消費税の申告・納付期限は、原則として課税期間の翌年の3月31日です。例えば、令和5年(1月1日~12月31日)分の消費税であれば、令和6年3月31日が納付期限となります。この期限までに確定申告を行い、消費税を納付する必要があります。
ただし、振替納税を利用する場合は、納付期限が延長され、例年4月中旬から下旬頃(具体的な日付は毎年国税庁から発表されます)に指定の口座から引き落とされます。振替納税の手続きは、事前に税務署へ依頼書を提出する必要があります。
また、前年の消費税額(地方消費税額を含まない国税の額)が48万円を超える個人事業主は、中間申告と納付が必要になります。中間申告の回数と納付期限は、前年の消費税額に応じて異なります。
|
前年の消費税額(地方消費税額を含まない) |
中間申告・納付の回数 |
申告・納付期限 |
|
48万円超630万円以下 |
年1回 |
課税期間の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(通常8月31日まで) |
|
630万円超4,800万円以下 |
年3回 |
各中間申告対象期間(課税期間の開始の日から3ヶ月ごとの期間)の末日の翌日から2ヶ月以内 |
|
4,800万円超 |
年11回 |
課税期間の開始の日以後1ヶ月ごと(最初の期間を除く)および3ヶ月ごとの期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
中間申告が必要な場合でも、最終的な年間の消費税額は確定申告で調整されます。
法人が消費税をいつ払うか
法人の消費税の申告・納付期限は、原則として各事業年度(課税期間)の終了の日の翌日から2ヶ月以内です。例えば、3月決算の法人であれば、5月31日が納付期限となります。
法人も個人事業主と同様に、前事業年度の消費税額(地方消費税額を含まない国税の額)が48万円を超える場合は、中間申告と納付が必要になります。中間申告の回数と納付期限は、前事業年度の消費税額に応じて異なります。
|
前事業年度の消費税額(地方消費税額を含まない) |
中間申告・納付の回数 |
申告・納付期限 |
|
48万円超630万円以下 |
年1回 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
|
630万円超4,800万円以下 |
年3回 |
事業年度開始の日以後3ヶ月ごとの各期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
|
4,800万円超 |
年11回 |
事業年度開始の日以後1ヶ月ごと(最初の期間を除く)および3ヶ月ごとの各期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
中間申告の義務がある法人も、確定申告によって年間の消費税額を精算します。
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合
これまで免税事業者だった方が、インボイス発行事業者の登録を受けると、課税事業者になります。課税事業者になった場合、消費税の申告・納付義務が発生します。
消費税をいつ払うかについては、個人事業主であれば上記の「個人事業主が消費税をいつ払うか」で説明したスケジュール、法人であれば「法人が消費税をいつ払うか」で説明したスケジュールに従うことになります。インボイス発行事業者として登録を受けた課税期間から、消費税の申告・納付が必要となる点に注意しましょう。
例えば、個人事業主が令和5年10月1日からインボイス発行事業者になった場合、令和5年10月1日から12月31日までの期間が最初の課税期間となり、その期間の消費税を令和6年3月31日までに申告・納付する必要があります(2割特例などの特例措置を適用する場合は、計算方法が異なりますが、納付期限の原則は変わりません)。
すでに課税事業者の場合、消費税をいつ払うかは変わる?
すでに課税事業者である場合、インボイス制度の導入によって消費税の納付時期が変わることはありません。個人事業主であれば原則翌年3月31日、法人であれば原則事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内という期限は維持されます。
ただし、インボイスの保存が仕入税額控除の条件となるため、経理処理のミスには注意が必要です。
インボイス制度後の消費税はどう払う?支払方法と注意点
インボイス制度が導入された後も、消費税の基本的な納付方法は大きく変わりません。しかし、適格請求書発行事業者として消費税を納める際には、利用できる支払方法やそれぞれの注意点を改めて確認しておくことが大切です。この章では、消費税の具体的な支払方法と、万が一納付金額に誤りがあった場合の対処法について解説します。
消費税の支払方法一覧!
消費税の納付には、いくつかの方法があります。ご自身の状況や利便性に合わせて最適な方法を選びましょう。主な支払方法とその特徴は以下の通りです。
1,口座振替で支払う(振替納税)
振替納税は、事前に指定した預貯金口座から、納期限に自動的に消費税が引き落とされる方法です。一度手続きをすれば、納付忘れを防げるメリットがあります。利用するには、事前に税務署へ「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要があります。手数料はかかりませんが、引き落とし日までに口座残高が不足しないよう注意が必要です。
2,e-Taxで電子納税する
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネット経由で消費税の電子納税が可能です。自宅やオフィスのパソコンから、金融機関の窓口やコンビニへ行く手間なく納付できます。ダイレクト納付(事前に税務署へ届出をした預貯金口座から、e-Taxを通じて即時または期日を指定して納付する方法)や、インターネットバンキングを利用した納付が選択できます。利用には、e-Taxの利用開始手続きや、場合によっては電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要です。
3,クレジットカードで支払う
「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、クレジットカードでの消費税納付が可能です。納付額に応じた決済手数料が発生しますが、クレジットカードのポイントが付与されたり、支払いを一時的に先延ばしにできるメリットがあります。利用できるクレジットカードブランドや、一度に納付できる金額の上限(通常1,000万円未満)を確認しておきましょう。
4,コンビニのQRコードで支払う
国税庁のウェブサイトなどで納付に必要な情報(氏名や税額など)を入力してQRコードを作成し、そのQRコードをコンビニエンスストアのレジで提示することで、現金で消費税を支払うことができます。30万円以下の納付に限られますが、手軽に利用できる方法の一つです。利用可能なコンビニエンスストアを確認しておきましょう。
主な支払い方法の特徴をまとめると以下のようになります。
|
支払方法 |
メリット |
デメリット・注意点 |
主な手続き |
|
口座振替(振替納税) |
自動引落、納付忘れ防止、手数料無料 |
事前手続必須、残高不足注意 |
税務署へ口座振替依頼書提出 |
|
e-Tax(電子納税) |
場所を選ばず納付可能、24時間対応(一部除く) |
利用開始手続、電子証明書が必要な場合あり |
e-Tax利用開始手続、ダイレクト納付届出など |
|
クレジットカード |
ポイント付与、支払猶予 |
決済手数料発生、利用限度額あり |
国税クレジットカードお支払サイト利用 |
|
コンビニQRコード |
手軽、現金払い可能 |
30万円以下、QRコード作成の手間 |
国税庁サイト等でQRコード作成 |
納付金額が合わないときはどうする?追納・修正申告の対処法
万が一、申告した消費税額が実際よりも少なかった場合や、逆に多く納めすぎてしまった場合には、速やかに正しい税額に修正する手続きが必要です。税額が不足していた場合は「修正申告」を行い、追加で納付(追納)します。逆に納めすぎた場合は「更正の請求」という手続きを行うことで、過払い分の還付を受けることができます。これらの手続きは、誤りに気づいた時点で、できるだけ早く所轄の税務署に相談し、指示に従って進めましょう。期限後に修正申告を行う場合は、延滞税などがかかる可能性もあるため注意が必要です。
消費税の支払い遅れに要注意!発生するリスクと対応方法
消費税の納付は、事業者にとって重要な義務の一つです。インボイス制度の開始に伴い、経理処理が複雑化し、うっかり納付期限を過ぎてしまうケースも考えられます。支払い遅れには、延滞税や加算税といったペナルティが科されるため、十分な注意が必要です。この章では、消費税の支払い遅れによって生じるリスクと、万が一遅れてしまった場合の対応方法について解説します。
延滞税・加算税のペナルティとは?
消費税の納付が期限に間に合わなかった場合や、申告した税額が本来納めるべき金額より少なかった場合には、法律に基づいてペナルティが課されます。主なペナルティには「延滞税」と「加算税」があります。
延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、未納の税額に対して課される利息のようなものです。納付が遅れるほど延滞税の金額は増えていきます。
加算税は、申告内容に不備があった場合や、正当な理由なく申告・納付を行わなかった場合に課される税金です。加算税にはいくつかの種類があり、状況に応じて適用されるものが異なります。
|
加算税の種類 |
概要 |
主な税率 |
|
過少申告加算税 |
期限内に提出した申告書の税額が、本来納めるべき税額よりも少なかった場合に課されます。ただし、税務調査の通知前に自主的に修正申告した場合は課されません。 |
新たに納めることになった税額の10%。ただし、新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。 |
|
無申告加算税 |
法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されます。ただし、期限後申告を自主的に行った場合など、一定の要件を満たせば軽減されることがあります。 |
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%。税務調査の通知前に自主的に期限後申告した場合は5%に軽減されます。 |
|
不納付加算税 |
源泉徴収等による国税が、法定納期限までに納付されなかった場合に課されます。(消費税の申告・納付においては直接的には該当しにくいですが、税のペナルティとして存在します。) |
納付すべき税額の10%。ただし、税務署からの告知前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。 |
|
重加算税 |
事実を隠蔽したり、仮装したりして意図的に税額を少なく申告した場合や、申告しなかった場合に課される最も重いペナルティです。 |
過少申告加算税に代えて課される場合は、追加本税の35%。無申告加算税に代えて課される場合は、納付すべき税額の40%。 |
インボイス制度導入後は、適格請求書(インボイス)の保存・管理が仕入税額控除の要件となるため、経理処理の正確性がより一層求められます。意図しない申告漏れや計算ミスが起こらないよう、日頃から適切な会計処理を心がけましょう。
うっかり忘れた場合の対応は?期限後でもできる手続き方法
消費税の納付をうっかり忘れてしまった、あるいは申告期限を過ぎてしまったことに気づいた場合でも、放置せずに速やかに対処することが重要です。気づいた時点で自主的に正しい申告と納税を行えば、ペナルティが軽減される可能性があります。
まず行うべきことは、正しい税額を計算し直し、できるだけ早く「期限後申告」または「修正申告」を行うことです。期限後申告は法定申告期限を過ぎてから申告する場合、修正申告は一度申告した内容に誤りがあり税額を増額する場合の手続きです。これらの手続きは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するか、所轄の税務署に申告書を書面で提出することにより行えます。
申告手続きとあわせて、未納分の消費税と、発生している場合は延滞税も納付する必要があります。納付方法には、金融機関の窓口での納付、口座振替(事前に手続きが必要)、クレジットカード納付、コンビニ納付(QRコード利用)などがあります。
もし手続き方法が分からない場合や、計算に不安がある場合は、税務署の窓口や電話相談センターに問い合わせるか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。放置してしまうと延滞税が日ごとに加算され、場合によっては税務調査の対象となる可能性も高まりますので、誠実かつ迅速な対応を心がけましょう。
Q&A|インボイス制度での消費税の支払いに関するよくある質問
インボイス制度の導入に伴い、消費税の支払い時期について疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。具体的なケースごとに解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
2割特例を利用する場合、消費税はいつ払う?
2割特例を利用する場合でも、消費税の納付期限は通常のスケジュールと変わりません。2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方の納税額計算に関する負担軽減措置であり、支払い時期そのものを変更するものではないためです。
具体的な納付期限は以下の通り、納税者の区分によって定められています。
|
納税義務者 |
消費税の納付期限 |
|
個人事業主 |
課税期間の翌年3月31日 |
|
法人 |
課税事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
このため、2割特例の適用を受ける場合も、上記の期限までに申告と納税を済ませる必要があります。
少額特例と消費税の支払い時期は関係ある?
少額特例(例えば、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除を可能とする措置や、1万円未満の適格返還請求書の交付義務免除など)は、経理事務の負担を軽減するための措置です。
したがって、、消費税の支払い時期自体には影響しません。
主な少額特例と支払い時期への影響は以下の通りです。
|
少額特例の例 |
内容の概要 |
支払い時期への影響 |
|
少額な課税仕入れに係るインボイス保存不要措置 |
一定の条件を満たす事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイス保存を不要とし帳簿保存のみで仕入税額控除を認めるもの。 |
なし |
|
少額な適格返還請求書の交付義務免除 |
売上げに係る対価の返還等について、その金額が税込1万円未満の場合には、適格返還請求書の交付義務を免除するもの。 |
なし |
インボイス制度開始で消費税の支払い時期は変わる?
インボイス制度が開始されたこと自体によって、消費税の基本的な申告・納付期限が変更されるわけではありません。既に課税事業者である場合は、これまでと同様のスケジュールで消費税を納付することになります。
ただし、インボイス制度の導入を機に、これまで免税事業者だった方が新たに課税事業者(インボイス発行事業者)になった場合は、消費税の納税義務が発生します。その場合の支払い時期の考え方は以下の通りです。
|
事業者の状況 |
インボイス制度開始に伴う支払い時期の変更 |
備考 |
|
制度開始前から課税事業者の方 |
変更なし |
従来の納付スケジュールに従います。 |
|
制度開始を機に免税事業者から課税事業者になった方 |
新たに納税義務が発生 |
課税事業者としての納付スケジュールに従います。 |
ご自身の状況に応じて、正しい納付期限を確認しましょう。
新たにインボイス発行事業者になった場合の最初の消費税支払いはいつ?
免税事業者の方がインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になった場合、最初の消費税の申告・納付は、登録を受けた日から始まる課税期間が対象となります。個人事業主と法人で、課税期間の区切り方や具体的な納付期限が異なります。
|
納税義務者 |
最初の課税期間(原則) |
納付期限 |
|
個人事業主 |
登録日からその年の12月31日まで |
課税期間の翌年3月31日 |
|
法人 |
登録日からその法人の事業年度終了日まで |
課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
例えば、個人事業主の方が2023年10月1日にインボイス発行事業者として登録した場合、2023年10月1日から2023年12月31日までの期間にかかる消費税を、原則として2024年3月31日までに申告・納付することになります。法人の場合は、登録日を含む事業年度の終了後2ヶ月以内となりますので、ご自身の事業年度に合わせて確認が必要です。
インボイス制度の導入により、消費税の納付方法や管理の手間が少し増えた一方で、支払うタイミングそのものはこれまでと大きく変わりません。個人事業主の方は原則として翌年の3月31日まで、法人の方は事業年度終了から2ヶ月以内が納付期限となります。新しくインボイス発行事業者になった方も、このスケジュールに従って申告・納税が必要です。口座振替やe-Taxなど、便利な方法を選んで、期限内に忘れず対応するようにしましょう。うっかりミスを防ぐためにも、早めの準備が安心です











