インボイス請求書の保存は紙でも電子でもOK!保存方法や期間を徹底解説!
更新日:2025.12.23
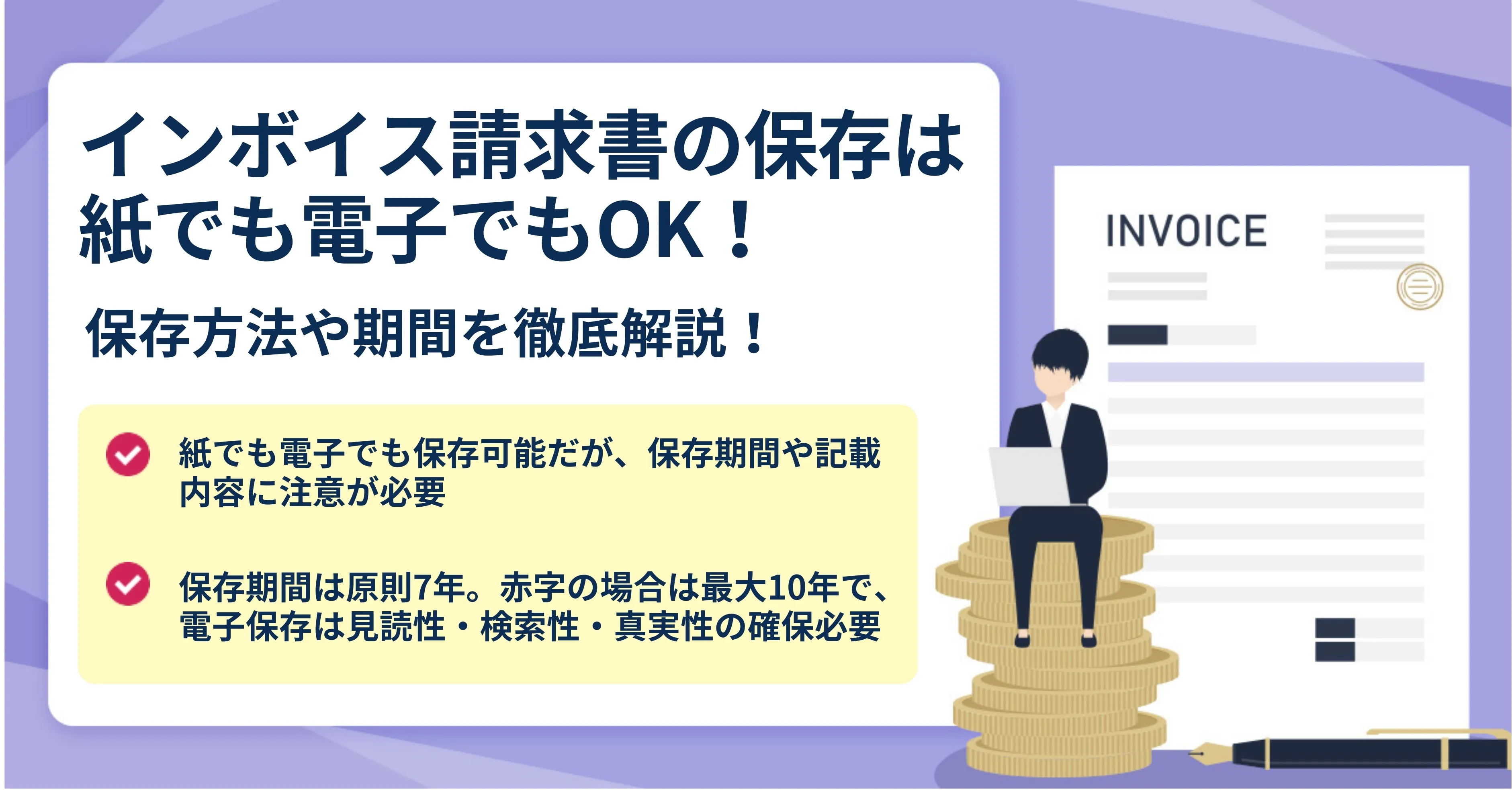
ー 目次 ー
本記事では、インボイス請求書の正しい保存方法や保存期間、紙保存・電子保存のポイント、電子帳簿保存法に沿った実務対応までを徹底解説します。最新制度に対応し、効率的・安全にインボイスを保管するコツがすぐに分かります。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは何か
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる新しい消費税の仕入税額控除方式です。2023年10月1日から日本全国で導入され、消費税の負担と納税の透明性を高めることを目的としています。インボイスとは、売り手が買い手に対して発行する適格請求書のことで、一定の要件を満たす事業者が発行できます。インボイス制度により、事業者は取引ごとに発行・受領した請求書の保存が必須となり、仕入税額控除を適用するためにはインボイスの保存が必要です。
この制度によって、請求書の様式や保存に関する要件が明確化され、より適正に消費税の申告・納税が行われる仕組みとなりました。従来の請求書保存方式から大きく制度変更されたことにより、多くの中小企業・個人事業主をはじめとする事業者は、正しい対応が求められています。
インボイス請求書が求められる背景
インボイス請求書が導入された背景には、消費税の仕入税額控除の適正化と、税務コンプライアンスの強化があります。インボイス制度以前では、一定の情報を記載した請求書等を保存することで仕入税額控除が認められていましたが、記載事項が不足していたり、確認が困難なケースがありました。
特に、免税事業者との取引による「益税」問題や、架空取引防止の観点からも、厳格な請求書管理が必要となっていたため、国税庁主導のもとインボイス制度が導入されました。
|
導入前の課題 |
インボイス制度導入後の変化 |
|
請求書の記載内容にばらつき・不備が多かった |
適格請求書(インボイス)の記載要件が明確化 |
|
免税事業者との取引で仕入税額控除の不透明性 |
適格請求書発行事業者のみ仕入控除の対象 |
|
税務調査時の証拠書類として不備が生じやすかった |
インボイスの保存義務が明確化、証拠能力向上 |
|
架空・水増し請求による脱税リスク |
請求書情報の厳格管理で不正抑止 |
このような背景から、インボイス請求書の発行・保存が事業活動において不可欠な義務となっています。買い手は、仕入税額控除を受けるために、「発行事業者登録番号」「発行日」「適用税率ごとの税抜金額と消費税額」など要件を満たしたインボイスの保存が求められます。制度開始後は、各事業者にとってインボイス請求書の管理方法や保存形式を見直すことが必要不可欠となっています。
インボイス請求書の正しい保存方法!
インボイス制度に対応するためには、適格請求書(インボイス)の正しい保存が不可欠です。紙での保存、電子データでの保存、それぞれにルールや注意点があります。ここでは、インボイス請求書の保存方法について、具体的な手順や実務上のポイントまで詳しく解説します。
紙での保存方法
インボイス請求書を紙で保存したい場合は、原則として発行された請求書そのもの、もしくは受領したものを整理して保管する必要があります。国税庁のガイドラインに沿ってきちんと管理することで、税務調査時にも安心です。
紙保存のメリットと注意点
|
メリット |
注意点 |
|
印刷物のまま保管でき、管理がなじみやすい |
経年劣化や紛失リスクがある |
|
インボイス番号や適格請求書発行事業者番号が目視で確認しやすい |
書類量が多いと収納スペースが必要 |
|
税務調査時に即時提示しやすい |
紙の破損・汚損に注意が必要 |
紙で保存する場合は、火災や水濡れなどの災害対策や、取り出しやすい整理整頓も重要です。
バインダーやファイルでの管理方法
インボイス請求書は、A4・A5サイズなどに合わせたバインダーやクリアファイルで保管する方法が一般的です。月別・取引先別にインデックスを付けてまとめておくと、後日の検索や税務署からの請求書提示要求にもスムーズに対応できます。下記に具体的な管理手順を示します。
|
作業工程 |
具体的な方法 |
|
分類 |
月ごと・取引先ごとに分別する |
|
保管 |
2穴バインダーやクリアポケットに格納し、目次やラベルを付ける |
|
見読性の確保 |
複写やコピーではなく、原本を保管 |
|
バックアップ |
重要書類はコピーを別保管する |
電子データでの保存方法
電子インボイスやスキャンした請求書など、電子データとして保存する場合は、電子帳簿保存法などの要件を満たす必要があります。単なるデータの保存ではなく、運用ルールを守ることで初めて証拠書類として有効となります。
PDF・JPEGなどの電子ファイル形式
多くの請求書発行システムや会計ソフトでは、PDF形式やJPEG形式でインボイス請求書を保存・出力できます。電子データをフォルダごとに分類し、ファイル名に日付・取引先名・請求書番号などを入れることで迅速な検索や抽出が可能です。
|
ファイル形式 |
特徴 |
注意点 |
|
|
改ざん防止性が高く、誰でも閲覧しやすい |
パスワード管理やバックアップを必ず実施 |
|
JPEG/PNG |
スマートフォンなどで手軽に保存できる |
画像劣化やファイルサイズに注意が必要 |
|
Excel/CSV |
大量のデータ処理が得意 |
取引内容の真正性の確保が必須 |
クラウドストレージや会計ソフトの活用
Dropbox、Googleドライブ、Microsoft OneDriveなどのクラウドストレージや、国産会計ソフトと連携させることで、安全かつ効率よくインボイス請求書を保存可能です。クラウド保存ではアクセス権限の設定やバージョン管理も重要になります。
- クラウドストレージに自動バックアップを設定し、データ消失や災害対策を行う
- 社内規程を整備し、担当者ごとの閲覧権限を設定
- 会計ソフトと連携することで取引の証憑データと仕訳を紐付けでき、検索や抽出が容易になる
一方で、セキュリティやプライバシーにも留意し、外部流出のリスク対策も不可欠です。
データ保存とスキャナ保存の違い
電子保存には、「電子データ保存」と「スキャナ保存」の2種類があります。それぞれの違いを理解して正しく運用することが重要です。
|
保存方法 |
概要 |
主な要件 |
|
電子データ保存 |
元から電子データで受け取ったインボイス(PDF・電子請求書など)をそのまま保存 |
|
|
スキャナ保存 |
紙の請求書をスキャンして電子データとして保存 |
|
国税庁の指導通り、いずれも真正なデータ保存・管理体制が求められます。自社の運用に合わせて最適な方法を選択しましょう。
インボイス請求書の保存期間と電子帳簿保存法とは?
保存期間は何年か
インボイス制度においては、適格請求書(インボイス)を発行・受領した事業者は、消費税法に基づきこれらの書類を一定期間保存することが義務付けられています。原則として、請求書や領収書などの重要な証憑書類の保存期間は「7年間」と定められており、これは紙保存・電子保存ともに同じです。
個人事業主の場合は事業年度終了後から7年、法人の場合は会計期間終了後から7年の保存が必要です。さらに、青色申告書を提出している場合や欠損金が生じている場合など、保存期間の延長(最大10年)が求められるケースもあります。
|
帳簿書類の種類 |
保存期間 |
保存期間の起算点 |
|
インボイス(適格請求書) |
7年 |
確定申告期限の翌日から |
|
仕入明細書・領収書 |
7年(※赤字等の場合は最大10年) |
事業年度終了後 |
保存期間中は、税務調査などで提示を求められることがあるため、正確かつ整然と保存し、直ちに書類を提出できる体制を整えておくことが大切です。
改正電子帳簿保存法との関係
2022年1月1日より電子帳簿保存法が改正され、インボイス請求書等の電子データ保存に関する要件が大きく変わりました。これにより、電子データで受け取ったインボイスは、原則として電子保存が義務付けられます。
具体的には、PDFやJPEGなど電子データで受領した文書を、そのまま電子データで保存する必要が生じました。一方、紙で受け取ったインボイスを電子化して保存(スキャナ保存)を行う場合も、電子帳簿保存法が関連します。
|
保存方法 |
対象文書 |
主な要件 |
|
電子データ保存 |
電子メール添付・WEBダウンロード等 |
タイムスタンプ付与、検索機能、見読性の確保 |
|
スキャナ保存 |
紙で受領したインボイス |
解像度や階調、タイムスタンプ、真実性の担保 |
|
紙保存 |
紙で受領し、そのまま保存 |
改ざん・滅失防止対策(従来どおり) |
電子帳簿保存法では、保存した電子データの「真実性」「可視性」「可読性」を満たすことが求められています。また、検索機能(取引年月日、取引金額、取引先で検索できること)や、タイムスタンプ付与による改ざん防止対策も必須となっています。
なお、一定の猶予措置が認められているものの、今後はインボイス請求書の電子保存が主流となるため、最新の法令や国税庁のガイドラインを確認しながら適切に対応することが重要です。
紙保存と電子保存のそれぞれのポイント!
紙保存を選ぶ場合に注意すべき点
紙でインボイス請求書を保存する場合には、適切な管理方法と保存環境を整えることが大切です。紙の原本管理は改ざん防止や紛失リスクに特に注意が必要となります。以下に、紙保存の際の主なポイントをまとめます。
|
ポイント |
具体的な対策 |
注意点 |
|
保存場所の確保 |
耐火キャビネットや専用ファイルを利用し、湿気・虫害を防ぎましょう。 |
直射日光や高温多湿を避けることが重要です。 |
|
整理・分類 |
インボイスごとに年月や取引先別で分けてファイリングし、台帳で管理。 |
混在や紛失防止のためラベルを明記してください。 |
|
改ざん防止 |
訂正・加筆は「二重線+訂正印」で管理し、原本を必ず残します。 |
無断で書き換えたり、修正液は使用不可。 |
|
保存期間管理 |
保存義務期間満了後に適切に処分できるよう、開始日と終了日を明記。 |
途中廃棄は税務調査時に問題となるため注意。 |
加えて、取引の証拠能力を確保するためにも、インボイスの控えや関連書類(契約書・納品書など)もあわせて管理することが推奨されます。
電子保存を選ぶ場合に必要な要件
電子データでインボイス請求書を保存する際には、電子帳簿保存法に従った厳格な要件が求められます。特にデータの真実性・可視性・検索性の確保が大切です。
タイムスタンプや真実性の確保
電子保存ではデータが改ざんされていないこと、偽造されていないことの証明が不可欠です。主な要件として下記の施策が挙げられます。
- タイムスタンプ付与による保存時刻の記録(電子署名と併用可)
- 電子保存システムやクラウドサービスのアクセスログ保管
- データの正当性を担保するためのバックアップ取得
なお、タイムスタンプは受領後おおむね7日以内に付与する必要があります。ただし、電子インボイス自体が真正なものである場合や、訂正・削除履歴が自動的にシステム保存される場合はタイムスタンプ不要となる場合もあります。
検索機能や見読性の要件
電子インボイス保存では、税務調査などに備え、速やかに該当取引の記録が確認可能であることが必要です。
- 取引日、取引金額、取引先の名称による検索機能の確保
- 保存されたデータを画面上で明瞭に表示し、プリントアウト可能な状態に保持
- データフォーマット(PDF, JPEG, Excel, CSVなど)を要件に合わせて選択
- システム障害など緊急時のために定期的なデータのバックアップも必須
加えて、電子帳簿保存法対応済みの経理ソフトウェアやクラウドストレージを利用することで要件を効率的に満たすことができます。電子保存で保存義務を果たすためには、社内規程の整備や業務フローへの組み込みも必要です。
Q&A|インボイス請求書保存のよくある質問
スマホ撮影の画像データ保存は認められる?
インボイス請求書をスマートフォンで撮影し、画像データ(JPEG・PNGなど)として保存することは、電子保存として認められる場合があります。ただし、根拠となる法律は「電子帳簿保存法」です。この法律に基づき、画像データで保存する場合には、一定の要件を満たす必要があります。例えば、タイムスタンプの付与や、改ざん防止措置、検索性の確保が求められます。
一方で、単にスマホ内で保存するだけではなく、クラウドサービスや電子帳簿保存法対応の会計ソフトで一元管理することが推奨されます。また、原則として紙の証憑の保存義務は、電子化保存要件を満たさない場合は従来通り必要です。
改ざんや紛失時の対応方法は?
インボイス請求書の原本やデータが改ざんや紛失した場合、税務署から問い合わせがあった際に根拠となる証憑の提示が求められます。誤って紛失・消去した場合は次の対応が重要です。
|
ケース |
対応方法 |
|
紙の請求書を紛失 |
取引先から再発行・再送付を依頼する。再発行が難しい場合、取引内容を証明する書類(メール履歴、銀行振込記録等)を保管しておく。 |
|
電子データの改ざん・消去 |
バックアップから復元。定期的なバックアップやクラウドサービス活用による多重保存を推奨。 改ざん防止の履歴(ログ)を記録する運用が重要。 |
また、帳簿や証拠書類の紛失・改ざんが税務調査で判明した場合、必要経費の否認や重加算税などのリスクがあります。日頃からの適正な保存管理・定期点検を心がけてください。
インボイス請求書の保存期間は?
インボイス請求書の保存期間は原則7年間です。これは「消費税法」や「電子帳簿保存法」に基づくもので、仕入税額控除を正しく適用するために保存が義務付けられています。なお、法人税法や所得税法でも帳簿書類の7年間保存が求められています。
|
帳簿・書類の種類 |
保存期間 |
|
インボイス請求書(仕入書類/控え/写し等) |
7年間 |
|
青色申告者の帳簿 |
7年間 |
|
白色申告者の帳簿 |
5年間 |
また、7年の保存期間が過ぎるまでは、税務署による調査や問い合わせに対応できるよう、確実に管理・保管しましょう。
電子保存の場合の「タイムスタンプ」は必須?
電子データでインボイス請求書を保存する場合、「タイムスタンプ」の付与は任意ではなく、一定の条件下で必須です。電子帳簿保存法では、以下のいずれかの方法で真実性を確保することが求められています。
|
真実性確保の方法 |
内容 |
|
タイムスタンプ付与 |
国税庁が認定したタイムスタンプサービスを利用し、受領後速やかに付与。 |
|
事務処理規程の作成・運用 |
所定の社内規程を策定し、定期的な点検や運用を実施。 |
|
訂正・削除履歴の記録機能 |
使用するシステムにおいて、データ変更時のログが記録される。 |
タイムスタンプが困難な場合も、運用規程と訂正削除履歴が残る会計ソフトやクラウドサービスの活用等で要件を満たせることがあります。詳細は国税庁のガイドラインを参照して下さい。
インボイス請求書のスキャナ保存の要件は?
紙で受領したインボイス請求書をスキャナ等で電子化して保存する場合、「スキャナ保存」として認められるには以下の要件があります。
- 解像度200dpi以上・カラーまたはグレースケールで読み取り。
- 受領日または作成日のおおむね7営業日以内に電子化し保存。
- タイムスタンプの付与、または訂正・削除履歴が残るシステムを利用。
- 帳簿との相互関連性が明確な状態で電子保存。
- 税務調査時に、速やかにプリントアウトまたは画面表示が可能であること(見読性が担保されていること)。
- 日付や金額検索が即座にできる検索機能を保有していること。
要件を満たさずに電子化保存した場合は、紙原本の保存が必要となるのでご注意ください。
クラウドストレージ・会計ソフトでの保存でも要件を満たせる?
クラウドストレージ(Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDriveなど)や、市販の会計ソフトを使ったインボイス請求書の保存は可能です。ただし、以下の電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
- データの改ざん・削除防止(タイムスタンプや履歴機能)
- 日付、金額、取引先名等による検索性
- ディスプレイやプリンタによる速やかな出力(見読性の確保)
- 保存データのバックアップ・保全体制
会計ソフトやクラウドサービスの中には、電子帳簿保存法対応を明示しているものも多いので、利用前に各サービスの機能や対応状況を確認し、必要な設定や運用規程を整えておくことが大切です。
個人事業主や小規模事業者でも電子保存は義務?
インボイス制度において、インボイスや請求書の電子保存は原則として義務ではありません。紙での保存も引き続き認められています。ただし、電子データで受領したインボイス請求書を紙に出力せずに保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす保存が必要です。
また、電子インボイス(Peppolなど)普及の流れもあり、将来的に電子保存の重要性は高まっていくと予想されます。現在は義務ではありませんが、事業規模や事務効率、将来の制度動向を踏まえた保存方法の選択が求められています。
取引先がインボイス未登録事業者の場合の保存は?
取引先が「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に登録していない場合、受け取った請求書は通常の書類保存義務に従い保存します。
ただし、仕入税額控除の適用はできません。インボイス制度への完全移行(2023年10月~猶予期間終了まで)後は、インボイス無しの取引については消費税の仕入控除が認められなくなるので、請求書保存はしつつ、取引内容ごとの管理・帳簿記載を徹底しましょう。
まとめ
インボイス請求書の保存は、紙と電子の両方が認められていますが、それぞれ保存期間や必要な要件が異なります。国税庁のガイドラインや電子帳簿保存法の要件を守ることが重要です。自社に合った保存方法を選び、確実に記録・管理しましょう。










