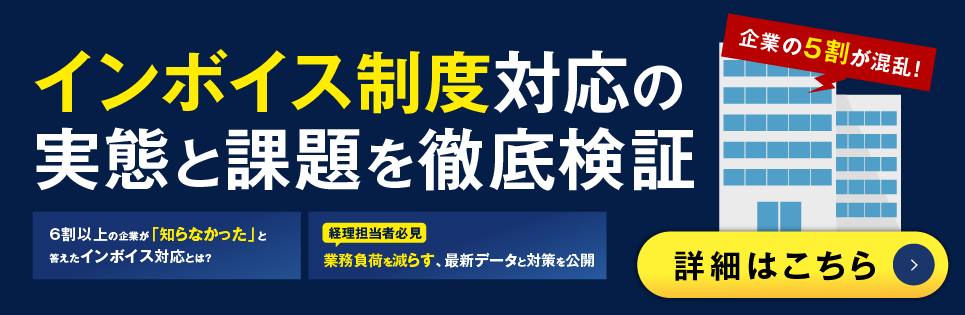インボイス制度が原因で倒産する?知らないと損する制度の罠
更新日:2026.01.15
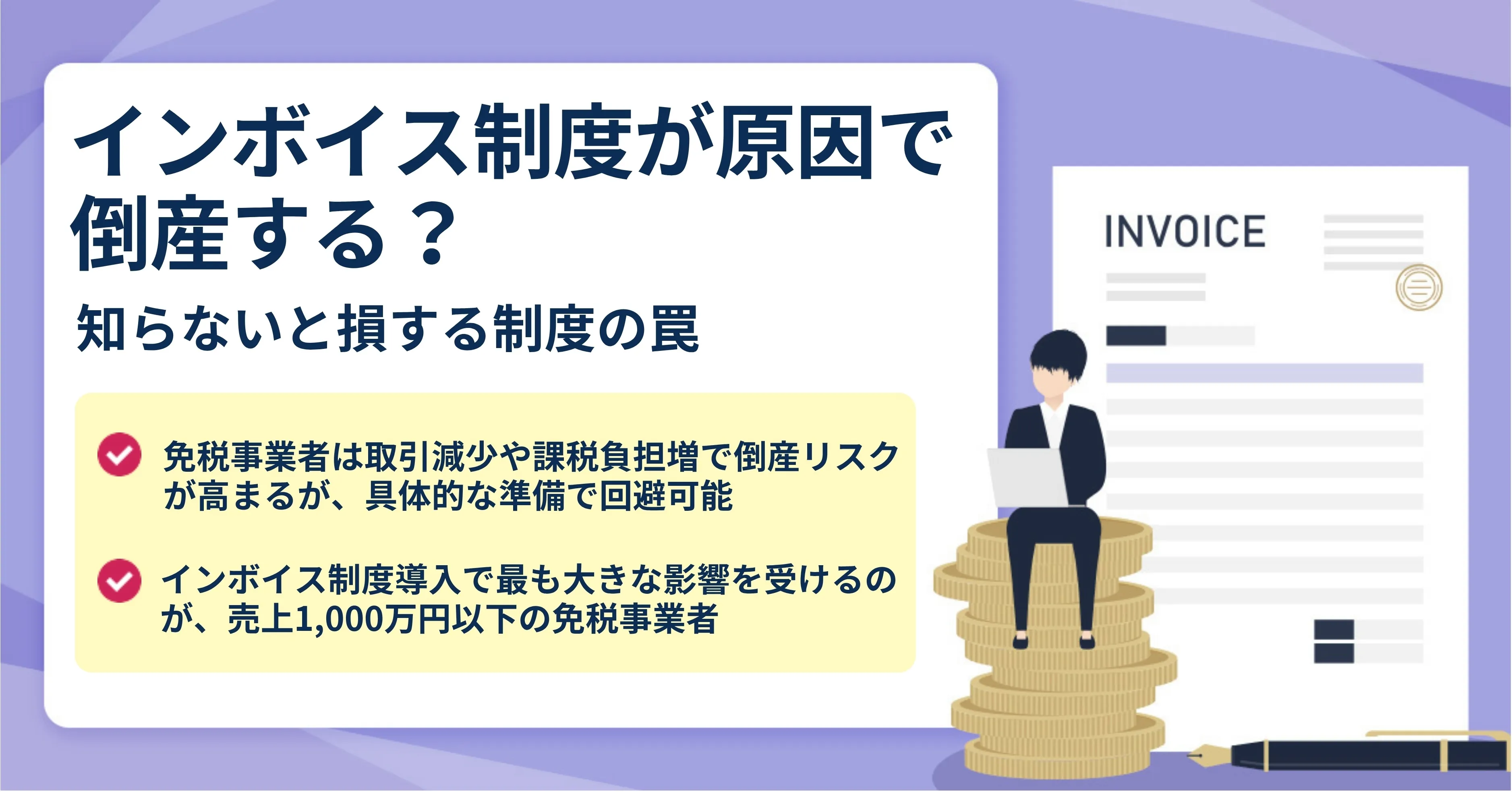
ー 目次 ー
「インボイス制度のせいで経営が立ち行かなくなるのでは...」と不安に感じていませんか?この記事では、制度がどのように倒産リスクに影響するのか、影響を受けやすい事業者の特徴を分かりやすく解説しつつ、実際に気をつけたいポイントや対策まで丁寧にご紹介します。制度の仕組みを正しく知って、リスクに備えていきましょう。
インボイス制度の基本をわかりやすく解説
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者に影響を与える新しい消費税の仕入税額控除の仕組みです。この制度を正しく理解することが、今後の事業運営において非常に重要となります。
そもそもインボイス制度とは?概要と目的
インボイス制度とは、複数税率(標準税率10%と軽減税率8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。具体的には、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がこれを保存することで、買手は消費税の仕入税額控除を受けることができるようになります。
この制度の主な目的は、以下の2点です。
- 消費税の仕入税額控除の適正化:軽減税率制度の導入により複雑化した消費税の計算を正確に行い、適正な納税を促すこと。
- 取引の透明性の向上:請求書に記載される情報が統一されることで、取引内容の透明性を高めること。
インボイス制度導入以前は、区分記載請求書等保存方式が採用されていましたが、インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額などの記載が追加で必要となりました。
適格請求書発行事業者とは何か
適格請求書発行事業者とは、納税地を所轄する税務署長に申請して登録を受けた事業者のことを指します。この登録を受けることができるのは、消費税の課税事業者に限られます。免税事業者は適格請求書発行事業者になることはできません。
登録を受けると、事業者ごとに「T」から始まる13桁の登録番号が発行されます。この登録番号は、適格請求書(インボイス)に記載する必要がある重要な情報の一つです。
適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)には、以下の事項を記載する必要があります。
|
記載事項 |
内容 |
|
発行事業者の氏名または名称および登録番号 |
適格請求書発行事業者の氏名または名称と、税務署から通知された登録番号を記載します。 |
|
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日を記載します。 |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
販売した商品や提供したサービスの内容を具体的に記載します。軽減税率の対象品目については、その旨がわかるように記載が必要です(例:※印など)。 |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率 |
適用される税率(10%または8%)ごとに、合計した取引金額(税抜きまたは税込み)と、適用税率を明記します。 |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
適用される税率ごとに計算した消費税額または地方消費税額を記載します。 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
取引の相手方(買手)の氏名または名称を記載します。 |
買手側は、原則としてこの適格請求書(インボイス)の保存がなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。そのため、適格請求書発行事業者でない事業者(主に免税事業者)からの仕入れについては、買手側が仕入税額控除を行えないという問題が生じ、取引関係に影響を与える可能性があります。
なぜインボイス制度で倒産すると言われるのか?その理由を解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者にとって大きな影響を与える制度です。ここでは、なぜインボイス制度が倒産のリスクを高めると言われているのか、その主な理由を解説します。
免税事業者が直面するインボイス倒産の危機
インボイス制度導入で最も大きな影響を受けるのが、売上1,000万円以下の免税事業者です。免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、取引先の課税事業者は、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除を受けられなくなります。
この結果、課税事業者である取引先から以下のような対応を迫られる可能性があります。
- 適格請求書発行事業者との取引を優先するための取引打ち切り
- 消費税相当額の値引き要求
これらの要求に応じざるを得ない場合、免税事業者は売上の大幅な減少や利益率の低下に見舞われ、資金繰りが悪化し、最悪の場合、事業継続が困難となり倒産に至るケースが懸念されます。特に、取引先が限定されている小規模な免税事業者ほど、このリスクは高まります。
課税事業者への転換負担とインボイス倒産
免税事業者が取引を継続するために、自ら課税事業者へ転換するという選択肢もあります。しかし、課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。これは実質的な増税となり、利益を圧迫する要因となります。
さらに、課税事業者には以下の負担も生じます。
- 適格請求書の発行・保存といった経理業務の煩雑化
- インボイス制度に対応した会計ソフトの導入やシステム改修のコスト
- 税理士への相談費用や記帳代行費用の増加
これらの新たな負担は、特に資金力や人的リソースに乏しい小規模事業者にとっては大きな重荷となり得ます。納税資金の確保が難しくなったり、事務負担の増加に対応しきれなくなったりすることで、経営状況が悪化し、倒産へと追い込まれる可能性が指摘されています。
インボイス制度が引き金となる連鎖倒産の可能性
インボイス制度の影響は、個々の事業者の倒産リスクを高めるだけでなく、サプライチェーン全体に波及し、連鎖倒産を引き起こす可能性もはらんでいます。例えば、ある事業者がインボイス制度への対応が遅れたり、資金繰りが悪化したりして倒産した場合、その事業者と取引のあった他の事業者も影響を受けます。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 取引先の倒産による売掛金の回収不能
- 主要な仕入先や販売先の喪失による事業継続の困難化
特に、建設業や運送業など、多くの下請け業者を抱える業界や、特定の取引先に依存している企業は、取引先の経営状況の変化に大きく左右されるため、連鎖倒産のリスクが高まる傾向にあります。インボイス制度が、こうしたドミノ倒しのような状況の引き金になることが懸念されているのです。
インボイス倒産しやすい事業者の特徴と具体的なケース!
インボイス制度の導入により、特に影響を受けやすく、経営状況が悪化し最悪の場合倒産に至る可能性が指摘される事業者が存在します。ここでは、どのような特徴を持つ事業者がインボイス倒産のリスクに直面しやすいのか、具体的なケースを交えながら解説します。
小規模事業者や個人事業者とインボイス倒産
小規模事業者や個人事業主、特にこれまで免税事業者であった方々は、インボイス制度による影響を大きく受ける可能性があります。主な理由としては、取引先である課税事業者から適格請求書(インボイス)の発行を求められるケースが増えるためです。
具体的なケースとして、以下のような状況が考えられます。
- フリーランスのデザイナーやライター:主要な取引先が企業(課税事業者)である場合、インボイスを発行できないと取引を打ち切られたり、消費税相当額の値引きを要求されたりする可能性があります。これにより収入が減少し、事業継続が困難になるケースです。
- 個人経営の飲食店(企業向けの仕出し弁当などBtoB取引がある場合):企業からの大口の注文が売上の柱であった場合、インボイスに対応しないことでその取引を失い、資金繰りが悪化する可能性があります。
- 一人親方(建設業など):元請け企業からインボイスの発行を求められ、対応できない場合は仕事を得にくくなる、あるいは報酬の減額交渉を受けるリスクがあります。
これらの事業者が課税事業者に転換する場合、消費税の納税義務が生じるだけでなく、経理処理の負担も増加します。この負担増が経営を圧迫し、インボイス倒産へと繋がる危険性があります。
|
事業者の種類 |
主なリスク要因 |
倒産に至る可能性のあるシナリオ例 |
|
免税事業者のフリーランス |
取引先からのインボイス発行要求、取引停止、値下げ圧力 |
主要取引先を失い収入が激減、固定費が支払えず廃業 |
|
個人経営の小規模店舗(BtoB取引あり) |
課税事業者への転換負担(納税、事務作業増)、BtoB取引の喪失 |
売上減少とコスト増により利益が圧迫され、運転資金がショート |
建設業や運送業など特定の業種とインボイス倒産
業種によっては、その構造的な特徴からインボイス制度の影響を特に受けやすく、倒産リスクが高まる場合があります。建設業や運送業はその代表例と言えるでしょう。
建設業:
建設業界は、元請けから一次下請け、二次下請けへと仕事が発注される重層的な下請け構造が一般的です。この構造の中で、免税事業者である一人親方や小規模な下請け事業者が多数存在します。元請けや上位の下請け企業が仕入税額控除を受けるためには、下位の事業者からのインボイスが必要となります。そのため、インボイスを発行できない事業者は取引から排除されたり、不利な条件での取引を強いられたりする可能性が高まります。
運送業:
運送業、特に軽貨物運送などでは、個人事業主として業務委託契約を結んでいるドライバーが多くいます。荷主や元請けの運送会社(課税事業者)は、これらの個人事業主ドライバーに対してインボイスの発行を求めるようになります。燃料費の高騰など、ただでさえ厳しい経営環境にある中で、インボイス制度への対応がさらなる負担となり、廃業や倒産を選択せざるを得ないケースが懸念されます。
具体的なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 建設業の一人親方:長年取引のあった元請け企業から、インボイス登録をしないのであれば今後の発注は難しいと通告され、収入の道が途絶えてしまう。
- 軽貨物運送の個人事業主:複数の荷主からインボイス発行を求められ、課税事業者になることを決めたものの、消費税負担と経理作業の増加で手取りが大幅に減少し、事業継続が困難になる。
下請け構造におけるインボイス倒産のリスク
日本の産業構造において、下請け企業は重要な役割を担っていますが、インボイス制度はこの下請け構造に大きな影響を与える可能性があります。特に、親事業者(発注元)が課税事業者で、下請け事業者が免税事業者である場合にリスクが顕在化しやすくなります。
親事業者は、仕入税額控除を確保するために、下請け事業者に対して以下のいずれかの対応を求めることが考えられます。
- 適格請求書発行事業者への登録(課税事業者への転換)
- 消費税相当額の値引き
立場の弱い下請け事業者は、これらの要求に応じざるを得ない状況に追い込まれがちです。課税事業者へ転換すれば納税負担と事務負担が増加し、値引きに応じれば利益が減少します。いずれの選択肢も、下請け事業者の経営体力を削ぎ、資金繰りを悪化させる要因となり得ます。
特に、以下のようなケースでインボイス倒産のリスクが高まります。
- 親事業者に依存した経営体質の下請け企業:主要な取引先である親事業者からの要求を断れず、不利な条件を飲まざるを得ない場合。
- 価格交渉力が弱い小規模な下請け事業者:原材料費の高騰などを価格に転嫁できていない状況で、さらにインボイス制度による負担増が重なる場合。
- 代替の取引先を見つけるのが困難な専門性の高い下請け業務:親事業者との関係が悪化すると、事業継続そのものが危うくなる場合。
独占禁止法や下請法では、優越的地位の濫用にあたる一方的な取引条件の変更は禁じられていますが、実態としてどこまで遵守されるかは不透明な部分もあり、下請け事業者は常に注意が必要です。インボイス制度をきっかけとした取引条件の見直しが、結果的に下請け事業者の経営を圧迫し、倒産に繋がるケースが懸念されています。
知らないと損する!インボイス制度の罠を紹介
インボイス制度は、多くの事業者にとって影響が大きい制度変更です。しかし、制度の細部や影響範囲を正確に理解していないと、思わぬ「罠」にはまり、最悪の場合、事業継続が困難になる可能性も否定できません。ここでは、特に注意すべきインボイス制度の罠について解説します。
インボイス登録の判断と廃業率
インボイス制度への対応として、適格請求書発行事業者への登録を検討する事業者は多いでしょう。しかし、この登録判断自体が最初の大きな罠となり得ます。登録のメリット・デメリットを十分に比較検討しないまま判断すると、後々大きな負担を強いられる可能性があります。
免税事業者がインボイス登録をしない場合、課税事業者である取引先から消費税分の値引きを要求されたり、最悪の場合は取引を打ち切られたりするリスクがあります。これは売上減少に直結し、資金繰りを圧迫する要因となり得ます。一方で、安易に課税事業者へ転換しインボイス登録を行うと、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生し、経理事務の負担も大幅に増加します。この新たな負担が、小規模事業者にとっては致命的になるケースも考えられます。
実際に、インボイス制度を機に廃業を決める事業者が増えるとの見方もあります。特に、高齢の個人事業主や、ギリギリの利益率で運営してきた小規模事業者にとって、制度対応の負担が事業継続の最後の引き金となる「罠」となり得るのです。
経過措置を理解せずインボイス倒産
インボイス制度には、免税事業者との取引がある課税事業者の負担を軽減するための経過措置が設けられています。しかし、この経過措置の内容を正確に理解していない、あるいは楽観視しすぎることが、もう一つの大きな「罠」となります。
経過措置とは、免税事業者からの仕入れであっても、制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できるというものです。この措置があるからといって安心してしまうと、将来的に大きな問題に直面する可能性があります。具体的には、控除できる割合は段階的に引き下げられ、最終的には全く控除できなくなります。
|
期間 |
免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
|
2029年10月1日以降 |
控除不可 |
この経過措置のスケジュールを把握せず、当初の80%控除が続くと誤解していると、控除割合が50%に減少するタイミングや、完全に控除できなくなるタイミングで、急激に納税額が増加し、資金繰りが悪化する危険性があります。特に、免税事業者との取引が多い事業者は、この「罠」にはまりやすく、計画的な対策を怠ると、経過措置の終了が倒産への引き金となりかねません。経過措置はあくまで時限的な措置であり、恒久的な対策ではないことを理解しておく必要があります。
インボイス倒産を防ぐための具体的な対策
インボイス制度の導入により、多くの事業者が経営への影響を懸念しています。しかし、適切な対策を講じることで、倒産リスクを軽減し、事業を継続していくことは可能です。ここでは、インボイス倒産を防ぐための具体的な方法を解説します。
取引先との価格交渉と契約見直し
免税事業者から課税事業者へ転換する場合や、免税事業者のままでいることを選択した場合でも、取引先との関係性や取引条件の見直しは不可欠です。特に、売上への影響が大きい主要な取引先とは、早期に協議の場を設けることが重要となります。
課税事業者になる場合は、新たに発生する消費税負担分について、価格への転嫁を交渉する必要があります。その際、インボイス制度の趣旨や自社の状況を丁寧に説明し、理解を求める姿勢が大切です。仕入税額控除の観点から、取引先も適格請求書発行事業者との取引を優先する可能性があるため、交渉は慎重に進めましょう。一方、免税事業者を継続する場合は、取引先が仕入税額控除を受けられないことによる影響を考慮し、値下げ要求の可能性も視野に入れなければなりません。契約内容についても、インボイス(適格請求書)の発行義務の有無、支払い条件、消費税の取り扱いなどを改めて確認し、必要に応じて覚書を交わすなど、書面での合意形成を心がけましょう。
課税事業者への転換シミュレーションと資金計画
免税事業者が課税事業者への転換を検討する際には、事前の詳細なシミュレーションが極めて重要です。単に消費税の納税義務が発生するだけでなく、経理処理の負担増、会計ソフトの導入コストなども考慮に入れる必要があります。具体的には、以下の点をシミュレーションし、資金計画を策定しましょう。
- 年間売上高と課税売上高の予測
- 仕入れにかかる消費税額(仕入税額控除額)の試算
- 納税する消費税額の概算(原則課税と簡易課税制度の比較検討を含む)
- 経理業務にかかる時間やコストの増加分(会計ソフト導入費、税理士費用など)
- 納税資金の確保方法とキャッシュフローへの影響、運転資金の確保
簡易課税制度を選択できる場合は、業種ごとのみなし仕入率を用いて納税額を計算できるため、事務負担を軽減できる可能性があります。自社の事業規模や業態、取引先の状況に合わせて、原則課税と簡易課税のどちらが有利になるか、または免税事業者を継続するかの判断を慎重に行うことが、資金繰りの安定化、ひいてはインボイス倒産の回避に繋がります。
補助金や支援策の活用でインボイス倒産を回避
インボイス制度への対応には、システム導入や専門家への相談など、一定のコストが発生する場合があります。国や地方自治体は、こうした事業者の負担を軽減するための様々な補助金や支援策を用意しています。これらを積極的に活用することで、資金的な負担を抑え、制度対応を円滑に進めることができます。
代表的な支援策としては、以下のようなものがあります。最新の公募状況や詳細な要件は、各制度の公式サイト等で必ず確認してください。
|
支援策の名称(例) |
概要 |
対象となりうる経費(例) |
|
IT導入補助金 |
中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするもの。インボイス対応の会計ソフトや受発注システム導入も対象となる枠があります。 |
会計ソフト購入費・クラウド利用料、受発注システム導入費、PC・タブレット等ハードウェア購入費(一部枠のみ) |
|
小規模事業者持続化補助金 |
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するもの。インボイス対応に伴う業務効率化のための投資も対象となる場合があります。 |
広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、業務効率化のための設備投資、インボイス対応のための専門家謝金など |
|
中小企業庁・よろず支援拠点など |
国が設置する無料の経営相談所。インボイス制度に関する相談や、経営全般に関するアドバイスを専門家から受けることができます。 |
専門家相談費用(無料)、事業計画策定支援など |
これらの支援策は、公募期間や要件がそれぞれ異なりますので、最新情報を各省庁や自治体のウェブサイト、商工会議所・商工会などで確認し、自社に合ったものを検討しましょう。早期の準備と申請が重要です。
会計ソフトの導入と専門家への相談
インボイス制度への対応をスムーズに行うためには、制度に対応した会計ソフトの導入が非常に有効です。適格請求書の作成・保存機能はもちろんのこと、電子帳簿保存法への対応、消費税の計算(複数税率対応)、経理業務の自動化・効率化など、多くのメリットがあります。クラウド型の会計ソフトであれば、法改正へのアップデートも迅速に行われ、場所を選ばずに作業できる利便性もあります。これにより、経理負担を軽減し、本業に集中できる時間を確保することにも繋がります。
また、インボイス制度は複雑な側面も多く、自社だけで判断に迷うケースも少なくありません。そのような場合は、税理士や会計士、中小企業診断士といった専門家に相談することを強く推奨します。専門家は、個々の事業者の状況に応じた最適なアドバイスを提供し、課税事業者の選択(有利不利判定)、価格交渉の進め方、資金繰り対策、補助金の活用方法、経理体制の構築支援など、多岐にわたるサポートを行ってくれます。特に、顧問税理士がいる場合は、早めに相談し、制度開始後の影響について具体的な対策を練ることが、インボイス倒産を回避する上で不可欠です。商工会議所や商工会でも相談窓口を設けている場合がありますので、積極的に活用しましょう。
まとめ
インボイス制度は、特に免税事業者や小規模な事業者にとって、大きな負担となることがあります。しかし、正しい情報をもとに早めに準備し、取引先との関係を見直したり、支援制度を活用したりすることで、そのリスクを減らすことは十分可能です。「知らなかった」では済まされない制度だからこそ、今からできる対策を一つずつ進めていきましょう。