公正取引委員会が喚起するインボイス制度の問題とは?注意事例を詳細に解説
更新日:2025.03.27
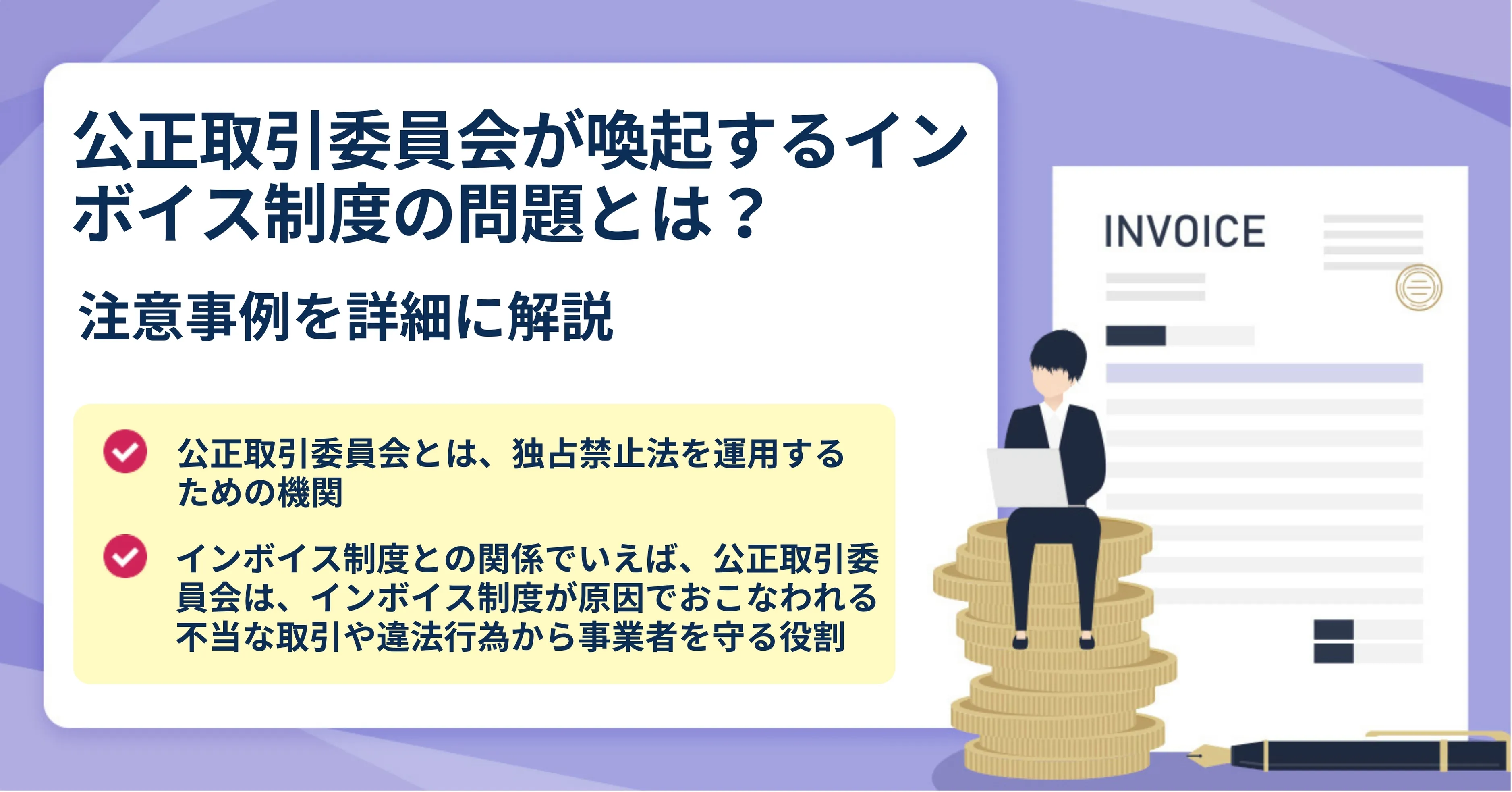
ー 目次 ー
公正取引委員会では適正な市場の活性化を図るために、独占禁止法や下請法の管理・執行をおこなう機関です。
そんな公正取引委員会は、2023年に施行されたインボイス制度における注意事例を公表しています。ここで取り挙げられた注意事例の多くは、仕事を依頼する側と受ける側で大きな格差がある点で共通しており、事業者がおこなうさまざまな取引にあてはまります。
このようにインボイス制度はすべての事業者に影響する制度であるため、私たちも公正取引委員会が注意するトラブルに巻き込まれるリスクがあります。不当な取引に対して、適切かつ迅速に対応するために、公正取引委員会が提供する注意事例を把握しておくことが大切です。
本記事では、公正取引委員会が喚起するインボイス制度の問題について、注意事例を詳細に解説します。
インボイス制度とは、消費税の計算や書類の作成方法を定めたルール
インボイス制度とは消費税の計算方法や、書類の作成方法などに関する対応を定めたルールです。2023年10月に、事業者が納める税金を国が正確に把握することを目的として定められました。
そんなインボイス制度の特徴は以下のとおりです。
- 「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必須
- 「インボイス発行事業者」の登録が必要
- 「仕入税額控除」が適用でき、税負担が軽減される
上記の特徴のなかでも、とくに「インボイス」をめぐって実務的な対応が大きく変更となっています。
しかし、要件を満たせば「仕入税額控除(売上にかかる消費税から、仕入れで支払った消費税が差し引ける仕組み)」が利用でき、従来の方式と比べると、税負担を軽減できる可能性があります。
関連記事:【消費税の新ルール】インボイス制度とは?2割特例や経過措置も紹介
公正取引委員会とインボイス制度の関係は?関連する法律も紹介
公正取引委員会とは市場の活性化を適正におこなえるように、独占禁止法や下請法の運用や違反行為への対処などに対応するための機関です。委員会は委員長と4名の委員で構成され、ほかの機関とは独立して職務をおこなう特徴があります。
インボイス制度との関係において、制度が原因でおこなわれる不当な取引や違法行為から事業者を守る役割を担っています。
各事例の理解を深める前に、インボイス制度に影響を与える関連法令についての理解をしておきましょう。
ここでは、公正取引委員会とインボイス制度の関係について、関連する法律を解説します。
独占禁止法とは、公正・自由な競争を促すルール
「独占禁止法」とは私的独占やカルテル、入札の談合などの不当な取引を制限し、公正かつ自由な競争を促すためのルールです。この法律は、事業の大小問わず、すべての事業者を対象としています。
独占禁止法では、違反した場合に対する命令や罰則も定められています。
下請法とは、不当な行為から下請事業者を守るルール
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」とは、代金の支払遅延や買いたたきなどの下請事業者が不当に取引を害されることを防ぐためのルールです。この法律では下請事業者を取引先として有する親事業者を対象としています。
下請法に違反した場合には、勧告や指導、また罰金も科せられるおそれがあります。
公正取引委員会から喚起されたインボイス制度の注意事例とは?問題となるポイントを解説
インボイス制度が原因で、公正取引委員会が相談を受けた事例がいくつか存在します。これらの事例は、仕事を依頼する側と受ける側で大きな格差がある点で共通しており、さまざまな取引にあてはまります。
そのため、注意事例を踏まえて、もし不当な対応を迫られていると感じていれば、公正取引委員会への相談がおすすめです。また、取引を依頼する立場として、取引先に対して適正な対応をおこなえるようにしておきましょう。
ここでは、公正取引委員会から喚起されたインボイス制度の注意事例について、問題となるポイントを解説します。
- 「免税取引先からの消費税相当額を負担しないこと」を決定する
- 消費税額の負担分を徴収する
- 消費税額の負担分を差し引く
①「免税取引先からの消費税相当額を負担しないこと」を決定する
|
<事例> 協同組合が、組合員と免税取引先との取引において、組合員が消費税相当額を負担しないことを決定すること |
この事例では、インボイス制度の登録事業者と免税事業者との取引において、制度に登録している事業者が消費税額分の負担をしないと決定したものです。
このような事例では「消費税額分の負担をしない決定」に対して、独占禁止法の違反行為にあたるおそれがあります。インボイス制度の登録事業者が取引に対して優位である立場を利用したものとみなされるためです。
上記のような事例を踏まえて、もし消費税の負担が気になるようであれば、自社が抱える課題を丁寧に取引先に伝え、お互いが納得するような形で交渉をおこなうようにしましょう。
②消費税額の負担分を徴収する
|
<事例> 協同組合の行うチケット事業において、免税組合員に対して従来のチケット換金手数料に加え消費税相当額として仕入税額控除に係る経過措置を考慮しない金額を徴収すること |
この事例では、インボイス制度の登録事業者と免税事業者との取引において、仕入税額控除にかかる経過措置を考慮しないで徴収をおこなっています。インボイス制度の登録事業者は免税事業者との協議をおこなっておらず、取引先はこの取引に対応しなければならない状況です。
このような事例において、インボイス制度の登録事業者が免税事業者との取引に対して優位な立場にあるうえでの対応と見られることから、不当な取引にあたるとされました。
消費税額の負担や特例・措置の適用有無などを踏まえて、お互いが合意する形で交渉をおこなわなければなりません。
③消費税額の負担分を差し引く
|
<事例> 協同組合が委託を受けた運送業務を消費税の免税事業者である組合員に再委託を行う場合に、当該再委託の代金について消費税相当額を差し引いて支払うこと |
この事例では、インボイス制度の登録事業者と免税事業者との協議は十分なものではなく、登録事業者側が自身の都合にあった協議内容で対応をおこなっていたものです。
このような事例は、独占禁止法において優越的地位の濫用として抵触しているおそれがあります。事業者間でおこなわれる協議は形式的なものであってはならず、必ずお互いが合意した内容であることが前提となっているためです。
もしこちら側から交渉をおこなう場合は、必ず相手の事情や意見をうかがい、お互いが合意のうえで対応をすることが大切です。
まとめ|公正取引委員会が提供した事例を確認し、不当な取引を避けよう!
本記事では、公正取引委員会が喚起するインボイス制度の問題について、注意事例を詳細に解説しました。
公正取引委員会が提供する事例は、インボイス制度が施行された昨今において多くの事業者にあてはまる事例です。
そのため、依頼を受ける側として、取引先が不当な対応を求めていないかは常に確認しておきましょう。また、依頼する側では、取引先に対する丁寧かつ慎重な対応が必要です。
本記事で紹介したような事例だけでなく、公正取引委員会が公表する最新の事例も確認しておくと、よりインボイス制度への理解も深まるでしょう。










