コンビニのレシートはインボイスになる?簡易インボイスや経理処理の方法も解説
更新日:2025.12.06
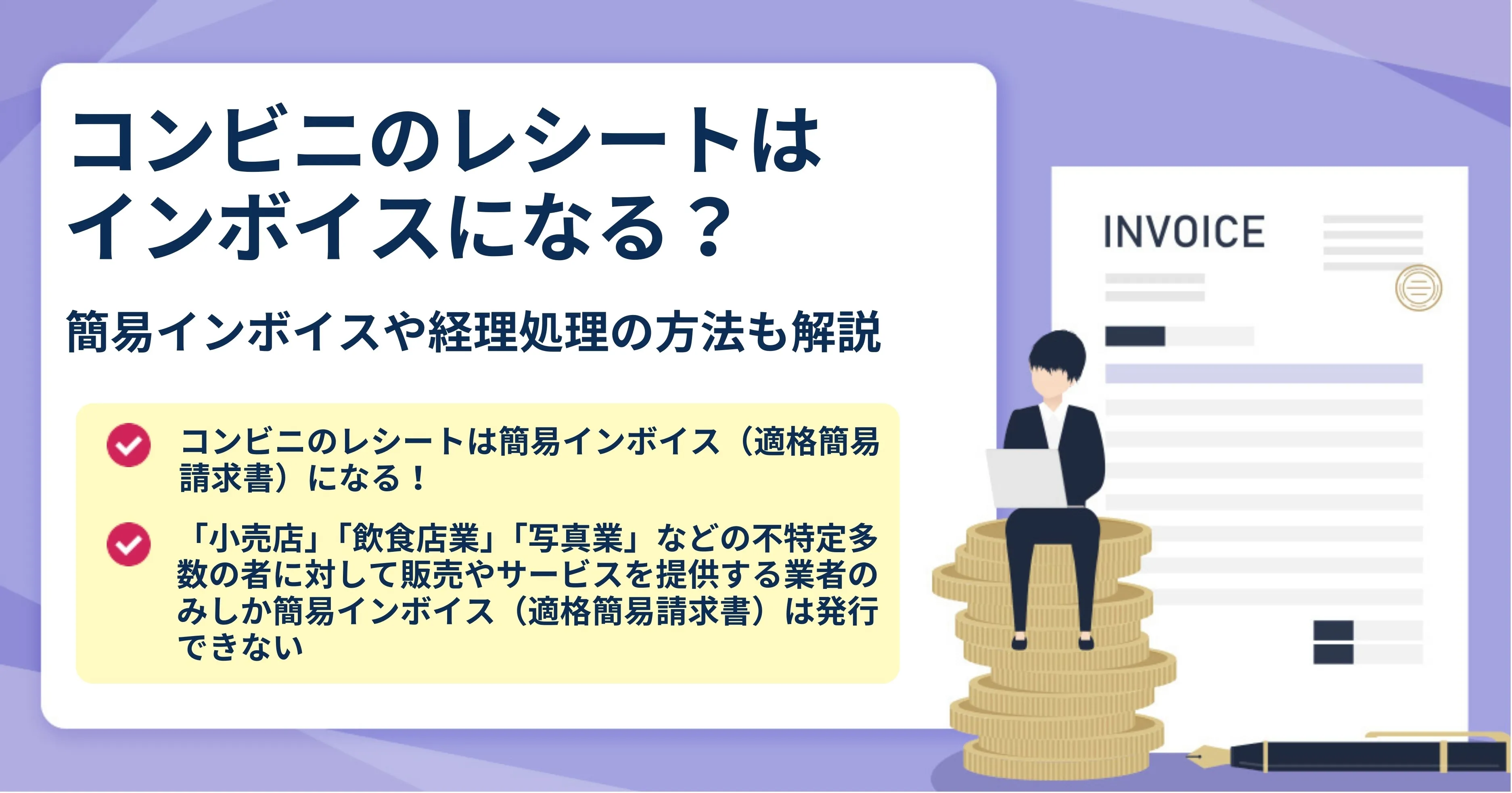
ー 目次 ー
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)の保存が原則として必要となりました。ただ、インボイスには記載方式が定まっており、コンビニで発行されるレシートがインボイスとして取り扱えるかを理解している事業者は多くありません。
インボイス制度は消費税にまつわるルールであり、経費精算や申告方法を誤ると大きなトラブルが起こるリスクがあります。このため、頻繁に利用するコンビニでのレシートが税務上どのように扱われるのか、正しい理解が重要です。
本記事では、コンビニのレシートがインボイスとして認められるかどうかや、インボイス対応レシートの保存方法、経理処理の方法について解説します。
【結論】コンビニのレシートは簡易インボイス(適格簡易請求書)になる!
コンビニで受け取るレシートは、その店舗がインボイス(適格請求書)発行事業者に登録していれば「簡易インボイス(適格簡易請求書)」として扱われて、インボイス制度における仕入税額控除の適用が可能です。レシートに適格請求書発行事業者の登録番号(「T」で始まる13桁の番号)が記載されていれば、簡易インボイスの条件を満たしていると判断できます。
コンビニのレシートに記載されているインボイス登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認可能です。この番号から、どの事業者がその店舗を運営しているかを知れるため、取引の透明性が確保されています。
簡易インボイス(適格簡易請求書)とは?おさえておきたいポイントも解説
簡易インボイス(正式名称:適格簡易請求書)とは、インボイス制度において、通常のインボイス(適格請求書)の記載事項を一部簡略化した請求書です。
ここでは、簡易インボイスについて、おさえておきたい3つのポイントをそれぞれ解説します。なお、簡易インボイスを交付できる業種や記載項目について以下の記事でも解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できる業種|記載項目と具体例、例外を紹介。
①「購入者の氏名または名称」が不要である
簡易インボイス(適格簡易請求書)と通常のインボイス(適格請求書)の最大の違いは、「書類の交付を受ける事業者(購入者)の氏名または名称」の記載が不要である点です。これにより、コンビニやスーパーなどの小売店では、顧客一人ひとりに名前や会社名を聞く必要がありません。
②簡易インボイスも仕入税額控除の要件を満たしている
簡易インボイス(適格簡易請求書)は、通常のインボイス(適格請求書)と同様に、仕入税額控除の要件を満たす証憑として認められています。簡易インボイスの保存で、課税事業者は支払った消費税額を控除できるため、改めて通常のインボイスを取り直す必要はありません。
③交付できる業種は限られている
簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行できるのは、不特定多数の者に対して販売やサービスを提供する特定の事業者に限定されています。具体的には、以下のような業種が該当します。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業 など
これらの業種では、多数の顧客と日々取引をおこなうため、レジごとに顧客の名前や会社名を記入することが現実的ではありません。そのため、簡易インボイスの発行が認められています。
コンビニで発行されるインボイスの注意点とは?
コンビニレシートをインボイスとして適切に扱うためには、一般的なインボイスのルールを理解した上で、コンビニ特有の事情や例外についても知識を持っておくことが重要です。インボイスの要件を満たしていないレシートを経費に計上すると、税務調査の際に指摘を受けるおそれがあります。
コンビニでの購入は日常的に発生するため、正確な経理処理をおこなうためにも、事前に適切な知識を持ち、実際のレシートを確認することが重要です。コンビニの事情や例外を把握しておくことで、税務上のリスクを回避し、正確な経理処理が可能です。
ここでは、コンビニで発行されるインボイスの注意点について解説します。
①インボイス発行事業者への登録状況は店舗ごとに異なる
コンビニ店舗の多くはフランチャイズ(FC)形式で運営されており、各店舗は地元の法人や個人事業主が経営しています。そのため、店舗によってはインボイス(適格請求書)発行事業者として登録していないかもしれません。
インボイス発行事業者に登録している店舗では、レシートにインボイス登録番号が記載されています。この番号があれば、そのレシートは簡易インボイス(適格簡易請求書)として仕入税額控除の対象となります。
②コンビニ支払いではインボイスは発行されない
公共料金の支払いや宅配便の発送など、コンビニが代行するサービスを利用した場合は、コンビニ自体がサービス提供者ではないため、簡易インボイスは発行されません。これらのサービスでコンビニが発行するのは、代金受領に関するレシートのみです。
これらのサービスに関するインボイスが必要な場合は、電力会社や宅配業者などのサービス提供事業者に直接依頼する必要があります。
③コンビニチェーンごとに税率区分の表示方法が異なる
レシート上での税率区分の表示方法は、コンビニチェーンごとに異なります。「軽」「標」「※」などの記号や、税率ごとに小計を分けて表示するなど、表示形式が統一されていません。このため、正確に税率区分を読み取れないと、経理処理で誤った税率を適用してしまうリスクがあります。
とくに、経費精算や会計処理をおこなう際には、この税率区分の正確な確認が重要です。
【重要】コンビニでの買い物は少額特例が適用できることが多い
コンビニでの買い物は「少額特例」が適用できるケースが多くあります。少額特例とは、インボイス制度で、税込価格が1万円未満の少額な取引に対して設けられた特例制度です。少額特例を利用すると、インボイスがなくても一定の条件を満たすことで仕入税額控除を受けられます。
少額特例の適用条件と内容は、以下のとおりです。
|
適用条件 |
1回の取引金額が税込1万円未満 |
|
内容 |
一定の事項を記載した帳簿の保存 |
|
記載事項 |
・仕入れ先の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率対象の場合には、その旨も記載) ・課税仕入れにかかる支払対価の額 |
コンビニでの買い物はほとんどの場合は1万円未満なため、少額特例が適用できることが多いです。少額特例では、帳簿に「少額特例対象」などの特別な記載は不要ですが、上記の基本的な情報は正確に記録する必要があります。
コンビニでインボイス(適格請求書)対応のレシートを受け取った際の保存方法2つ
コンビニでインボイスに対応したレシートを受け取った際の保存方法は「紙での保存」と「電子データでの保存」の2つがあります。2024年1月1日以降、電子取引の場合は紙での保存が認められなくなりましたが、紙のレシートをもらった場合は引き続き紙での保存が可能です。
法定保存期間は法人・個人を問わず7年間で、長期間の管理体制が求められるため、重要なレシートは複数の方法で保存しておくと安心でしょう。とくに高額な取引や税務調査で指摘されやすい項目には注意しましょう。適切な保存方法の選択で、仕入税額控除を確実に受けられるだけではなく、経理業務の効率化にもつながります。
ここでは、コンビニでインボイス対応のレシートを受け取った際の保存方法について解説します。
①紙で保存する
紙での保存は、レシートの原本をファイルやバインダーに整理して保管する方法です。日付順や支出カテゴリー別など、後で探しやすい方法で分類するのがおすすめです。また、ホッチキスやテープでA4用紙などに貼り付けると紛失を防げます。
レシート用紙は感熱紙で時間の経過と共に印字が薄くなる特性があるため、重要なレシートはコピーを取るか写真に撮っておくのがおすすめです。
②電子データで保存する
電子データでの保存には、いくつかの方法があります。それぞれの保存方法は、以下のとおりです。
|
スキャンによる保存 |
・レシートをスキャンしてPDFなどの電子データとして保存する方法 ・タイムスタンプの付与や検索性の確保などの「電子帳簿保存法」のスキャナ保存の要件を満たす必要がある |
|
スマホアプリによる撮影保存 |
・経費精算アプリを使用してスマホでレシートを撮影する方法 ・多くのアプリは自動で日付や金額を認識してデータ化してくれる ・電子帳簿保存法の要件を満たすアプリ選びが重要 |
|
経理システムとの連携 |
・クラウド会計ソフトと連携した経費精算システムを使用すると、撮影したレシートデータから自動で仕訳を作成できるサービスもある ・データ入力の手間が大幅に削減される |
まとめ|コンビニのレシートは簡易インボイスとして活用しよう
本記事では、コンビニのレシートがインボイスとして認められるかどうかや、インボイス対応レシートの保存方法、経理処理の方法について解説しました。
コンビニのレシートは、インボイス発行事業者に登録された店舗であれば、適格簡易請求書(簡易インボイス)として利用できます。レシートにインボイス登録番号(「T」で始まる13桁の番号)が記載されていれば、仕入税額控除の対象となります。
また、コンビニでの購入は税込1万円未満であることが多いため「少額特例」を活用できる場面も多いです。一方で、コンビニの代行サービス(公共料金支払いなど)のレシートはインボイスとして使えないため注意が必要です。
レシートの保存は紙保存と電子保存の2つの方法があり、法定保存期間は7年間となっているため、適切に管理しましょう。










