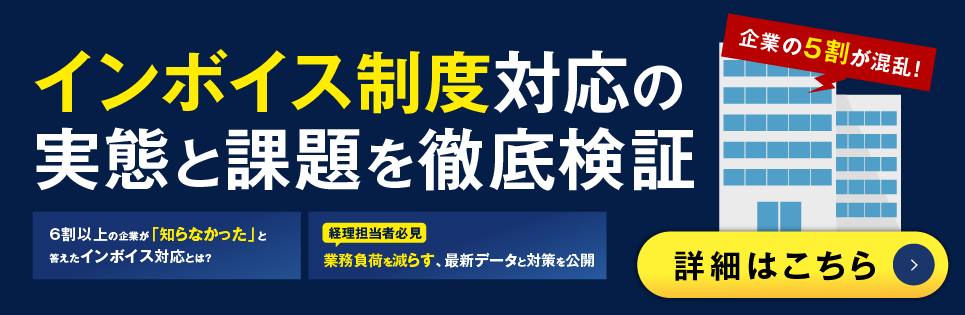インボイス制度のBtoCへの影響は?インボイス制度の基本をわかりやすく解説
更新日:2026.01.29
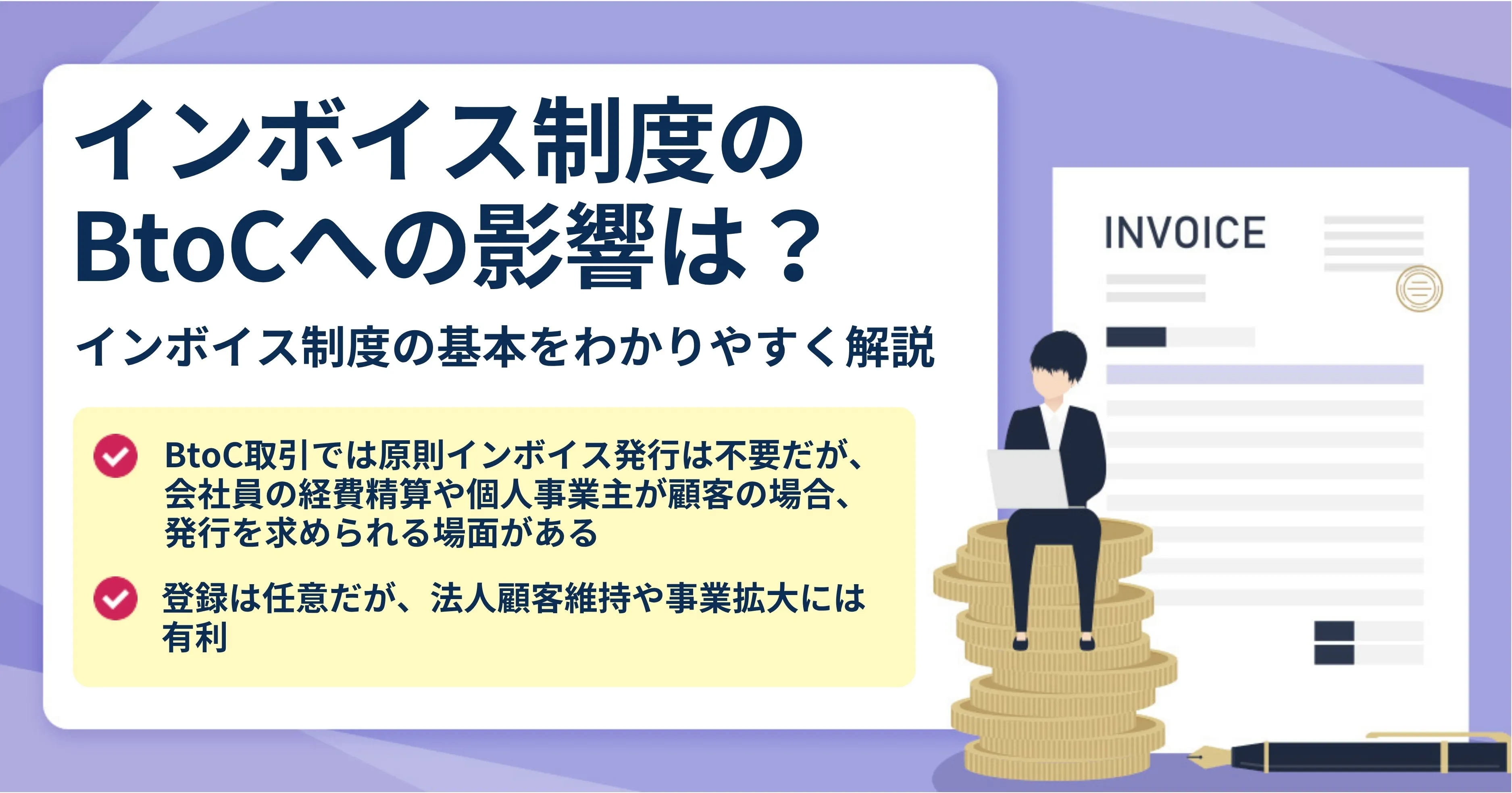
ー 目次 ー
インボイス制度は「BtoB取引向けの制度」と思われがちですが、BtoC(個人向け取引)にも間接的な影響があります。
結論から言えば、消費者が直接インボイスを求められる場面は基本的にありません。しかし、制度の影響で価格改定や税込表示の見直し、免税事業者の淘汰が進む可能性があり、結果的に「私たちの暮らし」にも関係してくるのです。
たとえば、小規模事業者がインボイス未登録のままだと、取引先からの仕事が減る → 価格転嫁せざるを得ない → 消費者価格が上がるという構図が生まれます。
また、適格請求書が必要な場面(医療費控除や確定申告など)では、インボイスの発行が前提となるケースもあるため注意が必要です。
本記事では、インボイス制度の基本と、BtoCにも関係してくる仕組みや今後の生活への影響についてわかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?基本を3分で理解
インボイス制度は、消費税の納税に関わる事業者にとって非常に重要な変更点を含んでいます。まずは、インボイス制度の基本的な仕組みをわかりやすく解説します。
インボイス制度の目的は"正確な消費税の把握"
インボイス制度が導入された最大の目的は、「取引における消費税の額と税率を正確に把握すること」です。日本では、2019年10月から消費税の軽減税率制度が導入され、標準税率10%と軽減税率8%という複数の税率が存在しています。どの商品やサービスにどちらの税率が適用されているのか、そして消費税額はいくらなのかを、売り手から買い手へ明確に伝えるための統一的なルールとしてインボイス制度が作られました。これにより、事業者が納める消費税額の計算をより正確に行うことを目指しています。
仕入税額控除の仕組みをわかりやすく解説
インボイス制度を理解する上で欠かせないのが「仕入税額控除」という仕組みです。仕入税額控除とは、事業者が国に納める消費税を計算する際に、売上にかかった消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引くことができる制度を指します。
例えば、ある事業者が商品を11,000円(うち消費税1,000円)で販売し、その商品の仕入れに5,500円(うち消費税500円)を支払っていたとします。この場合、納める消費税額は、売上で預かった1,000円から仕入れで支払った500円を差し引いた500円となります。この「差し引く行為」が仕入税額控除です。
インボイス制度の開始後は、この仕入税額控除を適用するために、原則として取引相手(売り手)から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。つまり、買い手側はインボイスがなければ仕入税額控除が受けられず、納税負担が増えてしまう可能性があるのです。
適格請求書(インボイス)と従来の請求書の違い
適格請求書(インボイス)とは、従来の請求書(区分記載請求書)に、新たに3つの項目を追加した書類やデータのことです。具体的に何が違うのか、以下の表で確認してみましょう。
|
記載項目 |
従来の請求書(区分記載請求書等) |
適格請求書(インボイス) |
|
発行事業者の氏名または名称 |
必要 |
必要 |
|
取引年月日 |
必要 |
必要 |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
必要 |
必要 |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額 |
必要 |
必要 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
必要 |
必要 |
|
登録番号 |
不要 |
必要 |
|
適用税率 |
不要 |
必要 |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
不要 |
必要 |
大きな違いは、税務署から発行される「登録番号」と、「適用税率」「税率ごとの消費税額」の明記が義務付けられた点です。この登録番号は、税務署に申請し、適格請求書発行事業者として登録された課税事業者のみが取得できます。
インボイス制度はBtoCにも影響する?影響をわかりやすく解説
インボイス制度は、一般消費者を相手にするBtoC事業者にとってどのような影響があるのでしょうか。ここでは、BtoC取引におけるインボイス制度の影響と、事業者が注意すべき点を具体的に解説します。
原則としてBtoC取引にインボイス発行は不要!
結論から言うと、取引相手が一般消費者であるBtoC事業においては、原則としてインボイス(適格請求書)の発行は不要です。
なぜなら、インボイス制度の根幹である「仕入税額控除」は、事業者が消費税を納める際に適用される仕組みだからです。一般消費者は消費税を納める義務がないため、仕入税額控除を行うことがありません。したがって、事業者に対してインボイスの発行を求める必要がないのです。
例えば、以下のような事業では、顧客のほとんどが一般消費者であるため、インボイスの発行を求められるケースは極めて少ないでしょう。
- スーパーマーケットやコンビニなどの小売業
- カフェやレストランなどの飲食業
- 美容室やネイルサロンなどのサービス業
- 学習塾や習い事教室
- 個人向けオンラインストア
このように、顧客が事業者ではなく個人の場合、インボイス制度への対応は基本的に必要ないと考えて問題ありません。
BtoC事業者がインボイス制度で気をつけたいポイント
原則としてインボイス発行が不要なBtoC取引ですが、事業者として知っておくべき注意点がいくつかあります。特に、インボイス発行事業者として登録した場合の対応は重要です。
ポイント1:レシートや領収書もインボイスの要件を満たす必要がある
インボイス発行事業者として登録した場合、相手が事業者であれ消費者であれ、求められた際にはインボイスを交付する義務が生じます。しかし、小売業や飲食業のように不特定多数の顧客に商品を販売する事業では、会計のたびに詳細な請求書を発行するのは現実的ではありません。
そのため、下記の特定の事業者に限り、記載項目を簡略化した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。普段使用しているレシートを簡易インボイスの要件に対応させるのが一般的です。
|
項目 |
従来のレシート等からの変更・追加点 |
|
発行事業者の氏名または名称 |
(従来通り) |
|
登録番号 |
(追加必須) |
|
取引年月日 |
(従来通り) |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
(従来通り) |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込) |
(従来通り) |
|
税率ごとに区分した消費税額等 または 適用税率 |
(いずれかの記載が追加必須) |
簡易インボイスでは、通常のインボイスと異なり「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要です。現在お使いのレジシステムが簡易インボイスに対応しているか、必要であれば改修や入れ替えを検討しましょう。
ポイント2:顧客に個人事業主や法人が含まれていないか確認する
BtoCがメインの事業でも、顧客の中に個人事業主や法人が含まれる場合があります。例えば、飲食店で「会社の経費として処理するため、インボイス対応の領収書をください」と求められるケースです。このような取引先に対しては、インボイスの交付ができないと、取引が敬遠される可能性があります。
自社の顧客層を改めて分析し、事業者との取引が一定数見込まれる場合は、インボイス登録を検討する必要があります。この点については、次の章で詳しく解説します。
注意!BtoC事業者がインボイスを求められるケースとは?
飲食店や小売店、サロンといったBtoC(個人向け)事業者は、原則としてインボイス(適格請求書)の発行は不要です。しかし、顧客の属性や利用目的によっては、インボイスの発行を求められるケースが存在します。ここでは、BtoC事業者がインボイスを求められる具体的なケースについて解説します。
出張の経費精算でインボイスが必要な会社員
BtoC事業者にとって最も注意すべきなのが、顧客が会社員であるケースです。例えば、出張中の会社員が飲食店で食事をしたり、タクシーを利用したり、手土産を購入したりすることがあります。この場合、会社員は支払った代金を「立替経費」として後から会社に請求します。
会社側は、その経費を仕入税額控除の対象とするために、インボイスの提出を社員に義務付けていることがほとんどです。そのため、一見すると個人利用に見えるお客様でも、会社の経費として精算するためにインボイスの発行を求めてくる可能性があるのです。
顧客が個人事業主や法人(課税事業者)の場合
お客様が個人名でサービスを利用したり商品を購入したりしていても、実は個人事業主やフリーランスで、事業に必要な経費として計上する場合があります。例えば、Webライターが仕事で使うパソコンを家電量販店で購入したり、法人が来客用のお茶菓子を小売店で購入したりするケースです。
このような顧客が課税事業者である場合、支払った消費税について仕入税額控除を受けるためにインボイスを必要とします。そのため、事業者であることを伝えられた上で、インボイスの発行を依頼されることがあります。
インボイスの交付義務について
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録している場合、取引の相手方(課税事業者に限る)からインボイスの発行を求められた際には、それに応じる法的な義務があります。これを「インボイスの交付義務」と呼びます。
一方で、免税事業者のままでいる場合、そもそもインボイスを発行できないため、交付義務もありません。自社の登録状況によって対応が異なるため、以下の表で確認しておきましょう。
|
自社の登録状況 |
顧客からの要求 |
対応 |
|
インボイス発行事業者 |
課税事業者である顧客からインボイスの発行を求められた |
交付義務あり (インボイスを発行する必要があります) |
|
免税事業者(未登録) |
顧客からインボイスの発行を求められた |
交付義務なし (インボイスを発行できません) |
BtoCでもインボイス登録すべき?メリット・デメリットを解説
顧客のほとんどが一般消費者であるBtoC事業者は、インボイス登録をすべきか迷うことが多いでしょう。インボイス登録は義務ではありませんが、事業の状況によっては登録した方が有利になるケースも存在します。ここでは、適格請求書発行事業者になることのメリットとデメリットを具体的に解説し、登録を判断するための材料を提供します。
BtoCにおけるインボイス登録で得られるメリット!
BtoC事業者がインボイス登録をすることで、主に課税事業者である顧客との取引においてメリットが生まれます。具体的には以下の点が挙げられます。
課税事業者である顧客の維持・獲得
あなたの顧客が一般消費者に加えて、法人や個人事業主である場合、インボイス登録は大きなメリットになります。例えば、飲食店や小売店、宿泊施設などで、会社の経費として利用する顧客は、経費精算のためにインボイス(適格請求書)を求めます。インボイスを発行できないと、仕入税額控除ができないこれらの顧客から敬遠され、取引機会を失う可能性があります。登録事業者になることで、こうした顧客を逃さず、新たな法人顧客の獲得にも繋がります。
事業拡大の選択肢が広がる
現在はBtoCが中心でも、将来的にBtoB(企業間取引)への展開を考えている場合、インボイス登録は事実上必須となります。あらかじめ登録しておくことで、将来の事業拡大に向けた準備が整い、ビジネスチャンスを逃すことなくスムーズに移行できます。
登録を迷いやすい理由とデメリット
多くのBtoC事業者が登録をためらうのには、明確な理由があります。特に、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者にとっては、影響の大きいデメリットが存在します。
消費税の納税義務の発生(免税事業者の場合)
これまで基準期間の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税を免除されていた免税事業者がインボイス登録をすると、課税事業者となり消費税を納める義務が生じます。これは、売上にかかる消費税を国に納付する必要があることを意味し、手元に残る利益が減少する最大のデメリットです。
経理処理の負担増加
インボイス制度に対応するためには、経理業務が煩雑になります。具体的には、以下の対応が必要です。
- 登録番号や税率ごとの消費税額などを記載した、適格請求書の要件を満たすレシートや領収書の発行
- 発行したインボイスの写しの保存義務
- 正確な消費税額を計算し、申告・納税する作業
これらの業務に対応するため、会計ソフトの導入やシステムの改修、税理士への依頼など、新たなコストや手間が発生する可能性があります。
BtoC事業者がインボイス登録を検討する際のメリット・デメリットを以下にまとめました。ご自身の事業状況と照らし合わせて判断しましょう。
|
比較項目 |
メリット(登録した場合) |
デメリット(登録した場合) |
|
取引機会 |
法人や個人事業主といった課税事業者の顧客を維持・獲得しやすくなる。 |
顧客のほとんどが一般消費者の場合、取引上のメリットは限定的。 |
|
税負担 |
(影響は特にない) |
免税事業者だった場合、新たに消費税の納税義務が発生し、利益が減少する。 |
|
事務負担 |
BtoBへの事業展開を見据えた経理体制を構築できる。 |
インボイス対応のレシート発行や、消費税申告など経理業務が煩雑になり、コストが増加する可能性がある。 |
Q&A|インボイスとBtoCに関するよくある質問
ここでは、インボイス制度とBtoC取引に関して事業者様から寄せられることの多い質問にお答えします。制度の特例や税額のシミュレーションなど、具体的な疑問を解消していきましょう。
インボイス制度の経過措置の適用ってなに?
インボイス制度の開始に伴う事業者の急激な負担を緩和するために設けられた、期間限定の特例措置です。この措置により、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)ではない免税事業者からの仕入れであっても、事業者は一定期間、仕入税額相当額の一定割合を控除することが認められています。
BtoC事業者自身が免税事業者である場合、取引先(買い手)がこの経過措置を適用できるため、インボイスを発行できないことによる取引への影響が緩和される可能性があります。具体的な控除割合と期間は以下の通りです。
|
期間 |
控除可能な割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
2029年10月1日以降は、この経過措置は適用できなくなり、インボイスがなければ仕入税額控除は一切できなくなります。
インボイス制度で実際にいくら納税額が増えるか影響額の試算はどうやる?
これまで免税事業者だったBtoC事業者がインボイス登録をして課税事業者になった場合、消費税の納税義務が発生します。納税額の計算方法は主に「原則課税」と「簡易課税」の2種類があり、どちらを選択するかで納税額が変わります。
原則課税の場合:
(売上にかかる消費税額)-(仕入れや経費にかかる消費税額)= 納税額
仕入れや経費の支払いが多い業種に向いています。
簡易課税の場合:
(売上にかかる消費税額)-(売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)= 納税額
「みなし仕入率」は事業の種類によって定められています。この制度を利用するには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることや、事前の届出が必要です。
|
事業区分 |
みなし仕入率 |
該当する事業の例 |
|
第一種事業 |
90% |
卸売業 |
|
第二種事業 |
80% |
小売業(飲食店業を除く) |
|
第三種事業 |
70% |
製造業、建設業など |
|
第四種事業 |
60% |
飲食店業 |
|
第五種事業 |
50% |
サービス業、運輸通信業など |
|
第六種事業 |
40% |
不動産業 |
さらに、インボイス制度を機に課税事業者になった方向けの負担軽減措置として「2割特例」があります。これは、売上税額の2割を納税額とすることができる制度で、2026年9月30日の属する課税期間まで適用可能です。多くの場合、この2割特例が最も納税額を抑えられますが、ご自身の事業内容に合わせてどの計算方法が有利になるか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
インボイス制度は基本的にBtoB取引を前提とした仕組みですが、BtoC事業者にとっても無関係ではありません。顧客の中に法人や個人事業主が含まれている場合、思いがけずインボイスの発行を求められることがあるため、自社の顧客層や将来的な事業展開を踏まえた判断が必要です。
経過措置などの制度も活用しつつ、ご自身の事業に合った対応を選び、スムーズに運用できる体制を整えていきましょう。