合計請求書はインボイス対応できない|対応した様式について解説。
更新日:2024.12.27
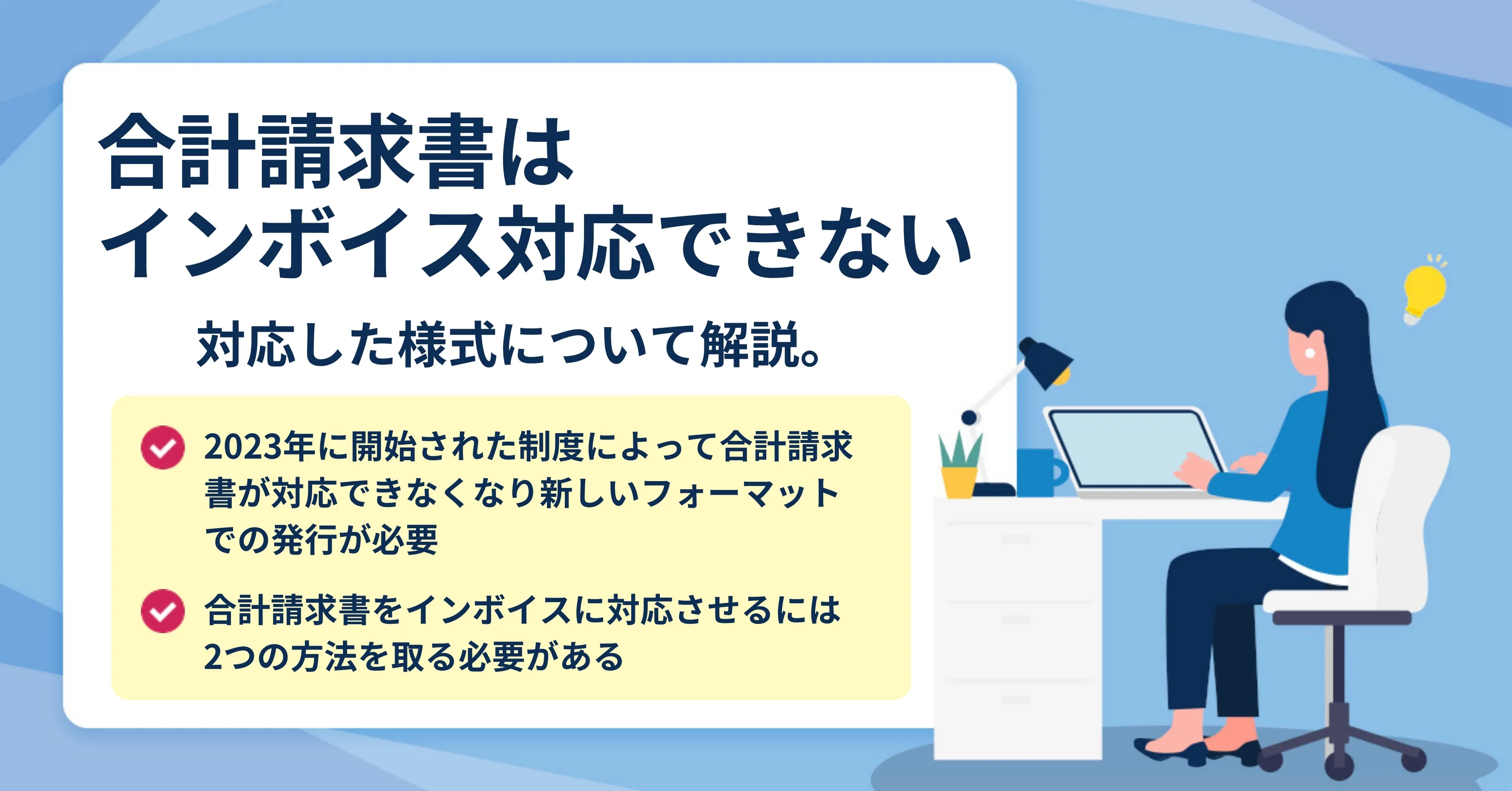
ー 目次 ー
合計請求書とは、複数の取引を1つの書類にまとめた請求書のことです。2023年に開始されたインボイス制度によって、従来の合計請求書が対応できなくなり、新しい様式での発行が必要になります。
今回の記事では、合計請求書がインボイス対応できない理由や、インボイス制度に対応した合計請求書の様式をご紹介します。
|
▼今回の記事の内容
|
インボイスに登録したばかりで切り替えが上手くいっていない経理担当の方や個人事業主の方はぜひ最後までご覧ください。
請求書・支払明細、あらゆる帳票に対応!
合計請求書ではインボイス対応できない
合計請求書とは、複数の取引をまとめて1枚の請求書に記載する形式のことです。
合計請求書のメリットとして、すべての請求書の支払期日と請求残高を一括して記載できるため、発行側も受取側も経理業務の効率化に大きく貢献できるといったメリットがあります。
しかし、従来使用されていた合計請求書は2023年から開始されたインボイス制度に対応することができません。インボイス制度における適格請求書としての役割を果たすには、納品書を合わせて発行するなどの方法を取る必要があるのです。この方法についてはのちほど詳しく説明します。
合計請求書がインボイス対応できない理由
合計請求書がインボイス対応できない理由は以下の2点です。
- 理由①|インボイスに必須の項目が不足している
- 理由②|取引内容が明記されていない
ここからは、それぞれの理由について詳しく解説します。
理由①|インボイスに必須の項目が不足している
1つ目の理由は、インボイスに必須の項目が不足していることです。インボイスにおける適格請求書には、以下の3つの項目を記載する必要があります。
- インボイス発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
ここからは、それぞれの項目について見ていきます。
1. インボイス発行事業者の登録番号
インボイス制度に登録した事業者には、税務署から登録番号が交付されます。この登録番号は、適格請求書を発行する事業者であることを証明するものであり、記載がない請求書は適格請求書として認められません。
合計請求書は複数の取引をまとめるため、個々の取引における登録番号の記載が漏れてしまう可能性があります。
2. 適用税率
取引内容によって、標準税率(10%)または軽減税率(8%)が適用されます。適格請求書には、それぞれの取引に適用される税率を明確に記載する必要があります。
合計請求書では、複数の取引の税率が混在している場合、個々の取引の適用税率を正確に記載することが難しい場合があります。
3. 税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度では、標準税率と軽減税率の取引を区分して消費税額を計算し、それぞれを記載する必要があります。
合計請求書では、複数の取引の消費税額が合算されてしまうため、税率ごとの消費税額を正確に記載することができません。
理由②|取引内容が明記されていない
合計請求書は、複数の取引をまとめて1枚に記載するため、個々の取引内容が十分に明記されていない場合があります。インボイス制度では、適格請求書として認められるためには、以下の取引内容を具体的に記載する必要があります。
|
項目 |
内容 |
|
商品名または役務の内容 |
具体的にどのような商品やサービスを提供したのかを記載 |
|
数量 |
商品やサービスの数量を記載 |
|
単価 |
商品やサービスの単価を記載 |
|
適用税率 |
標準税率(10%)または軽減税率(8%)のいずれが適用されるのかを記載 |
合計請求書では、これらの情報が省略されたり、大まかにまとめられたりすることがあります。例えば、「商品代金一式」といった記載では、具体的な商品や数量が不明確であり、適格請求書として認められません。
インボイス制度では、取引内容を明確にすることで、消費税の仕入税額控除を適正に行うことを目的としています。そのため、合計請求書であっても、個々の取引内容を詳細に記載することが求められます。
合計請求書をインボイス対応させる方法
合計請求書をインボイスに対応させるには、以下の2つの方法を取る必要があります。
- 方法①|合計請求書に各取引の納品書を添付する
- 方法②|合計請求書内に適格請求書としての要件を取り入れる
ここからは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
方法①|合計請求書に各取引の納品書を添付する
1つ目の方法は、合計請求書に各取引の納品書を添付することです。取引内容、適用税率、消費税額などが記載された納品書を添付すれば、インボイス制度に対応することができます。
合計請求書と納品書は必ず紐づけて管理し、必要な時にすぐに添付できるような状態にしておきましょう。
方法②|合計請求書内に適格請求書としての要件を取り入れる
2つ目の方法は、合計請求書内に適格請求書としての要件を取り入れることです。合計請求書自体に、先述したインボイス制度で求められる項目(インボイス発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等)を記載すれば、インボイス制度に対応することができます。
インボイス制度に登録している事業者の方が合計請求書を発行する場合は、合計請求書内に適格請求書の要件を揃えるように気をつけましょう。
合計請求書だけではインボイス対応できない!要件を満たすようにしよう!
今回の記事では、合計請求書がインボイス制度に対応できない理由とその対策について詳しく解説しました。
従来の合計請求書は、複数の取引をまとめて記載するため、インボイス制度で求められる詳細な情報が不足している場合が多く、そのままでは適格請求書として認められません。具体的には、インボイス発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額、そして個々の取引内容(商品名、数量、単価など)が明記されていないことが問題となります。
今回の記事が、中小企業の経理担当者や個人事業主の方々にとって、インボイス制度への対応を進める上で少しでもお役に立てれば幸いです。インボイス制度は複雑な部分もありますが、正しく理解し、適切な対応を取ることで、スムーズな取引を実現することができます。ぜひ、この記事を参考に、インボイス制度への対応を進めてみてください。
請求書・支払明細、あらゆる帳票に対応!









