発注書と請求書の違いとは?発行タイミングを取引の流れで紹介
更新日:2025.01.30
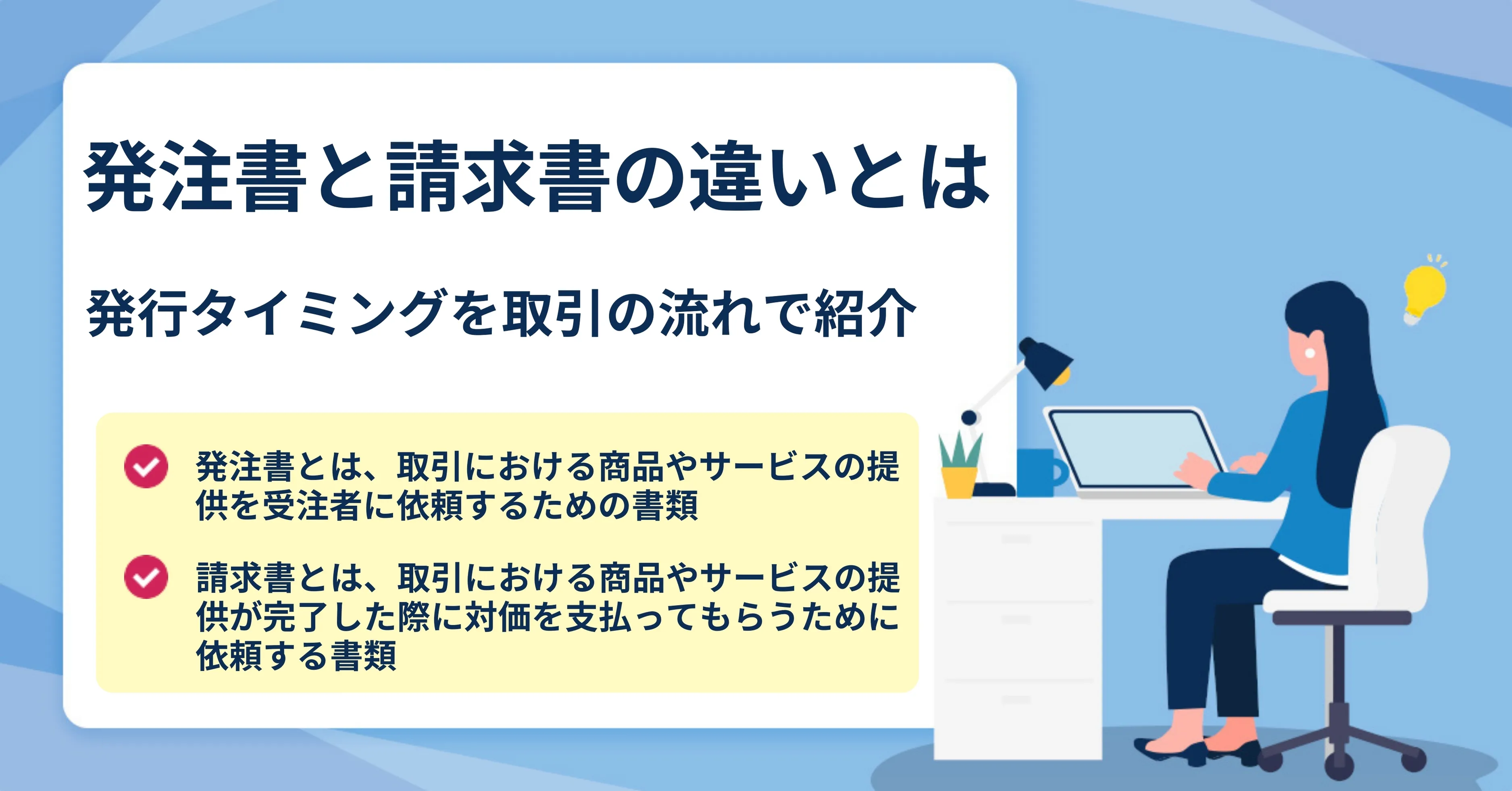
ー 目次 ー
発注書や請求書はビジネスシーンで頻繁に使用される書類です。ほかにもさまざまな書類が取引で使用されるため、それぞれの役割や書き方などを明確に把握していない方も少なくありません。
また、2023年10月に施行された「インボイス制度」の影響も受け、ルールに従わない場合には税制上のトラブルになりかねないことから、それぞれの書類の内容や役割、ルールの把握が必要です。
本記事では、発注書と請求書の違いについて、発行タイミングや書き方を交えて解説します。
【結論】発注書と請求書はその役割が大きく違う!それぞれのポイントを紹介
発注書と請求書では、それぞれ役割や内容、また発行タイミングなどが大きく異なります。どちらも取引で頻繁に使われる書類であるため、ビジネスマナーとしてその違いについて知っておきましょう。
ここでは、発注書と請求書について、それぞれのポイントを解説します。
- 発注書とは、取引内容を相手へ依頼する書類
- 請求書とは、取引が完了した際の対価の支払いを依頼する書類
発注書とは、取引内容を相手へ依頼する書類
発注書とは、取引における商品やサービスの提供を受注者に依頼するための書類です。取引内容の依頼をするためのものであり、取引のスタートにおいて大切な役割を担っています。
似たような書類で「注文書」が存在しますが、発注書と同様に扱われています。
請求書とは、取引が完了した際の対価の支払いを依頼する書類
請求書とは、取引における商品やサービスの提供が完了した際に対価を支払ってもらうために依頼する書類です。基本的に受注者が発注者に対して発行するものであり、さまざまなルールが絡む重要な書類となっています。
書き方や扱い方を誤ると大きなトラブルになりかねないことから、記載事項や発行タイミングなどの細かなルールを知っておくことが必要です。
発注書や請求書が登場するタイミングを取引の流れに沿って紹介!
取引では発注書や請求書のほかにさまざまな書類が使用されます。それぞれ内容や役割があり、発行タイミングや発行者、また書き方などが異なります。
取引においてはビジネスマナーとなる基本的な知識であることから、どのようなタイミングでどのような役割を持った書類が必要であるかをあらかじめ把握しておきましょう。
ここでは、発注書や請求書が登場するタイミングについて、取引の流れに沿って紹介します。
- 見積依頼
- 発注
- 納品と受領
- 請求
- 入金
①見積依頼(見積書)
取引を始める前に、種類や数量、期間などのシミュレーションを立てた見積りが必要です。
この際に「見積書」を発行し、取引先に対して取引の内容や数量、納期などを、予算やニーズなどを踏まえて検討してもらいます。
②発注(発注書)
見積書の内容を踏まえて、取引内容が確定すれば発注者から受注者に対して発注をおこないます。
この際に「発注書」を発行し、発注書には最終的に依頼したい商品・サービスの種類や数量、納期を明記します。
③納品と受領(納品書・検収書・受領書)
取引内容にしたがって商品・サービスの準備が完了すると、発注者に対して成果物の納品をおこないます。
この際に、受注者は「納品書」を発行し、発注書で依頼を受けた内容に相違がなかったことを発注者に対して伝えなければなりません。一方で、発注者は納品内容に問題がなければ、「受領書」を発行し、請求対応に移行して問題ないことを受注者に伝える必要があります。
なお、提供された成果物が商品であった場合には、発注者は検収をおこない、内容に問題がなければ「検収書」も発行します。
④請求(請求書)
受領書をもとに依頼に相違がないことを確認したら、対価の支払いを取引先へ依頼する必要があります。
この際に「請求書」を発行し、取引内容や支払先情報、また支払期日などを取引先へ伝えます。
なお、請求書はインボイス制度の影響を大きく受けた書類であり、細かなルールが定められていることから注意して対応を進めなければなりません。
⑤入金(領収書)
発注者は請求書の内容をもとに、受注者に対して支払対応をおこないます。
受注者は請求書の内容どおりの支払を確認したら、発注者に対して「領収書」を発行します。
発注書や請求書の書き方とは?テンプレートを紹介
発注書や請求書は法律や商慣習上から書き方が定められています。もし必要な記載事項がない場合には、税制上のトラブルになりかねません。これは取引先にも影響があることから、トラブルを避けるためにも基本的な書き方を知っておきましょう。
ここでは、発注書や請求書の書き方について、テンプレートを交えて紹介します。
発注書
発注書はインボイス制度による影響は受けない書類であるものの、書き方は商慣習上で決まっています。取引で依頼したい商品・サービスの数量や単価、合計金額なども含めた以下の記載事項が必要です。
- 受注事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 発行事業者の氏名または名称、登録番号
- 番号
- 備考
発行日:20XX年XX月XX日 発注書 〇〇株式会社 御中 自社名 件名:〇〇の発注について
※軽減税率(8%)の対象商品
|
請求書
請求書では、請求の対象となる取引内容や消費税額などを明記する形で作成しなければなりません。インボイス制度の影響を大きく受けた書類であるため、制度を利用する際には以下の記載事項が求められます。
- 受領事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 発行事業者の氏名または名称、登録番号
- 支払先情報(支払方法や口座情報など)
- 請求書番号
- 備考
発行日:20XX年XX月XX日 請求書 〇〇株式会社 御中 自社名 件名:〇〇のご請求について
※軽減税率(8%)の対象商品
|
まとめ|発注書や請求書の役割を理解し、取引先に失礼がないようにしよう
本記事では、発注書と請求書の違いについて、発行タイミングや書き方を交えて解説します。
発注書や請求書はビジネスでは何度も登場する書類であり、経理に携わる者として最低限の知識はおさえておかなければなりません。また、インボイス制度の施行によって新しいルールも適用されているため、書類にまつわるルールの把握も大切です。
書類で起こる1つのミスが大きなトラブルに発展し、取引先を巻き込むリスクもあります。このような事態を避け、取引先との良好な関係を築くためにも、法令の動向も踏まえた対応をおこなっていきましょう。










