【例文あり】請求書をメールで送付する際の書き方とは?記載項目やメリットを解説。
更新日:2025.09.08
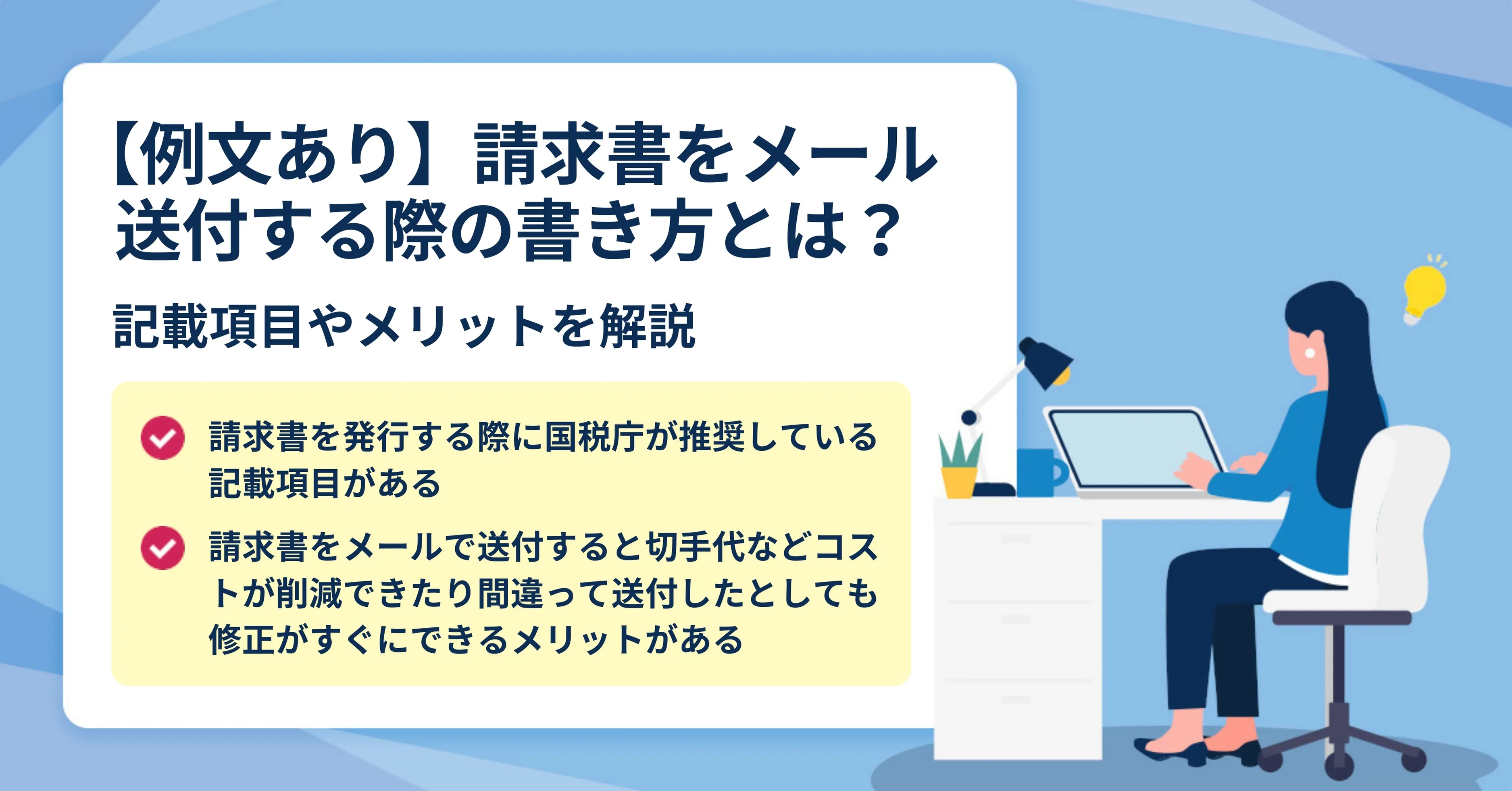
ー 目次 ー
「請求書をメールで送付しても大丈夫だろうか?」「初めてのメール送付、どんな文面にすれば失礼がないだろう?」
こう悩んでいる方は少なくありません。
顧客に無断で請求書をメール送付すると、
- マナー違反と受け取られる
- 信頼関係に悪影響を及ぼす
といったリスクがあります。そのため、事前に了承を得ておくことは非常に重要です。
初めての送付時は以下のような文面を用意しましょう。
|
株式会社XX いつもお世話になっております。 XX株式会社XX部のXXXXと申します。 この度、請求書の送付方法をメールに変更させていただきました。 YYYY年MM月分の請求書をPDFにて添付いたしました。 ご確認いただき、お支払いのほどよろしくお願いいたします。 もし、紙媒体での請求書をご希望の場合は、お気軽にお申し付けください。 請求金額:XXXXXX円 【振込先】 |
さらに、送付前には以下を必ず確認しましょう。
- 売上集計の正確性
- 請求書の記載漏れ
- PDF形式での送付
- 件名・ファイル名の簡潔さ
- 請求書控えの保存
この記事では、請求書メール送付前の確認事項、具体例文、注意点、そして紙からメールに切り替える際のポイントまで詳しく解説します。
現場で役立つ実践的な内容をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも請求書はメールで送付しても良い
結論から言うと、請求書はメールで送付しても問題ありません。
請求書は、取引の事実を証明するための書類であり、法律上、紙媒体での発行や郵送が義務付けられているわけではありません。請求の意思表示があれば、送付方法にかかわらず法的に有効です。そのため、メールで送付した請求書(電子請求書)は紙の請求書と同等の効力を有します。
近年、テレワークの普及、電子帳簿保存法の法改正、ペーパーレス化の推進に伴い、メールでの請求書送付に切り替える企業が増えています。
請求書をメールで送る際の件名・本文の書き方【例文を紹介】
この章では、請求書をメールで送る際の件名と本文の書き方について、例文をまじえてご紹介します。件名に「請求書」を記載したり、メールで送る際はPDFで作成したりすることで、トラブルを回避できます。
件名
件名に「請求書」という文言を入れることで、相手に請求書であることを明示します。また、いつの請求書なのかを明記することで、取引先が迅速に請求書を特定できます。
以下のように、請求書の件名を記載します。
- 「XXXX年X月の請求書のご案内|会社名」
- 「XXXX年X月分請求書送付のご連絡」
請求書の送付後は、取引先へどのような件名で請求書を送付したかを伝えておくことが重要です。
例文①:原本を郵送しない場合の例文
請求書をメールに添付して原本を送らない場合は、請求書はPDFにして送るとよいでしょう。WordやExcelと違い、請求内容などが変更できないため、改ざんのリスクを避けられます。
請求書をPDFでのみ送付する場合は、以下のような文章で送りましょう。
|
株式会社XX 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り、ありがたく御礼を申し上げます。 早速ではございますが、XXXX年XX月月分の請求書を添付ファイルにて送付申し上げますので、何卒ご査収下さい。 お手数ではございますが、お手元に届きましたら、内容をご確認の上、期日までにお支払いいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 ご請求期間: XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日 上記についてご不明な点がございましたら、お手数ではございますがお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。何卒、宜しくお願い致します。 |
例文②:原本も郵送した場合の例文
取引先によってはメールで送付と合わせて、原本郵送を希望する場合があります。原本も同時に送付する場合の例文は以下です。
|
株式会社XX いつもお世話になっております。 XXのお取引に関して請求書を添付しております。ご査収のほどよろしくお願いいたします。 【添付内容】 なお、請求書原本も併せて郵送させていただきました。 本請求書中に記載の振込先へ、XXXX年XX月XX日までにお振込みくださいますようよろしくお願い申し上げます。 また、お手数をおかけいたしますが、添付ファイルが開封できないなど不都合な点やご不明な点がございましたら、ご一報いただきたく存じます。 何卒よろしくお願いいたします。 |
例文③:初めてメールで請求書を送付した場合の例文
請求書の送付を電子データでメール送付に切り替えた際の最初のメールの文面を紹介します。
請求書をPDFでのみ送付する場合は、以下のような文章で送りましょう。
|
株式会社XX いつもお世話になっております。 XX株式会社XX部のXXXXと申します。 この度、請求書の送付方法をメールに変更させていただきました。 YYYY年MM月分の請求書をPDFにて添付いたしました。 ご確認いただき、お支払いのほどよろしくお願いいたします。 もし、紙媒体での請求書をご希望の場合は、お気軽にお申し付けください。 請求金額:XXXXXX円 お支払方法:下記銀行口座へお振込みください。 【振込先】 |
請求書をメール送付する際の記載項目
請求書には定められた記載項目やフォーマットはありません。ただし、請求書を発行する際に、国税庁が推奨している記載項目があります。具体的な項目については下記の通りです。
- タイトル...「御請求書」や「御見積書」「○月分御請求書」などと記載する。
- 請求番号...社内で請求書の管理に用いる通し番号。
- 宛先...取引先の会社名・住所・担当者名を記載する。
- 発行日...締め日の日付を記載しても良い。
- 作成者...一般的に会社の角印を捺印する。発行者の会社名と住所が記載されていれば、印鑑が必要ない場合もある。
- 請求明細...商品名・単価・数量・消費税率・消費税額・合計金額・備考などを記載する。
- 振込先...振込先の口座情報や支払期限を記載する。振込手数料を取引先に負担してもらう場合は、「誠に勝手ながら、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします」と記載しておく。
- 支払期限...取引先の社内規定により期限を定める。
2023年10月から開始されるインボイス制度では、取引先の課税事業者が仕入税額控除を受けられるように、以下の項目を請求書に記載し、適格請求書として発行する必要があります。
- 登録番号(課税事業者のみ登録可)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
上記の3つの項目を含めて作成しましょう。また、適格請求書を発行できるよう適格請求書発行事業者への登録申請も済ませましょう。
請求書はメールで送付する際のチェックポイント
請求書は、取引先へ代金を請求するための書類のことを指します。請求書と見積書はよく間違われることがありますが、見積書は取引前に発行される見積もり書類です。請求書は法律上の義務がないため、メールで送付しても問題ありません。
この章では、請求書を送付する前に確認しておくべき3つのポイントを解説します。
メール送付で問題ないか取引先に了承を得る
請求書の取り扱いについては、取引先に事前に確認することが重要です。取引先に了承なくメールで送付すると、マナー違反になる場合があります。
一部の企業では、原本でなければ請求書と認めないというルールがあるため、請求書の送付時には原本を郵送するべきか確認しましょう。
また、メールのやり取りが多い取引先の場合、請求書が見落とされる可能性があります。必ず事前に送付時のルールなどを確認しましょう。
担当者のメールアドレスを確認する
取引窓口と経理処理を担当する人物が異なる場合があるため、請求書を送付する宛先を必ず確認しましょう。
正しい担当者のメールアドレスに送付しなければ、請求書が適切に処理されない可能性があります。
押印形式を確認する
請求書に押印する方法には、捺印をスキャナーでPDF化する方法と、データ化した印鑑を使用する方法があります。
後者の場合は、取引先へ事前に確認が必要です。電子化した印鑑は法的効力がないため取引先によっては認めないケースがありますので、事前に使用可否を確認しておきましょう。
請求書のメール送付における5つの注意点
請求書のメール送付には、いくつかの注意点があります。注意点を押さえずに処理するとトラブルの元になりますので、必ず確認してから請求書のメール送付を行うようにしましょう。
事前に取引先の売上を集計する
請求書を細かく作成し送付すると、経理業務が煩雑化する可能性があります。そのため、事前に取引先の売上を集計してから請求書を作成することが重要です。
売上の集計によって、一括請求やまとめ請求など効率的な請求方法を選べます。
請求書に記載漏れがないか確認する
請求書の記載事項に不備があると、トラブルになる可能性があります。請求書を送付する前には必ず記載漏れがないかを確認することが必要です。
請求書に記載する金額や支払い期日など、すべての項目が正確に記載されていることを確認しましょう。
請求書はPDF形式で送付する
請求書のファイル形式は、改ざんのリスクが低いPDF形式を使用することが推奨されます。WordやExcel等で送付してしまうと、開封した時に誤って編集してしまいトラブルにつながる可能性があります。作成した請求書をPDFに変換して送付しましょう。
件名やファイル名を簡潔に記載する
請求書をメールで送付する際は、メールを開かなくても請求であることが分かるように、件名に請求書であることを記載しておくとよいでしょう。
また、ファイル名や件名も同様に、請求書であることや請求先、商品やサービス名、請求年月などを明記すると便利です。ファイルの命名規則をあらかじめ決めておくと、管理しやすくなります。
請求書の控えは必ず保管する
所得税法または法人税法上、請求書は発行側・受領側ともに一定期間の保存が必要と定められています。請求書の保管期間は、法人は7年間、個人事業主は5年間です。
この期間内に請求書の控えを保管しておくことが重要です。
請求書をメールで送付する2つのメリット
請求書をメールで送付すると、切手代やインク代のコストが削減できたり、間違って送付したとしても修正がすぐにできたりします。
メリットを理解した上で、請求書のメール送付の切り替えを検討するとよいでしょう。この章では、請求書をメール送付する2つのメリットを、それぞれ詳しく解説します。
郵送にかかる手間やコストを削減できる
請求書を郵送する場合、切手代やコピー用紙代、インク代などの費用がかかりますが、メールで送付することでコストを削減できます。年間に換算すると大幅な経費削減につながるでしょう。
また、請求書の送付準備に伴う残業も減らせます。請求書を電子データ化して保存することによって、保存場所の節約や作業の効率化、環境問題への取り組みにも貢献できます。
すぐに修正できる
請求書をメールで送付すれば、もしミスがあった場合でもすぐに修正が可能です。これにより、トラブルを未然に防げます。
メール送付に切り替えることで、送付先の宛名や住所の書き間違いによる未着や、切手不足によって取引先に配達料金が請求されるといったトラブルも防げます。
また、紙媒体で大量の請求書を出力する際にプリンタが故障してしまった場合、業者による修理に時間を要し、発行が遅れる可能性もあります。メールで送付することで、リスクを回避できるでしょう。
請求書の送付手段をメールに変えるタイミング2選
今まで紙で発行していた請求書の送付手段を、メールに変えるタイミングについて解説していきます。
自社サービスの料金変更や、2023年10月から始まるインボイス制度開始のタイミングが、キリよく請求書を紙発行からメール送付に切り替えられる良いタイミングになります。
商品やサービスの料金変更
自社の商品やサービスの料金を変更する場合、請求書の送付をメールに変えたい旨を提案してみるとよいでしょう。
料金変更など何かしらの方針変更を理由に、メールでの送付にフローを変更することが交渉しやすくなります。また、請求書の内容変更と同時に送付方法も変更することで、効果的なコミュニケーションを図れます。
インボイス制度開始の2023年10月から
2023年10月からはインボイス制度が開始されます。この制度により、課税事業者は請求書の記載項目が増え、経理業務も煩雑になるでしょう。しかし、インボイス制度の導入に合わせて請求書の送付方法をメールに切り替えることで、スムーズな対応や社内の業務効率化を図れます。
インボイス制度のタイミングでメール送付に切り替えることは、将来的な業務の負担軽減に繋がる重要な選択肢です。
請求書をメール送付して社内の業務を効率化しよう
請求書はメールで送付しても問題ありませんが、あらかじめ取引先にメール送付でも問題ないかや原本が必要かを確認しておくことが大切です。
また、件名や本文をわかりやすく簡潔なものにし、添付する請求書もPDFにして、わかりやすいファイル名にしておくようにしましょう。今まで請求書を紙で送付していた企業は、自社商品やサービスの料金変更、インボイス制度開始のタイミングで、メール送付に切り替えると社内の業務効率化やコスト削減につながります。
メールで請求書を送付することで、郵送の手間やコストを削減することが可能です。また、請求書の送付状況をリアルタイムで確認できるので、請求漏れや遅延を防げます。請求書をメールで送付する際には、宛名や請求内容を間違えないように正しく送付しましょう。









