請求書に消費税は記載するべき!表記方法や作成時の注意点も解説
更新日:2025.03.03
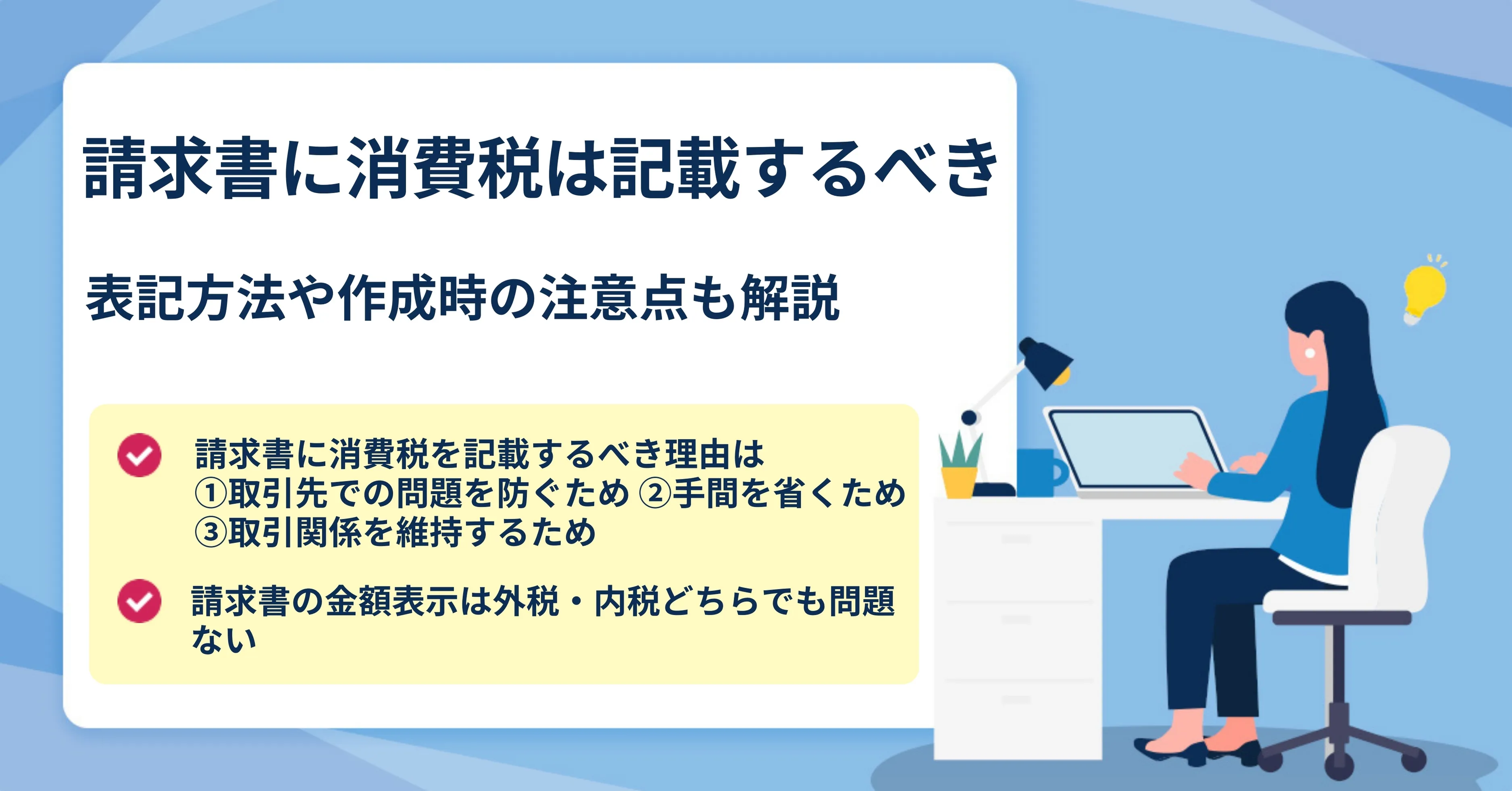
ー 目次 ー
企業間の取引では、請求書への消費税の記載は重要な要素の1つです。財務省によると、不特定かつ多数の者に対する価格表示には総額表示が義務づけられていますが、これは値札や新聞、ポスターなどが対象です。一方で、企業間取引の請求書では総額表示の義務はありません。
このような消費税にまつわるルールは、法律や制度で定められています。もし消費税の記載方法を誤った場合、取引先との関係に支障をきたしたり、余計な手間が発生したりする可能性があるため注意が必要です。
本記事では、請求書への消費税の記載について、表記方法や作成時の注意点をあわせて解説します。
請求書に消費税を記載するべき3つの理由とは?
請求書への消費税の記載は、法律で義務づけられているわけではありません。しかし、取引先との関係を円滑に進めるためにも、とくに最終的な請求金額は税込での記載がおすすめです。
ここでは、請求書に消費税を記載するべき3つの理由について解説します。
①取引先での問題を防ぐため
請求書に消費税を記載することで、取引先の経理担当者が金額の計算を間違えるリスクを防げます。
もし、消費税の記載がない場合、取引先の担当者が金額を誤って計算してしまい、本来振り込まれるべき金額が振り込まれないおそれがあります。
このような事態を防ぐためにも、請求書を作成する際には取引先の担当者が金額を正しく認識できるように、消費税の記載を忘れないようにしましょう。
②手間を省くため
消費税の記載がない請求書は、取引先から確認の連絡が入る可能性があります。この内容によっては請求書の再発行が必要になることも考えられ、双方に余計な手間が発生してしまいます。
このような状況を避けるためにも、請求書には消費税を明確に記載しておくことが大切です。
③取引関係を維持するため
請求書への消費税の記載は、取引先とのトラブルを未然に防げます。消費税の明確な記載があれば、取引金額に関する認識の相違を防げるため、取引先の経理処理がスムーズに進められます。
結果、取引先からの信用が高まり、良好な取引関係が築ける可能性が高くなるでしょう。
請求書の金額表示は外税・内税どちらでも問題ない
請求書における消費税の表示方法は、外税(税抜価格)表示と内税(税込価格)表示の2つがあります。どちらの表示方法を採用するかは事業者の判断に委ねられており、法律による規定はありません。
外税表示の場合は、商品やサービスの本体価格と消費税額が明確に分かれているため、税抜価格の把握が容易です。また、軽減税率対象品目がある場合も、税率ごとの消費税額を分かりやすく表示できます。一方で、最終的な支払金額を把握するには計算が必要です。
内税表示の場合は支払金額が一目で分かるため、取引先の経理処理がスムーズに進められます。しかし、税抜価格を確認する際には逆算が必要で、複数の税率が適用される場合は計算が煩雑になる可能性があります。
金額をどちらの方法で表示するかは、取引先との慣習や自社の管理体制などを考慮して判断するとよいでしょう。最終的な請求金額は税込表示が推奨されているため、外税表示を採用する場合でも、請求書の最後には税込の合計金額を記載することをおすすめします。
なお、以下の関連記事では、税込・税抜が混在する請求書の書き方について解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:税込・税抜が混在する請求書の書き方を解説!無料テンプレートやインボイス制度の対応方法も
請求書の記載項目とは?インボイス制度での書き方も紹介
従来、通常の請求書を作成する際には、商慣習上で定められた記載事項を満たしていれば取引に支障はありませんでした。
しかし、インボイス制度の開始にともなって、「インボイス(適格請求書)」の発行・保存が必要となりました。インボイスは従来の請求書の記載項目から、いくつかの項目が追加されています。
ここでは、請求書の記載項目について、インボイス制度での書き方もあわせて解説します。
一般的な記載項目
請求書の一般的な記載項目は以下のとおりです。
- タイトル(請求書)
- 宛名(取引先の名称)
- 発行日
- 取引年月日
- 取引内容(品名・数量・単価)
- 請求金額(税込)
- 支払期日
- 振込先情報
- 発行者情報(自社の名称・住所・連絡先)
消費税の記載に法的な義務はありませんが、取引先とのトラブルを避けて、円滑にやりとりするために記載が推奨されています。
インボイス制度に対応した追加の記載項目
2023年10月1日から開始されたインボイス制度では、基本の記載項目にくわえて以下の項目の記載が必要です。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
これらの項目が記載されていないと、インボイス(適格請求書)として認められず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。インボイス制度に対応した請求書を作成する場合は、記載項目の漏れがないよう注意が必要です。
仕入税額控除の計算の仕方とは?
仕入税額控除とは、消費税の二重課税を防ぐために設けられた制度です。仕入税額控除では、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引けるようになります。
請求書は消費税額を確認するための証拠書類となるため、適切な納税額を算出するためには消費税の記載が重要です。請求書の記載内容に誤りがあると、正確な仕入税額控除の計算ができなくなる可能性があります。
ここでは、仕入税額控除の計算の仕方について解説します。
①全額控除
全額控除は、課税仕入れにかかるすべての消費税を控除できる方式です。課税期間の課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上の場合に適用できます。
全額控除はシンプルな計算方法ですが、適用条件が厳しいため、利用できる事業者は限定されます。
②個別対応方式
個別対応方式は、課税仕入を「課税売上に係る仕入」「非課税売上に係る仕入」「共通仕入」の3つに区分して計算する方式です。以下の計算式で仕入税額を算出します。
- 売上にかかる仕入+(共通仕入×売上割合)
個別対応方式は正確な仕入税額控除が可能ですが、仕入の区分け作業に手間がかかるため、経理処理の負担が大きくなります。
③一括比例配分方式
一括比例配分方式は、課税仕入を個別に区分できない場合に使用する方式です。以下の計算式で仕入税額を算出します。
- 仕入れにかかる消費税額×売上割合
一括比例方式は個別対応方式と比べて計算が簡単ですが、正確な仕入税額控除ができない可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
④簡易課税制度
簡易課税制度は、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の場合に選択できる制度です。簡易課税制度では、以下の計算式で仕入税額を算出します。
- 課税標準額に対する消費税額×みなし仕入率
また、みなし仕入率は事業区分ごとに以下のように定められています。
- 第1種事業(卸売業):90%、
- 第2種事業(小売業):80%、
- 第3種事業(製造業など):70%
- 第4種事業(サービス業など):60%
- 第5種事業(不動産業など):50%
- 第6種事業(金融・保険業など):40%
まとめ|消費税が表記された請求書も請求書作成ツールで効率的に作成しよう
本記事では、請求書への消費税の記載について、表記方法や作成する際の注意点をあわせて解説しました。
企業間の取引では、請求書への消費税の記載に法的な義務はありません。しかし、取引を円滑に進めるためには、最終的な請求金額を税込表示にすることが推奨されています。消費税の記載があることで取引先での金額の誤認を防いで、経理処理の手間を省けます。
また、2023年10月から開始されたインボイス制度では、登録番号や税率ごとの消費税額など、新たな記載項目が必要です。混乱しがちな請求書への消費税の記載も、請求書作成ツールを使用すればミスなく記載できます。
取引先との良好な関係を維持して、効率的な経理処理を実現するためにも、請求書作成ツール導入の検討がおすすめです。










