請求書の時効はいつ?売掛金や債券の回収が可能な期限について徹底解説。
更新日:2025.09.04
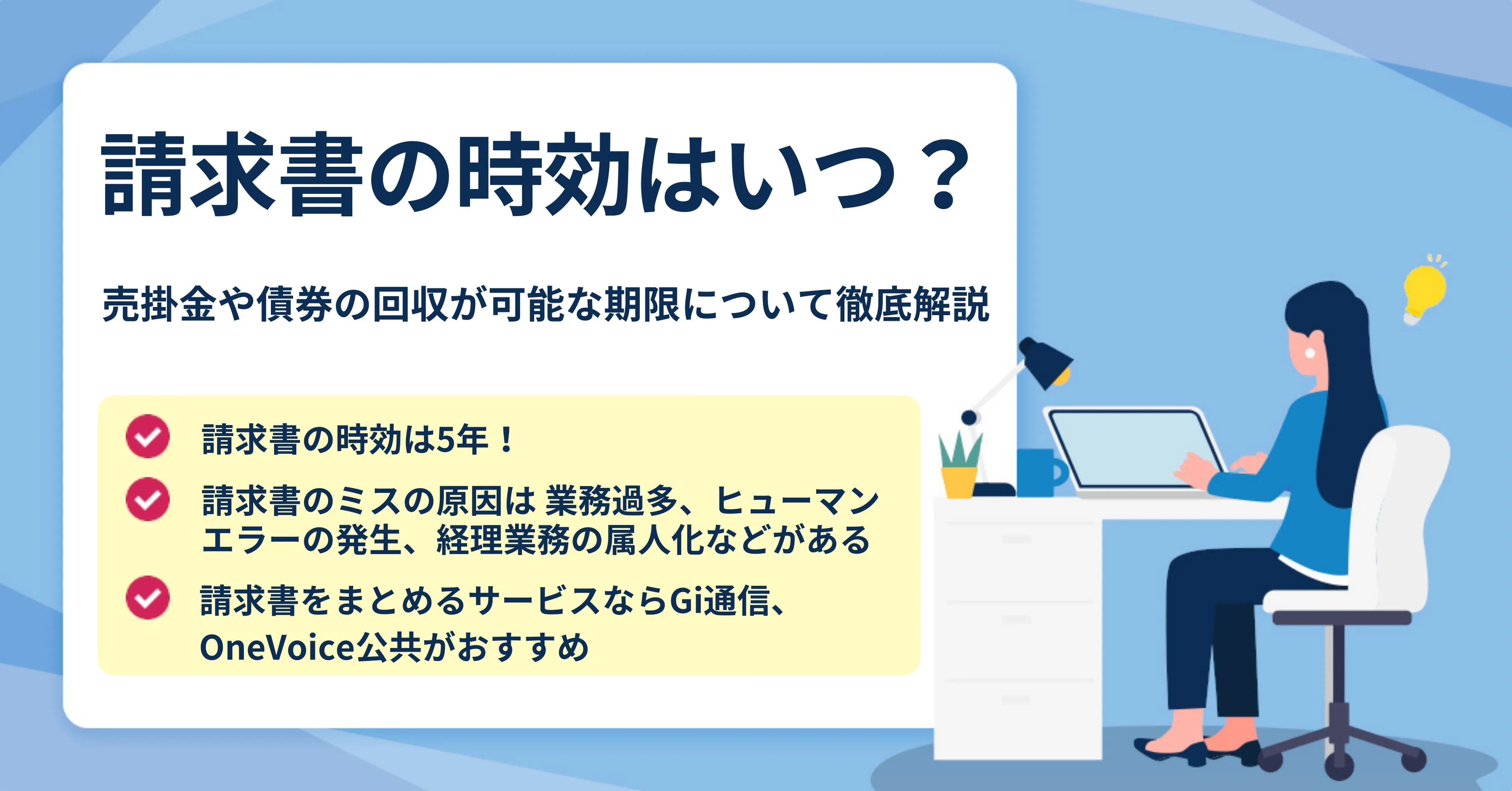
ー 目次 ー
請求書には時効が存在することをご存知でしょうか?時効とは、一定期間が経過すると権利を行使できなくなる制度です。
請求書の場合、時効が成立すると、たとえ未払いの債権があっても、法的に回収することが難しくなってしまいます。
本記事では、請求書の時効期間、時効が成立した場合の影響、時効を中断・延長する方法、未払いの請求書への対処法などを詳しく解説します。請求書に関するトラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を実現するために、ぜひ参考にしてください。
- 請求書の時効期間
- 時効が成立した場合の影響
- 請求書が未払いの場合の対処法
- 時効を中断・延長する方法
- 請求書をまとめるサービス
請求書の時効は5年!
請求書の時効は、民法第166条の1により、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間と定められています。(※)以前は支払期日の翌日から2年間が経過した時点で時効が成立していましたが、2020年に改正民法が施行され、請求書の時効が2年から5年に延長されました。(※)
従来の民法では、業種によって請求書の時効の成立期間に違いがあります。例えば、"運送賃に係る債権・旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権"などは1年、"医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権""工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権"などは3年でした。(※)現在は改正民法によって業種による差がなくなり、業種にかかわらず、請求書の時効は一律5年間に統一されています。
※出典:e-Gov法令検索「民法」
※出典:法務省「民法(債権関係)の見直し~「民法の一部を改正する法律」の概要~」
※出典:厚生労働省「民法改正に伴う消滅時効の見直しについて」p4
請求書の時効を迎えるとどうなる?
請求書を発行してから5年が経過すると、債権者が債務者に請求する権利が失われます。(※)未払いの売掛金があっても取引先から回収できなくなるため、債権者は請求書が時効を迎える前に未払金を回収しなければなりません。
取引先から送られてきた請求書に応じて代金を支払わないとどうなるかというと、まずは先方から問い合わせの連絡が入るのが一般的です。連絡を受けたにもかかわらず支払いに応じないと、内容証明が送られてきます。内容証明を使った催告は、時効中断の事由の一つです。内容証明が送付されると、時効期間が6カ月間延長されます。(※)
それでもなお支払いに応じないと、簡易裁判所から支払督促が発付されます。このとき、未払いを解消するか、あるいは異議申し立てを行わないと、仮執行宣言が発付され、強制執行の申し立てが可能です。仮執行宣言を行っても支払いが行われなかった場合、強制執行が実施され、債務者の財産が強制的に差し押さえられることになります。
未払いが単なるミスだった場合、ここまで問題がこじれることはないかもしれません。しかし、未払いの状態が続くと取引先との関係が悪化する恐れがあります。早急に支払い、未払いミスの再発防止に努めましょう。
※出典:法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」p3〜4,p8
請求書に関する基本は、以下の記事でご確認ください。
【請求書とは?必要な理由や確認すべきポイントを解説】
https://media.invoice.ne.jp/column/Invoices-and-receipts/with-invoice.html
請求書が未払いの場合の対処法
請求書を発行したにもかかわらず、支払期限を過ぎても入金がない場合は、適切な対処が必要です。放置すると、資金繰りに悪影響を及ぼすだけでなく、取引先との関係が悪化する可能性もあります。
請求書が未払いの場合、以下の手順で対処を進めることが一般的です。
手順
説明
1. 取引先に連絡する
2. 支払期日の再設定
3. 督促状を送付する
4. 内容証明郵便で送付する
5. 法的措置を検討する
請求書の事項を延長するための方法
請求書の支払期限を延長するには、取引先との合意が必要です。合意の内容は書面に残しておくことが望ましいです。
また、請求書には時効があり、時効が成立すると債権を回収できなくなる可能性があります。時効を中断するためには、催告を行う必要があります。催告とは、債務者に対して債務の履行を請求する行為です。催告を行うことで、時効の完成を一時的に阻止することができます。
催告は、口頭や電話でも行うことができますが、証拠を残すために、書面で行うことが一般的です。内容証明郵便を利用すれば、確実な証拠を残すことができます。
請求書が未払いの場合は、早めに対処することが重要です。放置すると、時効が成立したり、取引先との関係が悪化したりする可能性があります。上記の方法を参考に、適切な対応を行いましょう。
請求書をまとめるサービスならGi通信、OneVoice公共がおすすめ
請求書の処理業務を効率化するサービスはさまざまですが、バラバラに届く請求書を一括で管理したい場合は、株式会社インボイスの請求書おまとめるサービスである、Gi通信やOneVoice公共を利用するのがおすすめです。
Gi通信は通信料金の請求書を、OneVoice公共は電気・ガス・水道の請求書を、それぞれまとめられるサービスです。Gi通信やOneVoice公共を利用すると、以下のようなメリットがあります。
請求書の受け取り、支払い、電子データ化までお任せ
Gi通信とOneVoice公共を利用すれば、各社から送付された請求書の受け取りから支払い、電子データ化まで一貫して代行を依頼できます。各サービスの会社が発行した請求書を株式会社インボイスが受け取り、通信料金、公共料金ごとにまとめて処理してもらうことが可能です。請求書も電子データ化した状態で提供されるため、紙媒体で管理する必要がなく、かつパソコンなどへのデータ入力の手間も省けます。
幅広い会社に対応
通信事業やライフライン事業者は複数あり、どの事業者を利用するかは会社によって異なります。また、選択した事業者によって請求書の書式や様式が異なるため、複数の事業者を利用していると一括にまとめて管理するのは大変かもしれません。
Gi通信は利用している通信会社はもちろん、請求書の書式や様式も問わず、すべて一つの請求書にまとめて電子化できるので、事業者ごとに個別の対応を強いられずに済みます。OneVoice公共も、電気は150社以上、ガスは1,000社以上、水道は1,300自治体以上に対応しているため、公共料金の請求書の大部分をまとめてもらえるでしょう。
コストの見直しにも役立つ
Gi通信やOneVoice公共を利用すると、複数の請求書データをまとめて確認できるようになります。どのサービスにどのくらいの費用がかかっているのかを簡単に比較できるため、コストの見直しや適正なプランの選択などに役立ちます。
<h2請求書の処理漏れを防ぐための対策をしっかり行おう
請求書は5年で時効を迎えますが、未払いのまま放置すると催告状が届いたり、支払督促が発付されたりするおそれがあります。場合によっては強制執行の対象になる他、取引先との関係悪化につながるため、請求書が届いたら迅速かつ確実に処理することが大切です。
請求書の処理漏れなどのミスを防ぐために、ワークフローを作る、ダブルチェックやトリプルチェックの体制を整える、請求書のおまとめサービスを利用するなどの工夫が必要です。









