紙の請求書は読取後のデータで保存できる!OCRを使った方法も解説
更新日:2025.03.03
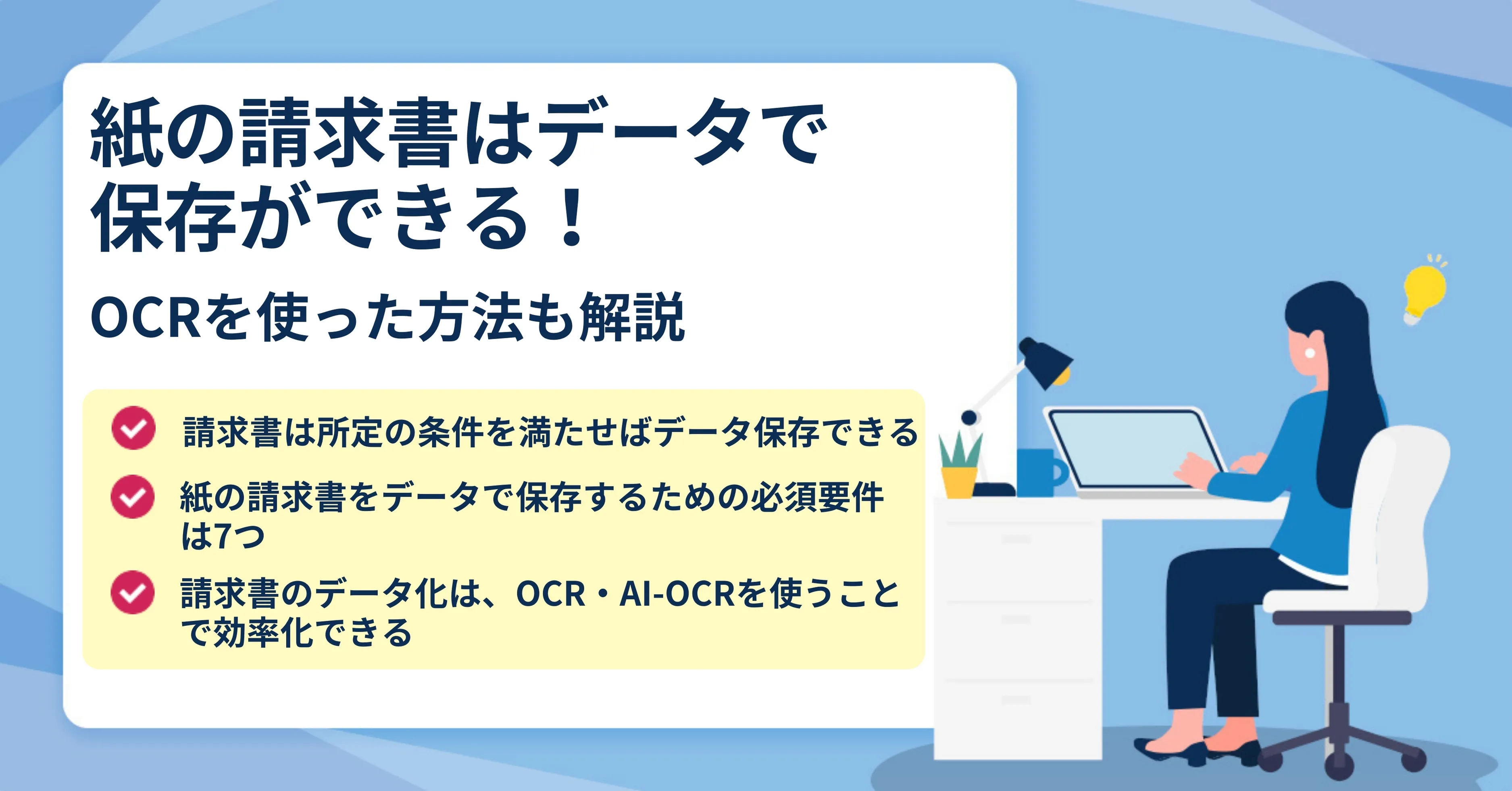
ー 目次 ー
請求書は重要な国税関係書類の1つであり、法律で一定期間の保存が義務づけられています。多くの企業では紙の請求書を保管していますが、書類の保管スペースの確保や必要な請求書の検索に時間がかかるなど、業務効率に大きな影響を与えています。
このような紙の請求書の保存にまつわる問題は、OCRでの読取とデータ保存で解決が可能です。紙の請求書をデータ保存すれば、保管スペースが削減されて素早い検索も可能なため業務効率を大幅に改善できます。
また、電子帳簿保存法に定められた要件を満たせば、紙の請求書の廃棄も可能です。
本記事では、紙の請求書の読取方法とデータ保存の手順について、OCRを使った方法もあわせて解説します。
【結論】紙の請求書はデータで保存できる
請求書は、所定の条件を満たせばデータでの保存が可能です。これは「e-文書法」と「電子帳簿保存法」の2つの法律で認められています。
e-文書法は紙の文書の電子保存を認める基本法で、電子帳簿保存法は国税関係書類の電子保存ルールを定めた法律です。2022年1月の法改正で、事前の税務署長の承認なしでもデータ保存が認められるようになりました。
これにより、請求書のデータ保存が以前よりも取り組みやすくなっています。ただし、電子帳簿保存法の要件を満たさない保存方法は認められず、違反した場合の罰則も厳格化されているため、適切なルールにしたがった運用が重要です。
関連記事:【2025年最新】電子帳簿保存法とは?何をすればいいかわかりやすく解説
紙の請求書をデータで保存するための必須要件7つ
請求書をデータで保存する場合には、電子帳簿保存法で定められた必須要件を満たす必要があります。必須要件を満たせば、請求書はデータで保存ができ、紙の請求書の廃棄も可能です。
ただし、データ化した後でミスが発見される可能性を考慮して、多くの企業では3〜5年程度は紙での保存も並行しておこなっています。
ここでは、紙の請求書をデータで保存するための7つの必須要件について、それぞれ解説します。
①入力期間の制限
請求書をデータで保存する際には、保存のタイミングに関する2つの方式から選択しなければなりません。2つの方式は、以下のとおりです。
- 早期入力方式:請求書の授受日から7営業日以内に保存する方式
- 業務処理サイクル方式:業務処理期間(最長2か月)+7営業日以内に保存する方式
請求書をデータで保存する際には、いずれかの方式を事業者側で選択して、一貫した運用が求められています。
②画質要件
請求書の読み取りには一定の品質基準(画質要件)が設けられています。これは、保存したデータから請求書の内容が鮮明に確認できる状態を維持するための要件です。
具体的には、解像度が200dpi以上であること、カラー画像の場合はRGBそれぞれ256階調以上での読み取りが必要です。
なお、請求書は白黒での保存は認められていないため、スキャナーの設定時にはカラーモードを選択する必要があります。
③検索機能
データ保存した請求書は、検索機能で以下の項目から2つ以上を組みあわせて検索できる状態にしておく必要があります。
- 年月日
- 金額
- 取引先名
検索機能により、請求書が必要になった際に素早く探し出すことが可能です。具体的な検索方法としては、ファイル名に取引日や取引先名を含める方法や、専用の管理システムを利用する方法があります。
④改ざん防止対策
請求書をデータ化した際の改ざん防止のために、タイムスタンプを付与する必要があります。タイムスタンプは、データがいつ作成されたか、また作成後に改ざんされていないことを証明する電子的な証明書です。
ただし、クラウドサービスを利用して請求書のデータを保存する場合は、以下のいずれかの機能があれば代替可能です。
- データの訂正・削除の履歴が確認できる
- データの訂正・削除ができない仕組みがある
多くのクラウドサービスではこれらの機能が標準で搭載されているため、個別にタイムスタンプを付与する必要はありません。
⑤バージョン管理
保存した請求書のデータに訂正や削除をおこなった場合は、その修正履歴(バージョン)を記録して確認できるシステムを導入・利用する必要があります。これは、データの改ざんを防止して、正当な修正経緯を残すための重要な要件です。
バージョン管理には以下の2つの方法があります。
- 修正履歴を残すシステムを導入する方法
- データの訂正・削除そのものができない形式で保存する方法
多くのクラウドサービスでは、これらの機能が標準で実装されているため、要件を満たした運用が可能です。
⑥帳簿との関連づけ
保存した請求書のデータと仕訳帳や経費帳、買掛金元帳などの会計帳簿の記録は、相互に関連付けができる状態にしておく必要があります。具体的には、請求書に記載された取引内容が会計帳簿上でも確認できる仕組みが必要です。
一般的な方法として、請求書への管理番号の付与があります。たとえば、請求書に「請求書No.」などの番号を記載して、会計帳簿の取引情報にも同じ番号を含めて記録することで、取引の紐付けが可能です。
⑦保存期間の遵守
データ保存した請求書は、法定期間の保存が必要です。
- 法人:7年間(赤字事業年度は10年)
- 個人事業主:5年間(適格請求書発行事業者の場合は7年)
法人の場合の保存期間起算日は、法人税の確定申告書の提出期限の翌日から計算します。たとえば3月決算の法人であれば、翌年5月末が確定申告書の提出期限となるため、その日から保存期間をカウントします。
OCR・AI-OCRを使って請求書を読み取る5つの手順
請求書の読取は、OCR・AI-OCRを使うことで効率化が可能です。OCR(Optical Character Recognition)は光学文字認識のことで、紙の書類をスキャンやスマホで読み込み、文字をテキストデータとして認識・抽出する技術です。OCRはPDFやJPEGなどの画像からもテキストを抽出できて、柔軟に対応できます。
AI-OCRは、従来のOCRにAI(人工知能)のディープラーニングを組みあわせた技術で、OCRより高度な認識ができます。フリーフォーマットの文書も認識できて、高い識字率の実現が可能です。
ここでは、OCR・AI-OCRを使って請求書を読み取る5つの手順についてそれぞれ解説します。
①請求書をスキャンする
最初に、請求書をスキャンします。スキャンする際の推奨解像度は300dpiです。電子帳簿保存法の最低基準は200dpiですが、OCRの読み込み精度とファイルサイズのバランスを考慮して設定をおこないます。
また、スキャナーの性能や設定で読取精度が異なるため、事前に適切な設定を確認しておくことが重要です。複数枚の請求書を一括でスキャンする場合は、原稿送り装置(ADF)の使用の検討がおすすめです。
②スキャンしたデータをアップロードする
スキャンしたファイルをOCRサービスに読み込ませます。アップロードの前に、スキャンデータの解像度や向きが正しいか確認しておくことで、認識精度を高められます。
また、頻繁に使われる商品名や取引先名などは事前に辞書登録しておくと、より正確な読取が可能です。大量の請求書をまとめてアップロードする場合は、ファイル名の付け方をルール化しておくと、後の管理がしやすいです。
③内容を抽出・保存する
アップロードしたデータを以下の必要な項目に分類してテキストデータを抽出します。
- 取引先名
- 請求金額
- 支払期限 など
抽出したデータはExcelやデータベースへの出力も可能で、CSV(テキストファイル)などさまざまなフォーマットに対応しています。また、電子帳簿保存法の要件を満たすため、原本はPDFなどの形式での別途保存が必要です。
なお、読取から保存までの一連の作業を自動化できるサービスも増えています。
④データを確認・修正する
抽出したデータを請求書の原本と照合して、誤認識があれば修正します。とくに手書きや特殊フォントは認識精度が低くなる傾向があるため、念入りに確認しましょう。
修正履歴を残すために、データの修正はシステム上で適切におこない、変更内容を記録できる状態にしておく必要があります。大量の請求書を処理する場合は、チェックリストを作成して確認漏れを防ぐ工夫も有効です。
⑤データを活用する
読み取ったデータは会計ソフトとの連携や、データ分析に活用できます。多くの会計ソフトではCSVによるデータ取り込みやAPI連携(システム間を直接つなぐ仕組み)に対応しており、仕訳の自動作成も可能です。
また、取引先ごとの請求傾向分析や、支払予定額の集計なども容易におこなえます。さらに、請求書の受領から支払までの進捗管理や、承認ワークフローとの連携で、経理業務全体の効率化が図れます。
データの活用方法を工夫することで、経営判断に役立つ情報の抽出も可能です。
請求書の読取やデータ化は、クラウドサービスの利用で効率化できる
OCR、AI-OCRを活用したクラウドサービスの利用で、請求書の読取とデータ保存作業を効率化できます。サービスを選ぶ際には、自社の業務にあわせた機能の確認が重要です。
たとえば、請求書以外の帳票と一括処理の必要があるのか、会計ソフトと連携できるのかといった点がポイントです。また、電子帳簿保存法の要件への対応状況や、セキュリティ対策が万全かどうかも確認しておく必要があります。
クラウドサービスによっては、請求書の受け取りから保存までをワンストップで対応できるものもあり、サービスの導入で大幅な業務効率化が期待できます。
まとめ|適切な手順で請求書を読み取って、データで保存しよう
本記事では、紙の請求書の読取方法とデータ保存の手順について、OCRを使った方法もあわせて解説しました。
請求書は必須要件を満たせば電子データとして保存できます。電子帳簿保存法の要件にしたがった適切な保存で、紙の原本も廃棄が可能です。
読取作業はOCRやAI-OCRの活用で効率化でき、クラウドサービスの利用でさらなる効率化も実現できます。サービス選びの際は、自社の業務フローにあわせて機能を比較検討し、最適なものを選択することが重要です。










