請求書に割引・値引きを書くのは違法?書き方や注意点を解説!
更新日:2025.03.03
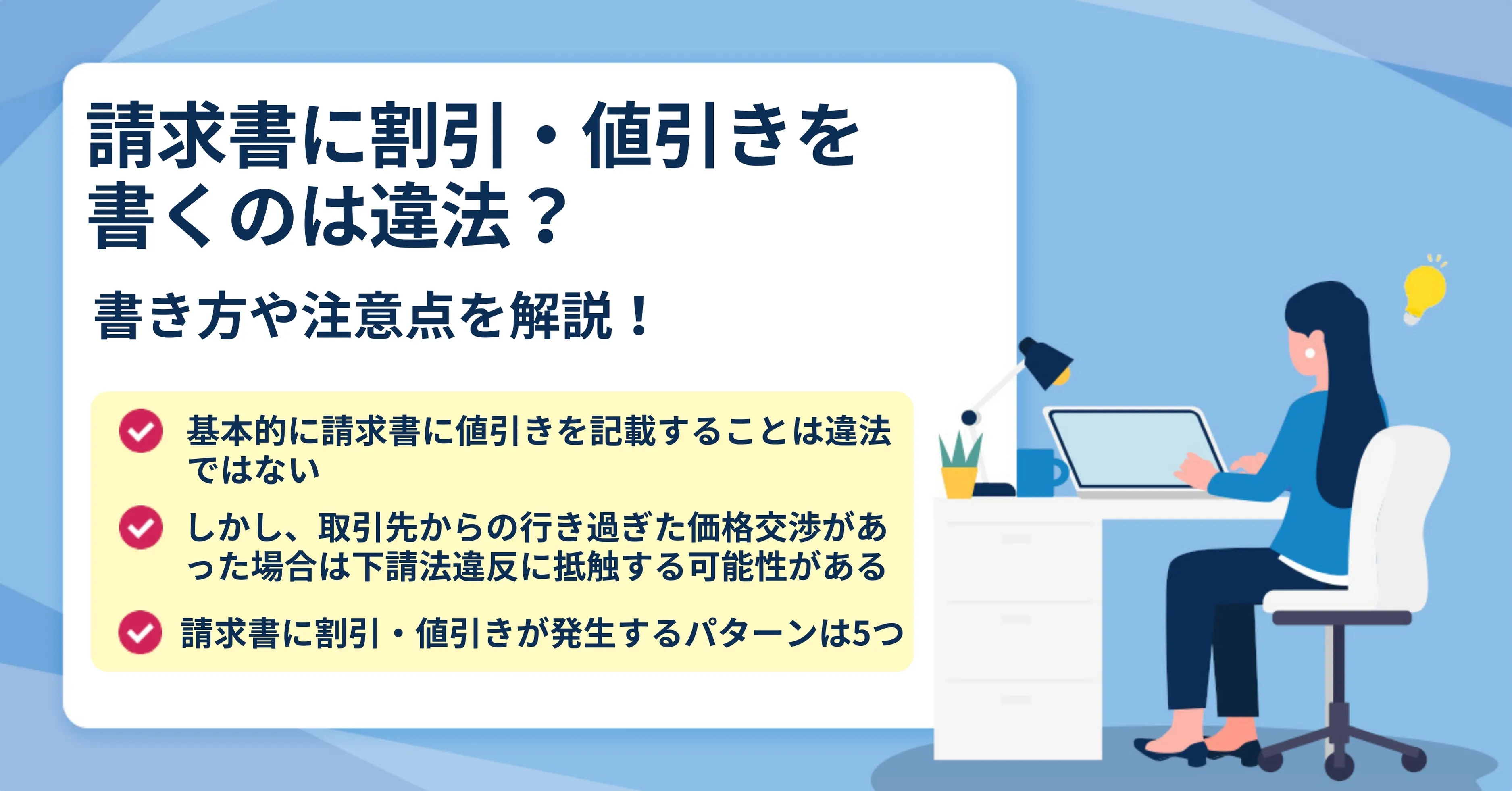
ー 目次 ー
ビジネスシーンでは、商品・サービスの割引・値引きをおこなうことは少なくありません。このような際の対応方法については、法律上でルールが定められているため、理解したうえで対応しましょう。
なお、商品・サービスの提供時に割引・値引きが必要になった場合、請求書にはその旨を記載する必要があり、状況にあわせて記載方法が異なります。また、請求書に差し引いた金額を記載する場合に、誤って発行すると取引先の信頼を失う可能性があるため注意しましょう。
本記事では、請求書に割引・値引きを記載する際の書き方や注意点を解説します。
【結論】請求書に割引・値引きを記載しても違法ではない
請求書に商品・サービスの割引・値引きを記載しても違法にはなりません。ただ、常識の範囲内の割引・値引きであったことを証明するためにも、割引・値引きをおこなう際には理由を明記しましょう。
一方で、取引先から常識外の価格交渉があった場合は、下請法や不正競争防止法などに抵触する可能性があるため注意が必要です。違法性がある値引きの内容については、以下の記事で詳細に解説しています。
請求書に割引・値引きが発生するパターンとは?
請求書に割引・値引きを記載する状況は、大量注文や相殺の発生などが考えられます。状況ごとに請求書に記載するべき内容が異なるため、割引・値引きをおこなう理由を理解しておくことが大切です。
ここからは、請求書に割引・値引きが発生するパターンを5つ解説します。
①大量注文
商品やサービスの注文を大量に受けた場合は、購入金額にあわせて対応する可能性があります。この割引・値引きは、「売上割戻」「リベート」「キックバック」「ボリュームディスカウント」と呼ばれており、企業によって名称は異なります。
大量注文を理由に割引・値引きを実施する際は、対象商品の下の行に「割引 ▲〇〇円」と記載することが一般的です。
割引をおこなう場合は取引先に数量と割引率の関係を説明しておくことで、認識の齟齬を防げます。
②相殺が発生した
以前におこなった取引に返金が発生しており、今回の取引金額から返金額を差し引く場合「相殺」で対応します。
相殺は、振込時にかかる手間を減らせるため、自社・取引先のどちらにもメリットがあります。ただし、相談なく相殺扱いにするとトラブルに発展する可能性があるため、事前に取引先へ連絡が必要です。
なお、相殺する際は対象商品の下の行に「相殺による値引き ▲〇〇円」と記載しましょう。
③納期調整
商品・サービスの手配に遅れがあり、納期の調整をおこなった場合は迷惑をかけたお詫びに割引・値引きする可能性があります。
このようなケースでは、「納期調整による値引き ▲〇〇円」と記載します。
納期調整による割引・値引きは事前に金額が決まっていないため、取引先と相談して決定することでトラブルを防ぐことが可能です。遅れた期間や合計金額をもとに、双方が納得する価格を決定しましょう。
④端数調整
請求金額に端数が出ている場合は、サービスで端数分を割引・値引きする可能性があります。たとえば、請求金額が100,050円であった際は、50円分を差し引くことで入金金額のきりが良くなります。
このようなケースでは、「端数調整による値引き ▲50円」と記載することが一般的です。
なお、端数調整をおこなう際は事前に取引先に伝えておくことで、相手が混乱する心配をなくせます。
⑤クレーム対応
提供する商品・サービスに問題があった場合、取引先からクレームが入る可能性があります。相談のうえ返品にならない際は、割引・値引きでの対応も選択肢にあります。
クレームによる値引きなら、「割引 ▲〇〇円」と記載しましょう。クレームの場合は厳密な割引額が決定していないため、取引先と金額を相談する必要があります。
【見本】請求書に割引・値引きがある際の書き方
割引・値引きが記載された請求書を作成する場合は、事前にテンプレートを用意しておくことでスムーズに請求書の作成ができます。自社にあわせたテンプレートを作成しておき、請求業務を簡略化していきましょう。
ここでは、請求書に割引・値引きがある際の書き方を解説します。
|
請求書 取引先企業名 自社の企業名 ご請求金額 ¥1,630-(税込)
※印は軽減税率の対象 |
||||||||||||||||||||||||||||||
請求書に割引・値引きを書く際の注意点
割引・値引きが記載された請求書を作成する際は、決められた記号の使用や消費税を計算するタイミングなどの注意点を理解しておく必要があります。注意点を理解しないまま請求書を作成し、取引先からの問い合わせがあった場合は信頼を失う可能性があるため注意しましょう。
ここからは、請求書に割引・値引きを書く際の注意点を解説します。
①請求書には割引・値引き理由や金額を明確にする
割引・値引きをおこなう際は、対象になる商品の下の行に差し引く金額を記載しましょう。
そもそも、請求書に差し引く金額を記載する箇所は明確に決まっていません。しかし、割引・値引きを受けた商品・サービスが判断できなければ、請求書を処理する取引先に迷惑がかかります。
対象になる商品の下に値引きの旨を記載しておくことで、取引先が判断しやすくなります。
②割引・値引きは「▲」や「-」の記号を使用する
割引・値引きが記載された請求書を作成する際は、「▲」や「‐」などの記号を使用しましょう。値引き金額の前に記号を記載しておくことで、数字の改ざんや訂正を防げます。
なお、請求書内の割引・値引きする金額を赤文字にするといった対応は一般的ではありません。必ず記号を使って割引・値引きを明示してください。
③請求書に記載する消費税は割引・値引き後の金額で計算する
消費税を計算する際は、割引額を差し引いた金額でおこないましょう。
請求書によって消費税を計算するタイミングが異なると、確定申告時に1枚ずつ請求書を確認する手間が増え、経理業務が煩雑になります。
社内で割引・値引き後に消費税を計算すると徹底しておけば、消費税の計算方法で混乱を避けられます。
④割引・値引きの理由が不当でないかを確認しておく
取引先から金額の変更を求められた場合、その内容が不当でないかを確認しておきましょう。
たとえば、購入する商品の量に対して非常識な割引や、購入者という立場を利用した理不尽な値引きを求められた場合は「下請法」「独占禁止法」に抵触する可能性があります。
取引先に受け取る金額から原価や人件費を考慮して、適正な金額かどうかを判断すると安心です。
まとめ|請求書で割引・値引きを書く際は理由や消費税の計算に注意しよう
本記事では、請求書に割引・値引きを記載する際の書き方や注意点を解説しました。
請求書は値引きや割引が必要になった場合は記載して問題ないものの、理由や対象の商品を明らかにしましょう。ほかにも、消費税を計算するタイミングを統一しておかなければ、確定申告時に確認する手間が増えます。
上記を踏まえて、割引・値引きが記載された請求書を作成する際は、本記事を参考に書類を作成しましょう。










