フリーランス・個人事業主の請求書の書き方は?交通費やインボイスのルールも解説
更新日:2025.01.30
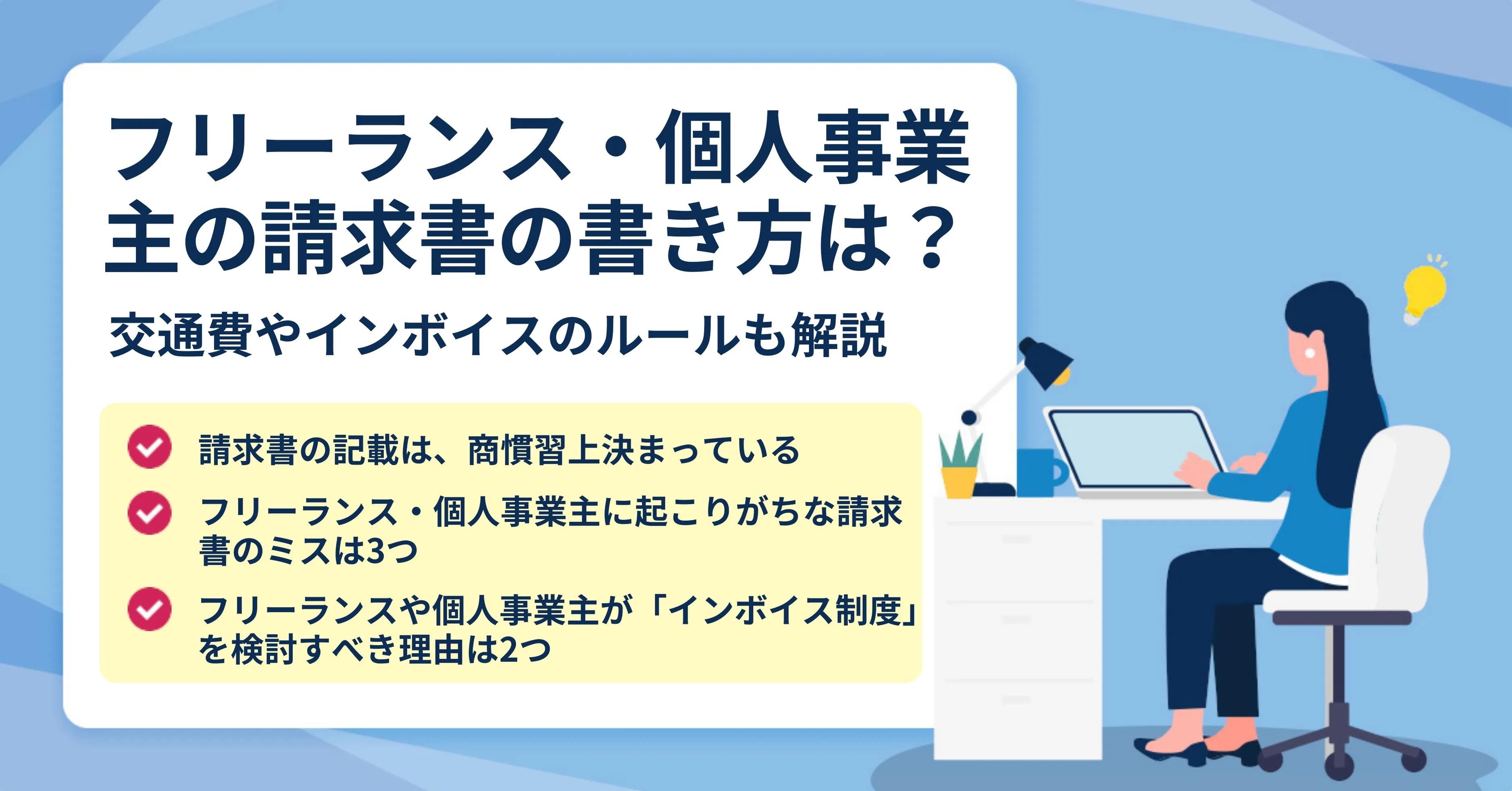
ー 目次 ー
2023年10月のインボイス制度の施行で、請求書の発行や保存に関するルールが変更となりました。多くの事業者がインボイス制度の対応に追われるようになり、これはフリーランスや個人事業主も例外ではありません。
請求書に関する新たなルールは税制に大きく影響するものであるため、理解しておかなければ取引先も含めた大きな税金のトラブルに発展します。
このような事態を避けるためにも、基本的な請求書に関する知識・ルールをおさえておくことが大切です。
本記事では、フリーランス・個人事業主の請求書の書き方について、交通費やインボイスのルールも交えて解説します。
【インボイス対応】フリーランス・個人事業主の請求書の書き方とは?
請求書は商慣習上で基本的な記載事項が決まっています。また、2023年10月からスタートしたインボイス制度において、ルールを適用する場合の請求書の記載要件も定められています。
このようなことから、インボイス制度に対応した請求書のフォーマットをあらかじめ作成しておくと、経理業務の負担を軽減できるだけでなく、記載漏れのようなミスを防ぐことが可能です。
ここでは、フリーランス・個人事業主の請求書の書き方について、解説します。なお、インボイス制度に対応した請求書の記載事項は以下のとおりです。
- 受領事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 発行事業者の氏名または名称、登録番号
- 支払先情報(支払方法や口座情報など)
- 請求書番号
- 備考
また、上記の記載項目を備えた請求書のサンプルは以下のとおりです。
発行日:20XX年XX月XX日 請求書 〇〇株式会社 御中 自社名 件名:〇〇のご請求について
※軽減税率(8%)の対象商品
|
①受領事業者の氏名または名称
請求書の宛先となる取引先の氏名または名称(屋号)を記載します。
もし、取引先が法人である場合、取引をおこなう部門や部署、また担当者氏名の記載が基本的なマナーです。なお、敬称については、法人名だけなら「御中」、担当者名も含めるなら「様」としましょう。
②取引年月日
請求書には、取引をおこなった日付を記載しなければなりません。
もし、複数の取引をまとめて請求する場合は、それぞれの取引年月日を記載しましょう。対象となる取引がすべて同じ取引年月日である場合は、まとめて記載しても問題ありません。
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も)
請求書には具体的な取引内容の名称や数量、また単価や金額の記載が必要です。
もし、複数の取引で税率がわかれる場合には、わかりやすく印(「※」の印など)をつけておかなければなりません。
④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
取引によって軽減税率と標準税率の区分が発生した場合、それぞれの合計額を記載しましょう。内訳として、消費税額や源泉徴収税額の記載があれば、第三者が確認した際にもわかりやすくなります。
なお、税込・税抜は任意で選択できる一方で、請求書内で統一する必要があります。
⑤税率ごとに区分した消費税額
取引によって軽減税率と標準税率の区分が発生した場合、それぞれの消費税額をわけて記載しなければなりません。
取引内容で対象品目の印をつけておけば、印にしたがって明記できるため、わかりやすい請求書の作成が可能です。
⑥発行事業者の氏名または名称、登録番号
発行事業者である自身の氏名または名称(屋号)を記載しましょう。また、インボイス制度に登録していれば、「T」からはじまる13桁の登録番号の記載も必要です。
⑦支払先情報(支払方法や口座情報など)
取引先から取引内容の対価を支払ってもらうために、支払方法や口座情報などの支払先情報を記載します。たとえば、口座情報の記載を誤った場合には誤送金のような大きなトラブルになるため注意してください。
⑧請求書番号
請求書ごとに請求書番号を設定しておけば、確定申告や過去の請求を確認する際に探しやすくなります。そのため、請求書番号も記載しておきましょう。請求書番号のルールを決めておけば、請求書の管理がしやすくなります。
⑨備考
取引先から特別な依頼や、こちらから何か申し出しておきたい際には、備考欄に記載しておきましょう。取引先によっては頻繁に利用することもあるため、請求書のフォーマットには必ず備考欄をつけておきましょう。
フリーランス・個人事業主に起こりがちな請求書のミスとは?
請求書のルールを誤ってしまうと、インボイス制度をはじめとしたさまざまな法律におけるトラブルに発展しかねません。このようなトラブルは自身だけでなく、取引先にも影響を与えるため、取引先からの信用を失うリスクがあります。
このようなことを避けるためにも、フリーランス・個人事業主に起こりがちなミスをあらかじめ把握しておき、事前に対策を検討しておきましょう。
ここでは、フリーランス・個人事業主に起こりがちな請求書のミスについて、解説します。
①源泉徴収の有無を確認しない
取引先が法人の場合には、「源泉徴収」が生じる可能性があります。このようなケースでは、源泉徴収税を報酬から差し引く対応が必要となるため、請求書には源泉徴収税額も含めた記載が必要です。
お互いにとって二度手間な対応が必要となるため、源泉徴収の有無は契約成立時に確認しておきましょう。
②交通費を請求に勝手に含める
取引の内容によっては、交通費が発生するケースが存在します。
この交通費は請求書に含めること自体はルール上問題がない一方で、取引先に事前に伝えておかないと、取引先は想定していない経費が発生してしまいます。取引先からの信用を失い、結果的に取引を打ち切られるリスクも否定できません。
そのため、取引に生じる経費の負担について、事前に取引先に相談することが大切です。
③払込手数料の負担を決めていない
銀行への振込で請求を依頼する場合、払込手数料が生じる可能性があります。
法律のルール上、払込手数料の負担は原則的に発注者側と定められています。しかし、このルールはあくまで任意の規定であるため、手数料負担を受注者側とする取引も少なくありません。
このようなことから、払込手数料の負担について取引先と事前に決めておくと良いでしょう。
関連記事:インボイス制度における振込手数料は誰が負担する?仕訳のポイントも解説
フリーランスや個人事業主が検討すべき「インボイス制度」とは?検討すべき2つの理由
インボイス制度は請求書の記載事項や保存方法、消費税の計算方法などを定めたルールです。この制度では、インボイス制度に登録した事業者同士で適格請求書(インボイス)の発行・保存をおこなうことで、経費に使った消費税を控除できるメリットが受けられます。
このようなことから、インボイス制度に登録している事業者と優先的に取引をおこなう事業者も少なくありません。フリーランス・個人事業主にも影響がある問題であるため、インボイス制度の登録を検討してください。
ここでは、フリーランスや個人事業主がインボイス制度の登録を検討すべき2つの理由について、解説します。
①仕入税額控除が受けられる
仕入税額控除とは、売上の消費税額から仕入・経費に使った消費税を差し引けるルールです。インボイス制度導入時のメリットであり、納税額の負担が抑えられる可能性があります。
税負担を抑えられることから、インボイス制度を積極的に活用したい事業者が多く存在します。
②取引先からインボイスの発行を依頼される可能性がある
インボイス制度の活用には、お互いが適格請求書発行事業者に登録しておく必要があります。もし、こちら側が登録していない場合、取引先はインボイス制度が使えないことになります。
取引先としてはインボイス制度に登録している別の事業者を選んだほうが税負担を抑えられ、取引の打ち切りや依頼数の縮小につながりかねません。
まとめ|フリーランス・個人事業主も請求書やインボイス制度を理解し、取引先と良好な関係を
本記事では、フリーランス・個人事業主の請求書の書き方について、交通費やインボイスのルールも交えて解説しました。
フリーランスや個人事業主にとって、請求書は頻繁に作成する重要な書類です。書き方や保存方法でさまざまなルールが存在する一方で、インボイス制度を活用すれば税制上のメリットが得られます。また、取引先とのトラブルを未然に防げ、良好な関係を築けるきっかけにもなるでしょう。
このようなことから、請求書の基本的な知識・ルールを理解しておくことが大切です。本メディアも参考に、自身の事業の「守り」を強めてください。










