電子インボイスとは?経理業務に与える6つの影響をやさしく解説
更新日:2025.09.05
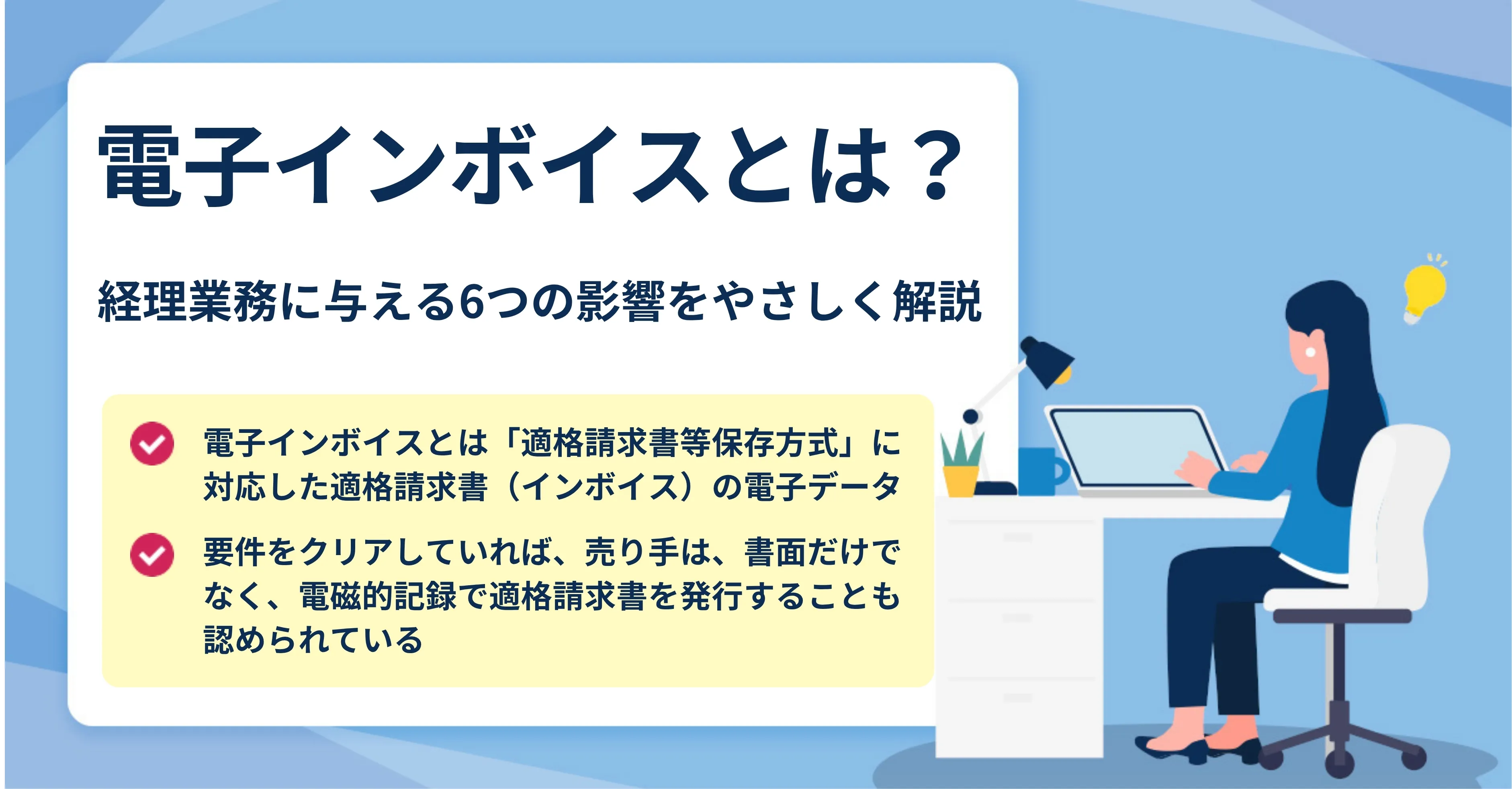
ー 目次 ー
電子インボイスとは、適格請求書(インボイス)をメールなどの電子データで発行することを指します。 2023年10月1日から導入された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に対応したもので、 デジタル化された請求書のやり取りが可能になります。
電子インボイスの導入により、請求や支払い、消込といった業務プロセスの自動化が進むほか、 経理部門のテレワーク対応も現実的となります。 業務効率化と法令対応の両立を図るうえで、企業にとって重要な制度です。
本記事では、電子インボイスの基本的な仕組みや特徴、導入による影響についてわかりやすく解説します。
電子インボイスとは電子化した適格請求書のこと
電子インボイスとは、2023年10月1日より導入予定の「適格請求書等保存方式」(以下、インボイス制度)に対応した適格請求書(インボイス)の電子データを指します。そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、正しい消費税率(8%または10%)を把握し、適切な仕入税額控除を適切に行うために導入されました。 【売り手】 ● 買い手から適格請求書を求められたら、発行しなくてはいけない ● 発行した適格請求書は控えを保存する ● 適格請求書を発行するためには、登録申請が必要 【買い手】 ● 仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要 ● 適格請求書でない請求書では、仕入税額控除が受けられない 上記のように、売り手・買い手、どちらにも影響のある制度です。適格請求書に必要な記載事項
請求書が適格請求書と認められるためには、下記の条件を満たしている必要があります。 1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号 2. 取引年月日 3. 取引内容 4. 税率ごとに区分された対価の額と適用税率 5. 税率ごとに区分した消費税額等 6. 書類を受け取る事業者の氏名または名称 1の登録番号は、税務署に登録申請をした「適格請求書発行事業者」しか発行できません。適格請求書は電子データでの交付も可能
以上のように、適格請求書と認められるためには、登録番号や取引年月日の明記など、さまざまな要件があります。 これらの要件をクリアしていれば、売り手は、書面だけでなく、下記のような電磁的記録で適格請求書を発行することも認められています。 ● 記録用媒による提供(磁気ディスクやフラッシュメモリ、など。) ● インターネット上のサイトを通じた提供 ● 電子メールでの送信 ● EDI(インターネットを用いて受発注の連絡ができる「電子的データ交換」) 上記に該当するものが"電子インボイス"です。電子インボイスは電子帳簿保存法に準じて保存しなければいけない
電子媒体による提供も可能な適格請求書ですが、保存する際は、「電子帳簿保存法に準じた方法」で行います。 買い手は仕入税額控除を受ける要件として、適格請求書の保存が必要です。電子インボイスを導入するためには、合わせて電子帳簿保存法も理解しなければいけません。 また、売り手も電子帳簿保存法に準拠した方法で、準拠する必要があります。電子インボイスの標準規格
 以上のように、適格請求書は電子的方法でのやり取りも可能です。そのため、将来的には送付コストの削減や、ペーパーレス化が進み業務の効率化にもつながる仕組みです。
しかし、現在の各企業では、請求書の様式も違えば、経理ソフトなど、導入しているシステムも異なります。さらに、EDIが使えるとしても、取引先にも同じものを導入してもらわなくてはいけません。そうなれば、さらに管理するシステムが増え、煩雑化する一方です。
以上のように、適格請求書は電子的方法でのやり取りも可能です。そのため、将来的には送付コストの削減や、ペーパーレス化が進み業務の効率化にもつながる仕組みです。
しかし、現在の各企業では、請求書の様式も違えば、経理ソフトなど、導入しているシステムも異なります。さらに、EDIが使えるとしても、取引先にも同じものを導入してもらわなくてはいけません。そうなれば、さらに管理するシステムが増え、煩雑化する一方です。










