請求書の電子保存は義務?紙のままでもOKなケースをわかりやすく解説!
更新日:2025.09.22
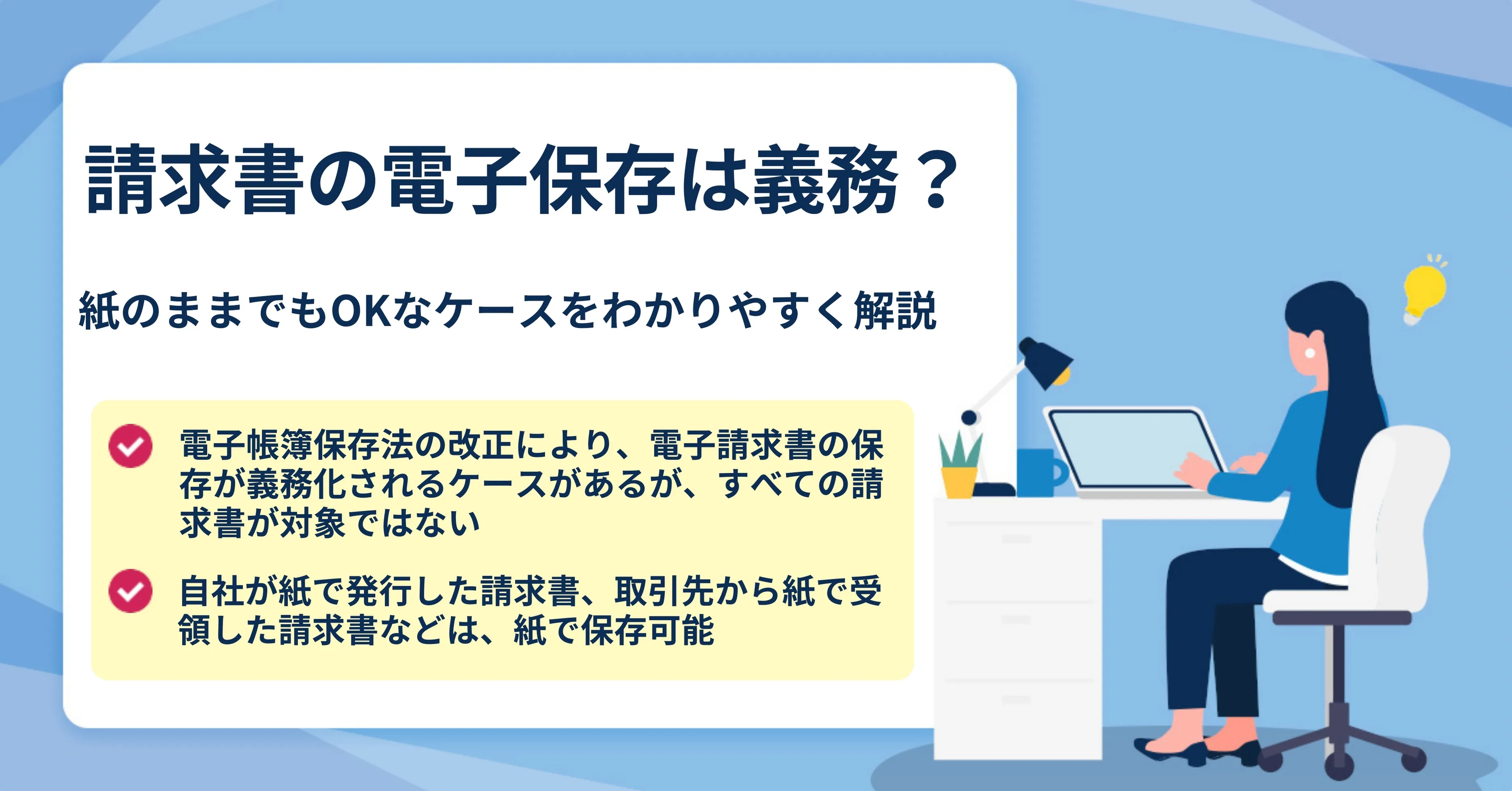
ー 目次 ー
2024年の電子帳簿保存法改正により、請求書の電子保存が強く求められるようになりました。しかし、「すべての請求書を電子保存しなければならないのか?」「紙の請求書はもう使えないのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、2024年1月1日から、「電子取引」で受け取った請求書などの電子データは 電子データのままで保存すること が義務になりました。紙に印刷して保存することは原則できません。
一方で、取引先から 紙で受け取った請求書 は、引き続き紙保存が認められています。スキャンして電子データ保存する「スキャナ保存」制度を使うこともできますが、これは任意であり、要件を満たす必要があります。
本記事では、請求書の電子保存が義務化されるケースや、紙の請求書をそのまま保存できる条件をわかりやすく解説します。また、電子保存のルールや具体的な対応方法についても詳しく紹介しますので、企業がどのように対応すべきかが明確になります。この記事を読むことで、電子保存の必要性や実務対応のポイントが理解でき、スムーズな導入が可能になります。
請求書の電子保存とは?
請求書の電子保存とは、紙の請求書をデータ化して保存する方法を指します。近年、デジタル化の進展や法律の改正により、電子データでの保存が推奨されるようになっています。特に「電子帳簿保存法」の改正により、一定の条件を満たせば電子請求書の保存が認められるだけでなく、義務となるケースもあります。
電子保存が求められる背景
請求書の電子保存が求められる主な背景には、以下のような要因が挙げられます。
- デジタル化の進展:紙の書類を使用するよりも、デジタルデータを活用することで業務の効率化が図れる。
- コスト削減:印刷コストや保管スペースの削減が可能。
- リモートワークへの対応:クラウド保存などにより、どこからでもアクセスできる環境の整備が求められる。
- 税制改正への対応:電子帳簿保存法の改正により、電子保存が認められるだけでなく、一定の場合には義務化される。
特に、2022年の電子帳簿保存法改正により、紙の書類に依存しない電子的な保存が重要視される傾向にあります。
電子保存の定義
電子保存とは、請求書や領収書などの取引関係書類を電子データとして保存することを指します。ただし、単にPDFとして保存するだけでは法的に認められない場合があり、適切な要件を満たす必要があります。
電子保存の主な方法は以下の通りです。
|
電子保存の方法 |
概要 |
主な要件 |
|
電子請求書の直接保存 |
PDFやデジタルデータとして発行された請求書をそのまま保存 |
改ざん防止措置(タイムスタンプ、訂正履歴管理など) |
|
スキャナ保存 |
紙の請求書をスキャンしてPDFや画像データとして保存 |
解像度や色の要件を満たしたデータ保存、入力期間の遵守 |
|
クラウド保存 |
クラウドサービスを利用して電子データを保存・管理 |
アクセス制限管理、データ改ざん防止 |
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法(電帳法)とは、企業が書類や帳簿を電子的に保存する際のルールを定めた法律です。この法律に基づき、請求書の電子保存も一定の条件下で認められています。
電子帳簿保存法のポイントとして、以下の3つが挙げられます。
- 帳簿や決算関連書類の電子化:仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類を電子データとして保存可能。
- スキャナ保存の要件:紙の請求書などをスキャンして保存する際には、適切な手続きが必要。
- 電子取引情報の保存:電子メールやクラウド上で受け取る請求書は、電子データのまま保存する必要がある。
特に、電子取引の書類については、紙に印刷して保存することは原則認められず、電子保存しなければなりません。(経過措置あり)
電子帳簿保存法の改正により、今後はより一層、電子保存への対応が求められることになります。そのため、企業では電子請求書の保存方法について正しく理解し、適切な対応を行うことが重要です。
請求書の電子保存は義務なの?
近年、電子帳簿保存法の改正により、請求書の電子保存が求められるケースが増えてきました。しかし、すべての企業や個人事業主に対して一律に電子保存が義務付けられているわけではありません。ここでは、そもそも電子保存が義務なのか、どのようなケースで電子化しなければならないのかを詳しく解説していきます。
電子帳簿保存法の対象範囲
電子帳簿保存法は、企業や個人事業主が税務に関する帳簿や書類を電子データとして保存する際のルールを定めた法律です。この法律が適用される範囲には、以下のような書類が含まれます。
- 請求書
- 領収書
- 見積書
- 契約書
- 決算書類
これらの書類は、紙で受け取る場合と、電子データで受け取る場合があります。電子保存の義務は、その受け取り方法によって異なります。
電子保存が義務となるケース
請求書の電子保存が義務となるのは、以下のような条件を満たす場合です。
|
保存対象 |
電子保存が義務となるか |
保存のポイント |
|
電子データで受け取った請求書 |
義務 |
紙に印刷しての保存は不可。電子データのまま保存する必要あり。 |
|
紙で受け取った請求書 |
任意 |
紙のまま保存可能。ただしスキャナ保存することも認められる。 |
|
自社が発行した請求書(電子データ) |
義務 |
電子データで管理し、改ざん防止策を講じる必要あり。 |
電子取引に該当する場合
2024年1月の改正電子帳簿保存法により、「電子取引」に該当するデータについては、電子保存が義務付けられました。電子取引とは、取引の相手からEメールやクラウドサービスを通じて電子データで請求書を受領するケースを指します。
電子取引に該当する代表的な例は、以下のようなケースです。
- メールでPDF形式の請求書を受領
- クラウド型の請求書発行サービスを利用
- EDI(電子データ交換)で請求書データを受領
これらのケースでは、紙に印刷しての保存は認められず、電子データのまま保存しなければなりません。なお、電子保存を行う場合には、検索機能の確保やタイムスタンプの付与などの要件を満たす必要があります。
小規模事業者の猶予措置
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引データの保存が義務付けられましたが、中小・小規模事業者に対しては一定の猶予措置が設けられています。たとえば、以下の条件を満たす場合、紙に印刷して保存することが認められています。
- システム導入が困難である正当な理由がある
- 税務調査時に必要なデータを提示できる
ただし、猶予期間を過ぎると完全義務化が予定されているため、早めに電子保存の準備を進めることが推奨されます。
電子保存をしない場合のペナルティ
電子取引データの電子保存が義務化されたにも関わらず、適切な保存を行わなかった場合、以下のようなリスクが生じます。
- 税務調査で指摘され、過少申告加算税や重加算税が課される可能性がある
- 電子データの改ざんが疑われた場合、行政指導や罰則の対象となる
税務当局が確認できる形で請求書データを保存し、法律の要件を満たしていることを証明することが求められます。
紙の請求書をそのまま保存できる場合を解説!
電子帳簿保存法の改正により、請求書の電子保存が求められるケースが増えています。しかし、すべての請求書を電子保存しなければならないわけではなく、一定の条件を満たせば紙の請求書をそのまま保存することも可能です。ここでは、紙の請求書を保存できるケースについて詳しく解説します。
紙の請求書のまま保存できる具体的なケース
紙の請求書をそのまま保存できるかどうかは、請求書の発行方法や受領方法によって異なります。以下のケースでは、紙の請求書を紙のまま保管することが認められています。
|
保存方法 |
紙のまま保存できる条件 |
|
自社で作成した請求書 |
紙で発行し、電子データとして保存していない場合 |
|
取引先から受領した請求書 |
取引先が紙で発行し、電子データでの授受が行われていない場合 |
|
インボイス制度に対応した請求書 |
適格請求書を紙で受領し、税務上の保存要件に従って保管する場合 |
|
電子データで受領したが紙に出力した請求書 |
一定の要件を満たし、「紙保存が認められる場合」に該当する場合 |
ただし、電子データで授受した請求書を紙に印刷して保存する場合は、電子保存が義務付けられるケースがあるため慎重に判断する必要があります。
紙の請求書を保管する際のリスク
紙の請求書をそのまま保存することは可能ですが、以下のようなリスクが存在します。
保存スペースの確保
大量の請求書を紙で保存する場合、収納スペースが必要になります。長期間にわたり保存義務があるため、適切な管理方法を確立しなければなりません。
紛失や劣化のリスク
紙の請求書は、紛失や劣化のリスクが伴います。火災や水害などの災害による損失のリスクも考慮し、保管場所の環境に注意を払う必要があります。
検索や管理の手間
紙の請求書は、必要な書類を探す際の手間がかかります。特に、過去の取引履歴を遡る場合には、膨大な書類の中から該当の請求書を探し出す作業が発生するため、業務効率が低下する可能性があります。
税務調査時の対応
税務調査が入った際、紙の請求書を適切に保管していない場合、証拠書類としての提出に問題が生じる可能性があります。特に、インボイス制度の適用を受ける事業者は、適格請求書の適正な保存が求められます。
以上のようなリスクを踏まえ、事業者は請求書の保存方法について慎重に検討する必要があります。電子保存が義務づけられていない場合でも、業務効率やリスク管理の観点から、電子保存を積極的に検討することが望ましいでしょう。
紙の請求書の保存方法は?
紙の請求書の保存期間
紙の請求書は、法律で定められた期間保存する必要があります。保存期間は、企業の形態や請求書の種類によって異なります。
|
請求書の種類 |
法定保存期間 |
根拠法令 |
|
法人税法上の保存が必要な請求書 |
7年間 |
法人税法 第126条 |
|
消費税法上の仕入税額控除の対象となる請求書 |
7年間 |
消費税法 第30条 |
|
所得税法上の保存が必要な請求書 |
5年間 |
所得税法 第232条 |
特に消費税の仕入税額控除に関わる帳簿書類は7年間保存する必要があるため、取引にかかわる請求書は原則として7年間保管するのが一般的です。
紙の請求書の適切な保管方法
紙の請求書は、税務調査に対応できるよう適切に管理・保管することが求められます。一般的に、以下のような保管方法が推奨されます。
① ファイリングによる分類保管
請求書を取引先ごと、または年月ごとに分類し、ファイルやバインダーに整理する方法です。
- 取引ごとに日付順に並べる
- ファイルのラベルを明確に記載する
- 急な税務調査にも対応しやすいよう索引を作成する
② キャビネットや専用保管庫での管理
紙の請求書は長期間保存が必要であり、散逸を防ぐためにキャビネットや専用保管庫に整理して管理します。
- 耐火キャビネットを利用し、消失リスクを低減
- 施錠できる専用保管庫で改ざんや紛失を防止
- アクセス権を限定し、管理者を明確化
③ デジタル管理との併用
紙の請求書を管理しやすくするために、スキャナで電子化して管理する企業も増えています。電子化することで、検索性の向上やバックアップ体制の強化が可能になります。
- スキャナ保存を行い、PCやクラウド上にデータを格納
- データベース化して検索性を向上
- 紙と電子データの両方を適切に保管
スキャナ保存する場合の要件
電子帳簿保存法に基づいて紙の請求書をスキャナ保存する場合、一定の要件を満たす必要があります。
① 認定スキャナを使用
スキャナ保存をする際には、一定の解像度や色調が確保された状態で読み取る必要があります。国税庁が指定する基準を満たしたスキャナを利用しましょう。
② 記録の改ざん防止措置
スキャナ保存したデータの改ざん防止措置として、タイムスタンプの付与やデータの訂正履歴の管理が必要です。
③ 適切な検索機能の確保
スキャナ保存した請求書は、必要なときに迅速に検索できるよう「日付」「取引先名」「金額」などで検索できる環境を整えます。
税務調査時の対応
税務調査が行われた場合、請求書の保存状況についてチェックされます。適切な保存義務を果たしていない場合、罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。
① 紙の請求書が適切に保存されているかの確認
税務調査では、請求書が法定期間内に適切に保存されているかを確認されます。ファイリングやデータ化の方法が不十分な場合、経費の証明ができなくなるリスクがあります。
② 電子化して保存している場合の対応
スキャナ保存やクラウド管理を行っている場合、税務調査時に適法な方法で保存している証明を求められることがあります。そのため、電子的に保存する場合は、事前に電子帳簿保存法の要件を満たしているかを確認しておきましょう。
③ 税務調査の際に準備すべき書類
- 直近7年間の請求書
- 保存方法に関する社内ルール
- 請求書の電子保存に関する証明書類(スキャナ保存実施記録など)
適切な保存体制を整え、法令に基づいた管理を行うことが重要です。
電子請求書の保存方法は?
電子請求書を適切に保存することは、電子帳簿保存法の要件を満たし、税務調査時の対応をスムーズにするために重要です。ここでは、電子請求書の保存方法について詳しく解説します。
電子保存のルールと要件
電子請求書を保存する際には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。この法律では、以下のようなルールが定められています。
- 真実性の確保(データの改ざんを防ぐ措置)
- 可視性の確保(必要な時に閲覧できる状態の維持)
- 検索機能の確保(一定の条件に従って検索できること)
これらのルールを満たすために、適切な保存方法を選ぶことが求められます。
タイムスタンプの必要性
電子請求書の保存において、タイムスタンプは重要な役割を果たします。タイムスタンプを適切に付与することで、データの改ざん防止を証明できます。
タイムスタンプの種類
|
タイムスタンプの種類 |
特徴 |
|
電子署名付きタイムスタンプ |
電子署名と組み合わせてデータの真正性を確保 |
|
単独のタイムスタンプ |
認定事業者が発行し、時刻の正確性と改ざん防止を証明 |
法律の要件を満たすためには、適切な方法でタイムスタンプを付与し、一定期間保持することが求められます。
データの改ざん防止策
電子請求書の保存では、データの改ざんを防ぐための対策が必要です。具体的には、次のような方法があります。
- システム内部でのアクセス制限を設定
- ログ管理機能を活用して変更履歴を記録
- タイムスタンプの付与と定期的な検証
- 書類をPDF形式など改ざんが困難なフォーマットで保存
これらの対策を講じることで、電子請求書の真正性を確保できます。
クラウドサービスを利用した保存方法
電子請求書の保存には、専用のクラウドサービスを利用する方法が有効です。クラウドサービスを利用すると、次のようなメリットがあります。
- バックアップ機能が充実しており、データ紛失のリスクを軽減
- 複数の担当者が同時にアクセスして業務を円滑に進められる
- 法令に則った保存環境が備わっているため、自社で要件を満たす負担を軽減できる
クラウドサービス選定のポイント
適切なクラウドサービスを選ぶためには、以下の点に注目しましょう。
|
選定ポイント |
チェックすべき内容 |
|
法令対応 |
電子帳簿保存法の要件を満たしているか |
|
セキュリティ |
データの暗号化・アクセス制限があるか |
|
操作性 |
使いやすいインターフェースで業務効率が向上するか |
|
料金体系 |
自社の予算に合ったプランがあるか |
電子請求書の保存をスムーズにするために、自社の業務に適したクラウドサービスを選ぶことが重要です。
電子保存義務化に向けての対応方法について解説!
電子保存の準備と導入手順
請求書の電子保存を適切に進めるためには、準備段階でしっかりとした計画を立てることが重要です。以下のステップを踏むことで、スムーズに電子保存への移行が可能になります。
|
ステップ |
内容 |
|
1. 現状の確認 |
自社における請求書の管理方法を整理し、電子化の必要性を確認する。 |
|
2. 法律の要件を確認 |
電子帳簿保存法やインボイス制度に関する最新の法規制を把握する。 |
|
3. システムの選定 |
最適な電子保存ツールやクラウドサービスを選定する。 |
|
4. 社内ルールの整備 |
電子データの管理、保管、削除のルールを設定する。 |
|
5. 従業員向けの研修 |
電子保存のフローやツールの使い方を従業員に周知する。 |
|
6. 運用テスト |
テスト環境で電子請求書の保存を試し、実運用に向けた課題を抽出する。 |
|
7. 本格運用開始 |
実運用を開始し、定期的に運用状況を見直す。 |
適切なシステムの選び方
電子保存をスムーズに進めるには、業務に合ったシステムを選ぶことが重要です。選定時には以下のポイントを考慮しましょう。
- 法令対応:電子帳簿保存法に準拠しているかを確認する。
- セキュリティ対策:アクセス制限やデータの改ざん防止機能が備わっているか。
- 操作のしやすさ:従業員が直感的に使えるインターフェイスであるか。
- 他システムとの連携:現在利用している経理・会計ソフトとの連携が可能か。
- コスト:導入・運用コストが適正か。
現在、多くの企業で利用されているクラウド型電子請求書管理システムには「Bill One」「楽楽明細」「freee請求書」などがあります。これらのサービスは、法令対応が進んでおり、安全性も高いため、導入を検討する価値があります。
社内ルールの整備が必要な理由
電子保存を適切に運用するためには、社内ルールを策定し、標準化することが欠かせません。具体的には以下のようなルールを決めておく必要があります。
- 請求書の保管期間:電子データの保存要件を満たし、法定期間の保存を徹底する。
- アクセス権限の設定:どの部署・誰が請求書データにアクセスできるかを明確化する。
- 証憑管理の方法:タイムスタンプを付与するタイミングや改ざん防止の仕組みを決める。
- 定期的な監査:適切に運用されているかを定期的にチェックし、問題を発見次第改善を行う。
これらのルールを明文化し、全社的に周知することで、トラブルを防ぎつつスムーズな運用が可能になります。
従業員への教育と運用のポイント
電子保存を社内で円滑に運用するためには、従業員の理解と協力が不可欠です。教育活動を通じて、電子保存の意義や具体的な運用方法を浸透させましょう。
教育プログラムとしては、以下のような施策が有効です。
- 電子帳簿保存法に関する基礎知識の研修
- 実際の電子請求書管理システムの操作研修
- 電子データの適正な管理・バックアップ方法の周知
- ミスやトラブル発生時の対応フローの確認
従業員の習熟度を高めるために、定期的な勉強会の開催や、マニュアル・FAQの整備を行うことも重要です。特に新しいシステムを導入した際には、混乱を避けるためにしっかりとしたトレーニングを実施しましょう。
また、システムへのログイン状況やデータの更新履歴を定期的に確認することで、適切に運用されているかをチェックし、継続的な改善を行うことが求められます。
以上の対応を進めることで、電子保存の義務化に適切に対応し、業務の効率化やコンプライアンスの強化が図れます。
まとめ
請求書の電子保存は、電子帳簿保存法の改正により、紙の請求書をデータで保存する企業にとって重要な課題となっています。電子保存が義務化されるケースもあり、適切な対応が求められます。一方で、一定の条件を満たせば紙のまま保存することも可能ですが、検索性やリスク管理の観点から電子化が推奨されます。
電子保存の方法としては、電子データの改ざん防止策を講じることが必要で、タイムスタンプの付与やクラウドサービスの活用が有効です。適切なシステムの導入と従業員教育を行い、社内ルールを整備することで、スムーズな運用が可能となります。
今後、電子保存義務化の流れが進む中で、企業は早めに対応を進めることが求められます。法改正の動向を把握し、自社に適した方法を選択することが重要です。










