電子帳簿保存法で自社発行した請求書の扱いは?発行側の保存方法や期間も解説
更新日:2025.09.04
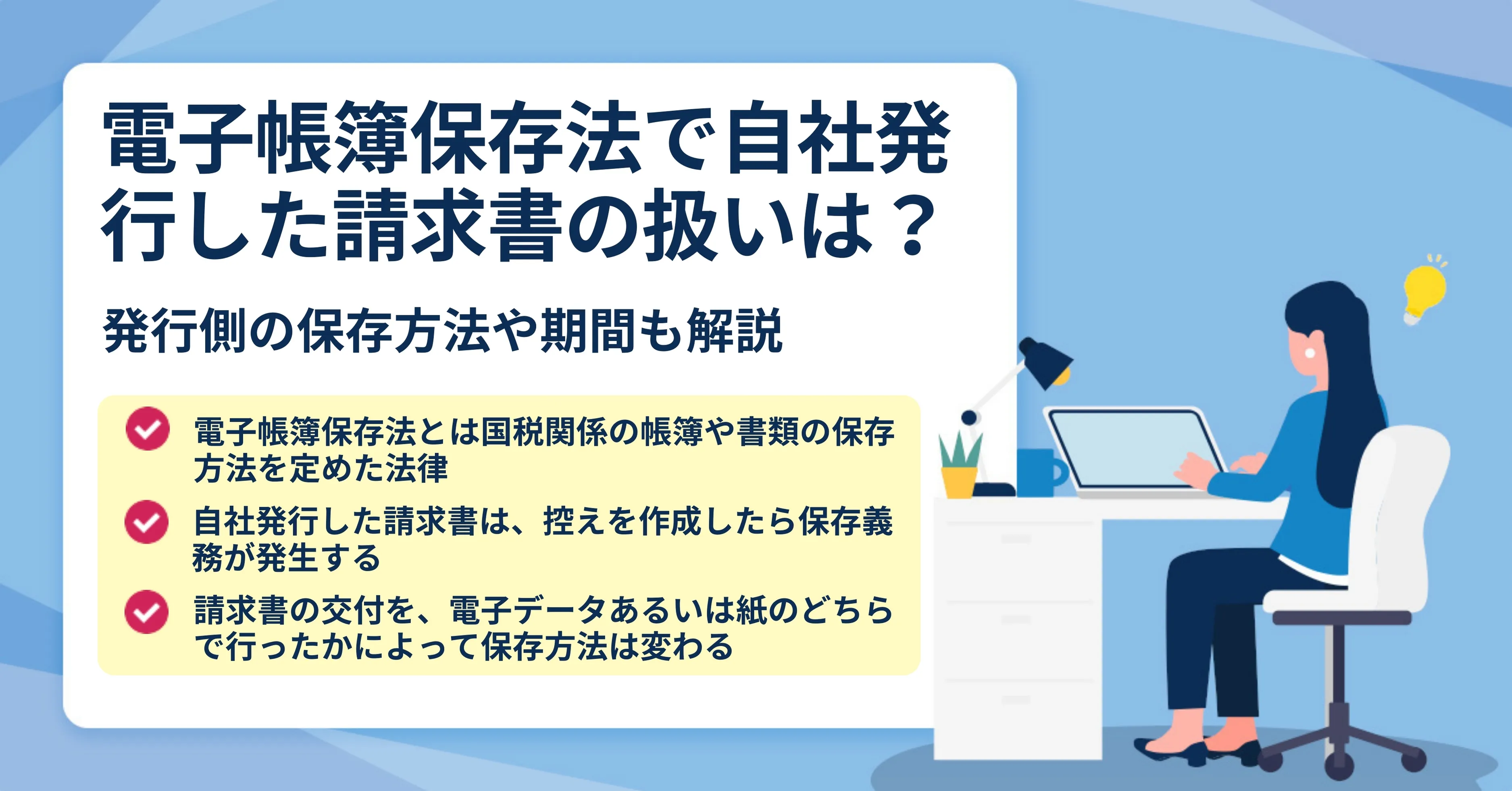
ー 目次 ー
国税関係の帳簿・書類の保存に関するルールを定めた電子帳簿保存法は、2022年に改正されました(※)。請求書も例外ではなく、法改正の影響を受ける部分が多くあります。
電子帳簿保存法に違反してしまうと、罰則を受けるおそれがあるため、経理や会計に携わる場合には基本的な知識を知っておく必要があるでしょう。
本記事では、改正後の電子帳簿保存法における自社発行の請求書の扱いを解説します。控えの作成義務や保存期間もあわせて解説しているため、あわせて参考にしてください。
(※)参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類の保存方法を定めた法律
電子帳簿保存法とは、仕訳帳や請求書などの国税関係の帳簿・書類のデータ保存に関するルールを定めた法律です(※)。
これまで、国税関係の帳簿・書類は紙での保存が義務とされていました。しかし、電子帳簿保存法が制定されたことにより、電子データとしての保存が可能になりました。一方で、メールやチャットなどで送付された電子データの保存は、電子データのままで保存する必要があります。
これらの変更点を知っておかないと、罰則の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
(※)参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
電子保存は3つの区分に分類される
電子帳簿保存法の対象となる帳簿や書類は3種類にわけられ、それぞれ保存方法が異なります。保存方法は以下の3つに区分され、帳簿や書類が作成されたプロセスによって分類されています。
- 電子帳簿等保存:電子データで作成した帳簿・書類を電子データとして保存(※1)
- スキャナ保存:紙で作成、受取した書類をスキャナでスキャンし、電子データとして保存(※2)
- 電子取引データ保存:メールやダウンロードにて、電子データ(PDFなど)として受け取った書類を電子データとして保存(※3)
(※1)参考:国税庁「電子帳簿・電子書類関係」
(※2)参考:国税庁「スキャナ保存関係」
(※3)参考:国税庁「電子取引関係」
改正によって電子取引の電子データでの保存が義務化された
2023年12月31日までは、電子データとして受領した書類であってもプリントアウトして紙で保存できました(※)。しかし、電子帳簿保存法の改正が適用される2024年1月1日以降は、電子データとして受け取った書類は電子データのまま保存することが義務付けられました。
なお、電子データとして保存する際は、保存要件を満たさなければいけません。保存要件は「受け取った請求書の保存要件」で解説しています。
(※)参考:国税庁「電子取引関係」
請求書発行側の控えの作成義務と保存期間とは?
電子帳簿保存法では、請求書の発行側にもルールが定められています。とくに、請求書の控えについてはルールが複雑であるため、電子帳簿保存法に対応するためにも正確な知識を理解しなければなりません。
ここでは、請求書発行側の控えの作成義務・保存期間について、解説します。
発行側は控えを作成したら保存が義務!保存期間のポイントを解説
請求書発行側は、控えの作成義務はありません。ただし、控えを作成した場合に保存義務が生じます。なお、控えの保存方法は以下のとおりです。
|
控えを電子データで作成した場合 |
電子データで保存 |
|
控えを紙で作成した場合 |
紙か電子データのどちらかで保存するか選択可能 |
①法人の保存期間は7年
法人の場合、請求書の控えの保存期間は7年間です。
保存期間のスタート日は、控えを作成した年の確定申告の期日の翌日になります。たとえば、請求書の発行日を2024年の5月、確定申告の期日を2025年3月15日とします。この場合、保存期間のスタート日は2025年3月16日です。
また、請求書を発行した年に欠損金が生じると保存期間は10年に延長します。
②個人事業主の保存期間は5年
個人事業主の場合、請求書の控えの保存期間は5年間です。
保存期間のスタート日は、控えを作成した年の確定申告の期日の翌日になります。たとえば、請求書の発行日を2024年の1月、確定申告の期日を2025年3月15日とします。この場合、保存期間のスタート日は2025年3月16日です。
③一定額以上の副業収入がある人の保存期間は5年間
前々年の副業収入が300万円を超えている場合、請求書や領収書などの現金預金取引関係の書類を5年間保存する義務があります。
保存期間のスタート日は、請求書の控えを作成した年の確定申告の期日の翌日になります。たとえば、請求書の発行日を2025年12月、確定申告の期日を2026年3月15日、2023年の副業収入を400万円で仮定すると、保存期間のスタート日は2026年3月16日です。
適格請求書発行事業者は控えの作成・保存が義務付けられている
インボイス制度の新設により、適格請求書を発行できるようになりました。適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書を交付する際には控えを作成し7年間保存しなければいけません。
なお、保存期間のスタート日は、適格請求書を交付した年の確定申告の期日の翌日から2ヶ月後になります。たとえば、請求書の発行日を2025年8月、確定申告の期日を2026年3月15日とします。この場合、保存期間のスタート日は2026年5月16日です。
【電子帳簿保存法に対応】自社で発行した請求書控えの保存方法
電子帳簿保存法では、請求書を電子データで作成・交付した場合と、紙で作成・交付した場合で、保存方法が異なります。電子帳簿保存法に違反しないためにも、控えの保存方法を確実に認識して、対応できるようにしてください。
ここでは、自社で発行した請求書控えの保存方法について、解説します。
請求書を電子データで作成・交付した場合
請求書を電子データで作成・交付した場合、控えも電子データで保存する必要があります。この際、電子取引の保存要件を満たさなければいけません。
なお、電子取引の保存要件については「電子取引のデータ保存の要件」で解説しています。
請求書を紙で作成・交付した場合
請求書を紙で作成・交付した場合、控えは紙あるいは電子データのどちらかで保存する必要があります。発行側はどちらの保存方法を選んでも問題ありません。
なお、電子データで保存する場合、スキャナ保存の要件を守る必要があります。スキャナ保存の要件については「スキャナ保存の要件」で解説しています。
電子帳簿保存法の改正で新しくなった保存要件
受け取った請求書を保存する際には、必ず電子帳簿保存法の保存要件を満たさなければいけません。しかし、法改正によって、保存要件が変更されたため、変更点に注意する必要があるでしょう。
ここでは、電子帳簿保存法の改正で新しくなった保存要件について、解説します。
電子取引のデータ保存の要件
電子取引データとは、メールの添付やクラウドサービスからのダウンロードで取得できる書類データです。
電子帳簿保存法の改正後、電子取引のデータは電子データのまま保存することになりました。電子データとして保存する際は「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。
真実性の確保とは?
「真実性の確保」とは、その電子データが信用できるのか保証するためのルールです。要件を満たすためには、法律で定められた以下の4つのうち1つを満たさなければいけません。
- タイムスタンプが付与された電子データで取引をおこなった
- 電子データの受取後、すぐにタイムスタンプを付与した
- 訂正や削除の履歴が残る、あるいは訂正や削除ができないシステムで電子データを保存した
- 不要な訂正や削除を防ぐためのルールを設定し、そのルールに従う
可視性の確保とは?
「可視性の確保」とは、その電子データを確実に閲覧できるようにするためのルールです。要件を満たすには、以下の3つの要素をすべて満たさなければいけません。
- 電子データを閲覧するための機材、機材のマニュアル、プリンターを保存場所に設置し、すみやかに出力できるようにしておく
- システムのマニュアルを備え付ける
- 検索機能を確保する
なお、3つ目の「検索機能の確保」にも要件があり、以下の3つを満たす必要があります。
- 取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
- 日付、金額の範囲指定で検索できる
- 2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
スキャナ保存の要件
紙で作成された書類をスキャンし電子データとして保存する場合、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。重要書類と一般書類で要件が異なるので注意しましょう。
|
要件(※) |
重要書類 |
一般書類 |
過去分重要書類 |
|
入力期間の制限 (書類の受領等後または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、すみやかに入力) |
◯ |
||
|
一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り |
◯ |
◯ |
◯ |
|
カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上) |
◯ |
◯ |
|
|
タイムスタンプの付与 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
解像度及び階調情報の保存 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
大きさ情報の保存 |
◯ |
◯ |
|
|
ヴァージョン管理 (訂正または削除の事実及び内容の確認) |
◯ |
◯ |
◯ |
|
入力者等情報の確認 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
適正事務処理要件 |
◯ |
◯ |
|
|
スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け |
◯ |
◯ |
|
|
整然・明瞭出力 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け |
◯ |
◯ |
◯ |
|
検索機能の確保 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
税務署長の承認 |
◯ |
◯ |
(※)参考:国税庁「Ⅱ 適用要件【基本的事項】」
なお、スキャナ保存の要件には上記以外にも細かな要件が設定されている箇所が多いため、国税庁の公式サイトにて一度確認するようにしましょう。
まとめ|自社発行の請求書を正しく扱って法改正に対応しよう
本記事では、改正後の電子帳簿保存法における自社発行の請求書の扱いを解説しました。
電子帳簿保存法を理解していないと、知らない間に法律に反するおそれがあります。電子帳簿保存法の罰則はさまざまで、会社法の違反に該当する場合、100万円以下の過料が科せられるケースがあります(※)。そのため、請求書を発行する際は、電子帳簿保存法について詳しく理解し、適切な対応をおこなうようにしましょう。
不安であれば、弁護士や専門家などの詳しい人に聞くのがおすすめです。電子帳簿保存法の法改正はこれからもおこなわれる可能性が高く、常に相談できる専門家が近くにいれば安心できるでしょう。
(※)参考:e-Gov 法令検索「会社法|第九百七十六条」









