請求書の日付は末日とは限らない!インボイス制度に対応した作成方法も解説
更新日:2025.01.30
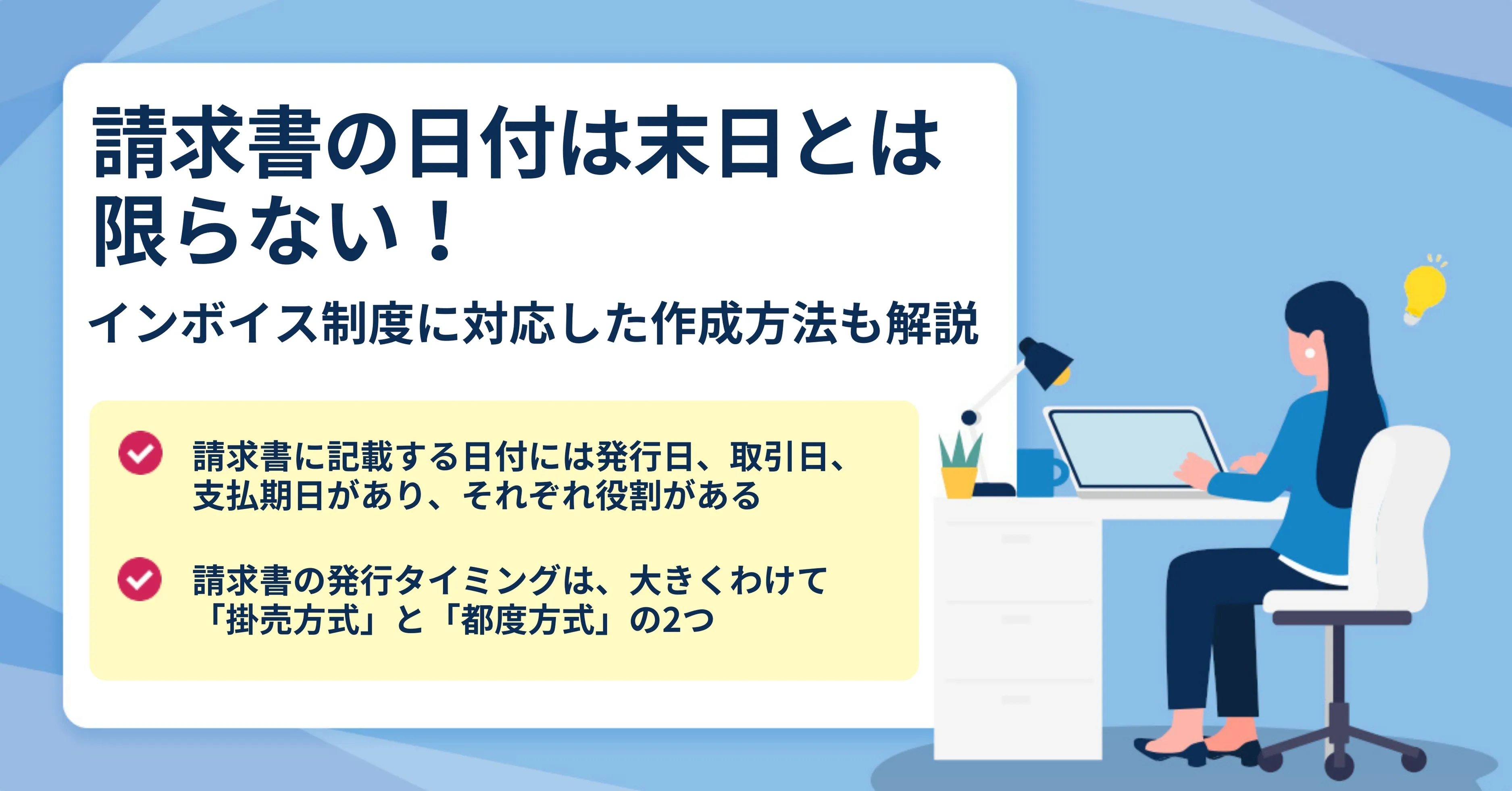
ー 目次 ー
請求書の発行は企業活動で重要な業務の1つですが、日付の設定に悩む方も少なくありません。とくに、「請求書の日付は月末にすべきか」といった疑問を持つ方が多いようです。
実際には、請求書の日付は必ずしも末日である必要はなく、取引形態や取引先との契約内容ごとに柔軟に設定が可能です。
また、2023年10月からインボイス制度が開始され、請求書の記載や保存、消費税の計算方法などが変更となっています。したがって、請求書の日付設定とあわせて、インボイス制度への対応も求められています。
本記事では、請求書の日付の設定の仕方について、インボイス制度に対応した作成方法とあわせて解説します。
【結論】請求書の日付は末日以外の場合もある
請求書の日付は、必ずしも末日である必要はありません。前提として、請求書には、発行日、取引日、支払期日の3つの重要な日付を記載する必要があります。
それぞれの日付の意味は、以下のとおりです。
|
発行日 |
請求書を発行した日 |
|
取引日 |
実際の取引がおこなわれた日 |
|
支払期日 |
代金の支払期限 |
これらの日付は、取引先の締め日(取引を集計する期間の区切り)ごとに異なり、たとえば10日締め、15日締め、20日締めなど、企業によってさまざまです。締め日は請求書の発行日を決める基準となるため、事前に取引先の締め日を確認しておく必要があります。
また、請求書に日付の記載がないと、架空取引や不正を疑われるかもしれません。とくに、複数月にわたって同じ金額の取引がある場合、日付がないと取引内容の特定が困難になり、トラブルの原因となる可能性があります。
以下の関連記事では、請求書の締め日について解説しているため、あわせて参考にしてください。
関連記事:請求書の締め日はどちらが決める?支払期日との違いや過ぎた場合の対応を解説
請求書発行の2つのタイミングとは?
請求書の発行タイミングは、大きくわけて「掛売方式」と「都度方式」の2つがあります。
それぞれの特徴を理解して、取引内容や取引先との関係性に応じた適切な方法の選択が重要です。また、法令遵守の観点から、下請取引の場合は支払期限に関する規制にも注意が必要です。
ここでは、請求書発行の2つのタイミングについて、それぞれ解説します。
①掛売方式
掛売方式は、一定期間(通常1か月)の取引をまとめて請求する方式です。たとえば月末締めの場合、その月の1日から末日までの取引を一括して請求します。
掛売方式では、複数回の取引があっても請求書は1枚のみ発行するため、効率的な事務処理が可能です。とくに継続的な取引がある企業同士でよく採用される方式で、取引先の経理処理の効率化にも貢献できます。
②都度方式
都度方式は、取引が発生するたびに請求書を発行する方式です。商品の納品やサービスの提供が完了した時点で請求書を発行するため、タイムリーな売上計上が可能です。
都度方式は新規取引先との取引や、継続的な取引予定がない場合は、個人向けビジネスなどで採用されることが多いです。ただし、取引頻度が高い場合は事務処理の負担が増加するため、取引先と相談するなどして掛売方式への変更を検討しましょう。
請求書の記載項目とは?インボイス制度に対応した方法も紹介
請求書には基本的な記載項目があり、さらにインボイス制度への対応で新たな記載項目が追加されています。適切な記載がないとインボイスとして認められず、取引先が仕入税額控除を受けられないといった問題が発生するかもしれません。
ここでは、請求書の記載項目について、インボイス制度に対応した方法とあわせて解説します。
①請求書の基本的な記載項目
請求書の基本的な記載項目は、以下のとおりです。
- 発行年月日
- 請求書番号
- 宛先
- 請求金額(税込)
- 支払期日
- 発行者情報
- 取引内容(品名・数量・単価)
- 請求金額の内訳(小計・消費税額・税込額)
- 振込先情報
とくに、日付と金額に関する情報は、取引の根拠となる重要な項目のため、正確に記載しましょう。
②インボイス制度に対応した請求書の記載項目
インボイス制度では従来の記載項目にくわえて、以下の記載が必須です。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
また、軽減税率の対象品目がある場合は、その旨を明記する必要があります。これらの項目がないとインボイスとして認められないため、登録番号の記載漏れや税率の区分ミスがないよう、十分な確認が必要です。
請求日と支払期日の決め方
請求日と支払期日は、取引先との契約内容や商慣習に基づいて設定します。適切な日付設定は、円滑な資金繰りと良好な取引関係の維持に重要です。
ここでは、請求日と支払期日の決め方について、それぞれ解説します。
①掛売方式の場合の請求日の決め方
掛売方式では、締め日に合わせて請求日を設定します。月末締めの場合は末日付、15日締めの場合は15日付で請求書を発行するのが一般的です。
たとえば、1月20日に納品した商品の請求書を発行する場合、取引先が月末締めであれば1月31日付で請求書を作成します。
また、請求書の発行が遅れると取引先の入金サイクルにも影響が出る可能性があるため、締め日までに確実に請求書を発行できるよう準備しておくことが重要です。とくに、決算期をまたぐ場合は、今期中に完了している業務を翌期の日付で請求すると「期ずれ」が発生し、決算処理に影響を与えるため注意が必要です。
②都度方式の場合の請求日の決め方
都度方式の場合は、商品納入日やサービス提供完了日が請求日です。都度方式では、売上が立つのと同時に請求金額が確定するため、掛売方式のように締め日まで待つ必要はありません。取引日と請求日が一致することで、どの取引に対する請求なのかが明確になるため、取引先との金額の認識違いや、支払遅延などのトラブルを防げます。
都度方式は、おもに継続的な取引予定がない場合や、個人向けビジネスで採用されることが多い方式です。ただし、取引頻度が高くなってきた場合は業務負担が増加するため、取引先と相談のうえ、掛売方式への移行を検討することで効率化が期待できます。
③支払期日の決め方
支払期日は一般的に「月末締め翌月末払い」や「月末締め翌々月末払い」などのパターンが多く採用されています。ただし、支払期日は取引先ごとに異なる場合もあるため、契約時に明確に定めておきましょう。
とくに下請取引の場合は「下請代金支払遅延等防止法」で商品やサービスを受領してから60日以内の支払いが義務付けられています。支払期日を当事者間の話し合いで自由に決められるとはいえ、下請け会社やフリーランスへの支払いは、この法定期限を超えないよう注意が必要です。
効率的な請求書作成におすすめな請求書発行システム・サービス3選!
請求書の作成業務を効率化したい場合、請求書発行システムの導入を検討しましょう。システムの導入には、インボイス制度対応やデータ管理の面でもメリットがあります。
ここでは、効率的な請求書作成におすすめな3つの請求書発行システム・サービスについて、それぞれ解説します。
①OneVoice明細
OneVoice明細は、複数の帳票を一括で作成・管理できるシステムです。請求書の自動作成機能や、取引先ごとの設定保存など、使い勝手の良さが特徴です。
また、無料トライアルも用意されているため、導入前に実際の使用感を確認できます。
②freee請求書
freee請求書は、40種類以上のテンプレートから選んで簡単に請求書を作成できる無料サービスです。インボイス制度で必要な記載要件を満たした適格請求書の作成に対応しており、自動計算機能で入力ミスを防げます。
③請求管理ロボ(ROBOT PAYMENT)
請求管理ロボは、請求業務を最大80%削減できる自動化システムです。請求書の発行から入金管理まで一括で対応可能で、さまざまな決済手段にも対応しています。
販売管理システム(SFA)との連携機能も備えており、業務効率の大幅な向上が期待できます。
まとめ|請求書発行システムでインボイス制度に対応した請求書を作成しよう
本記事では、請求書の日付の設定の仕方について、インボイス制度に対応した作成方法とあわせて解説しました。
請求書の日付設定は、必ずしも末日である必要はなく、取引形態や契約内容に応じた適切な設定が重要です。また、インボイス制度への対応も必須となっており、記載項目の追加や様式の見直しが必要です。
これらの課題に対応するため、請求書発行システムの導入の検討をおすすめします。システムの活用で、正確かつ効率的な請求書作成が可能になり、インボイス制度への対応も円滑に進められます。自社の規模や業務内容にあわせて、適切なシステムを選択しましょう。










