電子帳簿保存法はいつから義務化?罰則や導入手順も解説
更新日:2025.03.27
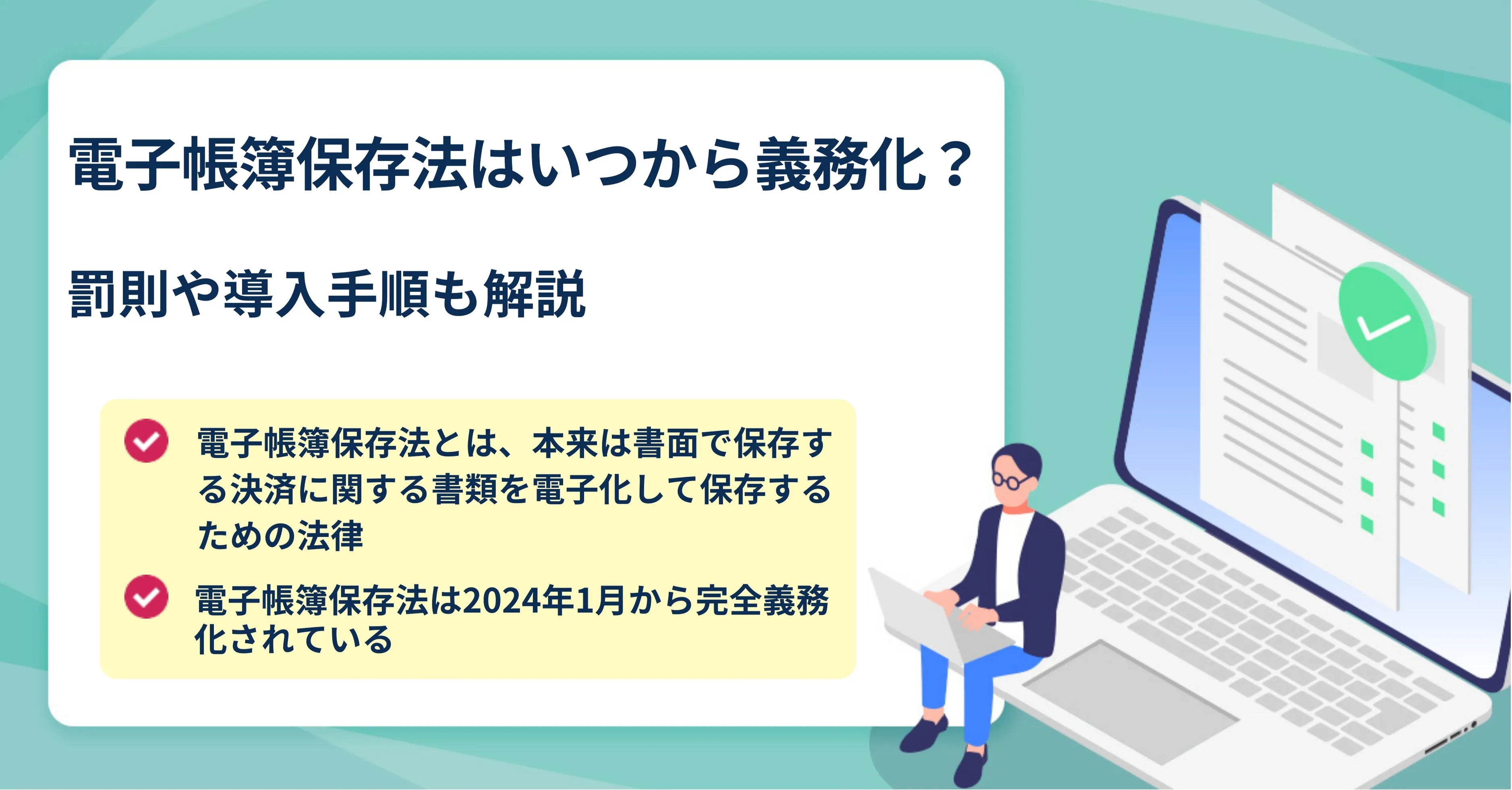
ー 目次 ー
電子帳簿保存法(電帳法)とは、会社の税金に関係する取引の記録や書類を、デジタル形式で保存する際のルールです。2022年に法律が見直され、2年間の宥恕(ゆうじょ)期間を経て、本格的に義務化されました。
しかし、法律の見直しによって要件の一部が変更されたため、事業者の中には知らないうちにルール違反の状態になっている人もいるかもしれません。もし違反してしまうと、事業者は青色申告の取消といった罰則が発生するため注意が必要です。
本記事では、電帳法の義務化の内容にくわえて、罰則や導入の手順についても解説します。
【前提】電子帳簿保存法とは電子化した会計書類を保存するためのルール
電子帳簿保存法とは、会社の取引記録にかかわる書類を、デジタル形式で保存する際のルールです。税務に関する帳簿や書類を使うすべての事業者に適用されます。
そのため、とくに会計や経理周りの業務に従事する担当者は内容を把握しておかなければなりません。場合によっては罰則を受けるおそれもあるため、注意しておきましょう。
保存する方法として、以下の3つの区分が用意されています。
|
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・ 書類をデータのまま保存) ②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存) ③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存) |
電子帳簿保存法の保存要件とは?
デジタルで保存する書類については、2つの保存要件が定められています。保存要件はわかりづらく、誤った認識でトラブルになりかねない内容となっています。
このようなことから、会計や経理業務に携わる担当者は電子帳簿保存法の保存要件について理解しておくことが大切です。
ここでは、電子帳簿保存法の保存要件について解説します。
①真実性の担保
内容に誤りや不当な修正がない状態のことを「真実性」といいます。データを後から勝手に変更されていないと証明できる仕組みを用意することで、担保が可能です。
電子帳簿保存法では、この「真実性の担保」が要件となっています。具体的には、以下の方法を施すことで、データが本物と証明ができます。
|
次のいずれかの措置を行う(規81) 一 タイムスタンプが付された後の授受 二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用 四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け |
②可視性の担保
すぐに見て確認ができる状態のことを「可視性」といいます。保存している書類を検索して確認できるようにしておくといった仕組みを用意することで、担保できます。
電子帳簿保存法では真実性の担保にくわえて、「可視性の担保」も要件としています。以下の3つの条件をそれぞれ用意すると可視性があると判断可能です。
|
電子帳簿保存法の義務化に関する注意点
書類を保存する担当者は、いくつかのポイントに注意する必要があります。間違った方法で保存すると、電子帳簿保存法に違反して、大きなトラブルになるおそれがあります。
電子帳簿保存法に関しての適切な理解が大切です。
ここでは、電子帳簿保存法の義務化に関する注意点について詳しく解説します。
電子帳簿保存法は2024年1月から完全義務化されている
国税庁は経済社会のデジタル化の浸透を踏まえ、電帳法の根本的な見直しを実施しました。2022年に法改正を施行した後、企業が準備するために宥恕(ゆうじょ)期間(※)が用意されていました。この宥恕期間は2年で終了し、2024年1月から義務化となりました。
一方で、以下の条件を満たしている場合は、引き続き措置が用意されています。
|
⑴ 電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存する ことができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると 認める場合(事前申請等は不要です。) ⑵ 税務調査等の際に、
にそれぞれ応じることができるようにしている場合 |
※施行後に企業が環境整備をする期間
関連記事:電子帳簿保存法の宥恕期間とは?義務化後の対処法についても徹底解説。
電子帳簿保存法の不正は罰則をうけるリスクがある
デジタルで管理しているデータにおいて、「真実性」と「可視性」がない場合は不正と判断されるリスクがあります。不正と判断された場合、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。なお、違反した場合には、以下の罰則が課せられます。
- 青色申告の取消
- 重加算税が課される
- 100万円以下の過料
青色申告の取消が発生すると最大65万円の控除や、赤字の繰越控除などが受けられなくなります。また、重加算税や過料は、企業の財務状況を圧迫するでしょう。
義務化された電子帳簿保存法を導入する4つの手順
取引で使用した書類は電子帳簿保存法の定められたルールにしたがって管理します。
しかし、正しい手順で導入しないと、管理の仕方が統一されないため、必要な書類がすぐに見つからないといったトラブルにつながるおそれがあるでしょう。
ここでは、電子帳簿保存法を導入する4つの手順を紹介します。
①現在の取引を把握する
まず自社で扱っているすべての会計書類の管理状況を把握しましょう。デジタルデータの書類を洗い出すことで現状を整理し、法律の要件に沿った方法での保存を決められます。
メールでのやり取りだけでなく、取引先からPDF形式で送られる請求書や、オンラインで受け取った領収書なども対象となります。
社内の各部署にヒアリングを実施し、どの書類がデジタルデータで存在しているか確認することがおすすめです。
②電子データの保存方法を決める
デジタルデータを把握できたら、次に真実性と可視性が満たされた保存方法を決めます。
たとえば、データを変更したときに記録を残したり、ファイル名のつけ方のルールを決めて、必要なときにすぐに書類を見つけられたりするようにしましょう。
定められている保存方法を理解して、自社での対応方法を決めます。
③システムを導入する
保存方法の方針を確定した後は、社内で使用するシステムを導入しましょう。
システムの導入を検討する際には、必要な機能が十分に備わっているか確認しておくことで、導入後の齟齬を減らせます。具体的には、以下の機能が充実しているものを選ぶと良いでしょう。
- タイムスタンプ機能
- アクセス権限の管理
- 検索機能
システムの導入や運用には費用がかかりますが、デジタル書類の管理が一元化され、探す手間や保管スペースの削減が可能になるため、業務効率化につながるでしょう。
④業務の流れを整える
システムを導入できたら、社内の業務フローを整えましょう。業務フローが確立していない場合、管理があいまいになってしまい適切に運用できなくなる可能性があるためです。
たとえば、以下のように業務のなかにルールとして取り決めをしましょう。
- メールで請求書を受け取ったら3営業日以内にシステムに登録する
- 月末に部門ごとにデータ保存状況をチェックする
業務フローが確立した後は、文書化して社内に共有し、必要に応じて研修も実施することで、全社員がデータを管理できる体制が整えられます。
電子帳簿保存法を導入する時に活用したいシステム3選
デジタルでの帳簿保存を社内で導入する際には、専用のシステムを活用することがおすすめです。システムを活用することで要件の遵守ができるだけでなく、自動化による業務効率化も期待できるでしょう。
ここでは、電子帳簿保存法を導入する際に活用したい3つのシステムを紹介します。
①OneVoice明細
OneVoice明細とは、各種帳票をアップロードするだけで書類の作成や発行が完了するクラウド型のシステムです。
電子帳簿保存法に対応しており、要件にあわせた管理もできます。また、各種帳票のレイアウトが豊富に用意されているため、必要な情報を入力すると即座に書類が完成します。電子請求書に関する業務を一括代行してもらえるため面倒な発行業務の負担を90%も軽減可能です。
導入する前でも実際に試し使いが可能なため、システムの使い心地が不安な方にもおすすめです。
②TOKIUMインボイス
TOKIUMインボイスは請求書の受領を代行し、支払い漏れを防ぐ管理システムです。
電子帳簿保存法やインボイス制度にも完全対応しており、法改正が今後発生しても安心して利用できます。また、請求書の事務業務を代行してもらえるため、作業にかかっていた時間を8割削減が可能です
このシステムは上場企業が250社以上も導入しているといった実績も豊富であり、人気のクラウドシステムといえるでしょう。
③楽楽電子保存
楽楽電子保存は電子帳簿保存法に特化した文書の一元管理システムです。
書類を読み込ませることで文字を自動で読み取るため、作業の手間が削減できます。さらに読み取った文字からファイル名も自動でつけられるため、索引簿の作成も手軽になります。
操作も簡単なため、社内に浸透させやすく企業の業務フローにも組み込みやすいでしょう。
まとめ|システムを活用して義務化された電子帳簿保存法の作業を効率化させましょう
本記事では、電帳法の義務化や要件をもとに違反した際の罰則や導入手順を解説しました。
定められた要件では、真実性と可視性の担保が求められています。もし、適切に保存ができていない場合、青色申告の取消や重加算税などの罰則を受けなければなりません。
全社員が管理する際には、システムの導入がおすすめです。システムを活用して会社全体での効率化を目指しましょう。










