電子帳簿保存法の重要書類と一般書類の違いとは?分類基準や保存要件のポイントを解説
更新日:2025.07.28
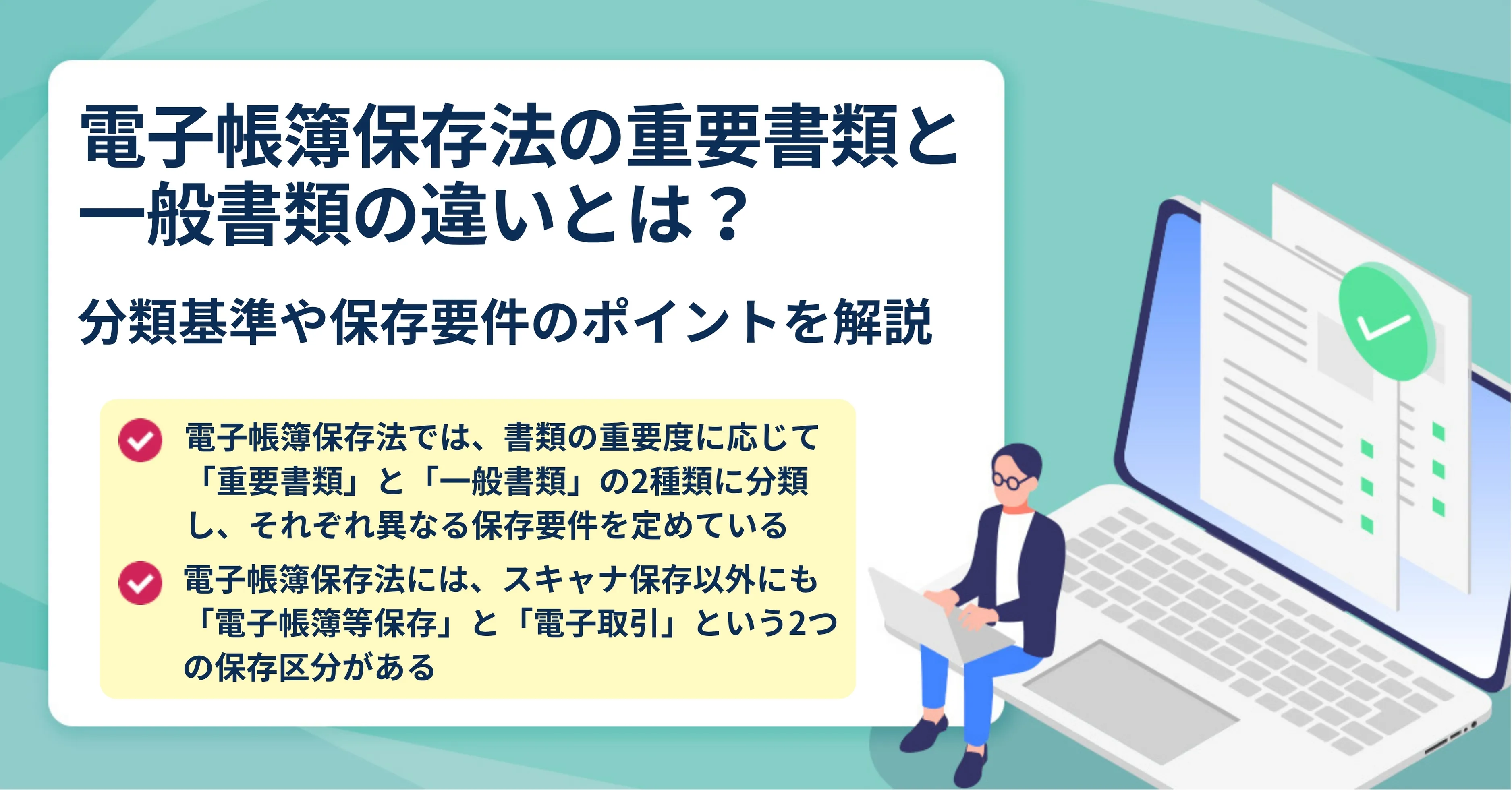
ー 目次 ー
電子帳簿保存法において、スキャナ保存の区分では書類を「重要書類」と「一般書類」の2つに分類しており、それぞれ異なる保存要件が定められています。この分類を正しく理解していないと、法令違反や税務調査の際に指摘を受けるなどのトラブルが発生するかもしれません。
とくに、重要書類と一般書類では入力期間の制限や読取情報の保存などの要件が大きく異なるため、適切な対応が求められます。また、書類の名称だけではなく実際の記載内容によって分類が変わる場合もあるため、慎重な判断が必要です。
本記事では、電子帳簿保存法の重要書類と一般書類の違いについて、分類基準や保存要件のポイントもあわせて解説します。
電子帳簿保存法における重要書類と一般書類とは?
電子帳簿保存法における「重要書類」と「一般書類」の分類は、おもに紙で受領した書類や紙で発行した控えなどをスキャナ保存する際に適用されます。これらは書類の重要度ごとに電子化する際の要件の厳しさが異なるため、正しい分類が重要です。
ここでは、重要書類と一般書類の基本的な定義と分類の違いについて解説します。
重要書類とは、資金や物の流れに直結・連動する書類
重要書類とは、資金や物の流れに直接関わる書類のことです。とくに、一連の取引過程の開始時点と終了時点の取引内容を明らかにし、取引の途中で作成される書類の真実性を補完する役割を持つ書類が含まれます。
具体的には、契約書や領収書などは重要度が高く、請求書や納品書はその次の重要度として分類されます。これらの書類は取引の根拠となる重要な証拠書類のため、保存要件が厳格です。
一般書類とは、資金や物の流れに直結・連動しない書類
一般書類は、資金や物の流れに直接関わらない書類のことで、法定保存文書のなかでは重要度が低いものの、保存義務がある書類を指します。
検収書や見積書、注文書などが該当し、取引の参考情報として重要ですが、重要書類と比べて保存要件が緩やかに設定されています。
なお、一般書類であっても、重要書類の保存要件を満たして保存することは問題ありません。実際、管理の簡素化のため、重要書類の要件ですべての書類を保存している企業も存在します。
両者は保存要件が異なるため注意が必要
重要書類と一般書類では、入力期間の制限や読取情報の保存などの点で保存要件が大きく異なります。保存要件を満たさない場合は、スキャナ保存として認められずに税務調査での指摘や青色申告の承認取り消しなどを受けるかもしれません。
重要書類と一般書類のそれぞれ異なる保存要件は、以下のとおりです。
|
要件項目 |
重要書類 |
一般書類 |
|
入力期間の制限 |
・制限受領後、速やか(おおむね7営業日以内)に入力 |
適時に入力 |
|
解像度・カラー画像による読み取り |
解像度200dpi以上かつ、赤・緑・青それぞれ256階調(24ビットカラー)以上のカラー画像 |
白黒階調(グレースケール)での読み取りも可能 |
|
帳簿との相互関連性 |
2024年1月1日以降は必要。スキャンした記録事項と、関連する国税関係帳簿の記録事項との間で、相互にその関連性を確認できること |
2024年1月1日以降は不要 |
|
見読可能装置 |
・14インチ以上のカラーディスプレイおよびカラープリンタ、操作説明書を備え付けること |
白黒階調保存の場合は、ディスプレイおよびプリンタはカラー対応である必要はない |
スキャナ保存以外の電子帳簿保存法の保存区分とは?
電子帳簿保存法には、スキャナ保存以外にも「電子帳簿等保存」と「電子取引」の2つの保存区分があります。これらの区分は、書類の作成・授受方法によって適用される保存要件が異なるため、自社で扱う書類がどの区分に該当するかを正しく理解することが重要です。
とくに、2024年1月1日以降は電子取引データの保存が義務化されており、適切な対応が求められています。
ここでは、スキャナ保存以外の保存区分の詳細について解説します。
- 電子帳簿等保存
- 電子取引
①電子帳簿等保存
電子帳簿等保存は、事業者が自らパソコンなどで作成した帳簿や書類を電子データとして保存するための区分です。国税関係帳簿および国税関係書類のうち、事業者が最初から電子的に作成したものが対象となります。
電子帳簿等保存の対象書類は、以下のとおりです。
- 国税関係帳簿:仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳など
- 国税関係書類:決算関係書類や取引関係書類など
保存する際には、訂正や削除を確認できるシステム、または訂正や削除をおこなえないシステムの利用や検索機能の確保などの要件を満たす必要があります。「優良な電子帳簿」として認定されれば、過少申告加算税の軽減や青色申告特別控除の適用も可能です。
②電子取引
電子取引は、電子メールやEDI(電子データ交換)、クラウドサービスなどを通じて授受された取引情報を保存するための区分です。電子的に授受された請求書や領収書などの取引関係書類が対象となります。
2024年1月1日以降、電子的に授受した書類は電子データでの保存が義務化されており、紙での保存は認められません。ただし、紙で受け取った書類は引き続き紙での保存が可能です。
保存する際には、タイムスタンプの付与や改ざん防止システムの利用などの真実性の確保と検索機能や明瞭な出力機能などの可視性の確保の要件を満たす必要があります。保存要件には一定の猶予措置はありますが、基本的には電子データでの保存が必須です。
重要書類と一般書類の保存におすすめのシステム3選
電子帳簿保存法対応のシステムは、法令で定められた保存要件を満たすよう設計されているため、重要書類と一般書類の両方を適切に保存できます。これらのシステムを利用することで、重要書類と一般書類の保存要件を効率的に満たせるだけではなく、書類管理業務の大幅な効率化も実現可能です。
ここでは、電子帳簿保存法対応のおすすめシステム3選について解説します。
- OneVoice明細
- 弥生会計
- Fleekdrive(電子帳簿保存法オプション)
関連記事:電子帳簿保存法対応のシステムとは?導入するメリットや選ぶ際のポイントも解説
①OneVoice明細
OneVoice明細は、株式会社インボイスが提供しているクラウド型システムです。請求書・納品書・支払明細・支払通知書・領収書など、ほとんどの帳票類に対応しており、現在使っているレイアウトもそのまま利用できます。
導入後2か月は専任スタッフが伴走サポートし、2か月目以降も電話・メールで継続的な支援を受けられます。初期費用は10万円、月額費用は25,000円からとなっており、コストパフォーマンスに優れています。
帳票の発行・受取を効率化したい企業や導入する際に伴走的サポートが欲しい中小企業におすすめです。
②弥生会計
弥生会計は、仕訳帳・総勘定元帳などの重要書類の電子帳簿等保存に対応した会計ソフトです。初心者向けのUIで導入・操作もわかりやすいのが特徴で、スマート証憑管理と連携すれば、一般書類も一元管理できます。
会計ソフトも一緒に導入して帳簿と証憑を一元管理したい事業者や、青色申告や法人決算を電子化・効率化したい事業者におすすめです。
③Fleekdrive(電子帳簿保存法オプション)
Fleekdriveは、スキャナ保存・電子取引データの両方に対応したクラウドストレージサービスです。タイムスタンプ・検索機能・アクセス制御など、法令要件をしっかりとクリアしています。
保存対象ファイルの自動分類・自動保管が可能で、ワークフロー機能で証憑の承認プロセスも一元化できます。
保存要件を厳格に満たしつつ、柔軟に運用したい中〜大規模事業者やセキュリティとコンプライアンスを重視する事業者におすすめです。
まとめ|重要書類と一般書類の分類を理解して、適切なシステム導入を!
本記事では、電子帳簿保存法の重要書類と一般書類の違いについて、分類基準や保存要件のポイントもあわせて解説しました。
重要書類は資金や物の流れに直結する書類で厳格な保存要件があり、一般書類はそれ以外の書類で比較的緩やかな要件となっています。書類を分類する際には、書類の名称だけではなく、実際の記載内容で分類を判断し、不明な場合は税理士や税務署に確認することが重要です。
電子帳簿保存法対応システムの導入で、法令遵守を確保しながら書類管理業務を大幅に効率化できます。自社の業務規模や要件に応じて、適切なシステムを選択し、効率的な書類管理体制を構築しましょう。










