電子帳簿保存法の改ざん防止措置とは?対応するシステムも解説
更新日:2025.07.28
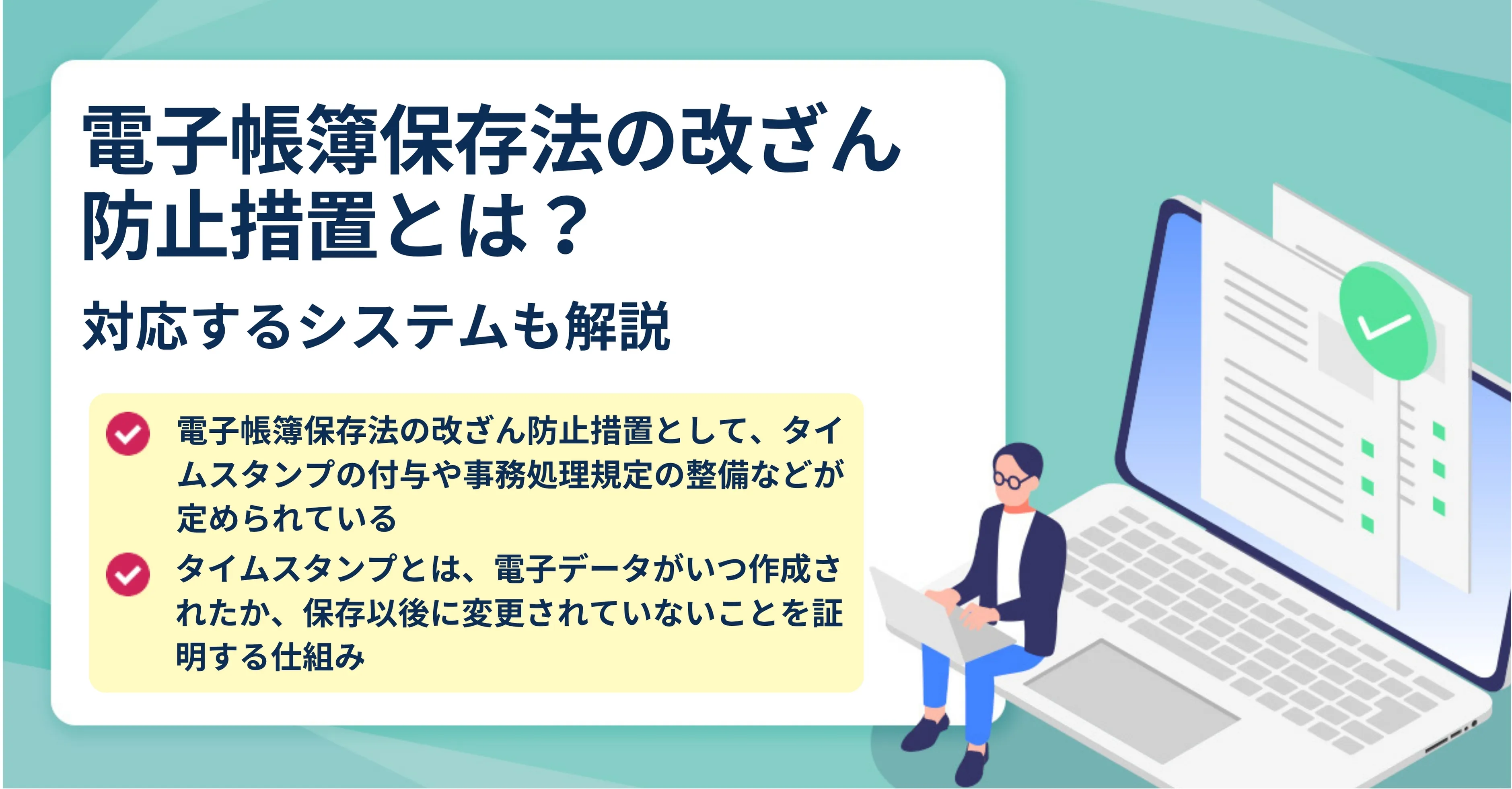
ー 目次 ー
電子帳簿保存法では、国税関係の帳簿や請求書・納品書などの書類データを保存する際に、改ざん防止措置の導入が法律で義務付けられています。
改ざん防止措置にはタイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の記録、事務処理規程の整備などが設けられており、事業者はいずれかに対応しなければなりません。
必要な措置を導入せずに電子保存をおこなうと、税務調査で法令違反とみなされ、青色申告の取り消しや追徴課税などの罰則を受ける可能性があります。
事業者が電子帳簿保存法に対応する際は、あわせて改ざん防止措置への理解も深めて、必要な準備をしましょう。
本記事では、電子帳簿保存法における改ざん防止措置について、対応するシステムも交えて解説します。
【前提】電子帳簿保存法の要件を満たすためには改ざん防止措置が必要
電子帳簿保存法では、データを保存する際に、「真実性の確保」と「可視性の確保」という保存要件が定められています。電子帳簿保存法における改ざん防止措置とは、この真実性の確保に記載された内容のことです。
電子帳簿保存法の保存要件は、「電子取引」と「スキャナ保存」で異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが、法令違反の防止につながります。
とくに、スキャナ保存では画像の解像度やタイムスタンプを付与する期間などが明確に定められているため、電子帳簿保存法を理解しつつ、必要なシステムを導入することが大切です。
スキャナ保存の詳しい保存要件が知りたい方は、下記の記事で解説しています。
関連記事:電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件とは?書類ごとの入力期間も解説
電子帳簿保存法の改ざん防止措置のルールと対応策とは?
電子帳簿保存法では、改ざん防止措置として「①タイムスタンプ付与」、「②訂正・削除履歴の管理」、「③事務処理規程の整備」が求められます。これらの措置を適切に導入することで、保存データの信頼度が高まり、電子帳簿保存法の保存要件を満たせます。
もし、どの措置もおこなわれていない場合、電子帳簿保存法違反となり、青色申告の取り消しや追徴課税につながるリスクもあるため注意しましょう。
ここでは、電子帳簿保存法の改ざん防止措置のルールと対応策を解説します。
- タイムスタンプの付与
- 事務処理規程の整備
- 訂正・削除履歴を残せるシステムの用意
①タイムスタンプの付与
タイムスタンプとは、電子帳簿や請求書などのデータに対して、「いつ作成・保存されたか」という情報を証明する技術です。データにタイムスタンプを付与しておくことで、税務調査の際に「保存後に改ざんされていない証拠」として認められます。
タイムスタンプは、書類を受領してから最長で「2か月とおおむね7営業日以内」に付与する必要があり、導入時は業務フローを整えておく必要があります。
なお、タイムスタンプを導入する際は、サービスによって価格や操作方法が異なるため、自社にあったものを選びましょう。
②事務処理規程の整備
電子帳簿保存法の改ざん防止措置の1つとして、社内で電子データの訂正・削除の防止を明文化した「事務処理規程」を整備する方法もあります。
事務処理規程とは、「誰が」「いつ」「どのように」「何の目的で」電子帳簿に関わる操作をおこなうのか、手順やルールを定めるものです。
たとえば、訂正時の承認フローや管理責任者の指定、操作ログの記録方法などを明記しておくことで、不正や誤操作が発覚しやすくなり、不正防止につながります。
事務処理規程を整備しておくことで、電子帳簿保存法の要件を満たしやすくなり、監査や税務調査の際に適切な運用をおこなっている証拠として活用できます。
③訂正・削除履歴を残せるシステムの用意
電子帳簿保存では、一度保存したデータの内容を変更する際に、「誰が」「いつ」「どんなデータを変更したか」という履歴の保存が求められています。訂正や削除の履歴が残らなければ、該当のデータが本当に変更されていないのかが証明できず、真実性が損なわれてしまうでしょう。
使用するシステムに訂正・削除のログが残ることで、改ざんの有無や責任の所在を確認でき、電子帳簿保存法の保存要件を満たせます。
手作業ではミスや抜けが生じるため、クラウド会計ソフトや電子帳簿保存対応のシステムを利用して、自動的にログを残すことがおすすめです。
電子帳簿保存法に対応できるシステム・会計ソフト3選
電子帳簿保存法に対応したシステムや会計ソフトを導入することで、自動的にタイムスタンプの付与や訂正・削除の履歴の保存がおこなわれ、保存要件を満たしやすくなります。システムや会計ソフトの多くは法令の改正にも対応するため、自社で都度業務フローを変更する必要もなくなります。
電子帳簿保存法に対応したシステムや会計ソフトにはそれぞれ特徴があるため、比較したうえで自社にあったサービスを選びましょう。
ここでは、電子帳簿保存法に対応できるシステム・会計ソフトを3つ解説します。
- OneVoice明細
- freee会計
- Misoca
①OneVoice明細
OneVoice明細は、請求書や納品書などの多様な帳票をクラウドで作成・保存できるシステムです。
書類の受領方法は取引先自身で選べ、自社が業務フローを変更する必要はありません。また、発行した書類のダウンロード状況が確認できることから、取引先の支払い漏れといったリスクも軽減できます。
契約に悩む場合には、無料のトライアル期間を活用して自社システムとの相性を確認できます。自社にあったサービスか判断がつかない場合は、まずはトライアルから利用しましょう。
②freee会計
freee会計は、請求書・見積書・納品書の発行から会計処理まで一体で管理できるクラウド型会計ソフトです。国税関係の帳簿作成もソフト内でできるため、確定申告時に必要な書類を1つのところにまとめられます。
全プランにチャットでのサポートが含まれており、不明点があればすぐに相談が可能です。お試し期間が30日間ついているため、実際に使用してから、自社にあっているか判断できます。
③Misoca
Misocaは、月の請求書が10枚までは、すべての機能が無料で使用できるクラウド型会計ソフトです。ソフト内で見積書や請求書などの書類を作成でき、取引に必要な書類を一括で管理できます。
有料プランであっても、無料お試し期間が最大1年間と長期な点が特徴のため、現在の会計ソフトと切り替えるか考えている場合にも、並行して利用できます。
有料プランには電話サポートもついており、わからないことがあれば、いつでも相談できるでしょう。
まとめ|電子帳簿保存法の改ざん防止措置への理解を深めて自社で対応しよう
本記事では、電子帳簿保存法における改ざん防止措置について、対応するシステムも交えて解説しました。
電子帳簿保存法の改ざん防止措置は、保存したデータの信頼性を確保するために設けられている要件の1つです。
これらの改ざん防止措置を確実に実施するためには、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入するか、事務処理規程を整備しなければなりません。
しかし、電子帳簿保存法は今後も改正される見込みがあるため、事務処理規程を作成する場合、都度内容を更新しなければなりません。
早めにシステムや会計ソフトを導入しておくことで、将来の法改正にも柔軟に対応できる体制を整えられます。
電子帳簿保存法の改ざん防止措置に悩む際は本記事を参考に、自社にあった方法を考えましょう。










