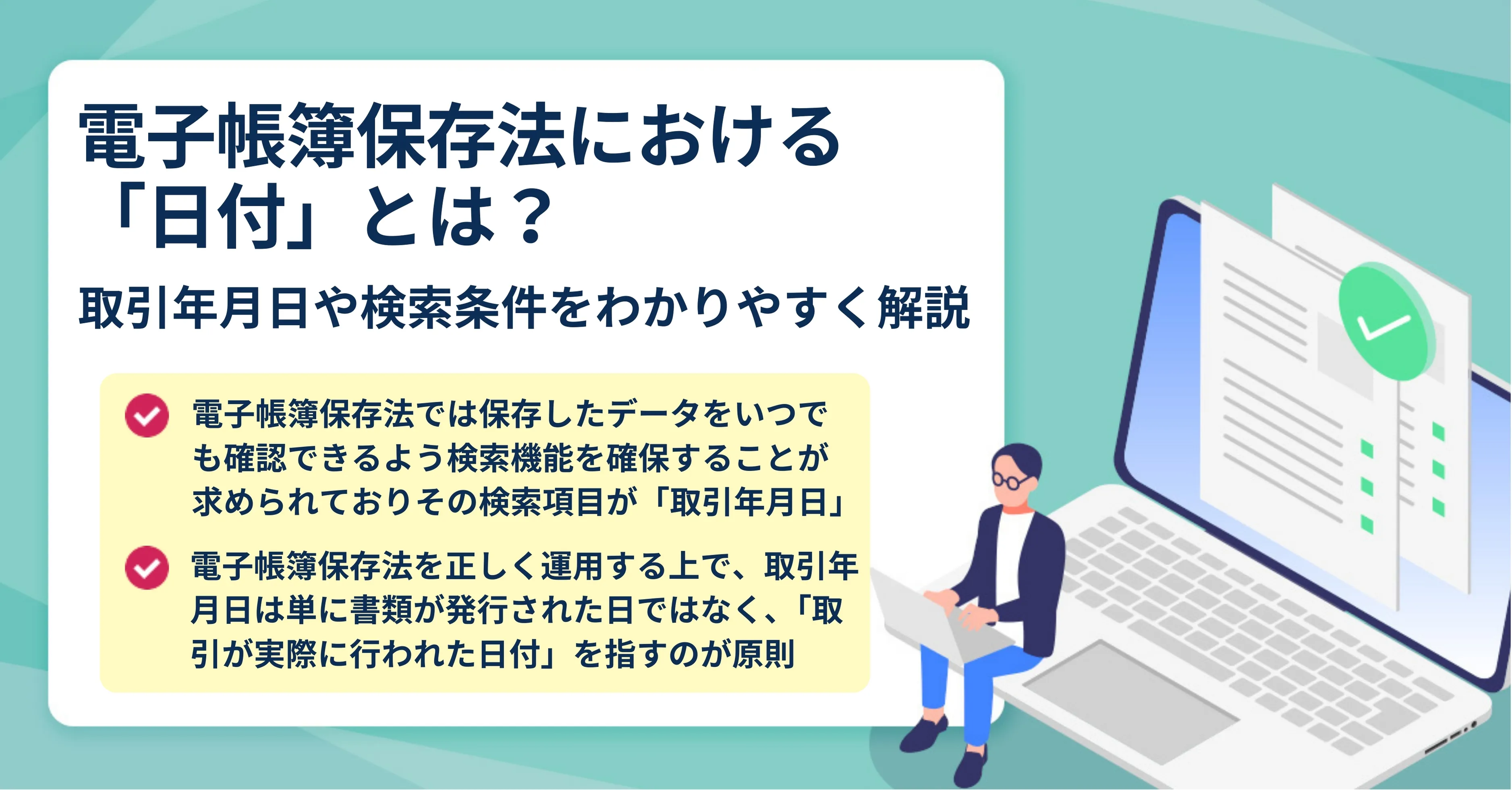知らないと罰則も?電子帳簿保存法に対応した契約書のスキャン保存、3つの必須ポイント
更新日:2025.10.21
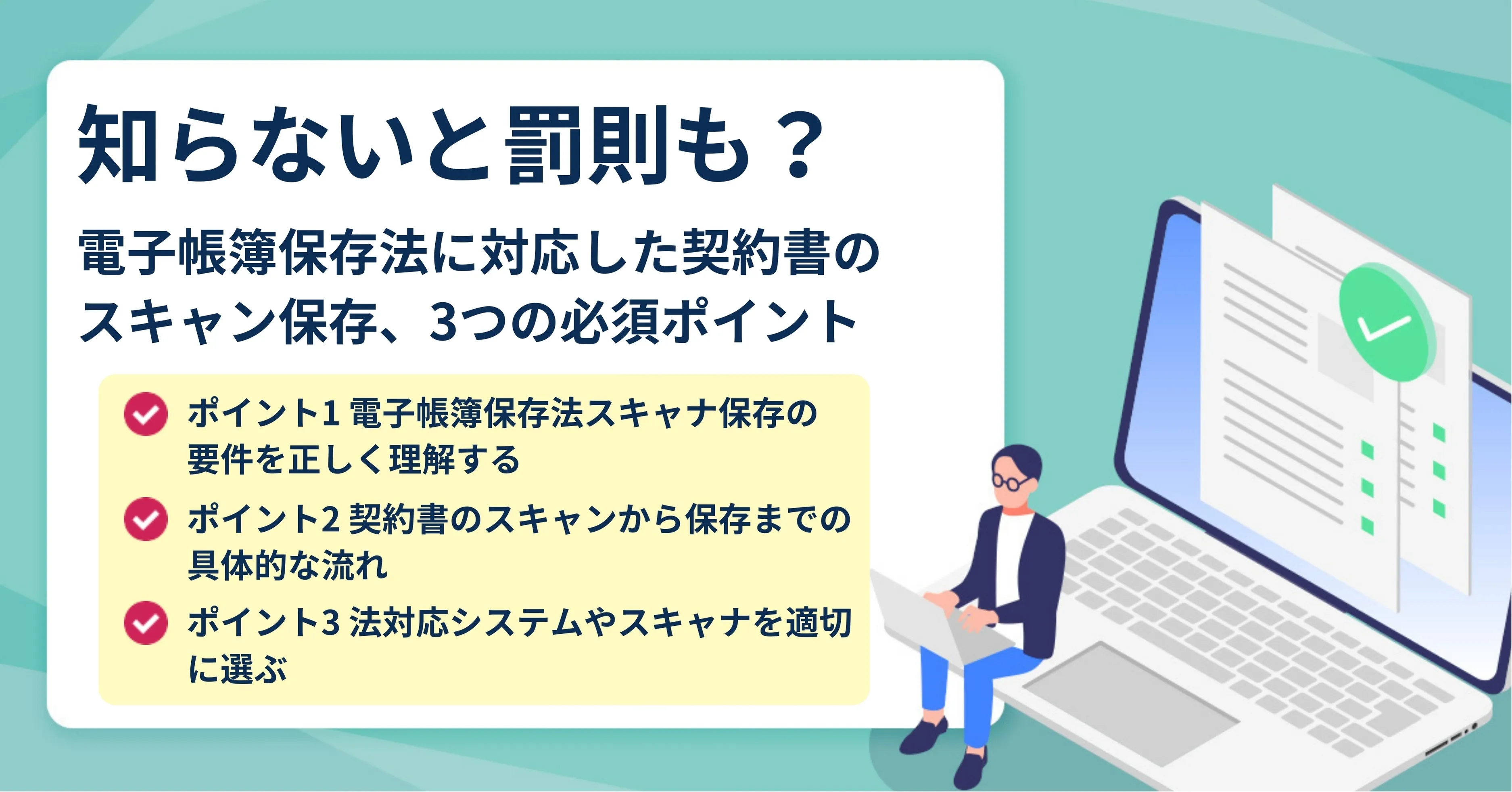
ー 目次 ー
「契約書をスキャンして保存すればいいだけ」と思っていませんか?実は、電子帳簿保存法の要件を満たしていない保存は、罰則や青色申告の取り消しといったリスクにもつながる重大な問題です。
本記事では、スキャナ保存を成功させるために欠かせない3つのポイントを、できるだけわかりやすくご紹介します。難しく感じられる法要件やシステム選定のコツも丁寧に解説していますので、「これから対応を始めたい」「そろそろ見直したい」という方はぜひ最後までご覧ください。
契約書の電子化は必須の時代へ 電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、法人税法や所得税法などで保存が義務付けられている帳簿や書類について、紙ではなく電子データでの保存を認める法律です。2022年1月の改正により、スキャナ保存の要件が大幅に緩和された一方で、電子メールなどで受け取った電子データのままの保存が義務化されるなど、企業はより一層この法律への理解と対応を迫られています。
本章では、まずこの電子帳簿保存法の全体像を掴むために、法律が定める3つの保存区分について解説します。
電子帳簿保存法における3つの保存区分
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の保存方法を大きく3つの区分に分けて定めています。契約書をスキャンして保存する方法は、このうち「スキャナ保存」に該当します。それぞれの区分の概要は以下の通りです。
|
保存区分 |
対象となる書類の例 |
概要 |
|
電子帳簿等保存 |
会計ソフトで作成した総勘定元帳、仕訳帳など |
PC等で最初から電子的に作成した帳簿や書類を、データのまま保存する方法。 |
|
スキャナ保存 |
紙で受領・作成した契約書、請求書、領収書など |
紙の書類をスキャナやスマートフォンで読み取り、画像データとして保存する方法。 |
|
電子取引データ保存 |
電子メールで受領した請求書PDF、Webサイトからダウンロードした領収書など |
電子的に授受した取引情報を、紙に出力せずデータのまま保存する方法。(※2024年1月より完全義務化) |
契約書のスキャン保存が関係する「スキャナ保存」制度
今回のテーマである「紙の契約書をスキャンして電子データで保存する」ことは、上記で示した3つの区分のうち「スキャナ保存」に該当します。スキャナ保存は、自社で作成した契約書の控えや、取引先から紙で受け取った契約書などをスキャナで読み取り、画像データとして保存する制度です。
この制度の要件を正しく満たして運用すれば、スキャン後の紙の契約書原本を破棄することが可能となり、保管コストの削減や管理業務の効率化に繋がります。ただし、スキャナ保存を適切に行うためには、データの「真実性」と「可視性」を確保するための詳細な要件が定められています。これらの具体的な要件については、後の章で詳しく解説します。
契約書は紙のまま保存してもよいのか?
電子帳簿保存法の改正により、契約書の保存方法にも大きな変化が求められるようになりました。結論から言うと、「一定の条件を満たせば」契約書を紙のまま保存することも可能ですが、今後の業務効率化やコンプライアンスの観点からは、電子保存への移行が推奨されています。
具体的には、契約書が取引先から紙で受領したものであり、かつ税務署長の承認が不要な「書面保存」区分に該当する場合には、引き続き紙保存が認められます。ただし、電子取引(PDFやクラウド上でやり取りされたもの)に該当する契約書は、原則として電子保存が必須であり、紙に印刷して保存するだけでは法令違反となる点には注意が必要です。
また、今後は電子化が主流になることが想定されるため、紙保存にこだわることで事務コストが増加したり、監査対応に支障をきたすリスクもあります。法令遵守と業務の最適化を両立するためにも、早めの電子契約・電子保存体制の構築を検討することが望ましいでしょう。
電子帳簿保存法に対応して契約書をスキャン保存するメリット
電子帳簿保存法への対応は、単なる法改正への義務的な対応ではありません。契約書をスキャナ保存することで、企業はコスト削減や業務効率化といった、経営に直結する多くのメリットを享受できます。ここでは、契約書の電子化がもたらす具体的な利点について解説します。
印紙税や保管スペースなどコストの大幅な削減
紙の契約書を電子データ化することで、これまで当たり前だった様々なコストを削減できます。特に、物理的な保管スペースが不要になる影響は大きく、オフィスの省スペース化や倉庫の賃料削減に直結します。
具体的に削減できるコストには、以下のようなものが挙げられます。
|
コストの種類 |
具体的な削減内容 |
|
保管・管理コスト |
キャビネットや書庫、外部倉庫などの物理的な保管スペースが不要になります。また、温湿度管理やセキュリティ対策にかかる費用も削減できます。 |
|
印刷・郵送コスト |
契約書の印刷代、インク・トナー代、封筒代、郵送費などが不要になります。契約締結のスピードも向上します。 |
|
備品・消耗品コスト |
ファイルやバインダー、ラベルシールといったファイリング用品の購入費用を削減できます。 |
|
人件費・作業コスト |
契約書のファイリング、検索、閲覧、廃棄といった一連の作業にかかる時間と人件費を大幅に削減できます。 |
また、将来的に契約業務全体を電子契約に移行すれば、課税文書にかかる印紙税も不要となり、さらなるコスト削減が期待できます。
検索性の向上による業務効率化
紙で保管された大量の契約書の中から、目的の一枚を探し出す作業は大きな負担です。スキャナ保存により電子データ化すれば、契約書の検索性が飛躍的に向上し、業務全体の効率化につながります。
電子データであれば、「取引先名」「契約日」「金額」といった複数の条件で瞬時に検索が可能です。これにより、監査対応や過去の取引内容の確認が必要になった際も、担当者が迅速に必要な情報へアクセスできます。
さらに、データはサーバーやクラウド上に保存されるため、場所を問わずに閲覧・共有が可能です。テレワークや複数拠点での業務においてもスムーズな情報連携が実現し、多様な働き方をサポートします。加えて、電子データはバックアップが容易なため、火災や地震といった災害時における書類紛失のリスクを低減し、BCP(事業継続計画)対策としても非常に有効です。
契約書のスキャン保存を成功させる3つの必須ポイント
電子帳簿保存法のスキャナ保存制度に適切に対応するためには、押さえるべき重要なポイントがあります。ここでは、契約書のスキャン保存を成功に導くための3つのポイントを具体的に解説します。
ポイント1 電子帳簿保存法スキャナ保存の要件を正しく理解する
契約書のスキャナ保存を行う上で最も重要なのが、電子帳簿保存法で定められた「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を正確に理解することです。これらの要件を満たさなければ、税務調査などで電子データが正規の保存書類として認められない可能性があります。
真実性の確保に関する要件
「真実性の確保」とは、保存されたデータが改ざんされていない、本物であることを証明するための要件です。具体的には、以下の措置が求められます。
|
項目 |
主な内容 |
補足 |
|
入力期間の制限 |
書類の受領後、速やか(最長2か月とおおむね7営業日以内)にタイムスタンプを付与する。 |
早期入力方式(おおむね7営業日以内)と業務サイクル方式(最長2か月以内)があります。 |
|
一定水準以上の解像度とカラー画像による読取り |
解像度200dpi相当以上でスキャンする。原則としてカラー画像での保存が必要です。 |
一般書類はグレースケールも認められますが、契約書は印影の確認等のためカラーが推奨されます。 |
|
タイムスタンプの付与 |
一財)日本データ通信協会が認定するタイムスタンプをスキャンデータに付与する。 |
訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムを利用する場合は、タイムスタンプの付与要件が緩和されます。 |
|
訂正・削除履歴の確保 |
訂正や削除を行った場合に、その事実と内容を確認できるシステム、または訂正・削除ができないシステムを利用する。 |
バージョン管理機能があるシステムなどが該当します。 |
|
相互関連性の確保 |
スキャンした契約書データと、関連する帳簿記録の相互関連性を確認できるようにしておく。 |
例えば、会計システム上の仕訳データと契約書の画像データを紐づけておく必要があります。 |
可視性の確保に関する要件
「可視性の確保」とは、保存した電子データを誰もが必要な時に、明瞭な状態で速やかに確認できるようにするための要件です。PCやディスプレイ、プリンタなどの操作説明書を備え付け、データをすぐに表示・出力できる環境を整える必要があります。
|
項目 |
主な内容 |
|
見読可能性の確保 |
保存場所に、PC、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、データを明瞭な状態で速やかに出力できるようにする。 |
|
検索機能の確保 |
「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目で検索できるようにする。日付や金額は範囲指定での検索、2つ以上の項目を組み合わせての検索ができることも要件です。 |
ポイント2 契約書のスキャンから保存までの具体的な流れ
法的要件を理解したら、次は実際に契約書をスキャンして保存するまでの業務フローを確立します。場当たり的な対応はミスや漏れの原因となるため、一連の流れをルール化することが不可欠です。
ステップ1 事前準備と事務処理規程の策定
まず、スキャナ保存を社内で正式に運用するためのルールを定めた「事務処理規程」を作成します。この規程には、スキャン対象となる契約書の種類、作業の責任者、具体的なスキャン手順、データのチェック体制、問題が発生した場合の対応などを明記します。明確な規程を設けることで、担当者が変わっても一貫した品質で業務を遂行でき、内部統制の強化にも繋がります。
ステップ2 契約書のスキャンとタイムスタンプの付与
事務処理規程に基づき、契約書をスキャンします。スキャナの解像度を200dpi以上に設定し、原則カラーでスキャンを実行します。スキャン後は、画像が不鮮明でないか、傾きや折れがないかを確認します。その後、定められた入力期間内に、スキャンデータにタイムスタンプを付与します。多くの電子帳簿保存法対応システムでは、データをアップロードすると自動的にタイムスタンプが付与される機能が備わっています。
ステップ3 検索条件を満たす形でのデータ保存
最後に、検索要件を満たす形でデータを保存します。ファイル名に「取引日_取引先名_金額」といった情報を含めるルールにする、あるいは会計システムや文書管理システムにこれらの情報を索引(インデックス)情報として入力します。これにより、後から税務調査などで特定の契約書を探す際に、日付、金額、取引先のいずれからでも迅速に検索できるようになります。
ポイント3 法対応システムやスキャナを適切に選ぶ
電子帳簿保存法の複雑な要件を自力で完全に満たすのは困難です。そのため、法対応のシステムや適切な性能を持つスキャナを導入することが、スキャナ保存を成功させるための近道となります。
JIIMA認証のシステムを選ぶメリット
システム選びで一つの基準となるのが「JIIMA認証」です。JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)は、市販のソフトウェアやサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、認証する制度を運営しています。JIIMA認証を取得したシステム(「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」など)を導入することで、法改正へのキャッチアップや要件適合性の確認といった手間を大幅に削減でき、安心して運用を開始できます。
スキャナ選びで確認すべき解像度や機能
スキャナは、法的要件である「解像度200dpi以上」と「カラー読み取り」に対応していることが最低条件です。その上で、業務効率を考慮した機能を確認しましょう。例えば、一度に複数枚の原稿を自動で読み取る「ADF(オートドキュメントフィーダー)」機能や、紙の重なりによる読み取りエラーを防ぐ「重送検知機能」があると、大量の契約書をスキャンする際の作業負担を大きく軽減できます。自社の契約書の量や種類に合わせて、最適なスペックのスキャナを選びましょう。
電子帳簿保存法に違反した場合の罰則とは
電子帳簿保存法の要件を満たさずに契約書のスキャン保存などを行った場合、単なる手続き上のミスでは済まされず、事業の根幹に関わる重大な罰則を受ける可能性があります。ここでは、具体的な罰則の内容を3つの観点から解説します。
青色申告の承認が取り消される可能性
電子帳簿保存法の保存要件を満たしていないと、税務調査などで指摘された際に「青色申告の承認」が取り消されるリスクがあります。青色申告が取り消されると、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越控除(欠損金の繰越控除)といった税制上の大きな優遇措置が受けられなくなります。これは、企業のキャッシュフローに直接的な打撃を与える非常に重いペナルティです。
追徴課税や加算税が課されるリスク
保存義務違反が発覚した場合、本来納めるべきだった税額との差額を「追徴課税」として納付する必要があります。さらに、追徴課税に加えてペナルティとして「加算税」が課されます。加算税にはいくつかの種類があり、特に意図的なデータ改ざんや隠蔽と判断された場合は、最も重い「重加算税」が課される可能性があります。
|
加算税の種類 |
内容 |
税率(目安) |
|
過少申告加算税 |
申告した税額が本来より少なかった場合に課される。 |
追加納付税額の10%〜15% |
|
無申告加算税 |
期限内に申告しなかった場合に課される。 |
納付すべき税額の15%〜20% |
|
重加算税 |
事実を隠蔽または仮装して申告した場合など、悪質と判断された場合に課される。 |
過少申告の場合:追加本税の35% 無申告の場合:納付すべき税額の40% |
なお、電子データに関して不正があった場合の重加算税は、通常課される税率にさらに10%が加重される厳しい措置が取られます。
会社法上の過料が科されることも
電子帳簿保存法は国税関係の法律ですが、違反は会社法上の問題にも発展する可能性があります。会社法では、会計帳簿や事業に関する重要な資料を適切に保存することが義務付けられています。この保存義務を怠った場合、代表者個人に対して100万円以下の「過料」が科されることがあります。税法上の罰則だけでなく、会社法上の責任も問われる可能性があることを認識しておく必要があります。
契約書の電子化で注意すべき点とよくある質問
契約書のスキャナ保存を検討する際、多くの担当者が疑問に思う点や見落としがちな注意点があります。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。スムーズな電子化を実現するために、事前に確認しておきましょう。
すべての契約書をスキャン保存する必要はあるか
結論から言うと、紙で受け取ったり作成したりしたすべての契約書をスキャン保存する必要はありません。電子帳簿保存法の「スキャナ保存」制度の利用は、あくまで事業者の任意です。そのため、従来通り紙のまま契約書を保管し続けることも認められています。
ただし、電子化によるコスト削減や業務効率化のメリットは大きいため、自社の状況に合わせて電子化する契約書の範囲を決定するのが現実的です。「取引金額が一定以上のものから」「特定の部署で扱う契約書から」など、段階的に導入を進める企業も少なくありません。
注意点として、電子メールの添付ファイルやクラウドサービス経由で受け取った電子契約書は「電子取引」に該当し、スキャナ保存の対象ではなく、電子データのまま保存することが義務付けられています。この違いを正しく理解することが重要です。
電子契約とスキャナ保存の違いとは
「電子契約」と「スキャナ保存」は、どちらも契約書を電子データで扱う点では似ていますが、電子帳簿保存法上の扱いは全く異なります。両者の違いを正しく理解しないと、意図せず法令違反を犯してしまう可能性があります。主な違いは以下の通りです。
|
項目 |
スキャナ保存 |
電子契約(電子取引データ保存) |
|
対象となる書類 |
紙で受領または作成した契約書などの国税関係書類 |
はじめから電子データでやり取りした契約書など |
|
保存方法の義務 |
電子保存は任意(紙のまま保存も可) |
電子データのまま保存することが義務 |
|
原本の扱い |
スキャン元の紙の契約書が原本(※) |
電子データそのものが原本 |
|
適用される保存区分 |
スキャナ保存 |
電子取引データ保存 |
※スキャナ保存の要件を満たして電子データを保存した場合、スキャン元の紙の契約書は破棄することが可能です。
このように、スキャナ保存は「紙から電子へ」の移行、電子契約は「電子のまま」の保存と覚えておくと分かりやすいでしょう。
過去の紙の契約書もスキャン保存の対象になるか
はい、過去に締結した紙の契約書も、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たすことで電子化し、保存することが可能です。これにより、書庫に眠っている大量の契約書をデータ化し、保管スペースの削減や管理コストの圧縮、検索性の向上を実現できます。
過去の契約書をスキャンする際も、原則として新規の契約書と同様の保存要件(真実性の確保・可視性の確保)を満たす必要があります。ただし、過去分の重要書類をスキャン保存する運用を始めるにあたり、税務署長への事前届出などは現在不要となっています。
過去分の書類は量が膨大になる可能性があるため、スキャン作業を外部のスキャニング代行サービスに委託することも有効な選択肢の一つです。その際は、電子帳簿保存法に対応した作業を行ってくれる信頼できる業者を選定することが重要です。
契約書の保存期間は何年?保存義務の起点に注意
契約書の保存期間は、原則として7年間とされています(法人税法・所得税法・電子帳簿保存法に基づく)。ただし、一定の要件を満たす場合や税務調査等の理由によっては、最長で10年間の保存義務が課されるケースもあります。
ここで重要なのが「保存期間の起点」です。多くの人が「契約締結日」から数えると誤解しがちですが、正しくは「契約が終了した日(契約満了日)」または「取引が完結した日」が起点となります。たとえば、3年間有効な契約書であれば、保存期間のカウントは契約終了後から始まる点に注意が必要です。
また、電子契約やスキャナ保存をしている場合でも、この保存期間のルールは変わりません。電子データであっても、税務上の証憑として法定期間を過ぎるまでは削除できないため、保存管理の体制を整えることが求められます。
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、経営効率やコスト面にも大きなメリットをもたらします。
とはいえ、「真実性」「可視性」といった難解な要件を満たすには、正しい知識と適切な準備が必要です。 この記事でご紹介した3つのポイントを押さえて、JIIMA認証システムの活用や業務フローの見直しを進めていただければ、安心してスキャナ保存に取り組むことができるはずです。 ぜひこの機会に、契約書の電子化を前向きに検討してみてください。