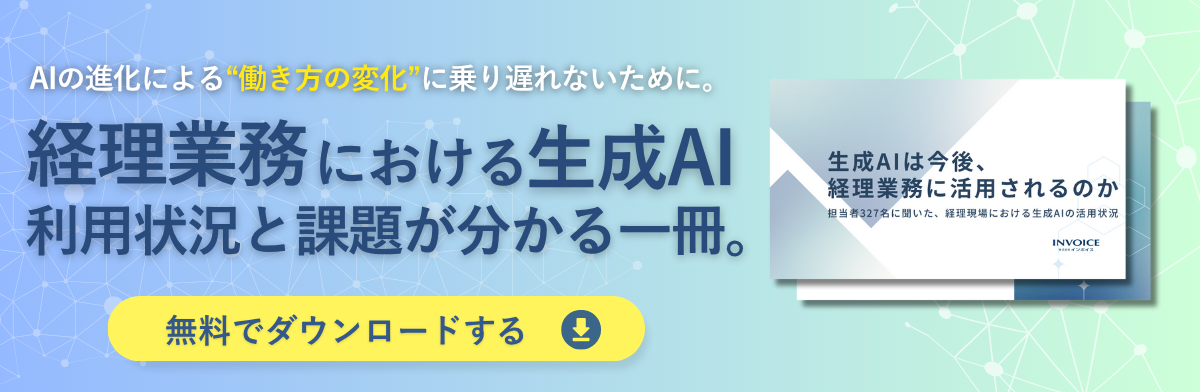電子帳簿保存法における「日付」とは?取引年月日や検索条件をわかりやすく解説
更新日:2025.08.21
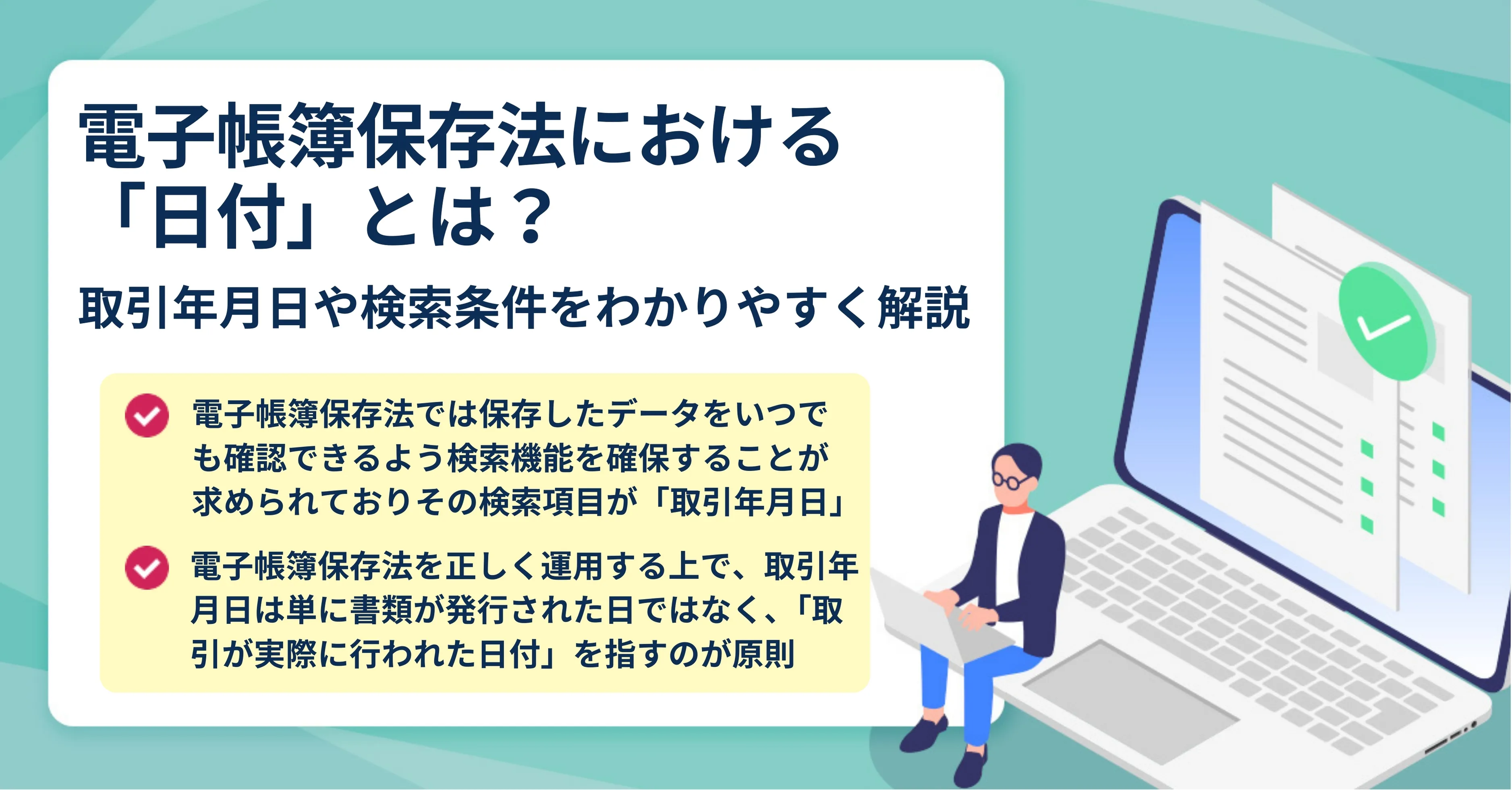
ー 目次 ー
「この請求書の日付って、どれを"取引年月日"にすればいいんだろう...?」電子帳簿保存法への対応を進める中で、そんな疑問を抱いたことはありませんか?実は、"日付"の管理を誤ると、検索条件を満たせなかったり、税務調査で不備を指摘されたりするリスクがあるため、軽視できないポイントです。
本記事では、書類別の「取引年月日」の考え方や、正しいファイル名の付け方、保存区分ごとの違いまでをわかりやすく整理しました。専門的なシステムを使っていない方でも、今日から取り組める管理方法を丁寧にご紹介していますので、ぜひご確認ください。
電子帳簿保存法で「日付」の正しい理解が不可欠な理由
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、多くの事業者にとって電子データの保存方法が大きく変わりました。特に、電子メールやクラウドサービスで受け取った請求書などの「電子取引データ」は、紙に出力しての保存が認められず、電子データのまま保存することが義務付けられています。この法令を遵守する上で、極めて重要な要素となるのが「日付」の管理です。
なぜなら、電子帳簿保存法では保存したデータが後からいつでも確認できるよう、検索機能を確保することが求められており、その中心的な検索項目が「取引年月日」だからです。日付のルールを正しく理解し、適切に管理できていない場合、意図せず法令違反となってしまう可能性があります。
日付の正しい理解がなぜ重要なのか、その理由を具体的に見ていきましょう。
|
日付管理が重要である理由 |
具体的な影響・リスク |
|
検索条件の充足 |
電子帳簿保存法では「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索が義務付けられています。日付が正しく設定されていなければ、この要件を満たせません。 |
|
税務調査への円滑な対応 |
税務調査の際、調査官の要求に応じて特定の取引データを迅速に提示する必要があります。日付管理ができていないと、書類の特定に時間がかかり、調査が長引く原因となります。 |
|
データの真実性の確保 |
正確な日付は、その取引がいつ行われたかを証明する根拠となり、データの改ざんがないことを示す「真実性の確保」という要件にも繋がります。日付が曖昧では、経費としての正当性が疑われる可能性もあります。 |
|
青色申告の承認取り消しリスクの回避 |
保存義務が適切に履行されていないと判断された場合、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。日付管理の不備は、その引き金になりかねません。 |
このように、電子帳簿保存法における「日付」は、単なる記録項目の一つではありません。次の章からは、具体的にどの書類のどの日付を「取引年月日」として扱えばよいのかを詳しく解説していきます。
電子帳簿保存法における「取引年月日」とはどの日付か
電子帳簿保存法を正しく運用する上で、取引年月日は単に書類が発行された日ではなく、「取引が実際に行われた日付」を指すのが原則です。
どの書類のどの日付を「取引年月日」として扱うか、社内で一貫したルールを定めておくことが、業務の効率化と法令遵守の両面で非常に重要になります。
請求書や領収書など書類別の「日付」の考え方
取引で授受する国税関係書類には、発行日や作成日、納品日など、複数の日付が記載されていることがあります。どの会社のどの担当者でも同じ基準で日付を判断できるよう、書類ごとの「取引年月日」の考え方を整理しておく必要があります。ここでは、主要な書類を例に、どの日付を取引年月日として扱うべきか、その原則を解説します。
請求書の日付
請求書における「取引年月日」は、原則として「請求の対象となる商品やサービスの提供が完了した日」を指します。
例えば、11月分のサービス利用料に関する請求書が12月5日に発行された場合、取引年月日は11月30日となります。ただし、継続的な取引でなければ、請求書の発行日を取引年月日として管理することも実務上認められています。重要なのは、自社でどちらの日付を基準とするかルールを統一し、一貫した運用を行うことです。
領収書の日付
領収書に記載されている「領収日」や「発行日」が、金銭の授受という取引が行われた日そのものであるため、この日付を「取引年月日」として扱います。
これは、スーパーやコンビニで受け取るレシートも同様で、レシートに印字されている日付が取引年月日に該当します。
契約書の日付
契約書における「取引年月日」は、原則として「契約締結日」となります。
契約書は、取引の基本的な合意が成立したことを証明する書類であり、その締結日が取引の起点となるためです。契約期間が別途定められている場合もありますが、電子帳簿保存法の検索条件としては、契約を締結した年月日を保存することが求められます。
納品書の日付
納品書では、物品の引き渡しという取引が完了した「納品日」を「取引年月日」とするのが一般的です。
納品書には書類の「作成日」が記載されていることもありますが、取引の事実があったのはあくまで納品日であるため、こちらを優先します。取引先による検収をもって取引完了とする場合は、その「検収日」を取引年月日として管理することもあります。自社の業務フローに合わせて、どの段階の日付を取引年月日とするか明確に定めておきましょう。
電子帳簿保存法の検索条件を満たすための日付の管理方法
検索機能の根幹をなすのが「日付」の正しい管理です。ここでは、法律で定められた検索条件と、それを満たすための具体的な日付の管理方法について解説します。
検索条件の3つの項目と「取引年月日」
電子取引データやスキャナ保存した書類を保存する際は、原則として以下の3つの項目で検索できる状態にしておく必要があります。特に「取引年月日その他の日付」は、すべての事業者にとって必須の検索項目です。
|
検索項目 |
内容 |
ポイント |
|
1. 取引年月日その他の日付 |
請求書や領収書などに記載された取引の年月日。 |
必須の検索項目です。この日付を基準にデータを整理・管理します。 |
|
2. 取引金額 |
取引の税込金額。 |
請求書や領収書に記載された合計金額を指します。 |
|
3. 取引先 |
請求書や領収書の発行元または受領先の名称。 |
正式名称で管理することが望ましいです。 |
さらに、上記の基本項目に加えて、以下の要件も求められます。
- 日付または金額の範囲を指定して検索できること(例:2024年4月1日から4月30日までの取引)
- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること(例:「2024年4月」かつ「株式会社A商事」の取引)
ただし、税務調査の際に税務職員からデータのダウンロードを求められた際に、それに応じることができるようにしている場合は、範囲指定検索と組み合わせ検索の要件は不要となります。多くの小規模事業者や個人事業主は、この緩和措置の対象となります。
ファイル名に日付を設定する具体的なルール
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや文書管理システムを導入していない場合でも、ファイル名の付け方を工夫することで検索条件を満たすことが可能です。最もシンプルで分かりやすい方法が、ファイル名に「取引年月日」「取引先」「取引金額」を含めるルールです。
例えば、2024年4月1日に「株式会社サンプル」から受け取った110,000円(税込)の請求書のPDFファイルは、以下のように命名します。
ファイル名の例: 20240401_株式会社サンプル_110000.pdf
この命名規則には、以下のようなメリットがあります。
- 日付の統一:ファイル名の先頭を「YYYYMMDD」形式の8桁の数字に統一することで、フォルダ内でファイルが日付順に自動で並び替えられ、管理が容易になります。
- 検索性の向上:パソコンの検索機能を使えば、「20240401」で該当日付の取引を、「株式会社サンプル」で取引先を、「110000」で金額を検索できます。
- 視認性の確保:ファイル名を見るだけで、いつ、どこから、いくらの取引だったのかが一目でわかります。
ファイル名の各要素を区切る記号は、アンダースコア(_)やハイフン(-)など、社内で統一したルールを設けることが重要です。このファイル名管理は、手軽に始められる一方、手作業による入力ミスや、取引件数が増えた際の管理の煩雑さがデメリットとなります。事業規模に応じて、専用システムの導入も検討しましょう。
保存区分別に見る電子帳簿保存法の日付要件
電子帳簿保存法は、データの保存方法によって「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分に分けられます。それぞれの日付に関する要件は異なるため、自社がどの方法で書類を保存するのかを把握し、対応する要件を確認することが重要です。
電子帳簿等保存における日付の取り扱い
電子帳簿等保存は、会計ソフトや販売管理システムなどを用いて、一貫して電子的に作成した国税関係帳簿や国税関係書類をデータのまま保存する方法です。この保存方法では、作成したデータ内に取引年月日が正確に記録されていることが前提となります。
保存したデータは、税務調査などの際に「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目で検索できる必要があります。多くの会計ソフトでは、これらの要件に対応した機能が標準で備わっていますが、自社で使用しているシステムが要件を満たしているか確認しておきましょう。
スキャナ保存における日付とタイムスタンプ
スキャナ保存は、紙で受け取った請求書や領収書などをスキャナやスマートフォンで読み取り、画像データとして保存する方法です。この方法では、検索条件である「取引年月日」のほかに、データの真実性を担保するための「タイムスタンプ」が重要な役割を担います。
タイムスタンプは、スキャンしたデータが特定の時刻に存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する電子的な時刻証明です。スキャナ保存を行う場合、定められた期間内にタイムスタンプを付与する必要があります。
|
入力方式 |
タイムスタンプ付与期間 |
主な対象 |
|
早期入力方式 |
書類の受領後、速やか(おおむね7営業日)以内 |
経理担当者がすぐにスキャンする場合など |
|
業務サイクル方式 |
業務の処理に係る通常の期間(最長2か月とおおむね7営業日)以内 |
月次でまとめて処理する場合など |
なお、スキャンしたデータの訂正または削除の事実および内容を確認できるクラウドシステムなどを利用し、入力期間内にデータを保存したことが確認できる場合は、タイムスタンプの付与要件が免除されます。
電子取引データ保存における日付のポイント
電子取引データ保存は、電子メールで受け取ったPDFの請求書や、ECサイトからダウンロードした領収書など、電子的に授受した取引情報をデータのまま保存する方法です。2024年1月1日からすべての事業者に対して義務化されています。
電子取引データ保存においても、「可視性の確保」と「真実性の確保」が求められます。日付に関しては、主に以下の2つの要件が重要です。
- 検索機能の確保:「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できるようにする必要があります。ファイル名を「20241031_株式会社〇〇_110000」のようにルール化する方法や、別途Excelなどで索引簿を作成する方法があります。
- 真実性の確保:データの改ざんを防ぐため、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- データ授受後、速やかにタイムスタンプを付与する
- データの訂正・削除の記録が残る、または訂正・削除ができないシステムを利用する
- 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿った運用を行う
特に中小企業では、コストを抑えられる「事務処理規程の備付け」を選択するケースが多く見られます。この場合、規程を作成し、社内で遵守することが求められます。
Q&A|電子帳簿保存法の日付に関するよくある質問
電子帳簿保存法における日付の取り扱いについては、多くの疑問が寄せられます。ここでは、特に質問の多い項目をピックアップし、わかりやすく回答します。
取引年月日を間違えた場合の訂正や削除の方法
電子帳簿保存法では、保存するデータの真実性を確保することが極めて重要です。そのため、一度保存したデータの訂正や削除には厳格なルールが定められています。
原則として、訂正や削除の履歴がシステム上で確認できること、または訂正・削除ができないシステムを利用することが求められます。もしファイル名の日付を間違えた場合、安易にファイル名を変更するだけでは要件を満たせません。訂正の事実と理由が客観的に追跡できるようにしておく必要があります。
利用しているシステムが訂正・削除履歴の保存に対応していない場合は、別途「事務処理規程」を社内で整備し、それに沿った運用が必須です。例えば、誤ったデータの訂正・削除を行う際には、その理由や申請日、担当者などを記載した申請書を作成し、承認を得た上で保管するといった手順を定めます。これにより、恣意的な改変ではないことを証明できます。
タイムスタンプと取引年月日の関係性とは
「タイムスタンプ」と「取引年月日」は、どちらも日付情報ですが、その目的と役割が全く異なります。混同しないように、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。
簡単に言うと、「取引年月日」は「いつの取引か」を示すための検索キーであり、「タイムスタンプ」は「そのデータがいつ存在し、改ざんされていないか」を証明するためのものです。両者の違いを以下の表にまとめました。
|
項目 |
取引年月日 |
タイムスタンプ(に記録される時刻) |
|
目的 |
取引の事実を特定し、検索のキーとするため |
電子データがその時刻に存在し、以降改ざんされていないことを証明するため(真実性の確保) |
|
基準となる日付 |
請求書や領収書に記載された、取引が実際に行われた日付 |
電子データを受領または作成した後、規定の期間内に付与した時刻 |
|
主な役割 |
検索条件の一つ |
真実性の確保要件の一つ(特にスキャナ保存で重要) |
日付管理は対応システムで効率化できるか
結論から言うと、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することで、日付管理は大幅に効率化できます。手作業でファイル名に日付を付与したり、Excelなどで管理台帳を作成したりする方法は、入力ミスや管理漏れのリスクが常に伴います。
多くの電子帳簿保存法対応システムには、以下のような便利な機能が搭載されています。
- OCR(光学的文字認識)機能: スキャンした請求書や領収書から、取引年月日、取引先、金額などを自動で読み取り、データ化します。手入力の手間とミスを削減できます。
- 検索機能の具備: システムに保存されたデータは、「取引年月日」「取引先」「金額」といった要件で簡単に検索できます。税務調査などで提示を求められた際も、迅速に対応可能です。
- タイムスタンプの自動付与: 書類をアップロードすると、要件を満たすタイムスタンプを自動で付与する機能を持つシステムもあります。
- 訂正・削除履歴の保存: データの訂正や削除を行った場合、その履歴が自動的に記録されるため、真実性の確保要件を容易に満たせます。
マネーフォワード クラウドやfreee会計、楽楽精算といった多くの会計ソフトや経費精算システムがこれらの機能を備えています。システムの導入は、法対応の負担を軽減し、経理業務全体の生産性を向上させる上で非常に有効な手段です。
まとめ
電子帳簿保存法では、「取引年月日」を正しく理解し、一貫したルールで管理することがとても大切です。書類ごとに何の日付を基準にするのか、社内でルールを明確にしておくことで、検索条件の対応や税務調査時のリスク低減につながります。
また、ファイル名の工夫や事務処理規程の整備といったちょっとした工夫でも、確実な法対応に近づけます。「うちの管理、これで大丈夫かな?」と不安な方も、できるところから見直してみてはいかがでしょうか。