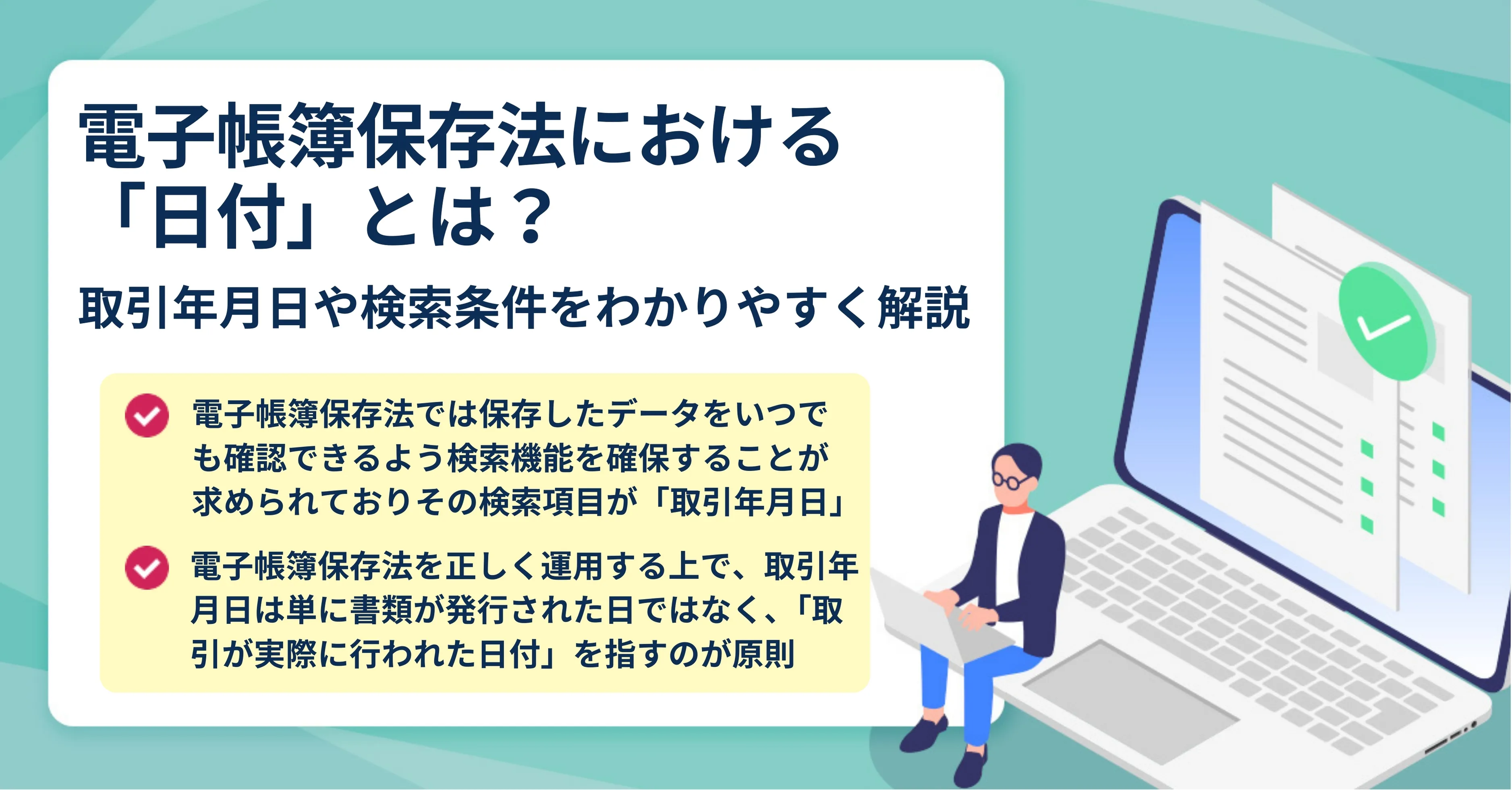知らないとまずい!電子帳簿保存法で義務化されたメールの見積書保存ルール
更新日:2025.09.09
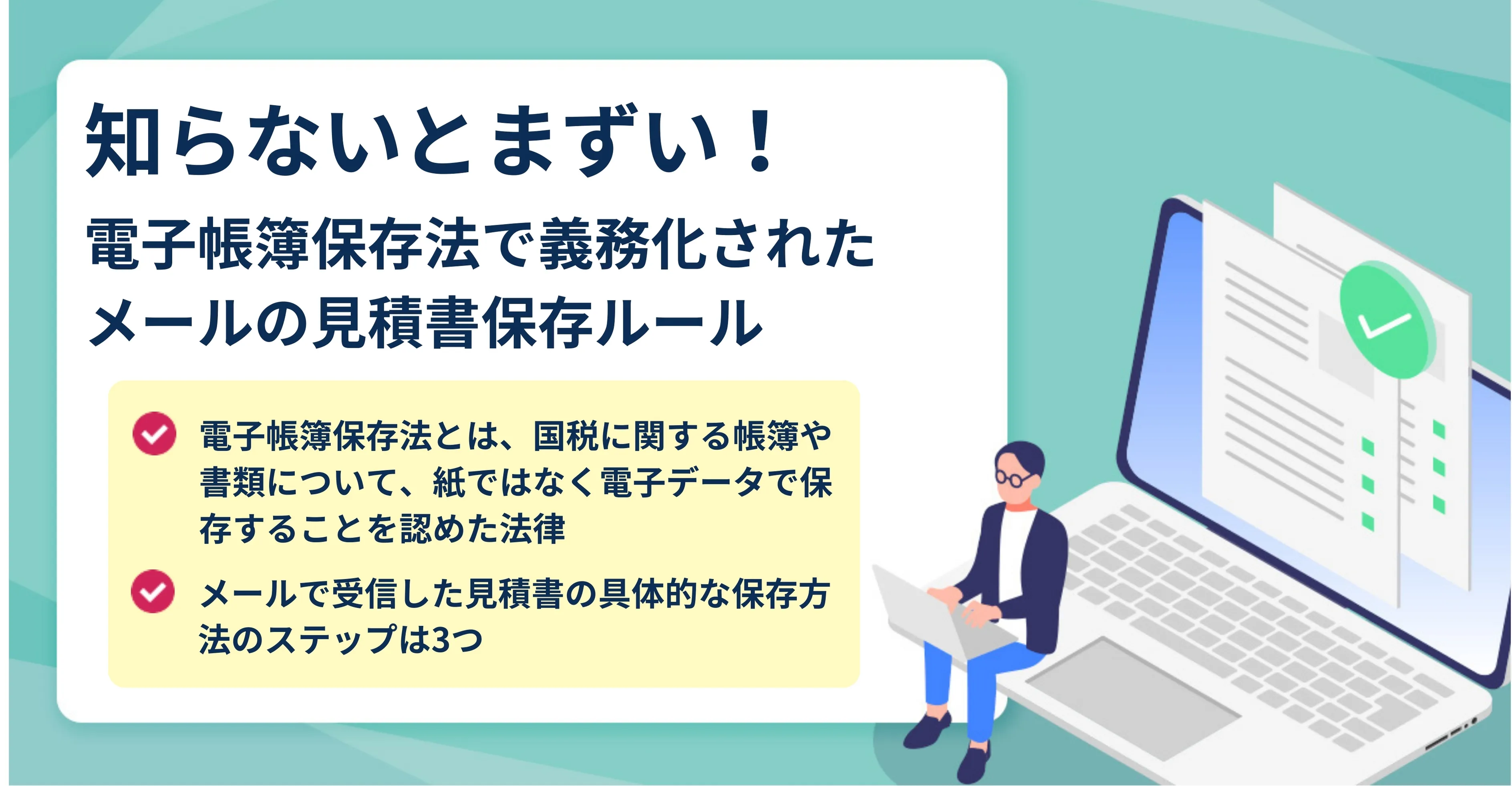
ー 目次 ー
「メールで届いた見積書、いつも通り印刷して保管していますが...」という方、少しご注意ください。2024年1月からは、電子データで受け取った見積書は"電子のまま保存すること"が法律で義務化されました。この変更は、大企業だけでなく中小企業や個人事業主の皆さまも対象です。
本記事では、見積書を正しく保存するための方法やNG例、そして見落としがちなリスクまで、やさしく丁寧に解説いたします。
今日からすぐにできる対応もご紹介しますので、今のうちに一緒に見直してみませんか?
メールで届いた見積書はどうしてる?電子帳簿保存法はもう他人事ではありません
取引先からメールに添付されて送られてくるPDFの見積書。日々の業務で当たり前のように受け取っているこの電子データ、あなたはどのように管理していますか?「とりあえず印刷してファイリングしている」「ファイル名もそのままデスクトップに保存している」という方も多いのではないでしょうか。
しかしその管理方法が、今後は認められなくなるかもしれません。2024年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、特定の条件下での電子データの保存がすべての事業者に対して義務化されたからです。これは大企業だけの話ではなく、中小企業や個人事業主も含む、すべての事業者が対象となります。
電子取引データの保存義務化とは?
今回の法改正で最も重要なポイントが「電子取引データ」の保存義務化です。電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引を指し、メールでの見積書や請求書のやり取りは、まさにこれに該当します。
これまで認められていた「メールで受け取った見積書を紙に印刷して保存する」という方法は、原則として認められなくなりました。電子データとして受け取ったものは、法律で定められた要件を満たした上で、電子データのまま保存する必要があります。
なぜ今、対応が急務なのか?
電子帳簿保存法の改正自体は以前から行われていましたが、多くの事業者が対応に苦慮している実態を踏まえ、宥恕(ゆうじょ)措置が設けられていました。しかし、その宥恕措置も2023年12月31日をもって終了し、2024年1月1日以降の取引については、法令に則った保存が完全義務化されています。
つまり、「知らなかった」では済まされない状況になっているのです。正しい方法で保存されていない場合、青色申告の承認が取り消されるなどのリスクも考えられます。
本記事では、この電子帳簿保存法について、特に日常業務で頻繁に発生する「メールで受信した見積書」の取り扱いに焦点を当て、具体的な保存方法や注意点を分かりやすく解説していきます。
そもそも電子帳簿保存法とは?3つの保存区分を解説
電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)とは、法人税や所得税など国税に関する帳簿や書類について、紙ではなく電子データ(電磁的記録)で保存することを認めた法律です。正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
この法律は、経理のデジタル化を促進し、ペーパーレスによる業務効率化やコスト削減を目的としています。2022年1月施行の改正により、特に「電子取引」で授受したデータの電子保存がすべての事業者に対して義務化され、対応が急務となりました。
電子帳簿保存法が定める保存区分は、大きく分けて次の3つです。それぞれ対象となる書類や対応方法が異なるため、正しく理解することが重要です。
|
保存区分 |
対象となるデータ・書類 |
対応の要否 |
|
電子取引データの電子保存 |
メールやWebサイト経由で授受した見積書、請求書、領収書など |
義務 |
|
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存 |
会計ソフトなどで自社が作成した帳簿(仕訳帳など)や書類(決算書など) |
任意 |
|
スキャナ保存 |
紙で受け取った、または自社で作成した見積書、請求書、領収書など |
任意 |
電子取引データの電子保存
電子取引データの電子保存は、3つの区分のうち唯一、すべての事業者(法人・個人事業主)に義務付けられているものです。メールで見積書を受け取った場合、この「電子取引」に該当します。
電子取引とは、EDI取引、インターネット上の取引、電子メール、クラウドサービスなどを介して、見積書・請求書・領収書といった取引情報をデータでやり取りすること全般を指します。この方法で受け取ったデータは、紙に印刷して保存するのではなく、必ず電子データのまま、定められた要件を満たして保存しなければなりません。2024年1月1日からは宥恕(ゆうじょ)措置も終了し、完全義務化となっています。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存
これは、会計ソフトなどを使用して、自社で一貫してコンピュータで作成した国税関係の帳簿や書類を、そのまま電子データとして保存することを認める制度です。一般的に「電子帳簿等保存」と呼ばれます。対応は任意であり、従来通り紙に印刷して保存することも可能です。
対象となるのは、仕訳帳や総勘定元帳などの「国税関係帳簿」と、貸借対照表や損益計算書といった「決算関係書類」です。この制度を利用するには、一定の要件を満たした会計システムの使用などが必要となります。
スキャナ保存
スキャナ保存とは、取引先から紙で受け取った、あるいは自社で紙で作成した見積書や領収書などの国税関係書類を、スキャナで読み取って電子データとして保存することを認める制度です。こちらも対応は任意です。
スキャナ保存を行うことで、紙の書類を破棄でき、保管スペースの削減や書類管理の効率化につながります。ただし、解像度やタイムスタンプの付与など、法律で定められた複数の要件を満たす必要があるため、導入には注意が必要です。
【本題!】メールの見積書保存で満たすべき電子帳簿保存法の要件
メール本文や添付ファイルで受け取った見積書は、電子帳簿保存法における「電子取引」に該当します。電子取引データの電子保存では、単にパソコンにデータを保存するだけでは不十分です。法律で定められた「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの大きな要件を満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件について具体的に解説します。
真実性の確保(改ざんされていないことの証明)
「真実性の確保」とは、保存された見積書データが作成されてから一貫して改ざんされていないことを証明するための要件です。意図しない訂正や削除を防ぎ、データの信頼性を担保することが目的です。この要件を満たすためには、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
|
措置 |
具体的な内容 |
|
タイムスタンプの付与 |
取引先からタイムスタンプが付与された見積書を受領するか、自社で速やかにタイムスタンプを付与する。 |
|
訂正削除の履歴が残る(または訂正削除ができない)システムの利用 |
データの訂正・削除の履歴が残るシステム、もしくはそもそも訂正・削除ができないシステムを導入して、見積書データを保存・管理する。 |
|
訂正削除の防止に関する事務処理規程の整備と運用 |
データの訂正や削除を原則禁止し、やむを得ず行う場合の手順などを定めた社内ルール(事務処理規程)を作成し、その規程に沿って運用する。 |
|
取引先との授受 |
発行者側でタイムスタンプが付与されたデータを受領する。 |
高価なシステムを導入しなくても、「事務処理規程」を定めて運用することで要件を満たせるため、多くの事業者にとって現実的な選択肢となります。国税庁のウェブサイトでは、事務処理規程のサンプルが公開されています。
タイムスタンプの付与
タイムスタンプとは、電子データがある時刻に存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術的な仕組みです。取引先から受け取る見積書にタイムスタンプが付与されている場合は、そのまま保存すれば要件を満たせます。自社で付与する場合は、時刻認証業務認定事業者(TSA)が発行する認定タイムスタンプに対応したシステムを利用する必要があります。
訂正削除の履歴が残るシステムの利用
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや文書管理システムの中には、データの訂正・削除を行うと、その操作ログ(誰が、いつ、どのデータをどうしたか)が自動で記録される機能を持つものがあります。このようなシステムを利用して見積書データを管理することで、真実性の確保が可能です。また、データの訂正や削除そのものができない仕様のシステムを利用することでも、要件を満たせます。
可視性の確保(誰でも確認できる状態の維持)
「可視性の確保」とは、保存した電子データを、税務調査などの際に誰もが必要な情報を速やかに探し出し、明瞭な状態で確認できるようにしておくための要件です。具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- パソコンやディスプレイ、プリンタなど、データを確認・出力するための装置を備え付けること。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できるようにすること。
特に重要なのが検索機能の確保です。原則として、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」を検索条件として設定できること。
- 日付または金額については、範囲を指定して検索できること。
- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること。
ただし、税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じられるようにしている場合は、範囲指定検索や複数項目での検索機能は不要となる緩和措置が設けられています。また、基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者についても、同様にダウンロードの求めに応じられれば、全ての検索要件が不要となります。
パソコンやディスプレイなど見読可能装置の備え付け
保存している見積書データを、税務調査官などがその場ですぐに確認できるよう、パソコン本体、ディスプレイ、プリンタといった装置と、それらの操作説明書を備え付けておく必要があります。クラウド上にデータを保存している場合でも、社内のパソコンからアクセスして画面に表示し、必要に応じて印刷できる環境が整っていれば問題ありません。
今日からできる!メールで受信した見積書の具体的な保存方法
電子帳簿保存法の要件を満たすことは、決して難しいことではありません。特別な会計ソフトを導入しなくても、日々の業務フローを少し見直すだけで対応可能です。ここでは、誰でも今日から実践できる、メールで受信した見積書の具体的な保存方法を3つのステップで解説します。
ステップ1 メールや添付された見積書ファイルを保存する
まず、取引先からメールで送られてきた見積書データをパソコンやクラウドストレージ上に保存します。見積内容がメール本文に直接記載されている場合はメール自体を、PDFファイルなどが添付されている場合はそのファイルを保存対象とします。
メール自体を保存する場合は、お使いのメールソフトの機能で「.eml」形式などでPC上にエクスポートします。PDFファイルの場合は、ファイルをダウンロードして保存しましょう。このとき、データを保存する場所として「2024年 見積書」といった年度別のフォルダや、「取引先A」のような取引先別のフォルダを作成し、整理しておくことをお勧めします。
ステップ2 検索しやすいファイル名に統一する
次に、保存したファイルの名前を、検索要件を満たせるように統一した規則で変更(リネーム)します。これは、税務調査などで特定の取引を探す際に、すぐに見つけ出せるようにするためです。ファイル名のルールは社内で決めておけば問題ありませんが、一般的には「取引年月日」「取引先名」「金額」の3つの要素を含めることが推奨されます。
例えば、以下のような命名規則が考えられます。
|
要素 |
ファイル名での記載例 |
備考 |
|
取引年月日 |
20241026 |
8桁の西暦で記載すると並び替えに便利です。 |
|
取引先名 |
株式会社サンプル商事 |
正式名称で統一します。(株)などの略称は避けます。 |
|
金額 |
165000 |
税込み金額を数字のみで記載します。 |
|
書類の種類 |
見積書 |
請求書や領収書など他の書類と区別しやすくなります。 |
上記のルールを組み合わせると、ファイル名は「20241026_株式会社サンプル商事_165000_見積書.pdf」のようになります。このようなルールを徹底することで、誰でも簡単に目的のデータを探し出せるようになります。
ステップ3 索引簿を作成するか対応システムを導入する
最後に、保存したデータをいつでも検索できる状態にするための仕組みを整えます。これには大きく分けて2つの方法があります。
索引簿(エクセルなど)で管理する場合
保存したデータの一覧表となる「索引簿」を作成する方法です。国税庁もこの方法を認めており、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで簡単に作成できます。ステップ2で命名したファイル名と関連付けられるように、以下の項目を含んだ一覧表を作成し、データ保存用のフォルダと同じ場所に保管しましょう。
|
連番 |
取引年月日 |
取引先 |
取引金額(税込み) |
備考(ファイル名など) |
|
1 |
2024/10/26 |
株式会社サンプル商事 |
165,000 |
20241026_株式会社サンプル商事_165000_見積書.pdf |
|
2 |
2024/10/28 |
合同会社テスト |
88,000 |
20241028_合同会社テスト_88000_見積書.pdf |
電子帳簿保存法対応システムを導入する場合
手作業での管理に不安がある場合や、取引量が多い場合には、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや経費精算システムの導入が有効です。これらのシステムは、メールで受信した見積書や請求書のPDFをアップロードするだけで、自動で日付や金額、取引先を読み取り、検索要件を満たした形で保存してくれます。
多くのクラウド会計ソフトが電子取引データの保存機能を提供しており、手作業によるファイル名の変更や索引簿の作成といった手間を大幅に削減できます。
注意!電子帳簿保存法における見積書保存のNG例
電子帳簿保存法への対応を進める中で、良かれと思って行った対応が実は法令の要件を満たしていない、というケースは少なくありません。ここでは、多くの方が陥りがちなNG例を具体的に解説します。
メールで届いた見積書を紙に印刷して原本を破棄する
最もやってはいけない代表的な例が、メールで受け取った見積書のPDFなどを紙に印刷し、安心して元の電子データを削除してしまうケースです。2022年1月の法改正により、電子データで受け取った国税関係書類(電子取引)は、電子データのまま保存することが義務付けられました。
紙に印刷したものは、あくまで「写し」や「控え」の扱いです。原本である電子データを破棄してしまうと、法律で定められた保存義務を果たしていないことになります。税務調査の際にデータの提示を求められても応じられず、青色申告の承認が取り消されるといったペナルティの対象となる恐れがありますので、絶対に行わないでください。
ファイル名をつけずにデスクトップなどに無秩序に保存する
受信した見積書のPDFファイルを、ファイル名を変更せずにデスクトップやダウンロードフォルダに散在させておくのもNGです。電子帳簿保存法では、保存したデータを後から誰もが確認できる状態にしておく「可視性の確保」が求められます。
この可視性の確保には「検索機能の確保」という要件が含まれており、税務調査官などから特定の取引データの提示を求められた際に、速やかに探し出せる状態でなければなりません。ファイル名が「見積書.pdf」や「scan_20240401.pdf」のような状態では、この検索要件を満たすことが困難です。ファイル名のルールを統一したり、取引先ごとにフォルダを分け、検索してすぐ見つけられる状態を確保しましょう。
Q&A|電子帳簿保存法とメールの見積書に関するよくある質問
見積書以外の請求書や領収書のメールも対象ですか?
はい、対象です。電子帳簿保存法では、見積書だけでなく、電子メールやクラウドサービスなどを介して授受した「電子取引」に関するデータはすべて電子保存の対象となります。
具体的には、請求書、領収書、注文書、契約書、納品書など、取引に関して発行または受領した書類データが該当します。これらはすべて、定められた要件に従って電子データのまま保存する必要があります。
データの保存期間はいつまでですか?
電子取引データの保存期間は、紙の書類と同様です。法人の場合、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
個人事業主の場合も、原則として確定申告期限の翌日から7年間です。一部、所得税法で5年間とされている書類もありますが、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには7年間の保存が必要なため、7年間と覚えておくのが安全です。
ただし、青色申告で欠損金(赤字)が生じた事業年度、または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金が生じた場合には、保存期間が10年間に延長される点に注意が必要です。
罰則はありますか?もし対応しなかったらどうなりますか?
電子帳簿保存法そのものに直接的な罰則規定はありません。しかし、保存要件を満たさず、電子データを適切に保存しなかった場合、税務上の不利益を受ける可能性があります。
|
リスクの種類 |
内容 |
|
青色申告の承認取消 |
適正な帳簿書類の保存が行われていないと判断された場合、最大65万円の特別控除など、税制上の優遇措置が受けられる青色申告の承認が取り消される可能性があります。 |
|
追徴課税・加算税 |
保存データが証拠書類として認められず、経費などが否認された場合、本来納めるべきだった税額との差額(追徴課税)に加え、過少申告加算税や、悪質な隠蔽と見なされれば重加算税が課されることがあります。 |
|
会社法上の過料 |
会社法では、会計帳簿や関連資料を10年間保存することが義務付けられています。これに違反した場合、100万円以下の過料が科される可能性があります。 |
このように、実質的なペナルティは非常に重いため、法令に則った対応が不可欠です。
まとめ
メールで受け取った見積書の扱い方は、今や「知っているかどうか」で大きく差がつく時代になりました。法律に対応するだけでなく、トラブルの予防や業務効率化にもつながる大切なポイントです。
保存方法に不安がある方も、本記事でご紹介した3ステップ(保存→命名→管理)を実践すれば、十分に対応できます。
まずは自社の保存ルールを見直すことから、ぜひ始めてみてください。