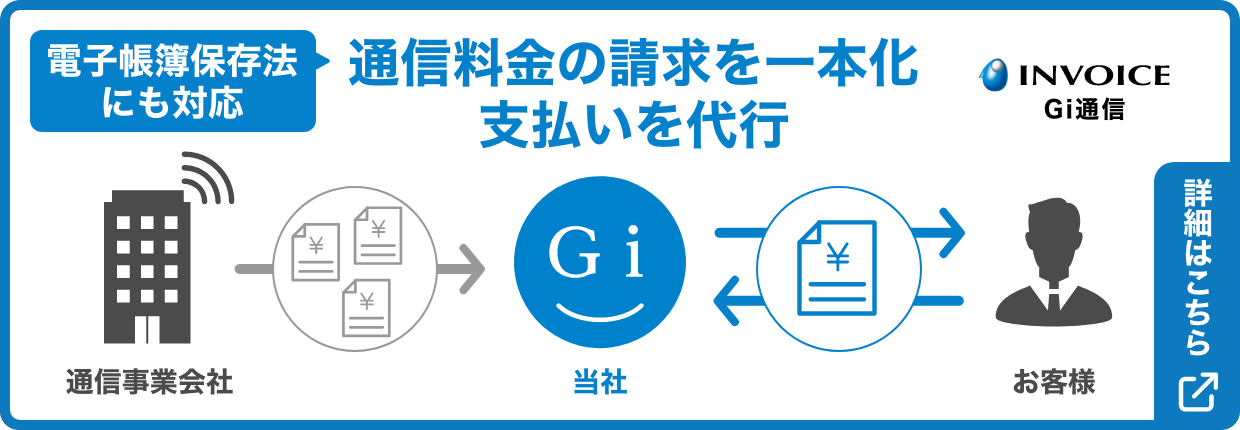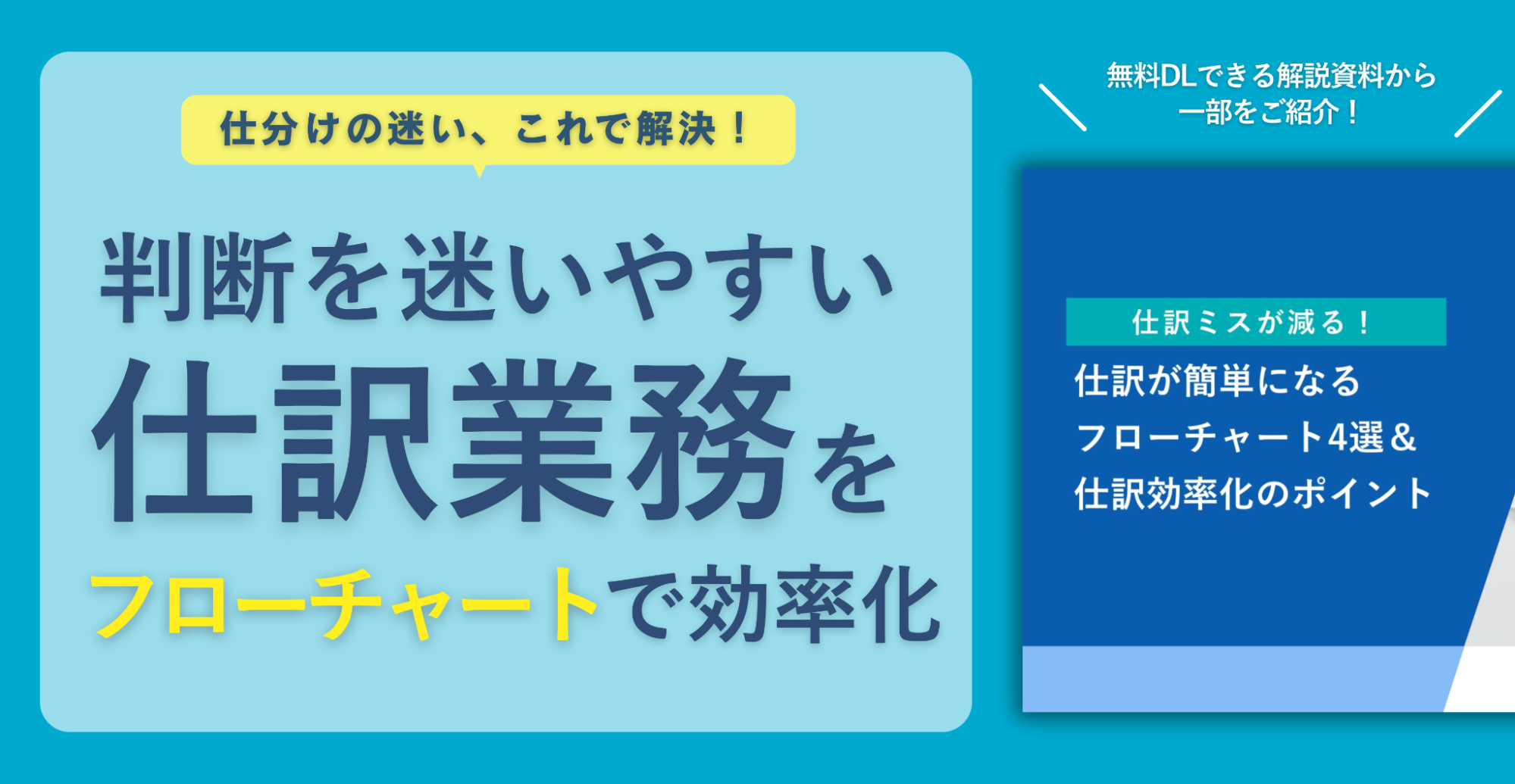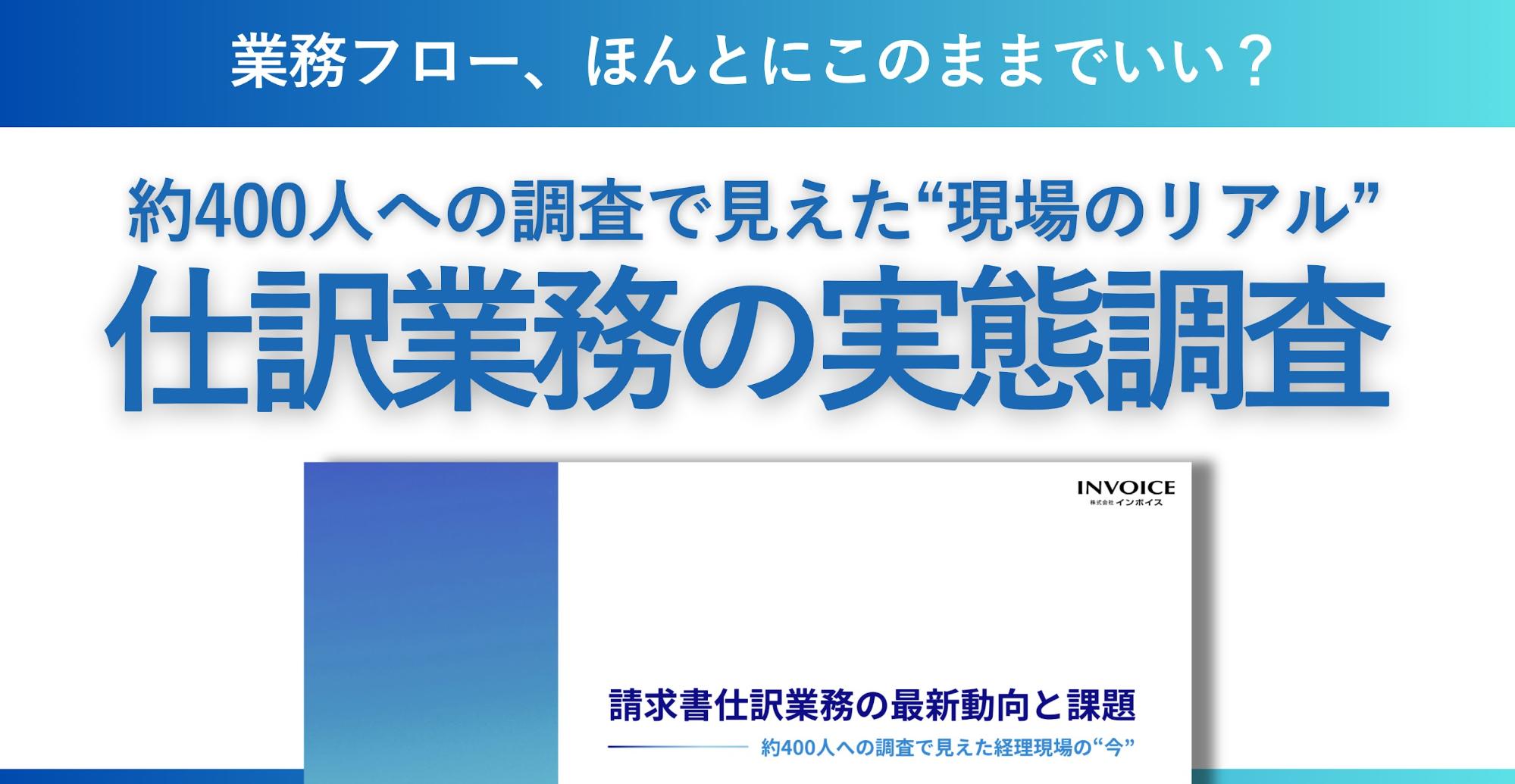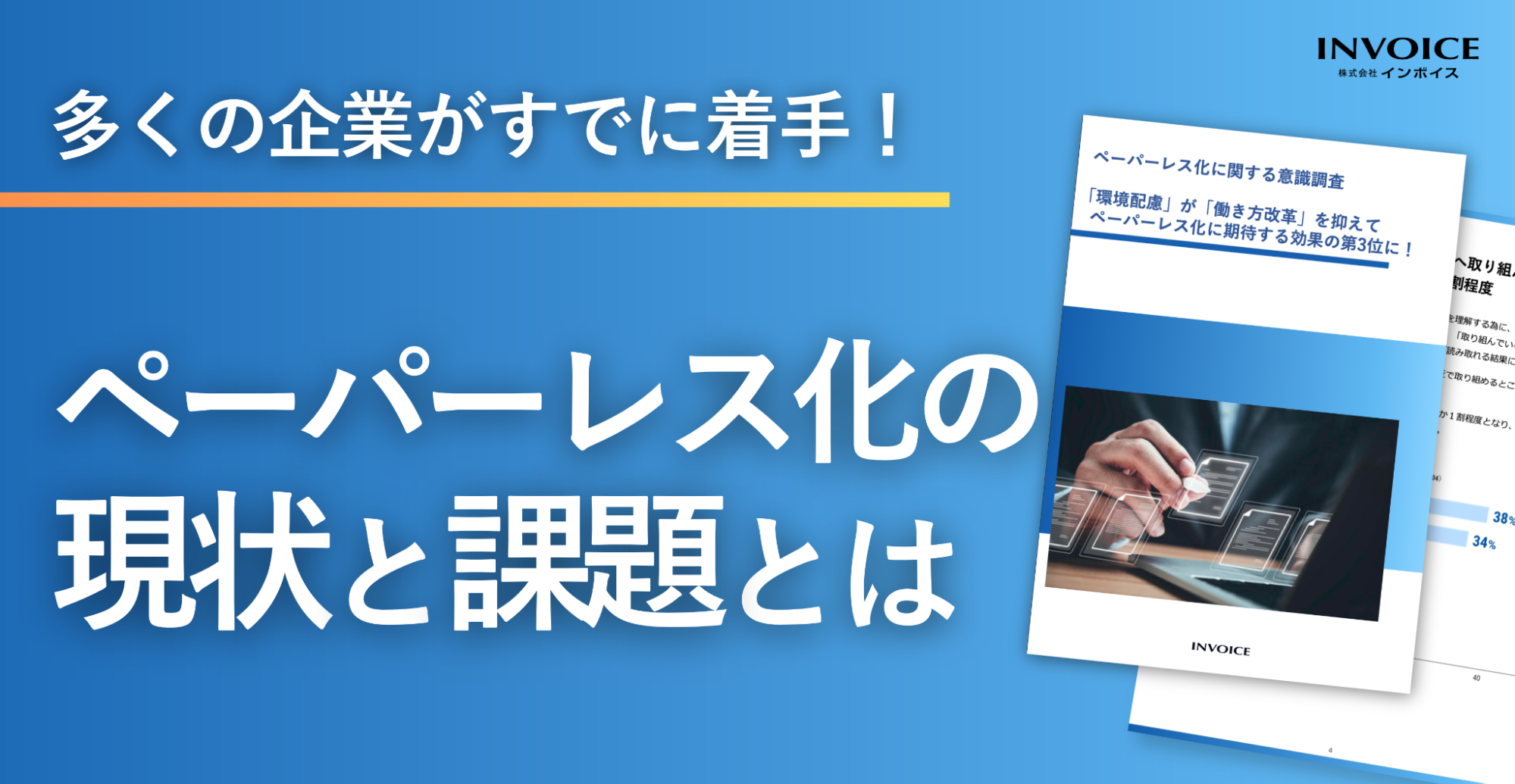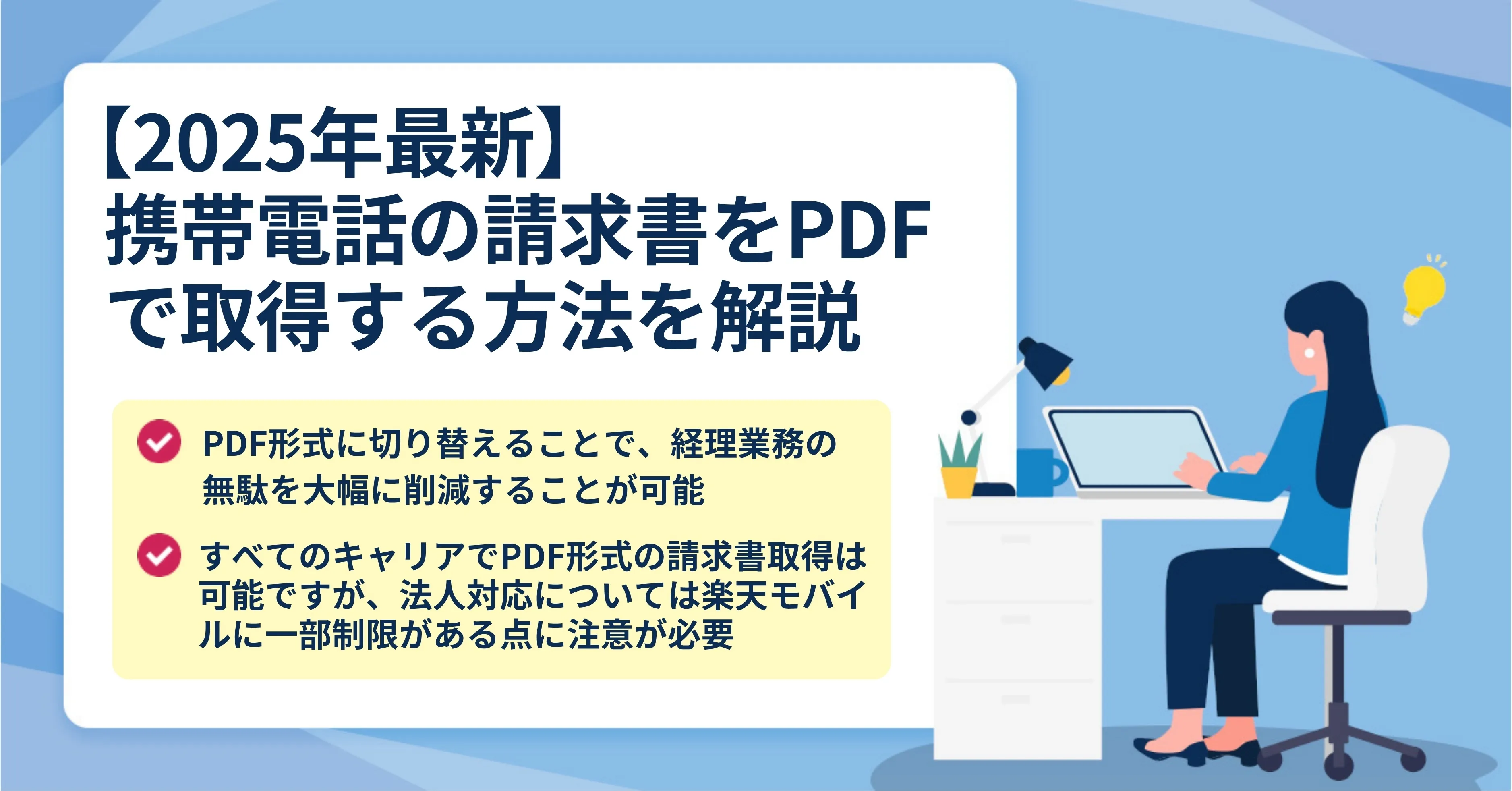領収書のPDF化は可能!電子帳簿保存法に則った要件や受領・発行側別のやり方やについて解説
更新日:2025.08.12
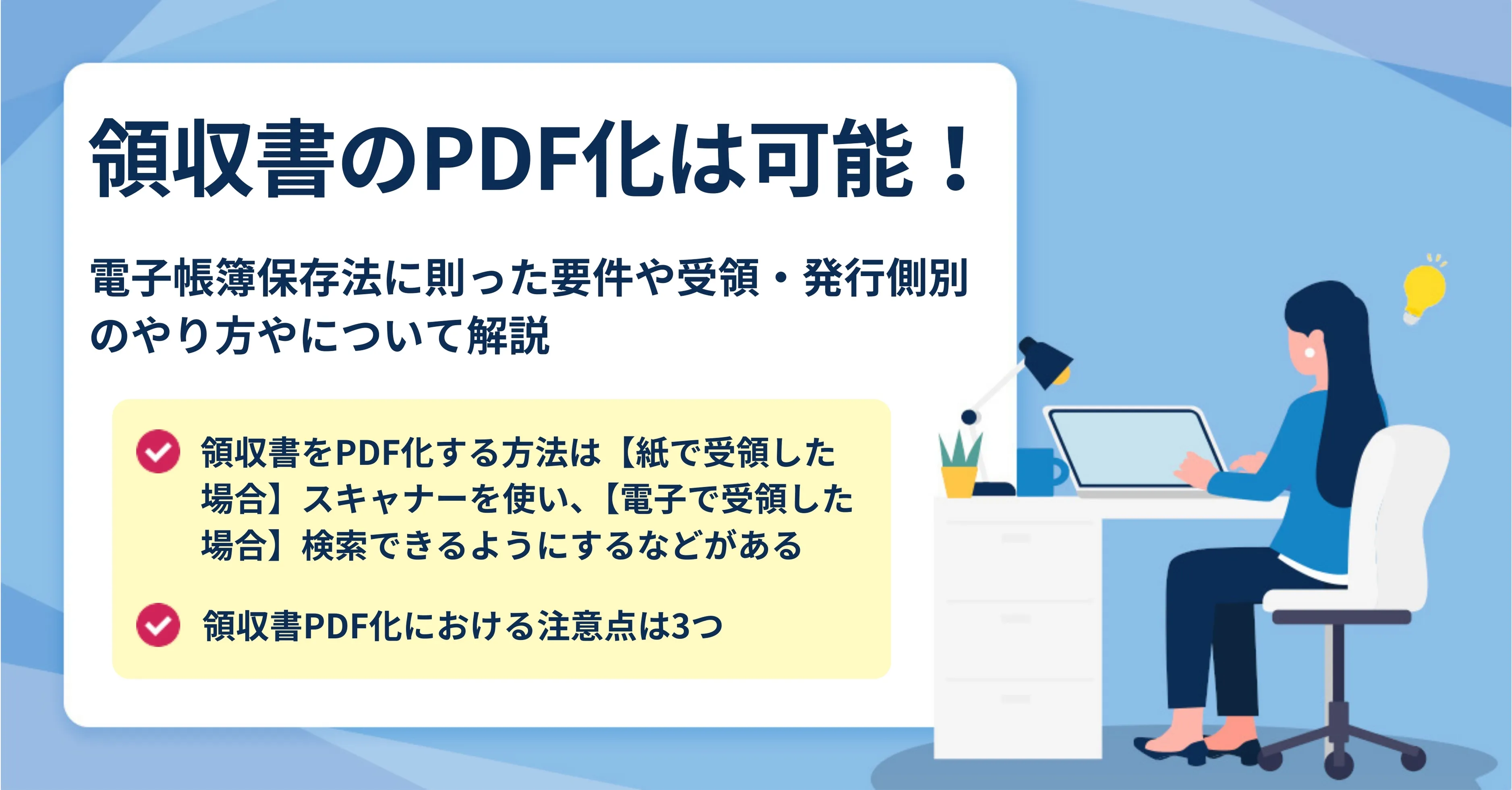
ー 目次 ー
紙の領収書は、以下のような管理上の課題があります。
- 経理処理の手間が多い
- 紛失のリスクが高い
- 保管スペースがかさむ
そのため、電子データ化、特にPDF化を検討している企業や担当者は少なくありません。
結論として、電子帳簿保存法の要件を満たせば、紙の領収書をPDF化して保存することは法的に問題ありません。
PDF化によって、以下のような業務効率化のメリットが得られます。
- 保管スペースの削減
- データ検索性の向上
- 管理コストの削減
ただし、スキャン後の電子データは、電子帳簿保存法に定められた検索要件を満たす必要があります。
本記事では、領収書のPDF化に関する重要ポイントを以下の内容で詳しく解説します。
▼この記事でわかる内容
- 領収書をPDF化する際の要件【電子帳簿保存法】
- 領収書をPDF化する方法
- PDF化した領収書の保存方法
- 領収書をPDF化する5つのメリット
- 領収書PDF化における3つの注意点
領収書の役割
領収書は、商品やサービスを提供する側が金銭を受け取った際に、その事実証明として発行するものです。一方で、商品やサービスを購入する側は、金銭を支払った事実証明として領収書を受け取ります。領収書は事実証明の他に、二重請求や過払いを防ぐ役割を持ちます。
領収書は事業者にとって、税務調査が入った際に売上や経費の根拠になる重要書類です。そのため、法人税法上で保管が義務付けられており、その保管期間は7年です。このように、領収書の役割は信憑書類という位置づけになります。
記載事項
領収書には明確なフォーマットがありません。つまり、以下の事項が記載されていれば領収書として認められます。
- 取引のあった日付
- 取引者の名称
- 取引金額と内訳
- 但し書き
- 宛名
また、5万円以上の取引金額の場合は収入印紙を貼り付ける必要があります。
領収書とレシートの違い
店舗などで商品を購入した際に発行されるレシートも、以下の事項が記載されていれば領収書のように利用できます。
- 取引のあった日付
- 取引金額
- 発行者の名称
- 受領した事実
レシートは領収書のように宛名がありませんが、その他の事項がしっかり記載されていれば問題ありません。
紙の領収書はPDF(電子化)で保管できる
紙媒体の領収書をPDF化、つまり電子化することは可能です。また、送付者と受取者の合意があれば、法的な効力を持たすこともできます。つまり、領収書のPDF化は双方の合意があって初めて効力が生まれるため、その証明ができるのかが重要となります。
一般的に双方の合意を証明するものとしては、文書やメールなどです。また、PDF化した領収書は見読性の確保が必須になります。画質は鮮明であるのか、出力を要求された場合にすぐに対応できるのかといった点に注意しましょう。加えて、領収書のPDF化は電子帳簿保存法の要件に沿う必要があります。
例えば、紙媒体の領収書であれば、スキャンした後にタイムスタンプの付与が必要です。電子帳簿保存法は2022年に一部改正され、電子取引の取引データは電子データで保存しなければならず、別途PDFで出力するケースでは検索要件の確保が難しいといった問題もあります。それでも、電子帳簿保存法の要件を満たすことで、PDF化した領収書でも正式な証憑書類として認められます。
領収書をPDF化する際の要件【電子帳簿保存法】
領収書をPDF化する場合は、電子帳簿保存法の要件に従う必要があります。電子帳簿保存法では、領収書の内容が改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプの付与が求められます。タイムスタンプは最長2ヶ月と7営業日以内に付与しなければなりません。以前までは税務署長の事前承認や、国税関係書類への自著などが必要でしたが現在は不要となっています。
また、電子帳簿保存法では、スキャンした電子データの検索要件を満たす必要があります。検索要件の確保では以下の3つが求められます。
- 日付・取引金額・取引先の3項目で検索できる
- 日付・取引金額は範囲を指定の上で検索できる
- 2つ以上の任意項目を組み合わせて検索できる
領収書をPDF化するのは容易ですが、この検索要件の確保が難しいところです。対策としては会計ソフトや自作の集計表などに紐づけることなどが挙げられます。
領収書をPDF化する方法
領収書をPDF化するには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。この章では、発行側と受領側それぞれの方法について詳しく解説します。
受領側である場合
受領側は、領収書のPDF化を行うためにいくつかやるべきことがあります。紙媒体と電子データ、それぞれのケースで詳しく解説します。
【紙で受領した場合】スキャナーを使う
領収書を紙媒体で受け取った場合は、スキャナまたはスマホを使用してPDF化します。PDF化する際は、データ改ざんの事実を否定するためにタイムスタンプの付与を行います。加えて、電子帳簿保存法の要件の一つである検索要件を守る必要があります。
【電子で受領した場合】検索できるようにする
領収書を電子データで受け取った場合(電子取引)は、PDFのファイル名を「日付・取引先・金額」がわかるような命名規則に変更する必要があります。また、検索要件を満たすためにExcelなどのツールを用いて、日付・取引先・金額で索引できるようにしておかなければなりません。
また、2022年度の電子帳簿保存法改正で書類を電子データで受け取った場合は電子データのままの保存が義務付けられています。ただし、令和4年度税制改正大綱にて宥恕期間が設けられ、2023年12月31日までは紙の出力が認められました。そのため、この期間中は紙での保存で良いものの、検索要件を満たすための準備が必要です。
発行側である場合
発行側は、領収書のPDF化を行うにあたって、まず取引先に確認を取るところから始めます。発行側がやるべきことを3ステップで詳しく解説します。
PDFで発行することを取引先に伝える
領収書のPDF化を行うにあたり、これまで領収書を紙媒体で発行していた事業者には、まずその旨を伝えてください。事業者の中には、紙媒体の領収書でなければ不都合な場合もあります。発行後のトラブルにならないよう必ず確認しましょう。
作成する
ExcelやWordなどのソフトで領収書を作成した場合は、そのままPDF化を行います。使うソフトによってはPDFに変換する機能が付帯しています。紙媒体の領収書の場合は、スキャンを行いPDFに変換しましょう。
送付する
PDF化した領収書をメールに添付して送信します。このとき、宛先や添付データに間違いがないかしっかり確認しましょう。宛先や添付データを間違えてしまうと、情報漏えいにつながり信用を失います。また、会計ソフトなど専用のシステムを使っている場合は、システム上で直接送付することが可能です。
PDF化した領収書の保存方法
領収書をPDF化して保存することは、ペーパーレス化や検索性の向上など、多くのメリットがあります。しかし、PDF化した領収書を正式な書類として認めてもらうためには、いくつかの注意点があります。
電子帳簿保存法の要件を満たす必要あり
電子帳簿保存法の要件を満たしていれば、PDFデータも正式な領収書として認められます。そのため、電子帳簿保存法に準拠した領収書発行システムを利用すれば、発行者は原本を紙で保管する必要がなく、電子データでの管理が可能になります。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
|
真実性の確保 |
データが改ざんされていないことを証明するため、タイムスタンプを付与するなどの措置が必要です。 |
|
可視性の確保 |
データの内容をいつでも確認できる状態である必要があります。 |
これらの要件を満たしていない場合、PDF化した領収書は税務調査などで認められない可能性があります。
※引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
領収書の保管期間は紙と同じ
PDF化した領収書であっても、保管期間は紙の領収書と同じです。
法人税法では、帳簿書類は7年間、消費税法では5年間の保存が義務付けられています。ただし、青色申告の承認を受けている場合は、帳簿書類を10年間保存する必要があります。
これらの保管期間を過ぎた領収書は、破棄しても問題ありません。
領収書をPDF化するメリット
領収書のPDF化は、受領側・発行側でさまざまなメリットがあります。この章では、領収書のPDF化するメリットについて詳しく解説します。
保存・管理がしやすい
領収書は重要書類である位置づけから、法人税法上で7年の保管義務が生じます。つまり、紙媒体の領収書であれば、社内などに保管スペースを作る必要があります。しかし、領収書をPDF化すればパソコンまたはクラウド上で保管できるため、社内などに保管スペースを作る必要がありません。
そもそも、紙媒体の領収書は保管スペースの問題に加え、劣化による視認性の確保が難しかったり紛失してしまったりする問題があります。電子データ化すれば劣化しない上、バックアップさえとれば紛失の心配もありません。領収書のPDF化は保存・管理において優れているといえます。
必要な領収書をすぐに取り出せる
領収書のPDF化は実際に領収書を探す作業が効率的になります。紙媒体の領収書であれば、保管スペース内にある膨大な書類の中から時間をかけて探すことになるでしょう。一方で、電子データ化された領収書であれば、パソコンまたはクラウド上で項目から検索をかけることですぐに見つけることが可能です。
そのためには、あらかじめファイル名の命名規則を決めておいたり、専門システムの導入をしたりしておくことが必要になります。
コストを削減できる
領収書を電子データ化すれば、紙媒体の領収書で発生する紙やインク代がかかりません。また、電子データ化された領収書のやりとりはメールなどになるため、郵送にかかる費用も不要です。加えて、原本廃棄が可能になります。電子データ化すればクラウド上などで保管できるため、社内などに設ける保管スペースは不要になります。
さらに、領収書をファイリングする必要もないため、経費処理にかかる時間や手間の削減にもつながっています。紙媒体の領収書は5万円以上の取引の場合、収入印紙を貼付しなければいけないと印紙税法で定められています。当然、電子データ化することで不要になります。
実際にかかっていたコストを削減できるだけでなく、社内などに設置していた保管スペースも不要になるため、事業者にとっては大きなコスト削減といえるでしょう。
業務効率化になる
紙媒体の領収書では、原本の管理が非常に重要です。原本管理をする性質上、どうしても保管するためのファイリング作業に手間や時間がかかってしまっていました。しかし、領収書を電子データ化すれば、原本の即時破棄が可能です。
例えば、外出先で領収書を受け取ったとして紙媒体のまま保管するのであれば、原本を会社に持ち帰る必要があります。しかし、電子化であれば、外出先で領収書をスマホなどで撮影するだけです。さらに、出先で社内の人間にメールなどしておけば、会社に戻ることなく経費処理が可能です。
近年、多くの企業が導入しているテレワークなどの働き方にも柔軟に対応できます。このように、領収書の電子データ化は、会社全体の業務効率化につながっています。
セキュリティ対策になる
領収書を電子データ化することで、セキュリティ面の強化にもつながります。領収書は重要書類である位置づけから再発行しにくく、紛失した場合のリスクが非常に高いです。しかし、電子データ化して、バックアップを取っていることで紛失の可能性がなくなります。
また、紙媒体の領収書であれば保管スペースの管理が甘い場合は外部への流出の危険性もあります。一方電子データ化された領収書は、パソコンまたはクラウド上で保管しているため、閲覧規制などを強化することで外部への流出を防げるでしょう。
領収書PDF化における注意点
領収書のPDF化はさまざまなメリットがある一方で、いくつか注意点もあります。この章では、領収書をPDF化する際に注意しておくべきことについて詳しく解説します。
電子押印・電子署名を検討する
領収書をPDF化する場合、改ざんの可能性を否定するために電子印鑑・電子署名の導入を考える必要があります。また、処理時の日付を証明するためのタイムスタンプの付与も同様です。しかし、法人税法上では押印は不要となっており、すべてのケースで該当するわけではありません。
システム上で電子帳簿保存法に対応した管理ができていればタイムスタンプの付与も不要となる場合もあります。
二重発行に気をつける
データ化された領収書は、紙媒体よりも再発行のプロセスが簡単です。ただし、領収書の再発行は不正利用などに悪用されるリスクがあるため、多くの企業では消極的ではあります。それでも、得意先に再発行を求められて対応するケースも発生することでしょう。
領収書を再発行する場合は再発行である旨を記載するなど、不正利用されない対策を取るようにしましょう。また、紛失ではなく汚損が理由の再発行である場合は、紙媒体の領収書であれば原本の回収をするなど領収書の取り扱いを徹底してください。
パスワードを付与する
PDF化した電子データを安全に管理するためには、パスワードまたは閲覧制限などを付帯する必要があります。近年は、サイバー攻撃によって不正アクセスやデータ改ざんなどが問題となっています。こうした問題に対応するためにもセキュリティ面の対策をしっかり行ってください。
また、初歩的な部分ですが誤送信などによる情報漏洩にも注意しましょう。
電子帳簿保存法の観点から領収書のPDF化に移行してみよう
本記事では、領収書のPDF化について詳しく解説してきました。近年は、さまざまな書類を電子データ化する動きが活発です。特に領収書はその性質上枚数が多くなる傾向があり、紙媒体のままでは管理が大変です。社内などに管理スペースを設ける必要があったり、紛失によるリスクも大きかったりします。一方で領収書をPDF化、つまり電子データ化すればパソコンまたはクラウド上で管理できるだけでなく、経理処理のプロセスも簡略化します。
2022年に電子帳簿保存法の改正が行われ、電子データ保存の要件が緩和されました。現在、紙媒体の領収書をメインとしている企業は、この機会に電子データ化への取り組みを推し進めてみてはいかがでしょうか。