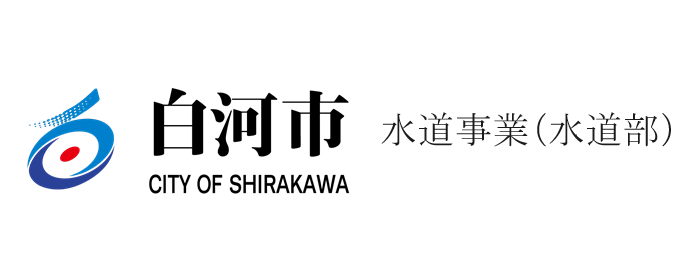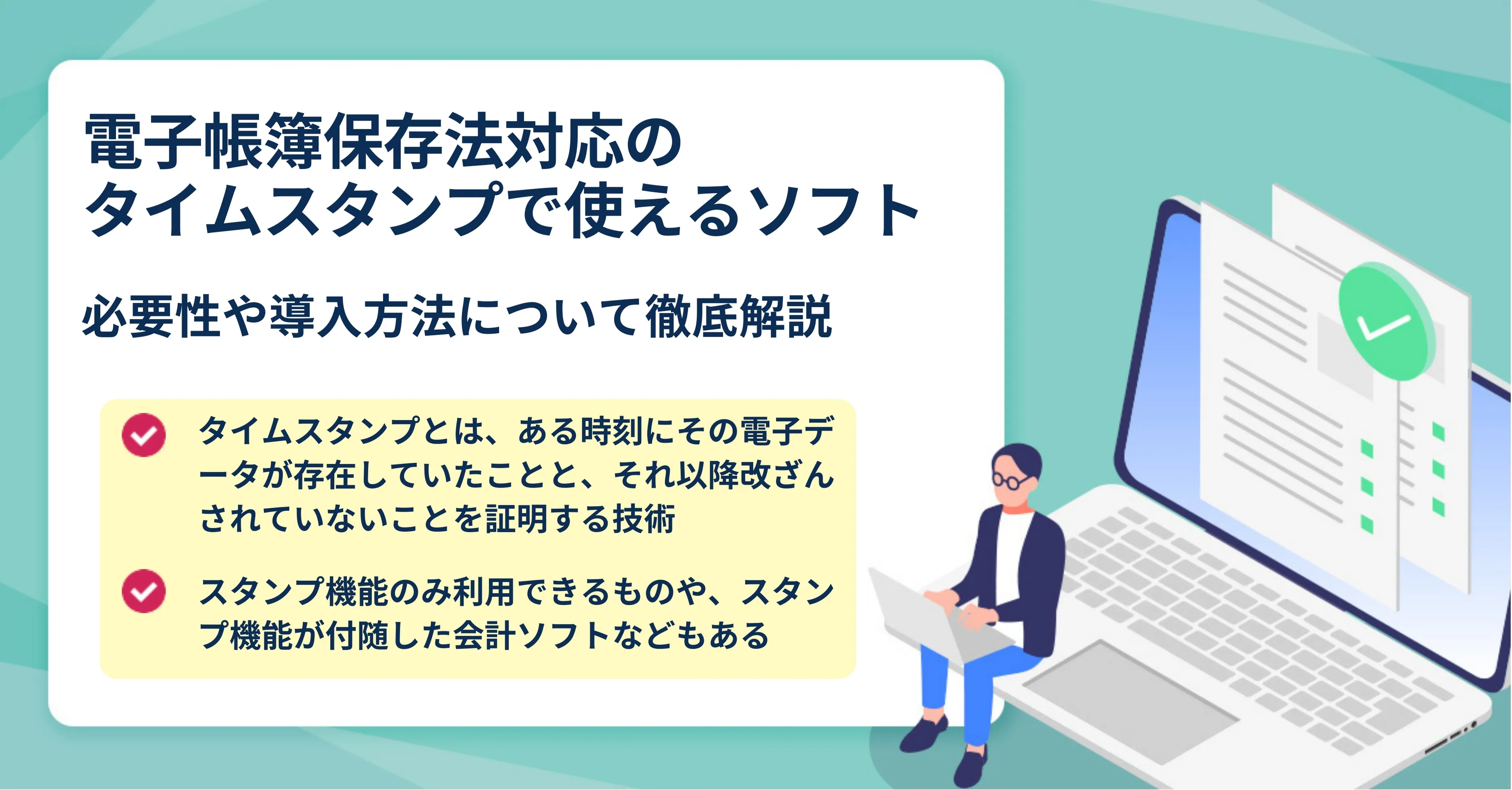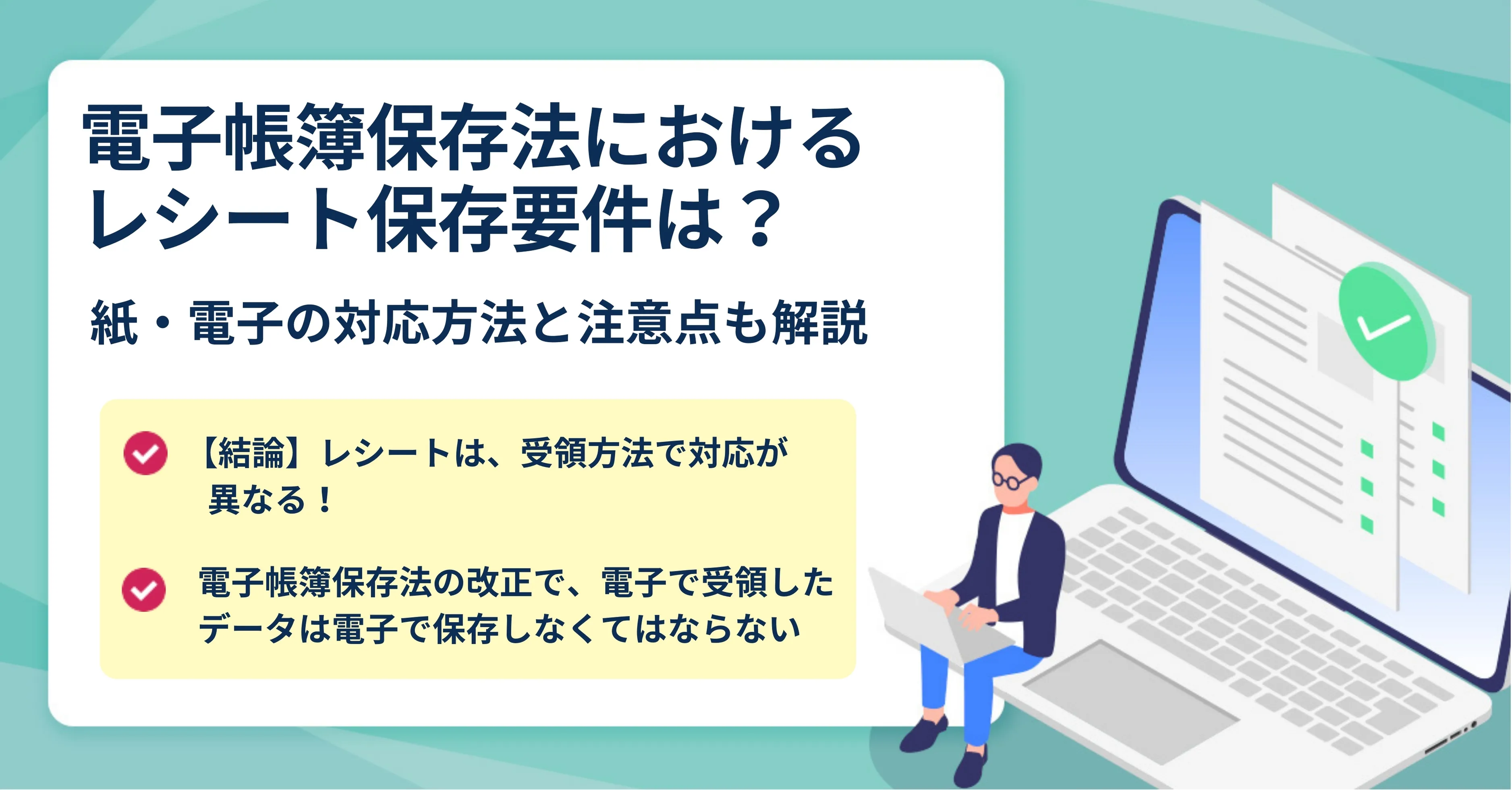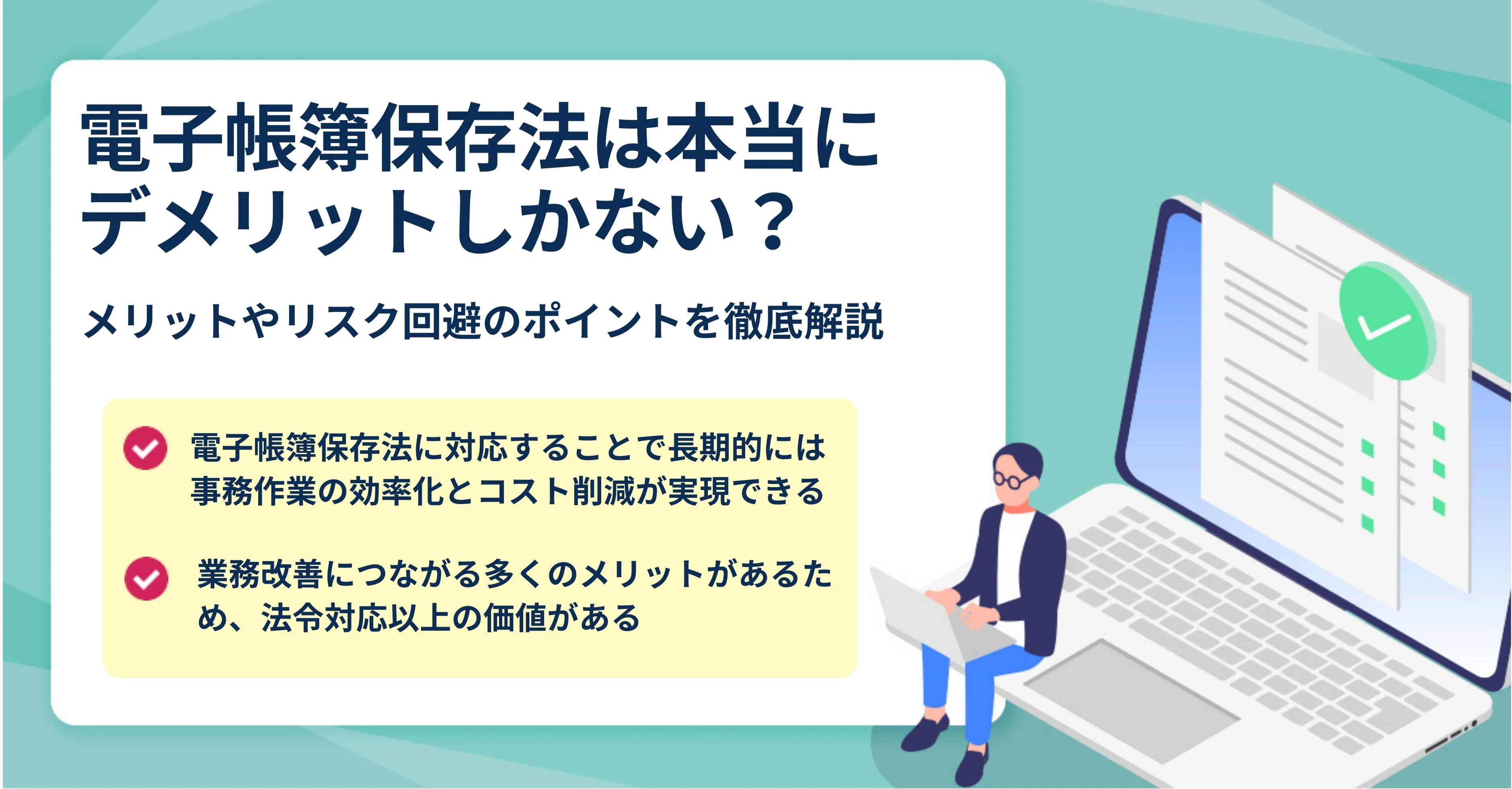【電子帳簿保存法】インボイスでタイムスタンプは必要?無料で導入する方法もあわせて解説。
更新日:2025.05.01
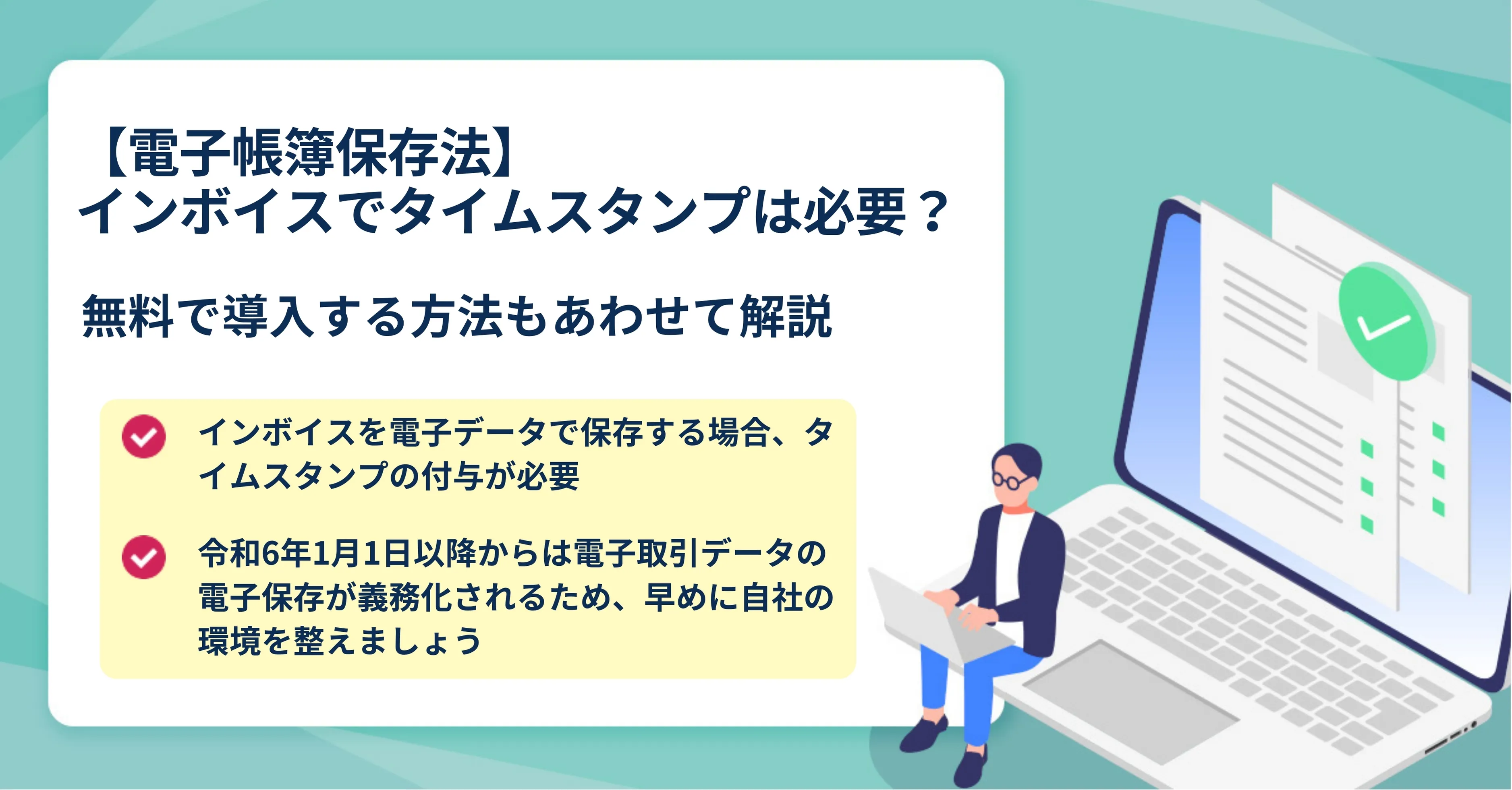
ー 目次 ー
令和3年度の税制改正により、一定の条件を満たす場合には、スキャナ保存時のタイムスタンプ付与が不要となる制度変更が行われました。これにより、電子帳簿保存法への対応が、従来よりも大幅に簡素化されています。
本記事では、タイムスタンプの基本的な役割や、電子帳簿保存法の概要について丁寧に解説するとともに、タイムスタンプが不要となる具体的な条件、そして改正後の電子帳簿保存法を自社に適用するための手順や注意点について、わかりやすく紹介します。電子データ保存を検討している方や、最新の制度変更に対応したい方は、ぜひ参考にしてください。
タイムスタンプとは電子データの存在と非改ざんを証明する技術
タイムスタンプとは、電子データの信頼性を担保する技術です。
具体的には第三者(時刻認証局)が時刻を電子データに刻印することで、その時刻よりも前にデータが存在していたこと、また、その時刻よりも後にデータが改ざんされていないことの証明ができるというものになります。
郵便局の消印と同じことを、データ上で行っていると考えると分かりやすいでしょう。
タイムスタンプの仕組み
電子データに時刻を入れるだけでは容易に捏造できてしまいます。
そのためタイムスタンプではハッシュ値に、時刻情報を結合し不正を防止しています。
ハッシュ値とは、元となるデータをハッシュ関数という計算手順で処理し、求められた値です。
同じデータからは同じハッシュ値が求められる一方、ハッシュ値から元データを復元できない点が特徴です。
上記の特性から、元データとスタンプを押した後のデータを比べれば、簡単に電子文書の不正を確認できます。
インボイスとタイムスタンプの関係性
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行・保存する義務が発生します。特に電子データで保存する場合、データの真正性と改ざん防止を証明するためにタイムスタンプの付与が重要になります。電子帳簿保存法では、電子取引データにタイムスタンプを付与するか、訂正・削除履歴を残す仕組みを設けることが保存要件とされています。そのため、電子インボイスを適正に保存するには、タイムスタンプの活用が現実的な手段のひとつとなっています。
電子帳簿保存法とは帳簿書類を電子データで保存する要件を定めた法律
次に、電子帳簿保存法を説明します。
電子帳簿保存法とは税法上、紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電子データで保存する際の要件をまとめた法律です。
情報化社会に対応し、国税関係書類の保存負担軽減を目的として平成10年3月に交付されました。
直近では、令和3年度の税制改正により、電子データの保存要件が大きく緩和されています。
タイムスタンプが使われる理由
タイムスタンプを使う大きな理由は、電子データの改ざん防止です。
従来の紙ベースの保管では、日付の明記や署名・捺印、指紋、筆跡など、複数の方法で偽装を判別できました。
しかし電子データは劣化の恐れがなく、紙以上に偽造が容易で見つけることも困難です。
そのため、これらの脆弱性を回避し、紙文書と同等の法的効果を保証する方法として利用されています。
タイムスタンプの使い方

タイムスタンプを使うためには、下記の準備が必要です。
● インターネットに接続された環境を用意する
● 一般財団法人日本データ通信協会の認証した時刻認証事業者と契約する
● タイムスタンプが使えるシステムを導入する
これらが整ったら、下記の手順でスキャナ保存した書類に押します。
● 紙書類をスキャナやスマートフォンで読み込み、PDF保存する
● 保存したPDF保存を専用のシステムに読み込ませる
● PDFにタイムスタンプが押される
なお、タイムスタンプの使い方はメーカーにより差があるため、事前に確認しましょう。
電子帳簿保存法改正後のタイムスタンプ不要条件
令和3年度の税制改正により、一定の要件を満たすシステムなどを利用する場合に限り、タイムスタンプに代えることができるようになりました。[注1]
具体的な条件は下記のとおりです。
● 入力期間内(最長2カ月と7営業日)に電子データの保存を行ったと確認できる
● 電子データの訂正または削除を行ったときは、その事実と内容を確認できる
● 電子データの訂正または削除を行うことができない
これらの条件を満たす場合、令和4年1月1日以降に行うスキャナ保存以降不要となります。
[注1]国税庁:電子帳簿保存法が改正されました p.3
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf (参照:2022-04-08)
その他の改正された条件
改正法では、他にも下記の条件が緩和されています。
● 税務署長の事前承認制度の廃止
● タイムスタンプの押す期間が最長2カ月と7営業日以内に延長
(従来は3営業日以内)
● スキャニング時の国税関係書類への自署不要
● 検索要件の記録項目が取引年月日、取引金額、取引先に限定
● 適正事務処理要件の廃止
上記以外にも優良な電子帳簿を保存すれば、過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
ただし、電子データの保存要件が緩和された反面、スキャナ保存や電子取引のデータに不正があったときは、罰則として10%の重加算税が導入されています。
令和4年度税制改正大綱により電子取引データの保存義務が延長
令和4年度税制改正大綱により、本来令和4年1月1日からスタートするはずだった電子取引のデータ保存義務化が、令和5年12月31日まで延長されました。[注2]
このため、電子的に受領した取引データの紙保存が上記期間までは認められます。
[注2]財務省:令和4年度税制改正の大綱 p.76
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf (参照:2022-04-08)
適正事務処理要件が不要になりスキャナ保存が容易に
令和3年度の同法の改正では、適正事務処理要件が廃止された点も大きなポイントです。
適正事務処理要件では、下記の3項目を社内規定などで定め、順守することが求められていました。
● 相互牽制
書類のスキャニングと原本との照合などをそれぞれ別の担当者が行い、互いの事務処理を確認する仕組みです。運用するためには2名以上の担当者が必要です。
● 定期的な検査
少なくとも年1回以上、電子データ保存の作業手順を守っているか、実際にスキャンしたデータに不備はないか確認が必要です。なお、検査の際は税務関係書類の原本が必要なため、終了するまで破棄できません。
● 再発防止
定期的な検査の際、不備が見つかった場合は原因究明や改善策の検討を行う体制を整えなければいけません。具体的には経営者を含む幹部社員に不備を報告した上で、改善策を議論しなければいけません。
法改正により、以上の適正事務処理要件とタイムスタンプが不要となったため、小規模事業所でもスキャナ保存が容易となりました。
改正電子帳簿保存法を適用する方法
改正後の電帳法を適用するためには、以前からスキャナ保存を導入していたかどうかにより方法が異なります。
令和4年1月1日以降に初めて導入するとき
施行日以降に初めてスキャナ保存などを導入するなら、税務署長への事前承認などの手続きは必要ありません。
保存条件を満たす環境が整っていれば、すぐに対応可能です。
以前に承認を受けたが改正後の条件でスキャン保存したいとき
同法の改正以前から、税務署長の承認を受けてスキャナ保存をしていた場合、承認は施行日以降も有効です。
そのため、改正法の条件で電子データを保存したいなら、承認の取りやめ届を税務署に提出しなければいけません。[注3]
[注3]国税庁:[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_02.htm (参照:2022-04-08)
引き続き改正前の条件でスキャナ保存したとき
以前からスキャナ保存をしている事業所では、改正後・改正前、どちらの条件に則るかは、事業者の判断にゆだねられます。
タイムスタンプを押す、改正前の方法で引き続きデータを保存しても問題ありません。この場合、承認の取りやめなどの手続きは不要です。
ただし、重加算税のペナルティは、どちらの条件に則っても、施行日以降の国税関連書類に適用されます。
電子帳簿保存法改正によりタイムスタンプ不要で電子データを保存できる!
令和3年度の改正により、電子データの保存要件が大きく緩和されました。これにより、訂正や削除の履歴が残るシステムを導入すれば、タイムスタンプに代えることが可能です。
特に、令和6年1月1日以降からは電子取引データの電子保存が義務化されるため、早めに自社の環境を整えましょう。