収益はどうなる?ユーチューバーのためのインボイス対応ガイド
更新日:2026.01.13
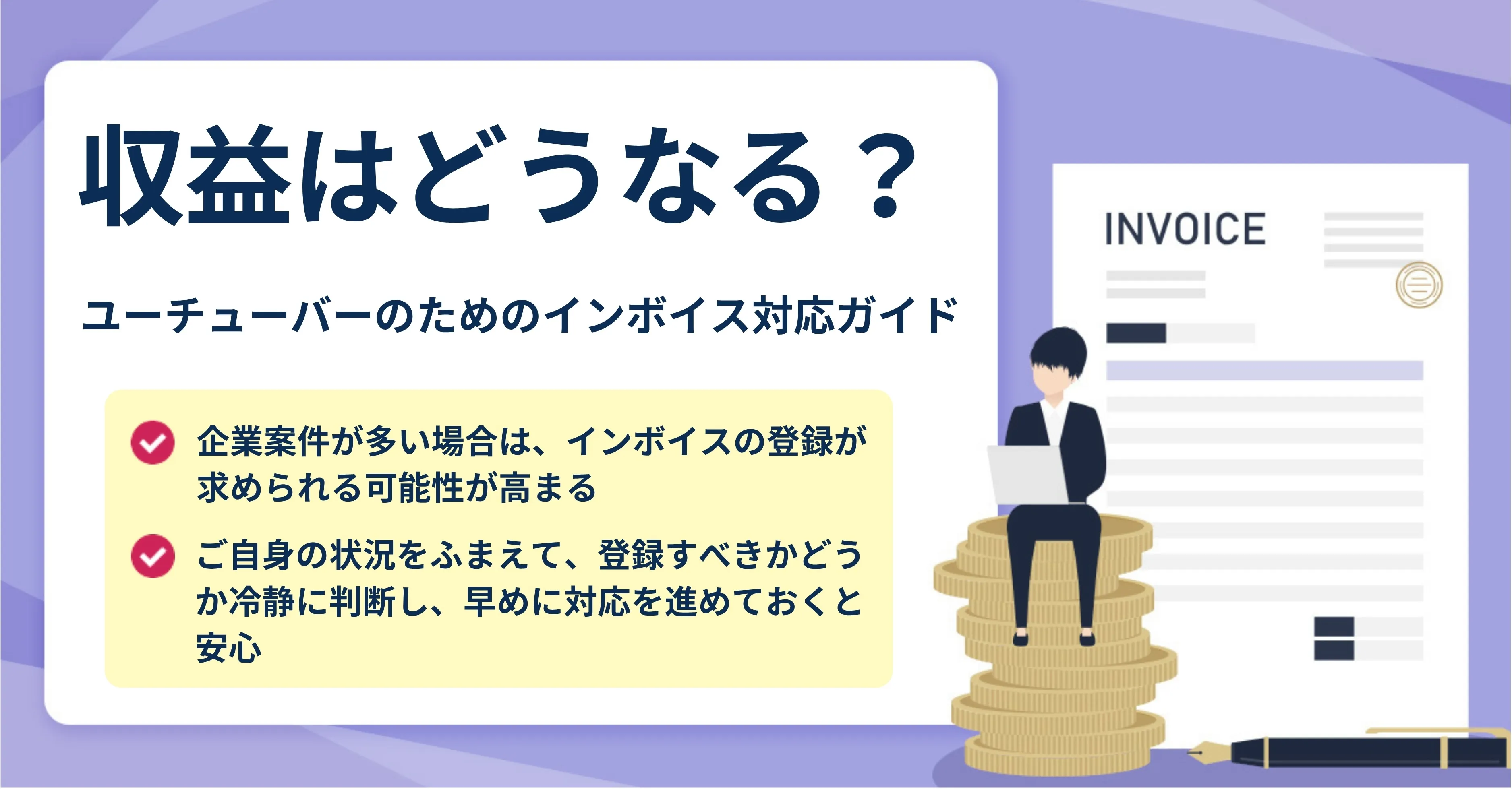
ー 目次 ー
インボイス制度、なんとなく聞いたことはあるけれど、「自分にも関係あるのかな?」と感じているユーチューバーの方も多いのではないでしょうか。この記事では、インボイス制度の基本から、収益・経費への影響まで実務に役立つ情報をできるだけわかりやすくまとめました。不安をクリアにして、安心して活動を続けるための参考になれば幸いです。
ユーチューバーとインボイス制度の基礎知識
インボイス制度は、ユーチューバーの収益や経費の取り扱いに影響を与える可能性があるため、基本的な知識を身につけておくことが不可欠です。この章では、インボイス制度の概要と、ユーチューバーにとってなぜ重要なのかを解説します。
インボイス制度とは? 背景や目的をわかりやすく解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。2023年10月1日から導入された消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。この制度は、複数税率(標準税率10%と軽減税率8%)に対応した消費税の仕入税額控除をより正確に行うことを主な目的としています。
インボイス制度導入の背景には、主に以下の点が挙げられます。
- 消費税の複数税率(軽減税率制度)への対応
- 仕入税額控除の適正化
- 事業者の取引における透明性の向上
ユーチューバーにとっても、YouTubeからの広告収益、企業案件の報酬、動画制作にかかる外注費や物品購入費など、消費税が関わる取引において、この制度への理解と対応が求められます。特に、取引先が課税事業者である場合、インボイス(適格請求書)の有無が取引条件に影響する可能性があります。
適格請求書って何?
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して発行する、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書や領収書などの書類のことです。適格請求書を発行するためには、事前に税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」としての登録を受ける必要があります。
適格請求書には、従来の請求書(区分記載請求書)の記載事項に加えて、以下の情報などの記載が義務付けられています。
|
主な記載事項 |
内容 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
「T」で始まる13桁の番号(法人番号または個人に割り当てられる番号) |
|
適用税率 |
税率(10%対象、8%対象など)ごと |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
各税率ごとに計算した消費税額 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
(従来の請求書にも記載) |
|
取引年月日 |
(従来の請求書にも記載) |
|
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
(従来の請求書にも記載、軽減税率対象の場合はその旨を明記) |
|
税率ごとに区分した合計額(税抜または税込) |
(従来の請求書にも記載) |
|
書類作成者の氏名または名称 |
(従来の請求書にも記載) |
買手側(発注者側)は、原則としてこの適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることができます。そのため、ユーチューバーが企業などから仕事の依頼を受ける際に、適格請求書の発行を求められるケースが増えることが予想されます。自身が免税事業者の場合、適格請求書は発行できません。
ユーチューバーの収益に影響アリ?インボイス制度がもたらす現実
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の具体的な影響と、その背景にある仕組みについて解説します。
インボイス未登録だと報酬が減る?仕入税額控除の仕組みとは
インボイス制度導入の大きなポイントは「仕入税額控除」です。これは、課税事業者が消費税を納める際に、仕入れにかかった消費税額を差し引ける仕組みのことです。
もしあなたが免税事業者(課税売上高1,000万円以下など)のままで、取引先(広告主や所属事務所など)が課税事業者だった場合、あなたがインボイス(適格請求書)を発行できないと、取引先はその取引にかかる消費税額を仕入税額控除できなくなる可能性があります。
その結果、取引先によっては以下のような対応を取る可能性が考えられます。
- 消費税相当額の報酬減額を求められる
- インボイスを発行できる他の事業者との取引を優先される
ただし、経過措置も設けられているため、すぐに全額控除不可になるわけではありません。
動画制作費や外注費も要注意?経費とインボイスの関係
インボイス制度は、報酬を受け取る側だけでなく、経費を支払う側にも影響します。もしあなたが課税事業者としてインボイス発行事業者になった場合、経費の支払いにおいてもインボイスの保存が重要になります。
例えば、以下のような経費を支払う際に、相手からインボイスを受け取る必要があります。
- 動画編集の外注費
- 撮影機材の購入費やレンタル費
- スタジオの利用料
- BGMや効果音、画像素材の購入費
これらの経費について、インボイスを適切に保存していれば、支払った消費税額を仕入税額控除に利用できます。逆に、インボイスがない場合や、取引相手が免税事業者でインボイスを発行できない場合は、その分の仕入税額控除が受けられず、結果として納める消費税額が増える可能性があります。
日頃から取引相手がインボイス発行事業者かどうかを確認し、必要な書類を確実に受け取ることが大切です。
活動形態別|ユーチューバーのインボイスの影響(事務所所属or個人)
ユーチューバーの活動形態によって、インボイス制度の影響の受け方や対応のポイントが異なります。
事務所所属のユーチューバー
事務所(MCNなど)に所属している場合、まずは事務所との契約内容や、事務所の方針を確認することが重要です。多くの場合、事務所が課税事業者であり、ユーチューバーへの報酬支払いを課税仕入れとして扱っていると考えられます。
この場合、事務所からインボイスの発行を求められる可能性があります。事務所によっては、所属クリエイターのインボイス対応についてサポート体制を整えている場合もありますので、相談してみましょう。
個人で活動するユーチューバー
個人で活動しているユーチューバーの場合、取引先との関係性を個別に考慮する必要があります。
|
取引の種類 |
主な取引先 |
インボイス制度の影響と留意点 |
|
広告収益(プラットフォーム経由) |
Google AdSenseなど |
プラットフォーム運営企業の対応によります。Google AdSenseからの収益は、支払元が海外企業であるため、消費税の課税関係やインボイス制度の直接的な影響は国内取引と異なる場合があります。最新情報を確認しましょう。 |
|
企業案件(直接契約) |
国内企業 |
企業側が課税事業者である場合、仕入税額控除のためにインボイスの発行を求められる可能性が高いです。インボイス未登録の場合、取引条件の変更や、取引自体を見送られるリスクがあります。 |
|
グッズ販売など |
購入者(消費者、事業者) |
購入者が事業者の場合、インボイスの発行を求められることがあります。消費者向けの販売が主であれば、影響は限定的かもしれません。 |
あなたは対象?ユーチューバーのインボイス登録の判断ポイントまとめ
インボイス制度が導入され、多くのユーチューバーがご自身への影響や、適格請求書発行事業者への登録が必要かどうかについて関心をお持ちのことでしょう。この章では、ユーチューバーがインボイス登録を検討する際に押さえておくべき判断ポイントを具体的に解説します。
年間どのくらい稼いでたら登録すべき?判断のポイント
インボイス登録が必要かどうかを判断するには、まず1年間の売上がどのくらいあるかを確認することが大切です。
原則として、個人の場合は「前々年の売上」が1,000万円を超えていれば、消費税を納める義務がある『課税事業者』になります。法人の場合は、前々事業年度の売上が基準です。
また、1,000万円以下であっても、一定の期間(たとえば前年の1月〜6月)に売上が多かった場合は、課税事業者とみなされることもあります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録した人に限られます。一度登録をすると、売上が1,000万円以下でも消費税を納める義務が発生する=課税事業者になるので、その点もふまえて判断する必要があります。
課税売上高が1,000万円以下で現在免税事業者のユーチューバーでも、以下のようなケースではインボイス登録を前向きに検討する必要性が高まります。
- 企業案件(スポンサードコンテンツ、商品PR、イベント出演など)からの収入がメインである、または今後増やしていきたい。
- 主な取引先である広告主、広告代理店、所属事務所などが課税事業者であり、インボイスの発行を求められている。
- インボイスを発行できないことが、他のユーチューバーとの競争において不利になる可能性がある。
ご自身のYouTubeチャンネルの収益や主要な取引先との関係性を考慮し、インボイス登録のメリット・デメリットを比較検討することが大切です。
登録してないと取引NG?企業案件で起こりうるパターンとは
ユーチューバーが企業からプロモーション案件などを受ける場合、相手の企業が「課税事業者」であれば、インボイス(適格請求書)を発行できるかどうかが、契約を続けられるかどうかに関わってくることがあります。
というのも、企業側が支払った消費税を自分の税金から差し引く(=仕入税額控除)ためには、インボイスを保存することが基本的なルールになっているからです。
もしあなたがインボイス発行事業者として登録していない場合(免税事業者のまま、または課税事業者であってもインボイス登録をしていない場合)、以下のような状況が発生する可能性があります。
インボイス未登録の場合に想定される企業側の対応
- 報酬(契約金額)の減額交渉:企業側が仕入税額控除を受けられない分、消費税相当額の支払いを抑えるために、報酬額の減額を打診してくるケースです。例えば、従来110,000円(消費税込)で契約していた案件について、インボイスが発行されない場合は100,000円(消費税抜きの本体価格)での契約を求められる、といった交渉が考えられます。
- 取引の敬遠または中止:特に新規の取引先や、多数のクリエイターと契約している企業の場合、経理処理の統一化や税務リスク回避の観点から、インボイスを発行できない事業者との取引を控える、あるいは既存の取引を見直す(契約を打ち切る)可能性も否定できません。
- 契約条件の変更要請:インボイス制度への対応を盛り込んだ新たな契約条件を提示されたり、インボイスが発行できない場合の取り扱いについて別途協議が必要になったりする場合があります。
取引継続のための交渉ポイント
インボイス未登録の状態で企業との取引を継続したい、あるいは不利な条件変更を避けたい場合、以下のような点を踏まえて交渉することも考えられます。
- 提供価値の再確認とアピール:ご自身のチャンネルの影響力(登録者数、視聴回数、視聴者層)、専門性、企画力、過去の実績など、企業にとって代替困難な独自の価値を具体的に示し、報酬維持の交渉材料とします。
- 経過措置の理解と説明:インボイス制度には、免税事業者等からの課税仕入れについても、制度開始から一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています(2023年10月1日から2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%)。この点を企業側に伝え、理解を求めることも有効な場合があります。
- 柔軟な価格調整の検討:全額の減額要求に応じられない場合でも、双方にとって受け入れ可能な範囲での価格調整や、付加価値の提供(例:追加のSNS投稿など)を提案することで、合意点を見いだせる可能性があります。
ただし、これらの交渉が必ずしも成功するとは限りません。ご自身の活動方針や取引先との力関係などを慎重に見極めることが求められます。
インボイス登録の申請方法!(ユーチューバー編)
インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者としての登録を考えているユーチューバーの皆さんに向けて、具体的な申請方法を解説します。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
登録に必要なものは?申請前に準備しておきたい書類・情報一覧
適格請求書発行事業者の登録申請を行うにあたり、事前に準備しておくべき書類や情報があります。以下のリストを参考に準備を進めてください。
|
準備するもの |
詳細・備考 |
|
マイナンバーカード |
e-Tax(電子申請)を利用する場合に主に使用します。お持ちでない場合は、通知カードと運転免許証などの本人確認書類の組み合わせで対応可能なケースもありますが、マイナンバーカードがあると手続きがより円滑に進みます。 |
|
登録申請書 |
正式名称は「適格請求書発行事業者の登録申請書」です。国税庁のウェブサイトからPDF形式でダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。e-Taxで申請する場合は、オンライン上で作成・提出が可能です。 |
|
納税地・氏名・屋号などの基本情報 |
申請書に記載する情報です。ユーチューバーとして屋号(チャンネル名など)で活動している場合は、屋号も正確に記載する必要があります。個人の場合は、事業所所在地または住所地が納税地となります。 |
|
(e-Tax申請の場合)利用者識別番号と暗証番号 |
過去にe-Taxを利用したことがある方は、その際に取得した利用者識別番号(16桁)と暗証番号を準備してください。初めてe-Taxを利用する場合は、事前にe-Taxの開始届出を行い、これらを取得する必要があります。 |
上記以外にも、状況に応じて追加で情報が必要になる場合があります。申請前には必ず国税庁のウェブサイトで最新情報を確認するようにしましょう。
インボイス登録はどこでできる?申請の流れをステップで解説
適格請求書発行事業者の登録申請は、主に「e-Tax(電子申請)」を利用する方法と、「郵送」で申請書を提出する方法の2種類があります。それぞれの申請手順とポイントを、ユーチューバーの方向けにわかりやすく解説します。
e-Tax(電子申請)での申請方法
e-Taxを利用すれば、税務署に出向くことなく、ご自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで申請手続きを完結できます。時間や場所を選ばずに申請できるため、多忙なユーチューバーの方には特におすすめの方法です。
ステップ1:e-Taxソフトへのアクセスとログイン
国税庁が提供するe-Taxソフト(PC版のWEB版やスマートフォン版のSP版など)にアクセスします。マイナンバーカードとICカードリーダライタ(PCの場合)またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを使用してログインするか、事前に取得した利用者識別番号と暗証番号でログインします。
ステップ2:登録申請書の作成・入力
ログイン後、申請・納税手続きの中から「適格請求書発行事業者の登録申請」に関連するメニューを選択します。画面の案内に従って、納税地、氏名、生年月日、屋号(ユーチューバー活動で使用している名称があれば)、登録希望日などの必要情報を正確に入力していきます。
ステップ3:電子署名と送信
入力内容に誤りがないか最終確認を行った後、マイナンバーカードを使用して電子署名を付与し、申請データを送信します。送信が完了すると、受付結果が通知されます。
ステップ4:登録通知の確認
申請内容に問題がなければ、審査を経て登録が行われます。登録が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに「登録通知書」が電子データで格納されます。この通知書には、適格請求書発行事業者登録番号(T+13桁の法人番号または数字)が記載されていますので、大切に保管してください。
郵送での申請方法
パソコン操作に不慣れな方や、書面でじっくりと確認しながら手続きを進めたいユーチューバーの方は、郵送による申請も可能です。
ステップ1:登録申請書の入手と記入
国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」のPDFファイルをダウンロードし、印刷します。または、最寄りの税務署の窓口でも入手できます。申請書には、ボールペンを使い、楷書で丁寧に必要事項を記入します。ユーチューバーとして屋号(チャンネル名など)を使用している場合は、屋号欄も忘れずに記入しましょう。
ステップ2:管轄のインボイス登録センターへ郵送
記入済みの登録申請書を、ご自身の納税地を管轄する「インボイス登録センター」宛に郵送します。送付先のインボイス登録センターの所在地は、国税庁のウェブサイトで確認できます。郵送の際は、簡易書留など追跡可能な方法を利用すると安心です。
ステップ3:登録通知書の受領
申請書がインボイス登録センターに到着後、審査が行われます。審査が完了し、登録が認められると、「登録通知書」が郵送で送られてきます。この通知書に記載されている登録番号は、今後の請求書発行に必要となるため、紛失しないように注意しましょう。
どちらの申請方法を選択するにしても、申請から登録通知を受け取るまでには一定の期間を要します。特に制度開始のタイミングや確定申告の時期などは申請が集中し、通常よりも時間がかかる場合があるため、登録が必要だと判断したら早めに手続きを開始することをおすすめします。
Q&A|ユーチューバーとインボイスに関するよくある質問
副業でYouTube活動をしていて、雑所得扱いだったけどインボイス登録は必要?
YouTube活動による収益が税法上「雑所得」として扱われるか「事業所得」として扱われるかと、インボイス登録の必要性は直接的には連動しません。インボイス登録を検討する上で重要なのは、主に以下の2点です。
|
判断ポイント |
詳細 |
|
消費税の課税事業者であるか |
原則として、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合、あなたは消費税の課税事業者となり、インボイス発行事業者への登録を検討する必要があります。免税事業者であっても、任意で課税事業者を選択し、インボイス発行事業者になることも可能です。 |
|
取引先からインボイス発行を求められるか |
企業案件のクライアントや所属事務所など、報酬を支払う側(買い手)が仕入税額控除を行うために、あなたに適格請求書(インボイス)の発行を求めることがあります。免税事業者のままではインボイスを発行できないため、取引の継続や条件に影響が出る可能性があります。 |
副業であっても、これらの状況に当てはまる場合はインボイス登録を検討する必要があります。ご自身の売上規模や取引先の状況をよく確認しましょう。不明な場合は税理士などの専門家にご相談ください。
海外企業からの広告収益にもインボイス制度って関係ある?
インボイス制度は日本の消費税法に基づく制度であるため、その取引が日本の消費税の課税対象となるかどうかがポイントです。例えば、Google AdSenseのようなプラットフォームからの広告収益の多くは、Google Ireland Ltd.など海外の事業者との契約に基づいているケースが一般的です。
このような国外事業者から受け取る広告収益は、多くの場合「国境を越えた役務の提供」に該当し、日本の消費税法上、消費税の課税対象外(不課税または輸出免税取引)となることが一般的です。消費税の課税対象外の取引については、インボイスの発行義務はありません。
ただし、契約内容やプラットフォームの運営主体(例えば、日本の法人格を持つ企業や、日本の登録国外事業者である場合など)によっては取り扱いが異なる可能性も考えられます。念のため、プラットフォームが提供する契約条件やヘルプページを確認したり、不明な点があればプラットフォームのサポートに問い合わせたりすることをおすすめします。最終的な判断に迷う場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
企業からインボイス登録番号を聞かれた際、どこで確認できる?
適格請求書発行事業者の登録が完了すると、税務署から「登録通知書」が送付されます。この登録通知書に、あなたの「T」から始まる13桁の登録番号が記載されています。
また、国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」でも、ご自身の登録番号や登録年月日などを確認することができます。このサイトでは、取引先の事業者が適格請求書発行事業者であるかどうかも検索可能です。
企業から登録番号の提示を求められた際は、登録通知書のコピーを提示するか、この公表サイトの情報を示すとよいでしょう。
まとめ
インボイス制度は、YouTubeで収益を得るユーチューバーの皆さんにとっても、無関係ではいられない重要な税制度です。年間売上が1,000万円を超える場合や、企業との取引が多い場合は、適格請求書発行事業者への登録が求められる可能性が高まります。ご自身の状況をふまえて、「登録すべきかどうか」を冷静に判断し、必要であれば早めに申請手続きを進めておくと安心です。この記事が、あなたの活動の継続と発展につながる一助となればうれしく思います。










