簡易課税制度選択届出書の書き方|インボイス制度対応ガイド
更新日:2025.12.06
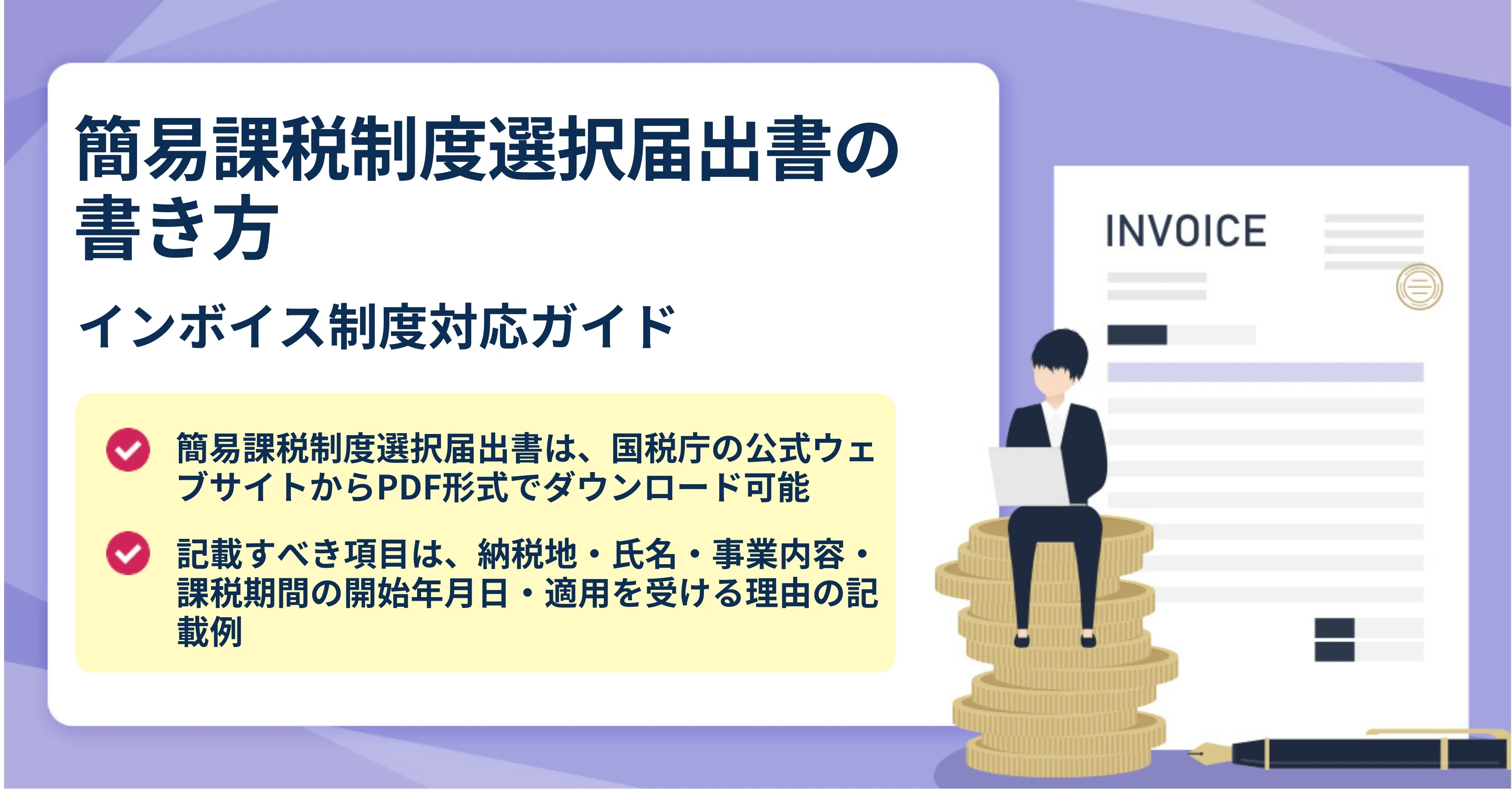
ー 目次 ー
2023年から始まったインボイス制度に対応するため、多くの事業者が「簡易課税制度選択届出書」の提出を検討しています。本記事では、簡易課税制度とインボイス制度の基本から、届出書の書き方、提出方法、必要なケース、注意点までを徹底解説。どの制度を選ぶべきか迷っている方も、この記事を読むことで自社に最適な判断ができるようになります。
簡易課税制度とインボイス制度の基本!
簡易課税制度とは何か
簡易課税制度とは、消費税の納税義務がある課税事業者が、実際の仕入税額控除の計算を簡略化するための制度です。一般課税の場合、売上に係る消費税額から仕入・経費などに含まれる消費税を差し引きますが、簡易課税制度では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って課税売上高に対する消費税の仕入控除を一律で計算する形式を採用します。
この制度は、主に中小事業者の事務負担軽減を目的としており、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下である事業者が対象です。ただし、一度選択すると最低2年間は継続適用しなければならないため、事業の将来的な売上規模や業種ごとのみなし仕入率も考慮して選択する必要があります。
業種ごとのみなし仕入率は以下の通りです。
|
業種 |
みなし仕入率 |
|
第一種事業(卸売業) |
90% |
|
第二種事業(小売業) |
80% |
|
第三種事業(製造業、建設業など) |
70% |
|
第四種事業(飲食店業など) |
60% |
|
第五種事業(サービス業など) |
50% |
|
第六種事業(不動産賃貸業など) |
40% |
このように、業種ごとに適用される割合が異なるため、自社の事業内容と経費構造を把握したうえで慎重に検討が必要です。
インボイス制度の概要と導入背景
インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、2023年10月1日から開始された新たな消費税制度です。この制度では、売手(事業者)が買手に対して「適格請求書(インボイス)」を発行し、買手がその請求書を保存することで、仕入税額控除が認められます。適格請求書を発行できるのは、税務署に登録申請をして「適格請求書発行事業者」として認められた課税事業者に限られます。
導入の背景には、課税の公平性と透明性の確保があります。従来の区分記載請求書保存方式では、仕入先が免税事業者であっても仕入税額控除が可能であったため、調整が不十分であったとされます。インボイス制度により、免税事業者との取引では仕入税額控除が適用できなくなることで、消費税の制度がより厳密となり、納税の正確性が向上することが期待されています。
この制度の開始により、特にフリーランスや小規模事業者が免税事業者から課税事業者へ転換する事例が増えており、事業運営や税務管理への対応が求められる場面が増加しています。
両制度の関係性と変更点
簡易課税制度とインボイス制度は、いずれも消費税に関する制度ですが、制度の目的や運用方法に違いがあります。インボイス制度は、仕入税額控除の根拠として「適格請求書」の保存を求める点が最も大きな特徴であり、仕入税額控除の厳格化によって、取引の相手方選定にも影響を与える可能性があります。
一方、簡易課税制度を選択している事業者も、インボイス制度の影響を受けるため、制度が重なる場面もあります。例えば、簡易課税制度を利用している課税事業者が売手側(=インボイス発行側)の場合、その事業者が適格請求書発行事業者として登録されていなければ、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引の継続が困難になる可能性もあります。
従って、簡易課税制度とインボイス制度は別の制度ながら、インボイス制度導入以降は両者の関係性を理解しておくことが非常に重要になります。特に令和5年(2023年)10月以降、免税事業者の選択による影響や、課税事業者の簡易課税制度選択との兼ね合いは、税務上の判断基準に密接に関わってくる課題となっています。
また、令和5年度税制改正では、インボイス制度の開始後3年間(2023年10月1日~2026年9月30日まで)においては、一定の条件下で経過措置が設けられており、簡易課税制度を選択している小規模事業者にとっても、制度の設計や準備の対応が求められます。
簡易課税制度選択届出書が必要なケースとは?
インボイス制度開始に伴う登録課税事業者への影響
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、免税事業者がインボイスを発行するためには、登録課税事業者となる必要があります。これまで消費税の申告・納付義務がなかった免税事業者も、インボイス発行の要請を受け、課税事業者へと移行するケースが増えています。
登録課税事業者になると、通常は「一般課税方式」によって消費税の納税額を計算しますが、「簡易課税制度」を選択することで、仕入税額控除の計算を簡素化できる可能性があります。特に、課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者にとっては、計算の手間と税負担面でメリットが大きいです。
そのため、インボイス発行を目的として課税事業者になる事業者は、「簡易課税制度選択届出書」の提出を検討すべきタイミングとなっています。
課税事業者になるタイミングと届出の必要性
簡易課税制度を適用するためには、「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。この書類の提出が必要になる主なケースは以下のとおりです。
|
ケース |
届出の必要性 |
備考 |
|
免税事業者から課税事業者に切り替える場合 |
必要 |
課税事業者選択届出書と同時提出が原則 |
|
すでに課税事業者で制度変更を検討する場合 |
必要 |
適用を受けたい課税期間開始の前日までに提出 |
|
インボイス制度開始に合わせて登録課税事業者となる場合 |
原則提出が必要 |
インボイス登録日を含む課税期間で適用したい場合は前倒し提出推奨 |
|
新設法人で課税事業者として設立時から申告する場合 |
必要 |
設立日までに提出が望ましい |
このように、課税事業者になる事情やタイミングによって、届出が必要になる場面が異なります。特に、インボイス制度の影響で課税事業者登録を行う場合、簡易課税制度を併用した方が適正な税務処理につながる可能性があり、慎重な制度選択が求められます。
また、簡易課税制度は一度選択すると2年間は変更できないという定めもあるため、一時的な売上増や業種の変更、経費計上状況なども総合的に確認しながら、届け出のタイミングを判断する必要があります。
簡易課税制度選択届出書の書き方!
書類の入手方法と提出先
簡易課税制度選択届出書は、国税庁の公式ウェブサイトからPDF形式でダウンロード可能です。また、税務署の窓口でも紙の様式を入手することができます。基本的には国税庁が定めた統一書式を使用する必要がありますので、必ず最新の様式を確認してください。
提出先は、納税地を所轄する税務署となります。法人であれば本店所在地、個人事業主であれば主たる事業所所在地の税務署が担当となります。
記載すべき項目の解説
納税地・氏名・事業内容の書き方
届出書の冒頭部分には、納税地・氏名(または法人名)・職業(または事業内容)などの基本情報を記載します。
|
項目名 |
記載内容のポイント |
|
納税地 |
個人は住居所在地、法人は本店所在地を書く。郵便番号も含めて正確に記載。 |
|
氏名・法人名 |
個人事業主は戸籍上の正式名称を、法人は登記上の名称を記載。印鑑の押印も必要。 |
|
職業・事業の内容 |
具体的な業種や業態を簡潔かつ正確に記載(例:ITコンサルティング業、不動産賃貸業など)。 |
内容に誤りがあると受理されない場合があるため、税務署に登録されている情報と整合性を取ることが重要です。
課税期間の開始年月日について
簡易課税制度の適用開始を希望する課税期間の初日を明記する必要があります。通常は「翌課税期間」からの適用となるため、届出書は原則として適用開始前の課税期間終了日までに提出しなければなりません。
例えば、2024年1月1日から簡易課税制度を適用したい場合、2023年12月31日までに提出が必要です。既に課税期間が始まっている場合、その期間には適用されない点に注意してください。
適用を受ける理由の記載例
「簡易課税制度の選択を希望する理由」の欄には、選択の背景や業種における合理性を簡潔に記載します。以下に記載例をいくつか紹介します。
|
業種 |
記載例 |
|
小売業 |
課税仕入れの管理が煩雑なため、計算の簡便化を目的として簡易課税制度を選択する。 |
|
飲食業 |
課税売上の大半が課税取引であり、仮払消費税額の記帳負担軽減を図るため。 |
|
サービス業 |
インボイス制度導入に伴う制度変更に対応し、正確な納税処理を行うため。 |
この欄の記載は形式的なものであり、制度適用の可否に大きな影響はありませんが、明確かつ合理的な理由を記載することで信頼性が向上します。
記載時の注意点とよくある誤記
簡易課税制度選択届出書を作成する際には、以下の点にも注意しましょう。
- 消費税法に基づく届出書であるため、漏れや誤記があると無効となる場合がある。
- 手書きの場合は楷書ではっきりと記載し、複写式の場合は全ての用紙が読み取れるように記載する。
- 法人の場合は代表者印、個人の場合は認印を原則押印する(e-Tax利用時は不要)。
また、原本の控えには受付印が押されるため、提出時には控え用書類を忘れずに持参・保存することが重要です。
簡易課税制度を継続・変更・取りやめる場合の手続き
制度適用の継続意志と届出書の提出
簡易課税制度の適用を継続するには、原則として毎年の届出は不要です。すでに「簡易課税制度選択届出書」を提出しており、税務署に認められている場合は、その後も継続して簡易課税制度が適用されます。
ただし、制度の適用を希望しない年や、要件に該当しなくなった場合には、適用を中止する届出が必要です。特に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により取引先から「課税仕入れ控除の適用のためには一般課税に変更してほしい」と要請されることが増えており、対応が求められる場面が多くなっています。
一般課税制度への変更手続き
簡易課税制度から一般課税制度に変更する場合、「簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。この届出書は、適用を取りやめる課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。
たとえば、令和6年(2024年)4月1日から一般課税制度に移行したい場合は、原則として令和6年3月31日までに届出が必要です。遅延すると、当該課税期間では簡易課税制度が引き続き適用され、変更は翌課税期間からとなります。
簡易課税制度選択不適用届出書の書き方と注意点
「簡易課税制度選択不適用届出書」には、以下の内容を記載します。
|
項目 |
記載内容 |
|
1. 納税地及び氏名・名称 |
納税地の所在地、法人名または個人名、代表者の氏名など |
|
2. 基準期間の課税売上高 |
1,000万円超である場合の確認 |
|
3. 簡易課税制度の取りやめ理由 |
インボイス対応、取引先からの要請、仕入税額控除を最大にしたい等 |
|
4. 不適用とする課税期間 |
変更を希望する課税期間の開始年月日 |
提出後の取り下げは原則認められないため、記載内容には最新の事業状況を反映させ、慎重を期すことが重要です。
インボイス制度改正後の対応戦略
令和5年10月に施行されたインボイス制度により、簡易課税制度を適用する事業者も、的確請求書発行事業者(いわゆるインボイス発行事業者)としての登録が可能になりました。しかし、簡易課税制度では仕入税額控除の計算方法が粗雑になるため、取引先から敬遠されるケースがあります。
特に、BtoB取引を中心に行っている中小企業やフリーランス事業者では、インボイス制度と簡易課税制度を併用するか、インボイス対応のために一般課税制度へ移行すべきか悩む場面も多くなっています。
以下のような事業者は一般課税制度への移行を検討する価値があります。
- 取引先の多くが一般課税事業者で、インボイスの発行を求められている
- 仕入れや外注費が多く、仕入控除額を最大化したい
- 複数税率に対応する複雑な取引を扱っている
一方で、個人事業主や小規模法人で、売上の大部分が一般消費者相手の場合は、簡易課税制度を継続したほうが納税計算が簡便で済む可能性もあります。
制度変更は原則として2年間の縛りがあり、一度届出を提出するとその期間中は変更ができません。将来的な税負担、記帳や請求書管理の煩雑さ、取引先との関係性などを総合的に評価し、最適な制度を選択しましょう。
各種提出書類の提出時期と提出方法について
簡易課税制度選択届出書の提出期限
簡易課税制度選択届出書は、課税期間が始まる前日までに税務署へ提出しなければなりません。通常、個人事業主であれば「翌年1月1日から適用したい場合」は、前年の12月31日までに提出が必要です。法人の場合は「事業年度開始の日の前日」までとなります。
つまり、適用開始を希望する課税期間の「開始前」が提出期限であり、「開始後」の申請は原則としてその課税期間には適用されませんので注意が必要です。
例えば、令和6年(2024年)4月1日から簡易課税制度の適用を受けたい場合、令和6年3月31日までに届出書を提出する必要があります。
e-Taxを利用した電子申請方法
「簡易課税制度選択届出書」は、紙での提出だけでなく、国税庁が提供する電子申告システム「e-Tax」からも提出可能です。電子申請は、時間・場所にとらわれず提出できる上、税務署の窓口混雑を避けられる利便性があります。
利用にあたっては、以下の準備が必要です。
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書(マイナンバーカードや商業登記電子認証など)の準備
- e-TaxソフトやWeb版e-Taxなど、申告に使う入力環境の整備
提出手順は次の通りです。
- e-Taxにログインし、「届出書等作成・送信」を選択
- 文書種類から「簡易課税制度選択届出書」を検索・選択
- 必要事項を記入し、電子署名を付けて送信
- 受付結果(受信通知)を確認し、データおよび控えを保管
e-Taxでは、提出日時が正確に記録され、証明力も担保されるため、期日直前での提出でも確実な証拠が残ります。
税務署窓口への提出と控えの保管
紙で「簡易課税制度選択届出書」を提出する場合は、納税地を所轄する税務署の窓口に持参するか、郵送で提出します。
持参する場合は、以下の点に注意しましょう。
- 届出書は2部作成(1部は控えとして返却されます)
- 税務署で「収受日付印」を押してもらう
- 控えは大切に保管し、後日の証明に備えること
郵送による提出も可能ですが、その場合は以下の手順を守ってください。
- 届出書を2部作成し、切手を貼った返信用封筒を同封
- 「簡易書留」など、配達記録が残る方法で郵送
- 控えに収受印を押したものが返送されてきたら保管
提出方法別の特徴比較表
|
提出方法 |
提出先 |
必要物 |
メリット |
注意点 |
|
e-Taxによる電子申請 |
e-Taxポータル |
電子証明書、PC環境、利用登録 |
即時提出、記録が残る、控え不要 |
事前準備が必要、操作に習熟が必要 |
|
税務署窓口に持参 |
所轄税務署 |
届出書(2部)、印鑑 |
その場で受領証がもらえる |
開庁時間内の来庁が必要 |
|
郵送提出 |
所轄税務署 |
届出書(2部)、返信用封筒 |
遠方からでも提出可能 |
到着・返送に日数がかかる |
提出方法は複数ありますが、どの方法を選ぶにせよ、控えの保管や証拠書類の整理が非常に重要です。「届出書を提出した事実」を後日求められる場合があるため、提出後も適切に保管しましょう。
専門家に相談するべきかどうかの判断ポイント
税理士への依頼が有効なケース
簡易課税制度選択届出書の作成や提出に不安がある場合、税理士に相談することは非常に有効です。特に以下のようなケースでは、専門家の支援を受けることで、制度選択のミスや申告漏れ、届出期限の遅延といったリスクを未然に防ぐことが可能です。
|
相談が有効なケース |
理由 |
|
インボイス制度と消費税の知識に不安がある |
制度変更が多く、自身のみで判断するのが困難なため、正確かつ効率的に手続きを進められる |
|
複数の事業を運営している |
業種ごとの課税売上高や仕入税額控除との関係を把握し、制度適用に影響が及ぶ可能性があるため |
|
過去に誤った申告・届出をした経験がある |
法令遵守を徹底し、ミスを繰り返さないためにも信頼できる専門家の助言が効果的 |
|
適用開始時期が迫っている |
提出期限に間に合わせるため、効率的な作成と提出をサポートしてもらえる |
上記に該当する場合は、自力での処理よりも税理士との面談を通じて正確性を担保するほうが安心です。また、顧問契約を結んでいない場合でも、スポットで相談できる税理士事務所も多数存在するため、早めのリサーチと問合せが推奨されます。
事業規模と業種による判断材料
簡易課税制度の適用が適切かどうかは、事業規模や業種によって大きく左右されます。誤って適用を選択すると、税負担が本来より重くなるケースもあるため、以下のような要素を基に慎重に判断することが求められます。
|
判断基準 |
具体的なポイント |
|
事業規模(課税売上高) |
課税売上高が5,000万円以下である必要がある。これを超えると簡易課税制度は適用不可 |
|
業種区分 |
みなし仕入率の有利不利が大きい。卸売業(90%)に比べ、サービス業(50%)は控除割合が少ない |
|
仕入や経費の割合 |
仕入税額控除と比較して、みなし仕入率のほうが不利な場合、一般課税が有利となる可能性が高い |
|
課税対象取引の構成 |
免税取引や非課税取引が多い場合、簡易課税での控除メリットが限定されるため要注意 |
たとえば、美容室、飲食業、建設業のような高額な仕入れが存在しない業種では、みなし仕入率が実態よりも高く設定されているため簡易課税が有利になりやすいです。一方で、医療機関のような非課税取引が中心の事業では、簡易課税の恩恵が得られにくため注意が必要です。
制度選択の可否が税務上の損益に直結するため、業種ごとの特性や取引内容を踏まえて、専門家のアドバイスを受けながら判断することが望まれます。
将来的な税負担を見据えた制度選択
簡易課税制度は一度選択すると、最低でも2年間の継続利用義務が発生するため、目先の税金額だけでなく、中長期的な税務戦略を踏まえた判断が求められます。以下の視点で検討し、将来的な変化に対する柔軟な対応ができるよう備えることが重要です。
- 売上高の伸び:簡易課税制度は年間課税売上高5,000万円以下が適用要件。将来、急成長が見込まれる場合は一般課税選択が適する
- 取引先の変化:インボイス制度により、取引先から課税事業者(インボイス発行事業者)を求められる可能性あり。その場合、制度選択も一因となる
- 設備投資の予定:今後大きな支出や設備投資を予定しているなら、実際の仕入税額を全額控除できる一般課税が向いている
- 法改正の動向:インボイス制度に関連する税制改正は今後も想定されるため、制度選択の柔軟性を確保する意味でも専門家の視点が役立つ
事業の規模や方針が変化すれば、課税制度の選択方針も再検討が必要になります。将来的な節税効果や資金繰りまで視野に入れておくとともに、必要に応じて税理士と継続的にコミュニケーションを取り、節目ごとに税制対応の再評価を行うことが賢明です。
簡易課税制度は一見すると申告・計算が簡易で利点が多いように見えますが、実態と合わない適用により不利益を被るケースもあるため、将来の事業戦略や今後の環境変化を見据えた専門的判断が不可欠です。
まとめ
インボイス制度の開始により、課税事業者となる場合は「簡易課税制度選択届出書」の提出が重要です。正しい書き方や提出期限を理解し、適用のメリットと注意点を把握して、業種や事業規模に合わせた制度選択を行うことが将来的な税負担の軽減につながります。迷った場合は税理士などの専門家への相談も検討しましょう。










