学校法人もインボイス対応が必要!対応すべきケースや消費税の取り扱いとは
更新日:2026.01.13
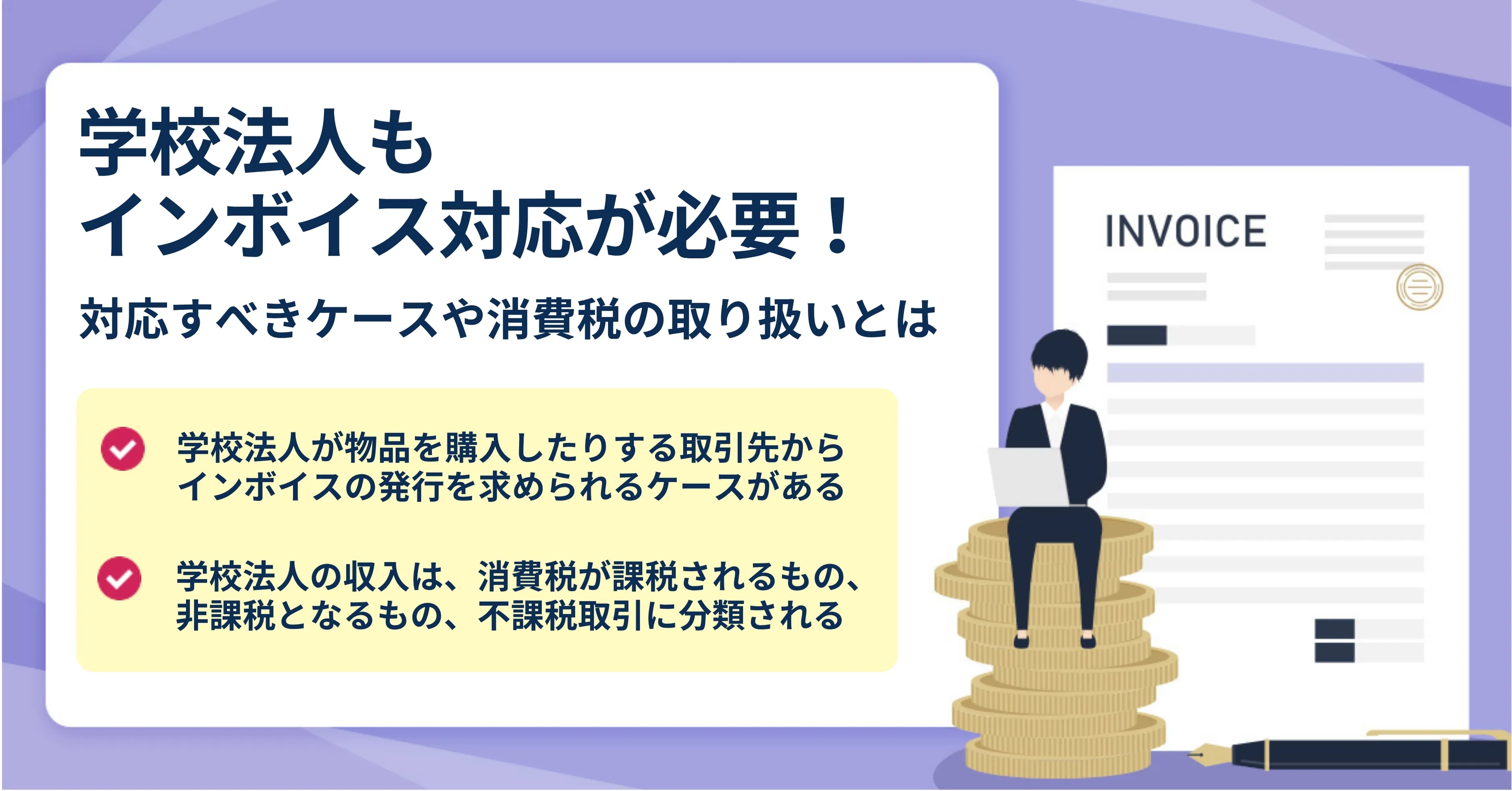
ー 目次 ー
学校法人もインボイス制度への対応が必要か、お悩みではありませんか?授業料などが非課税である一方で、取引先からインボイス発行を求められたり、課税売上が発生したりと、実は他人事ではありません。
学校法人であっても、すべての取引が非課税になるわけではありません。
課税売上がある場合や、課税仕入に対する仕入税額控除を受ける場合は、インボイス制度への対応が必要です。
具体的には、学食・売店・駐車場の運営、施設の貸出など、対価を得て行う事業活動が「課税売上」に該当します。
これらを継続して行っている場合、インボイス発行事業者への登録と適格請求書の発行が求められます。
また、仕入税額控除を確保するためにも、取引先からのインボイス取得や、帳簿・請求書の保存義務が発生します。
学校法人であっても、課税取引を行う限り、適切なインボイス対応は不可欠です。
本記事では、インボイス制度の基本から、学校法人が対応を検討すべき具体的な場面等、わかりやすく解説いたします。制度に向き合うためのヒントを、ぜひ見つけてください。
インボイス制度の基本と学校法人への影響
2023年10月1日から開始されたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除のあり方を大きく変えるものであり、多くの事業者に影響を与えています。学校法人も例外ではありません。本章では、まずインボイス制度の基本的な仕組みと、それが学校法人にどのような影響を及ぼしうるのかを解説します。
インボイス制度とは?分かりやすく解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。この制度は、複数税率(8%と10%)に対応した消費税の仕入税額控除の適正化を主な目的として導入されました。
適格請求書とは、売手が買手に対して発行する請求書や領収書等で、以下の情報が記載されたものを指します。
|
記載項目 |
内容 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
税務署から通知される「T」で始まる13桁の番号 |
|
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日 |
|
取引内容 |
軽減税率の対象品目である旨(例:※印など) |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 |
8%対象、10%対象それぞれの合計額と適用税率 |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
8%対象、10%対象それぞれの消費税額 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
取引先の名称 |
学校法人が課税事業者である取引先から物品を購入したりする場合、その取引先から適格請求書を受領し保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイス制度は学校法人の経理実務や取引関係に直接的な影響を与える可能性があるため、制度の正確な理解が不可欠です。
学校法人がインボイス対応を検討すべき具体的なケース!
本章ではどのような場合にインボイス対応が必要になるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
課税事業者である取引先からインボイスを求められる場合
学校法人が物品を購入したり、役務の提供を受けたりする取引先が課税事業者である場合、その取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められるケースが考えられます。これは、取引先が仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要となるためです。
例えば、学校が教材業者から教材を購入する場合や、清掃業者に校舎の清掃を委託する場合などが該当します。これらの取引先が、学校法人に対して「インボイスを発行してほしい」と依頼してくる可能性があります。特に、学校法人が免税事業者のままでインボイスを発行できない場合、取引先は消費税の仕入税額控除を受けられなくなるため、取引価格の見直しや、場合によっては取引の継続が難しくなることも想定されます。そのため、主要な取引先からインボイスの発行を強く求められる場合には、学校法人としてインボイス対応を検討する必要性が高まります。
学校法人が課税売上を行う場合のインボイス発行
学校法人の主な収入である授業料や入学金などは基本的に非課税ですが、以下のような課税売上が発生する場合には、インボイスの発行が必要となることがあります。
- 教科書や制服以外の物品販売(例:学校オリジナルグッズ、PTAや同窓会が運営する売店での一般消費者向け販売など)
- 学校施設の一時的な貸付(例:体育館やグラウンド、会議室などを外部の企業や団体に有料で貸し出す場合)
- 一般向けの有料セミナーや公開講座の開催(例:社会人向けの生涯学習講座、専門知識を活かした講演会など)
- 駐車場の一時利用(例:イベント開催時に外部からの来場者向けに駐車場を有料で提供する場合)
- 自動販売機の設置手数料(飲料メーカーなどから受け取る販売手数料や設置料)
これらの課税売上の取引相手が課税事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスを必要とする場合、学校法人はインボイスの発行を求められます。学校法人自身が課税事業者であればもちろん、免税事業者であっても、これらの課税取引の規模や取引先の状況によっては、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要が出てくるでしょう。
補助金や委託事業におけるインボイスの必要性
学校法人が国や地方公共団体などから受け取る補助金や助成金の多くは、特定の事業や活動を支援する目的で交付されるものであり、資産の譲渡や役務の提供の対価に該当しないため、原則として不課税取引となりインボイスの発行は不要です。
しかし、委託事業の場合は注意が必要です。国や地方公共団体、あるいは企業などからの委託を受けて学校法人が特定の事業(例:調査研究、研修プログラムの実施など)を行う場合、その委託費が「役務の提供の対価」として支払われるものであれば、課税取引に該当する可能性があります。この場合、委託元が課税事業者であり、仕入税額控除を行うためにインボイスを必要とするときは、学校法人に対してインボイスの発行を求めることがあります。
そのため、補助金や委託事業に関しては、その契約内容や性質を十分に確認し、それが課税取引に該当するかどうか、そしてインボイスの発行が必要となるケースかどうかを個別に判断することが重要です。不明な点があれば、税理士などの専門家や、補助金・委託費の交付元に確認することをおすすめします。
学校法人における消費税の取り扱いとインボイスの関係とは?
インボイス制度は消費税の仕入税額控除の仕組みに関わります。ここでは、学校法人の収入や支出における消費税の扱いや、インボイス制度がこれらにどう影響するのかを解説します。
学校法人の収入における消費税の課税・非課税の区分
学校法人の収入には、消費税が課税されるもの、非課税となるもの、そして消費税の対象外である不課税取引に分類されるものがあります。インボイス制度は主に課税取引に関連するため、これらの区分を正確に把握しておくことが重要です。
主な収入と消費税の区分の例は以下の通りです。
|
収入の種類 |
消費税の区分 |
インボイス発行の要否(原則) |
|
授業料、入学金、入園料、検定料、施設設備費(教育役務の対価として徴収するもの) |
非課税売上 |
不要 |
|
教科書・教材の販売(学校が購入し生徒に販売する場合など) |
課税売上 |
課税事業者であり、取引先(生徒等)から求められた場合は必要 |
|
学校運営の食堂・売店収入 |
課税売上 |
課税事業者であり、取引先から求められた場合は必要 |
|
不動産の貸付収入(事務所・店舗用など事業用) |
課税売上 |
課税事業者であり、取引先から求められた場合は必要 |
|
不動産の貸付収入(土地、住宅用) |
非課税売上 |
不要 |
|
寄付金収入 |
不課税取引(対価性のない収入) |
不要 |
|
国や地方公共団体からの補助金・助成金収入 |
不課税取引(対価性のない収入) |
不要 |
|
PTA会費、後援会費(任意加入で対価性がない場合) |
不課税取引 |
不要 |
※上記は一般的な例です。個別の取引がどの区分に該当するかは、契約内容や取引の実態に基づいて慎重に判断する必要があります。
学校法人における仕入税額控除とインボイス対応の経理
学校法人が事業運営のために物品を購入したり、サービスの提供を受けたりする際には、その対価に消費税が含まれている場合があります。この支払った消費税額のうち、一定の要件を満たすものについては、納付すべき消費税額から差し引くことができます。これを仕入税額控除といいます。
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)の保存が、この仕入税額控除を受けるための要件となりました。したがって、学校法人が課税仕入れ(例:事務用品の購入、施設の修繕費、外部業者への業務委託費など)を行い、仕入税額控除を受けようとする場合には、取引先から適格請求書発行事業者の登録番号などが記載されたインボイスを受領し、これを適切に保存する必要があります。
経理処理においては、受領したインボイスが適格請求書の要件を満たしているかを確認し、帳簿には取引年月日、取引内容、取引金額に加え、取引先の登録番号などを記載することが求められます。免税事業者など、インボイスを発行できない事業者からの仕入れについては、一定期間の経過措置が設けられていますが、控除できる割合が段階的に減少していく点に注意が必要です。会計システムもインボイス制度に対応したものへの更新や設定変更が求められる場合があります。
特定収入に係る仕入税額控除の特例とインボイス制度
学校法人のように、国や地方公共団体からの補助金、寄付金といった特定収入(消費税が課されない収入で、資産の譲渡等の対価に当たらないもの)の割合が高い事業者については、消費税の仕入税額控除に関して「特定収入に係る仕入税額控除の特例」という調整計算が定められています。この特例は、特定収入に対応する課税仕入れ等に係る消費税額については、仕入税額控除の対象としないように調整するものです。
インボイス制度導入後も、この特例計算の基本的な枠組みに変更はありません。しかし、この特例計算の基礎となる課税仕入れについては、他の課税仕入れと同様に、適格請求書(インボイス)の保存が原則として必要となります。つまり、インボイスに基づいて正確な課税仕入れの額を把握し、その上で特定収入割合に応じた調整計算を行うことになります。
この計算は複雑になるケースもあるため、会計処理においては、インボイスの適切な管理と正確な仕訳がより一層重要になります。必要に応じて、会計システムの設定を見直したり、税理士などの専門家のアドバイスを受けたりすることも検討しましょう。
学校法人が適格請求書発行事業者になるかの判断基準とは?
学校法人がインボイス制度に対応する上で、適格請求書発行事業者になるかどうかは経営判断に関わる重要な選択です。自校の事業規模や取引先の状況、将来の展望などを多角的に検討し、メリットとデメリットを比較衡量した上で、最適な道を選ぶ必要があります。この判断は、今後の学校運営や財務状況にも影響を与える可能性があるため、慎重な検討が求められます。
インボイス発行事業者になる学校法人のメリット
学校法人が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になることには、主に以下のようなメリットが考えられます。これらのメリットが自校にとってどれほど重要かを評価することが、判断の一つの軸となります。
まず、課税事業者である取引先との関係維持・強化が期待できます。取引先が仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書の保存が必要となるため、学校法人がインボイスを発行することで、取引先は消費税負担を軽減できます。これにより、既存の取引が継続しやすくなるだけでなく、新規の課税事業者との取引機会も広がる可能性があります。
次に、学校法人が行う課税売上の継続性が高まります。例えば、不動産賃貸収入(事業用)、駐車場収入、物品販売収入(教科書・教材以外のもの)、施設利用料(外部への有料貸出)など、消費税の課税対象となる事業を行っている場合、取引先からインボイスの発行を求められることが想定されます。
さらに、一部の補助金や国・地方公共団体からの委託事業においては、適格請求書発行事業者であることが応募条件や契約条件に含まれるケースが増えています。これらの事業への参加を検討している学校法人にとっては、インボイス発行事業者である方が有利になる場面が出てくるでしょう。
インボイス発行事業者になる学校法人のデメリット
一方で、適格請求書発行事業者になることには、いくつかのデメリットや負担増も伴います。特に、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者の学校法人にとっては、影響が大きい点を理解しておく必要があります。
最大のデメリットの一つは、免税事業者であった学校法人が課税事業者になることによる消費税の納税義務の発生です。これまで納める必要のなかった消費税を申告・納税する必要が生じるため、新たな税負担が発生し、資金繰り計画の見直しが必要になる場合があります。
また、経理業務の負担増加も避けられません。適格請求書の記載要件(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等)を満たした請求書の発行や、受け取ったインボイスが適格であるかの確認・保存、税率ごとの区分経理、消費税申告書の作成など、事務作業が複雑化し、量も増加します。これに対応するための人材育成や業務フローの見直しも必要となるでしょう。
加えて、インボイス制度に対応した請求書発行システムや会計システムの導入・改修が必要になる場合があります。これには初期費用やランニングコストが発生し、IT環境の整備が求められることもデメリットとして挙げられます。
学校法人が免税事業者のままでいる注意点
適格請求書発行事業者にはならず、免税事業者のままでいることを選択する学校法人も少なくないと考えられます。その場合に留意すべき点を以下に示します。
最も大きな注意点は、課税事業者である取引先との関係です。免税事業者からの仕入れについては、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません(ただし、制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合の控除が認められる経過措置があります)。これにより、取引先から値下げを要求されたり、インボイスを発行できる他の事業者との取引に切り替えられたりするリスクが生じます。
取引先への影響について、以下に整理します。
|
取引先の区分 |
学校法人が免税事業者の場合の影響(取引先視点) |
|
課税事業者(仕入税額控除を行っている) |
仕入税額控除が受けられないため、消費税負担が増加する可能性。取引価格の見直しや取引先の変更を検討する可能性あり。 |
|
免税事業者または一般消費者(生徒・保護者など) |
直接的な税負担の変動はないため、取引への影響は限定的。ただし、保護者が個人事業主で経費処理をする場合などは考慮が必要なケースも。 |
また、新規に課税事業者との取引を開始しようとする際に、インボイスを発行できないことが不利に働き、取引機会を逸失する可能性も考慮しなければなりません。さらに、前述の通り、補助金や委託事業の中にはインボイス発行を要件とするものがあるため、これらの活用を考えている場合は、免税事業者のままでいることが制約となる可能性があります。
学校法人においては、これらの点を総合的に勘案し、自校の教育研究活動や財務状況、そしてステークホルダーとの関係性を踏まえた上で、適格請求書発行事業者になるかどうかの判断を行うことが肝要です。
学校法人のインボイス制度への具体的な対応ステップ!
インボイス制度への対応は、学校法人にとっても重要な経営課題の一つです。ここでは、学校法人がインボイス制度へ対応するための具体的なステップを解説します。
適格請求書発行事業者の登録申請方法と流れ
学校法人が適格請求書(インボイス)を発行するためには、まず「適格請求書発行事業者」としての登録が必要です。登録申請から登録番号取得までの主な流れは以下の通りです。
登録申請書の入手と作成
適格請求書発行事業者の登録申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、所轄の税務署で入手できます。申請書には、学校法人の名称、所在地、法人番号などの基本情報に加え、登録を希望する日などを正確に記入する必要があります。
e-Taxによるオンライン申請または郵送による申請
作成した登録申請書は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで提出する方法と、管轄のインボイス登録センターへ郵送で提出する方法があります。e-Taxを利用すると、手続きが比較的スムーズに進められます。
登録通知書の受領と登録番号の確認
申請後、税務署による審査が行われ、問題がなければ登録通知書が送付されます。この通知書には、適格請求書発行事業者としての登録番号が記載されています。この登録番号は、今後発行する適格請求書に記載する必要があるため、大切に保管・管理してください。
請求書フォーマットの変更と会計システムのインボイス対応
適格請求書発行事業者の登録が完了したら、次に請求書のフォーマット変更や会計システムの対応が必要になります。これらは日々の経理業務に直結するため、計画的に進めましょう。
適格請求書の記載事項の確認とフォーマット修正
適格請求書には、従来の請求書に加えて以下の情報を記載する必要があります。現行の請求書フォーマットを見直し、必要な項目を追加・修正してください。
取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分した合計対価の額なども引き続き記載が必要です。
必要に応じたシステム改修や新規導入の検討
既存の会計システムがインボイス制度に対応できない場合や、より効率的な経理処理を目指す場合には、システムの改修やインボイス制度に対応した新しい会計ソフトの導入を検討することも有効です。特に、受領インボイスのデータ保存や仕入税額控除の計算など、制度対応で業務負荷が増える部分の効率化が期待できます。
学校法人内の経理体制の見直しとインボイス周知
インボイス制度への対応は、経理担当者だけでなく、学校法人全体の協力体制が不可欠です。制度の理解を深め、円滑な運用ができるよう、内部体制の整備と周知徹底を図りましょう。
インボイス制度に関する研修の実施
経理担当者はもちろんのこと、請求書の発行や受領に関わる可能性のある教職員に対しても、インボイス制度の概要、学校法人としての対応方針、具体的な業務フローの変更点などを説明する研修会を実施することが望ましいです。これにより、制度への理解不足によるミスを防ぎ、組織全体でのスムーズな対応を促進します。
経理規程や業務フローの見直しと整備
インボイス制度の導入に伴い、適格請求書の受領・発行ルール、保存方法、仕入税額控除の計算方法など、経理規程や関連する業務フローの見直しが必要になります。変更点を明確にし、マニュアル化することで、担当者が変わっても適切に業務を引き継げる体制を整えましょう。
取引先へのインボイス制度対応に関する連絡と協力依頼
学校法人が適格請求書発行事業者になった場合、その旨を取引先(特に課税事業者)に通知することが重要です。また、仕入れや業務委託を行う際には、取引先から適格請求書を確実に受領できるよう、事前に制度対応状況を確認し、必要に応じて協力を依頼しましょう。これにより、仕入税額控除を適切に受けるための準備が整います。
まとめ
インボイス制度は、収入の多くが非課税である学校法人にとっても、取引先との関係や経理処理において重要な変更点となります。特に、課税売上の発生や、取引先のニーズによっては、制度対応が避けられない場面も出てきます。自校の実情に合わせて、適格請求書発行事業者となるかどうかを慎重に検討し、必要な準備を早めに整えておくことが大切です。ご不安な点は、税理士などの専門家と相談しながら、確実に対応を進めていきましょう。










