結局インボイス対応はどうすればいい?登録の判断基準や申請方法をわかりやすく解説
更新日:2026.01.29
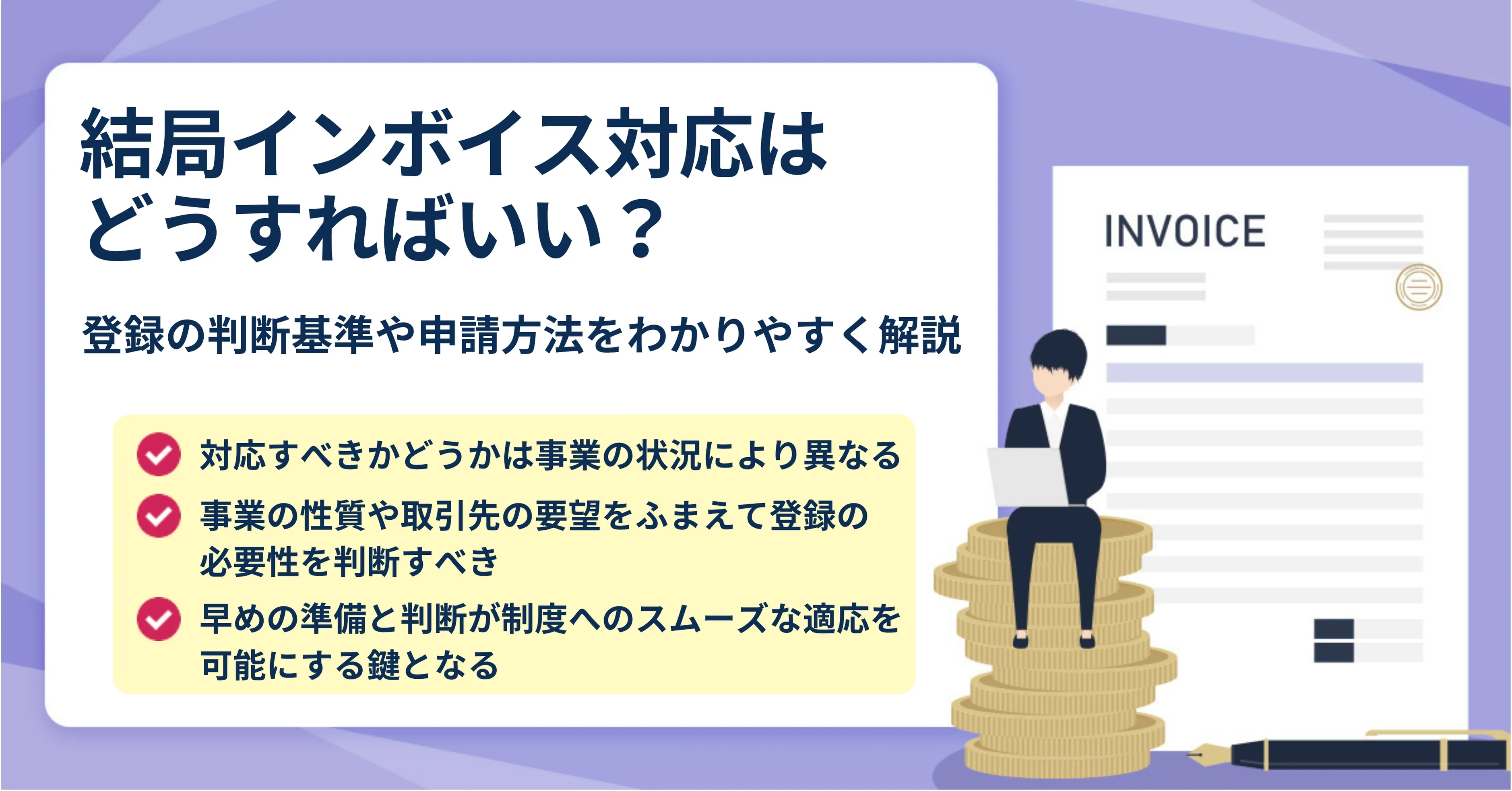
ー 目次 ー
「インボイス制度、結局どうすればいいの?」とお困りではありませんか。この記事を読めば、制度の基本から、個人事業主や免税事業者、課税事業者など立場別の具体的な対応策、登録の判断基準、そして申請方法までスッキリわかります。複雑なインボイス対応も、この記事であなたが取るべき行動が明確になります。
インボイス制度の基本を解説!
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をどうすれば良いのか、まだよくわからないという方も多いのではないでしょうか。この章では、まずインボイス制度の基本的な仕組みや導入された背景について、わかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?簡単に解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。この制度の下では、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを記載した「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がこれを保存することが求められます。
適格請求書には、従来の請求書に記載されていた項目に加え、以下の情報が必要となります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率(標準税率10%、軽減税率8%)
- 税率ごとに区分した消費税額等
この適格請求書を発行できるのは、事前に税務署に申請し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。買手側は、仕入れにかかった消費税額を売上にかかる消費税額から差し引く「仕入税額控除」の適用を受けるために、原則としてこの適格請求書の保存が必要になります。つまり、適格請求書がなければ、仕入税額控除が受けられず、結果として納付する消費税額が増加する可能性があるのです。
インボイス制度が導入された背景と目的
インボイス制度が導入された主な背景には、2019年10月の消費税率引き上げ時に導入された軽減税率制度(標準税率10%と軽減税率8%の複数税率)の存在があります。これにより、商品やサービスによって異なる税率が適用されることになり、事業者の経理処理が複雑化しました。インボイス制度は、このような状況を踏まえ、以下の背景と目的のもとに導入されました。
|
区分 |
内容 |
|
導入の背景 |
|
|
導入の目的 |
|
インボイス制度は、消費税の仕組みをより公平かつ正確なものにするために導入された制度であり、多くの事業者にとって対応が必要となる重要な変更点です。
立場別に解説|インボイス対応はどうすればいい?
インボイス制度への対応は、事業者の立場によって異なります。ここでは、それぞれの立場別に、具体的に何をすべきか、どのような点に注意すべきかを解説します。
個人事業主の場合|インボイス対応でまず考えるべきこと
個人事業主の方がインボイス制度に対応するにあたり、まず検討すべきは「適格請求書発行事業者」に登録するかどうかです。この判断は、ご自身の事業内容や取引先の状況によって大きく変わります。
主な判断材料としては、以下の点が挙げられます。
- 取引先に課税事業者が多いか(インボイスの発行を求められる可能性が高いか)
- 現在の売上規模と今後の事業拡大の見込み
- インボイス発行に伴う事務作業の負担を許容できるか
これらの要素を総合的に考慮し、登録の要否を判断する必要があります。特に、課税事業者である得意先との取引が多い場合は、インボイスを発行できないと取引継続が難しくなるケースも考えられます。
副業・兼業の個人事業主|低リスクだが将来見据えた判断も
副業や兼業で個人事業を営んでいる方は、本業の収入があるため、インボイス制度による事業への影響が比較的少ない場合があります。例えば、主な取引先が一般消費者や免税事業者である場合は、インボイスの発行を求められるケースは少ないでしょう。
しかし、副業であっても取引先が課税事業者であり、インボイスの発行を求められる場合には対応が必要です。また、将来的に副業を本業にしたり、事業規模を拡大したりする計画がある場合は、長期的な視点での判断も重要になります。現時点での影響が小さくても、今後の事業展開を見据えて、適格請求書発行事業者の登録を検討する余地があります。
免税事業者のままでいるとどうなる?知らないと困るインボイスの影響とは
適格請求書発行事業者に登録せず、免税事業者のままでいることを選択した場合、どのような影響があるのでしょうか。主なメリットとデメリット、そして注意点を理解しておくことが重要です。
|
項目 |
内容 |
|
メリット |
消費税の納税義務が引き続き免除されます。インボイス発行のためのシステム対応や、請求書の様式変更、消費税申告といった事務負担も発生しません。 |
|
デメリット |
課税事業者である取引先は、あなたからの仕入れについて仕入税額控除を受けられなくなります(一定期間の経過措置あり)。これにより、取引先から消費税相当額の値引きを要求されたり、インボイスを発行できる他の事業者との取引に切り替えられたりする可能性があります。 |
特に、企業間取引(BtoB)が中心で、取引先が課税事業者である場合には、このデメリットが顕著に現れる可能性があります。一方で、顧客が一般消費者(BtoC)や免税事業者のみである場合は、インボイスの発行を求められることがないため、免税事業者のままでいることによる影響は限定的と考えられます。
すでに課税事業者の人はどう動く?インボイス対応で見直したい3つのポイント
すでに消費税の課税事業者である方は、原則として適格請求書発行事業者の登録を行い、インボイス(適格請求書)を発行できるように準備を進める必要があります。対応にあたり、特に見直したいポイントは以下の3つです。
- 適格請求書の発行準備
請求書に記載が必要な項目(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額など)が追加されます。現在使用している請求書発行システムや会計ソフトがインボイス制度に対応しているか確認し、必要に応じてアップデートや入れ替えを検討しましょう。手書きやExcelで請求書を作成している場合は、記載事項を満たしたフォーマットに変更する必要があります。 - 受領する請求書の確認体制
仕入税額控除を受けるためには、原則として取引先から交付された適格請求書の保存が必要です。受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているか、記載された登録番号が有効なものかなどを確認する業務フローを整備しましょう。また、仕入先が免税事業者の場合、仕入税額控除が受けられない(経過措置あり)ため、経理処理にも注意が必要です。 - 経理処理・消費税申告の変更点把握
インボイス制度導入に伴い、消費税の計算方法や申告手続きにも変更が生じます。適用税率ごとに区分した経理処理や、仕入税額控除の対象となる取引の正確な把握がより一層重要になります。
これらのポイントを踏まえ、スムーズな制度移行ができるよう準備を進めていくことが大切です。
インボイス登録の判断基準!迷った場合に確認すべきポイントとは
ここでは、インボイス登録の必要性を判断するための基準や、迷った場合に確認すべきポイントを売手側・買手側それぞれの立場から解説します。
自分はインボイス登録は必要?チェックリストで確認
インボイス登録が必要かどうかは、ご自身の事業内容や取引先の状況によって異なります。まずは以下のチェックリストで、ご自身の状況を客観的に把握してみましょう。
|
確認項目 |
はい |
いいえ |
不明 |
|
主な取引先(売上上位)は法人または課税事業者ですか? |
|||
|
取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められていますか、または求められる可能性が高いですか? |
|||
|
あなたの事業の年間課税売上高は1,000万円を超えていますか?(または、近いうちに超える見込みがありますか?) |
|||
|
今後、新規で課税事業者との取引拡大を目指していますか? |
|||
|
インボイスを発行できない場合、取引の継続が難しくなったり、価格交渉で不利になったりする可能性を許容できますか? |
|||
|
提供している商品やサービスは、主に事業者向け(BtoB)ですか? |
このチェックリストで「はい」が多いほど、インボイス登録の必要性が高いと考えられます。特に、取引先との関係性や意向は、登録判断において非常に重要な要素となります。
売手側(受注側)のインボイス登録判断 どうすればいいか
売手側(受注側)の事業者がインボイス登録を判断する際には、以下のポイントを総合的に考慮することが重要です。
取引先の状況と意向の確認
最も重要なのは、主要な取引先が課税事業者であり、仕入税額控除のためにインボイスを必要としているかどうかです。取引先にインボイス発行の可否を尋ねられたり、今後の取引条件としてインボイス発行を求められたりする可能性があります。取引を継続・拡大するためには、取引先のニーズに応える形でインボイス登録を検討する必要が出てくるでしょう。
自身の事業規模と将来性
現在の年間課税売上高が1,000万円以下で免税事業者の場合でも、将来的に事業を拡大し、売上が1,000万円を超える見込みがある場合は、いずれ課税事業者となり消費税の申告・納付が必要になります。そのタイミングを見越して、インボイス登録を検討するのも一つの考え方です。
提供する商品・サービスと顧客層
顧客が一般消費者(BtoC)中心であれば、インボイスの発行を求められるケースは限定的です。しかし、事業者向け(BtoB)の取引が多い場合は、買手側が仕入税額控除を行うためにインボイスを必要とするため、登録の重要性が高まります。
競合他社の動向
同業他社がインボイス登録を進めている場合、自社が登録しないことで競争上不利になる可能性も考慮に入れる必要があります。特に価格やサービス内容で大きな差がない場合、インボイスを発行できるかどうかが取引先選定の一つの基準になることも考えられます。
事務負担の増加とコスト
インボイス登録を行うと、適格請求書の発行や保存、消費税の計算・申告といった経理事務の負担が増加します。会計ソフトの導入や税理士への依頼など、新たなコストが発生する可能性も踏まえて判断しましょう。ただし、これらの負担を軽減するための支援措置も存在します。
買手側(発注側)のインボイス対応 どうすればいいか
買手側(発注側)の事業者は、仕入税額控除を適切に行うために、インボイス制度への対応が求められます。以下のポイントを確認し、準備を進めましょう。
取引先のインボイス登録状況の確認
仕入れや経費の支払い先である取引先が、適格請求書発行事業者として登録されているかを確認する必要があります。登録状況は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、取引先の登録番号や法人番号、氏名または名称を入力することで確認できます。取引開始時や継続的な取引がある場合には、定期的な確認が推奨されます。
受け取る請求書の記載要件チェック
取引先から受け取る請求書が、インボイス(適格請求書)としての要件を満たしているかを確認することが不可欠です。具体的には、発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などが正確に記載されているかを確認します。不備がある場合は、仕入税額控除が認められない可能性があるため、取引先に修正を依頼する必要があります。
仕入税額控除の適用と帳簿・請求書の保存
要件を満たしたインボイスを適切に保存し、帳簿にも必要事項を記載することで、仕入税額控除を受けることができます。インボイスの保存期間は、原則としてその課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。電子データで受領した場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。
免税事業者や登録のない事業者からの仕入れの取り扱い
仕入先が免税事業者である場合や、適格請求書発行事業者として登録していない課税事業者である場合、原則としてその取引にかかる消費税額について仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。この経過措置の内容と適用期間を正しく理解しておくことが重要です。
経理システム・業務フローの見直し
インボイス制度の導入に伴い、経理システムや会計ソフトが制度に対応しているかを確認し、必要に応じてアップデートや新規導入を検討しましょう。また、請求書の受領から確認、保存、会計処理に至るまでの業務フローを見直し、制度に適合した体制を整えることが求められます。
インボイス登録申請の手順をやさしく解説|初めてでも迷わない進め方
インボイス制度への登録を決めたものの、具体的な申請方法が分からずお困りではないでしょうか。適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に対して登録申請手続きを行う必要があります。この章では、インボイス登録申請の準備から実際の申請方法、そして登録番号が通知されるまでの期間について、初めての方でもスムーズに進められるよう、ステップごとにわかりやすく解説します。
インボイス申請前に準備するもの
インボイス登録申請をスムーズに進めるためには、事前に必要なものを準備しておくことが大切です。申請方法によって準備するものが異なりますので、以下の表で確認しましょう。
|
申請方法 |
主な準備物 |
補足 |
|
e-Taxによる電子申請 |
|
利用者識別番号がない場合は、事前にe-Taxの開始届出書を提出して取得する必要があります。 |
|
書面による郵送申請 |
|
登録申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。プリンターがない場合は、税務署で入手することも可能です。 |
特にe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、マイナポータルアプリに対応したスマートフォンが必要になりますので、事前に環境を整えておきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請手続き
インボイスの登録申請手続きは、主に「e-Taxによる電子申請」と「書面による郵送申請」の2つの方法があります。それぞれの申請方法について、具体的な手順を見ていきましょう。
e-Taxによる電子申請の方法
e-Taxを利用した電子申請は、自宅やオフィスから24時間いつでも手続きが可能で、書類の郵送にかかる手間や時間を削減できるメリットがあります。また、処理状況をオンラインで確認できる点も便利です。
主な手順は以下の通りです。
- e-Taxソフト(WEB版・SP版)または確定申告書等作成コーナーへアクセス
国税庁のウェブサイトから、ご自身の環境に合った方法でアクセスします。スマートフォンからはe-Taxソフト(SP版)が便利です。 - ログインと申請手続きの選択
マイナンバーカード等でログイン後、申請・届出メニューの中から「適格請求書発行事業者の登録申請」に関連する項目を選択します。 - 必要事項の入力
画面の案内に従って、納税地や事業者情報、登録希望日などの必要事項を正確に入力します。課税事業者の方は、課税事業者となった年月日なども入力します。 - 電子署名と送信
入力内容を確認後、マイナンバーカード等を用いて電子署名を行い、データを送信します。送信後には受付結果(受信通知)がメッセージボックスに格納されるので確認しましょう。
e-Taxの操作に不安がある場合は、国税庁のウェブサイトに掲載されているマニュアルや、税務署の窓口で相談することも可能です。
書面による郵送申請の方法
パソコン操作が苦手な方や、紙で手続きを進めたい場合は、書面による郵送申請が適しています。国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して管轄のインボイス登録センターへ郵送します。
主な手順は以下の通りです。
- 登録申請書の入手と記入
国税庁のウェブサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」(PDF形式)をダウンロードし、印刷します。A4サイズで印刷してください。その後、申請書に必要事項をボールペン等で正確に記入します。個人事業主の場合は氏名、住所、マイナンバー(個人番号)または法人番号(法人の場合)などを記載します。 - 添付書類の準備(必要な場合)
申請内容によっては、本人確認書類の写しなどが必要になる場合があります。国税庁の案内を確認し、必要な書類を準備しましょう。 - 管轄のインボイス登録センターへ郵送
記入済みの申請書と必要な添付書類を同封し、ご自身の納税地を管轄するインボイス登録センターへ郵送します。郵送先は国税庁のウェブサイトで確認できます。簡易書留など、送達記録が残る方法で郵送すると安心です。
申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードするほか、税務署の窓口でも入手可能です。記入方法が分からない場合は、国税庁の記載例を参照するか、税務署に問い合わせましょう。
インボイス登録番号はいつ届く?通知までの期間
インボイス登録申請書を提出してから、登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)が通知されるまでの期間は、申請方法や申請時期によって異なります。国税庁からはおおよその目安期間が公表されていますが、申請が集中する時期などは通常より時間がかかる場合があります。
一般的に、e-Taxによる電子申請の方が、書面による郵送申請よりも早く処理される傾向にあります。
|
申請方法 |
登録通知までの目安期間(国税庁公表参考) |
|
e-Taxによる電子申請 |
約1ヶ月半~2ヶ月程度 |
|
書面による郵送申請 |
約2ヶ月半~3ヶ月程度 |
上記の期間はあくまで目安であり、申請件数の状況や書類に不備があった場合などには、さらに時間がかかることもあります。登録が完了すると、登録番号が記載された「登録通知書」が郵送(e-Tax申請の場合も書面で通知)されます。また、e-Taxで申請した場合は、審査完了後にメッセージボックスにも通知が届く場合があります。
登録番号の通知を受けたら、大切に保管し、請求書や領収書への記載準備を進めましょう。なお、登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でも確認できるようになります。
まとめ
インボイス制度への対応は、ご自身の事業規模や取引先の状況によって「どうすればいいか」の結論が異なります。本記事で解説した、個人事業主や免税事業者といった立場別の対応、登録の判断基準、申請手順を参考にご自身の状況に最適な選択をしてください。適格請求書発行事業者への登録は、売上や取引関係への影響を考慮し、必要性を慎重に見極めることが重要です。本記事でご紹介した内容が、ご自身の今後の方針を考えるうえでのヒントになれば幸いです。










