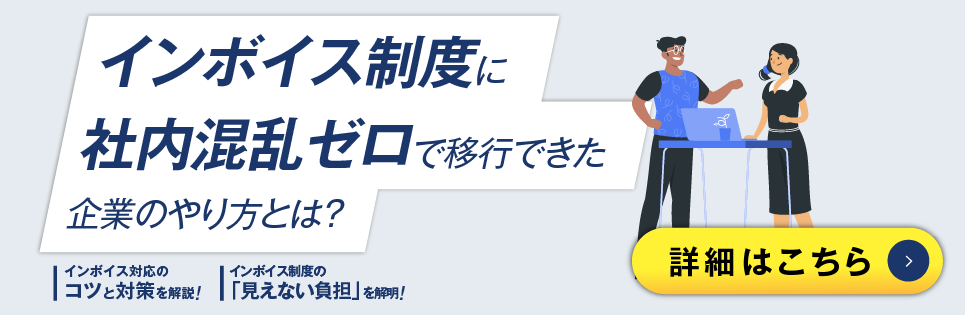インボイス制度の軽減措置とは?対象者・期間・申請方法をわかりやすく解説!
更新日:2026.01.29
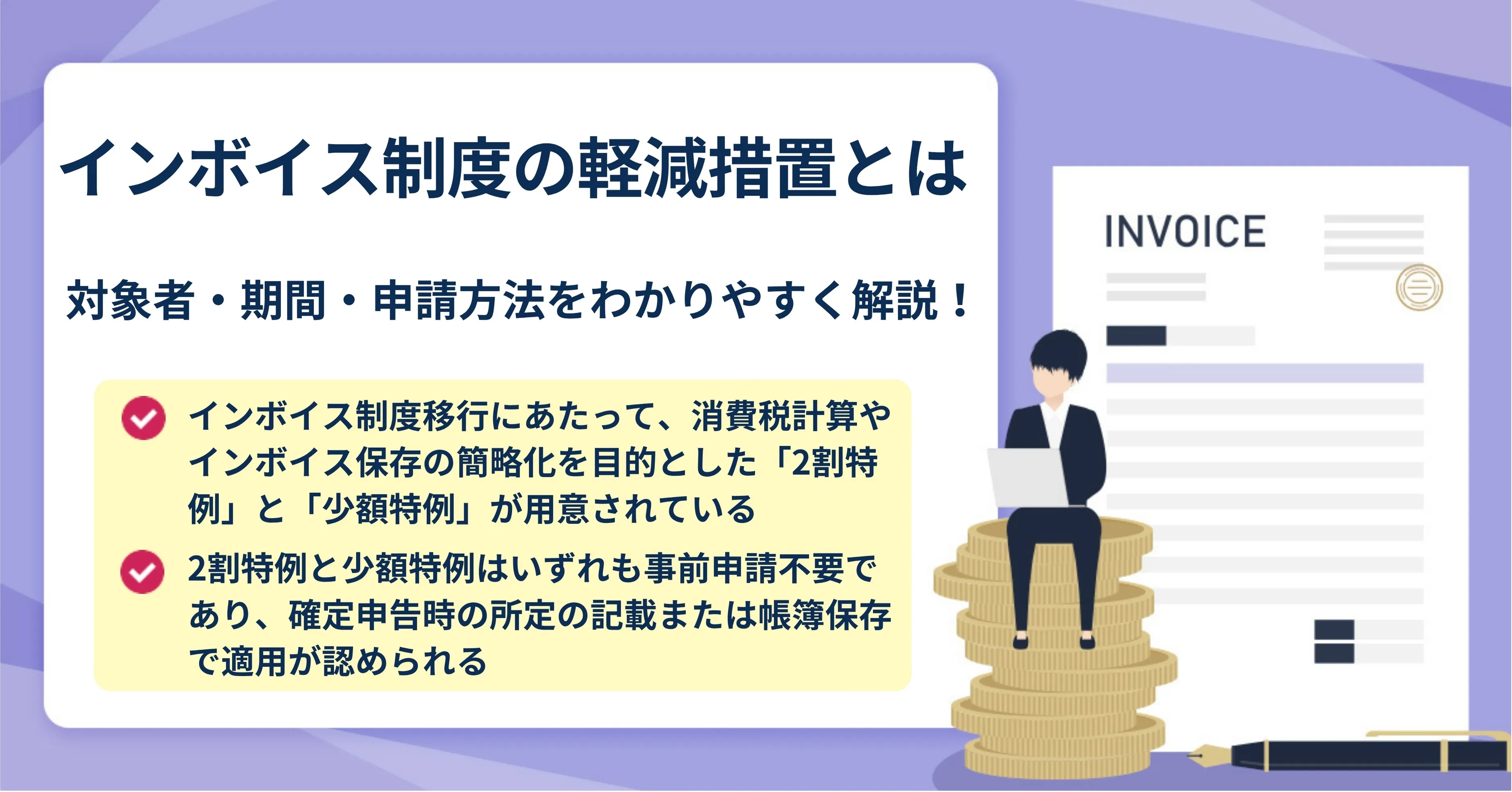
ー 目次 ー
インボイス制度導入による急激な負担増を避けるため、期間限定の軽減措置が用意されています。この記事を読めば、主に免税事業者からインボイス発行事業者になった方向けの「2割特例」や、事務負2023年10月1日からスタートした担を軽くする「少額特例」など、ご自身が使える軽減措置の種類、対象者、期間、申請の要否が明確に分かります。
インボイス制度の軽減措置とは 基本を解説!
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の仕組みに関わる大きな変更点です。この制度変更に伴い、事業者の負担を和らげるために様々な「軽減措置」が設けられています。この章では、まずインボイス制度の基本的な内容と、なぜ軽減措置が必要とされたのか、その目的について解説します。
インボイス制度の基本と軽減措置の目的
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額等を正確に伝えるための「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がこれを保存することで、買い手は消費税の仕入税額控除を受けることができるようになります。
インボイス制度のポイントを以下にまとめます。
|
項目 |
インボイス制度導入前 |
インボイス制度導入後 |
|
仕入税額控除の要件 |
区分記載請求書等と帳簿の保存 |
適格請求書(インボイス)と帳簿の保存(原則) |
|
請求書発行者 |
制限なし |
適格請求書発行事業者(登録を受けた課税事業者) |
|
免税事業者からの仕入れ |
一定の要件下で仕入税額控除が可能 |
原則として仕入税額控除が不可(経過措置あり) |
この制度変更により、特にこれまで消費税の納税が免除されていた免税事業者や、免税事業者と取引のある課税事業者にとっては、経理処理の変更や税負担の増加といった影響が生じる可能性があります。インボイス制度の軽減措置は、こうした制度移行期における事業者の負担を緩和し、制度への円滑な移行をサポートすることを主な目的としています。具体的には、小規模事業者の納税額の負担軽減や、事務負担の軽減などが図られています。
なぜインボイスに軽減措置が導入されたのか
インボイス制度の導入は、消費税の仕入税額控除の適正化を図る上で重要な制度ですが、その一方で、多くの事業者、とりわけ小規模事業者や個人事業主、そしてこれまで免税事業者であった方々にとっては、大きな変化を伴うものでした。
具体的には、以下のような懸念点が指摘されていました。
- 免税事業者が適格請求書発行事業者にならない場合、取引先である課税事業者が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引が見直される(値引き交渉や取引停止など)リスクがあること。
- 免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには課税事業者への転換が必要となり、消費税の納税義務が生じることによる税負担の増加。
- インボイスの発行や保存、経理処理の複雑化による事務負担の増加。
これらの懸念は、特に体力的に余裕のない小規模事業者にとって死活問題になりかねません。そこで、制度導入による急激な変化を避け、事業者が新しい制度に段階的に対応できるよう、準備期間を設けたり、負担を直接的に軽減したりするための措置として、インボイス制度の軽減措置が導入されることになりました。これにより、事業者が制度の趣旨を理解し、適切な対応を進めるための時間的猶予と支援を提供することが意図されています。
インボイスの軽減措置ってどんな内容?知っておきたい種類を解説
インボイス制度の導入に伴い、事業者の負担を軽減するためのいくつかの特例措置が設けられています。これらの措置を理解し活用することで、制度移行に伴う影響を和らげることができます。ここでは、特に重要な「2割特例」と「少額特例」について、その内容を詳しく解説します。
2割特例とは?インボイス発行事業者への負担軽減
2割特例は、インボイス制度の開始を機に免税事業者からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になった事業者を対象とした、消費税の納税額に関する特例措置です。具体的には、売上にかかる消費税額の2割を納税額とすることができるため、仕入れにかかる消費税額を個別に計算・積算する必要がなくなり、事務負担の大幅な軽減と納税額の負担軽減が期待できます。
2割特例の対象となる事業者
2割特例の適用を受けることができるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。
- インボイス制度が開始された2023年10月1日以降に、免税事業者からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録を受けた、または受ける事業者
- 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であるなど、本来免税事業者の要件を満たしていた事業者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、2割特例の対象外となりますので注意が必要です。
- 消費税の課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮する特例の適用を受けている課税期間
- 資本金1,000万円以上の新設法人(設立から2年間など)
- 調整対象固定資産や高額特定資産(棚卸資産を除く)を取得して仕入税額控除を行ったことにより、事業者免税点制度の適用を受けられない期間中の事業者
- インボイス発行事業者の登録とは関係なく、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるなど、元々課税事業者となる事業者
2割特例の適用期間はいつまで?
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間です。この期間内に開始する課税期間が対象となります。
|
区分 |
適用対象となる申告期間の例 |
|
個人事業者 |
2023年10月1日~12月31日分を含む2023年分の確定申告から、2026年分の確定申告まで |
|
法人(3月決算の場合) |
2023年10月1日~2024年3月31日の課税期間を含む事業年度の申告から、2026年4月1日~2027年3月31日の課税期間のうち2026年9月30日までを含む期間の申告まで |
この期間を過ぎると2割特例は利用できなくなるため、その後の消費税計算方法については別途検討が必要です。
2割特例の計算方法
2割特例を適用した場合の消費税の納税額は、非常にシンプルな計算式で算出できます。
納税額 = 売上税額(課税標準額に対する消費税額) × 20%
例えば、課税売上が500万円(税抜)で、適用税率が10%の場合、売上税額は50万円となります。この場合、2割特例による納税額は50万円 × 20% = 10万円です。この計算方法は業種を問わず一律であり、簡易課税制度のように事業区分を考慮する必要はありません。
少額特例とは?一定規模以下の事業者の事務負担軽減
少額特例(正式名称:一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)は、特定の条件を満たす事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(適格請求書)の保存がなくとも、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例です。これにより、少額の経費精算などが多い事業者のインボイス保存・管理にかかる事務負担を軽減することを目的としています。
少額特例の対象事業者とは
少額特例の適用対象となる事業者は、以下のいずれかの条件を満たす事業者です。
- 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
- 特定期間(個人事業者の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者
上記のいずれかを満たせば、インボイス発行事業者であるか否かを問わず、この特例を利用できます。
少額特例の適用期間はいつまで?
少額特例を適用できるのは、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行われる課税仕入れです。この期間内に行われた税込1万円未満の取引が対象となります。
少額特例の実務上のポイント
少額特例を適切に活用するためには、以下の実務上のポイントを理解しておくことが重要です。
- 対象取引の判定:税込1万円未満であるかの判定は、1回の取引の合計額ではなく、個々の商品やサービスの税込金額で行います。例えば、税込9,000円の商品と税込8,000円の商品を同時に購入し合計17,000円となった場合でも、それぞれの金額が1万円未満であれば、両方とも少額特例の対象となり得ます。
- 帳簿への記載:仕入税額控除を受けるためには、帳簿に通常の記載事項(取引の相手方の氏名または名称、取引年月日、取引内容、支払対価の額)を記載する必要があります。国税庁は、帳簿の摘要欄などに「少額特例」や「(特例)」といった記載を推奨していますが、必須ではありません。
- インボイスの受領義務:この特例はインボイスの「保存」を不要とするものであり、インボイスの「交付」を受ける義務が免除されるわけではありません。ただし、現実的には交付されなかった場合でも、帳簿への記載があれば控除が可能です。
- 対象外の取引:税込1万円以上の取引については、原則通りインボイスの保存が必要です。
` タグを2~3つに分けて整形し、1つの見出し内で読みやすい構造にしました。 文意やSEO効果を損なわず、可読性・専門性も保っています。
インボイス制度の経過措置「80%控除」とは?
80%控除のしくみとは?仕入税額控除が"段階的に減る"理由
インボイス制度が導入されると、原則としてインボイス(適格請求書)がない取引については仕入税額控除ができなくなります。 しかし制度の急激な変化による影響を緩和する目的で、免税事業者からの仕入れにも一定割合の控除を認める「経過措置」が設けられました。
この措置が「80%控除」です。 2023年10月〜2026年9月までの3年間、免税事業者(インボイス未登録者)との取引にかかる消費税について、本来の仕入税額控除の80%までを認めるという内容です。
控除率は段階的に引き下げられ、2026年10月〜2029年9月は50%、そして2029年10月以降には経過措置自体が廃止されます。 「いつまでも控除できるわけではない」点を踏まえ、取引先の登録状況や仕入れ戦略の見直しが求められます。
80%控除を利用できる事業者の条件
80%控除を利用できるのは、インボイス制度に基づいて消費税の課税事業者となっている「買い手側」の事業者です。 つまり、売り手(仕入先)が免税事業者であっても、自らが課税事業者であればこの特例を利用することが可能です。
利用にあたっては以下の条件を満たす必要があります。 1つ目は「帳簿」と「請求書(インボイスでなくても可)」の保存。 2つ目は、仕入れ内容が課税対象であり、かつ事業用であること。 3つ目は、仕入れ先が免税事業者であると明確にわかることです。
この特例は一時的なものであり、将来的に控除が完全にできなくなるタイミングを見越した対応が不可欠です。 免税事業者との継続的な取引にリスクが生じる可能性があるため、今のうちから取引先のインボイス登録状況の確認や、自社方針の再検討が必要です。
インボイス制度の軽減措置を受けるための申請手続き!
インボイス制度の導入に伴い、事業者の負担を和らげるためのいくつかの軽減措置が設けられています。これらの措置を適切に活用するためには、どのような申請手続きが必要になるのか、あるいは不要なのかを正確に把握しておくことが肝心です。ここでは、特に利用者の多い「2割特例」と「少額特例」について、それぞれの申請手続きの有無や方法を具体的に解説します。
2割特例の適用に申請は必要か
免税事業者からインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になった事業者を対象とした「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」については、原則として事前の申請手続きは不要です。
この特例の適用を受けるためには、消費税の確定申告を行う際に、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで足ります。具体的には、消費税の申告書様式の所定の箇所にチェックを入れるなどして意思表示を行います。適用対象となる事業者は、確定申告の際に忘れずにこの手続きを行うようにしましょう。
少額特例の適用に申請は必要か
基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められる「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)」についても、事前の申請手続きは不要です。
この少額特例は、適用対象となる事業者が、法律で定められた事項を記載した帳簿を適切に保存していれば、自動的に適用を受けることができます。したがって、税務署への届出や申請といった特別なアクションは必要ありません。日々の経理業務において、要件を満たした帳簿作成と保存を確実に行うことが、この特例を活用する上でのポイントとなります。インボイスの保存が免除されることで事務負担は軽減されますが、帳簿への正確な記録と管理が求められる点には注意が必要です。
これらの軽減措置に関する申請手続きの要点をまとめると、以下の表のようになります。
|
軽減措置の名称 |
事前の申請手続きの要否 |
適用を受けるための主な対応 |
|
2割特例 |
不要 |
消費税の確定申告書に適用を受ける旨を記載(付記)して申告する |
|
少額特例 |
不要 |
一定の事項を記載した帳簿を保存する |
このように、インボイス制度における主要な軽減措置である2割特例および少額特例は、いずれも適用を受けるための事前の申請手続きが不要とされています。ただし、それぞれの特例には適用対象者や適用期間、満たすべき要件が定められているため、自社が該当するかどうかを事前に確認し、確定申告時の対応や帳簿の記載・保存を正しく行うことが、これらの軽減措置を有効に活用するための鍵となります。
インボイス軽減措置を利用する上での重要ポイント
インボイス制度の導入に伴い、事業者の負担を軽減するための様々な措置が設けられています。これらの軽減措置を効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。本章では、軽減措置を利用する上での注意点や、確定申告時の処理について解説します。
複数のインボイス軽減措置は併用可能か
インボイス制度には、主に「2割特例」と「少額特例」という負担軽減措置があります。これらの措置を併用できるか否かは、多くの事業者が関心を持つ点です。結論から言えば、条件を満たせば両方の特例の対象となり得ますが、消費税の申告計算における適用関係を理解しておくことが重要です。
具体的には以下のようになります。
|
軽減措置 |
対象となり得る事業者 |
併用に関する考え方 |
|
2割特例と少額特例 |
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者(2割特例の対象)であり、かつ基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者(少額特例の対象) |
2割特例を適用して消費税の申告を行う場合、売上税額の2割を納付税額とするため、仕入れにかかる個々の取引について少額特例を適用して仕入税額控除の計算を行う必要はありません。ただし、少額特例の対象となる1万円未満の課税仕入れについて、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められるというルール自体は、2割特例適用者にも関係します。 |
2割特例は納税額を売上税額の2割に抑えることができるため、多くの小規模事業者にとって有利な制度です。
インボイス軽減措置の適用漏れを防ぐには
軽減措置の恩恵を確実に受けるためには、適用漏れがないように注意深く対応する必要があります。以下の点に留意しましょう。
適用条件の再確認
各軽減措置には適用対象となる事業者の条件や適用期間が定められています。例えば、2割特例は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において適用可能です。自社がこれらの条件を満たしているか、期間の変更がないかなどを定期的に確認することが重要です。特に、事業年度の変更や売上規模の変動があった場合は注意が必要です。
帳簿への正確な記載
少額特例を適用する場合、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この「一定の事項」の記載漏れがないように、日々の経理処理を正確に行うことが求められます。具体的には、取引年月日、取引内容、支払対価の額、相手方の氏名または名称などを記載する必要があります。
会計システムの活用
インボイス制度に対応した会計ソフトやシステムを導入・活用することで、軽減措置の適用判定や必要な帳簿記載を効率的に行うことができます。ただし、ソフトウェアの設定が正しく行われているかを確認し、アップデート情報にも注意を払いましょう。
専門家への相談
軽減措置の適用に関して不明な点や判断に迷う場合は、税理士や税務署などの専門家に相談することをおすすめします。誤った解釈で適用漏れや過少申告が生じると、後日追徴課税や加算税が発生するリスクもあります。
確定申告におけるインボイス軽減措置の処理
軽減措置を適用した場合、消費税の確定申告において適切な処理が必要です。ここでは、主な軽減措置に関する確定申告時のポイントを解説します。
2割特例を適用する場合の申告
2割特例の適用を受けるためには、消費税の確定申告書にその旨を付記する必要があります。具体的には、消費税の申告書(一般用または簡易課税用)の所定の欄に、2割特例を適用して計算した税額を記載します。事前の届出は不要ですが、申告書への記載を忘れないように注意しましょう。
少額特例を適用する場合の申告
少額特例は、適用を受けるための事前の届出や申告書への付記は必要ありません。帳簿に法定事項を記載し保存することで適用が認められます。確定申告時には、この特例を適用して計算した仕入税額控除額を基に消費税額を算出し、申告書に記載します。
確定申告書作成時の共通の注意点
確定申告書の様式や記載方法は、年度によって変更される可能性があります。必ず最新の国税庁のウェブサイトや手引きを確認し、正しい様式で正確に記載するようにしてください。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する場合も、入力画面の指示に従い、適用する特例に関する項目を正しく選択・入力することが重要です。申告内容に誤りがないか、提出前によく確認しましょう。
まとめ
インボイス制度開始に伴い、事業者の負担を和らげるための軽減措置が設けられました。特に「2割特例」や「少額特例」は、対象事業者にとって消費税の納税額や事務作業の負担を大きく減らす効果があります。結論として、これらの措置は制度への円滑な移行を支援し、事業者の負担軽減を目的としています。適用期間や条件を確認し、賢く活用して制度移行を乗り切りましょう。