【2025年最新】紹介料のインボイス処理|支払い側・受取側の対応と仕訳方法まとめ
更新日:2025.12.21
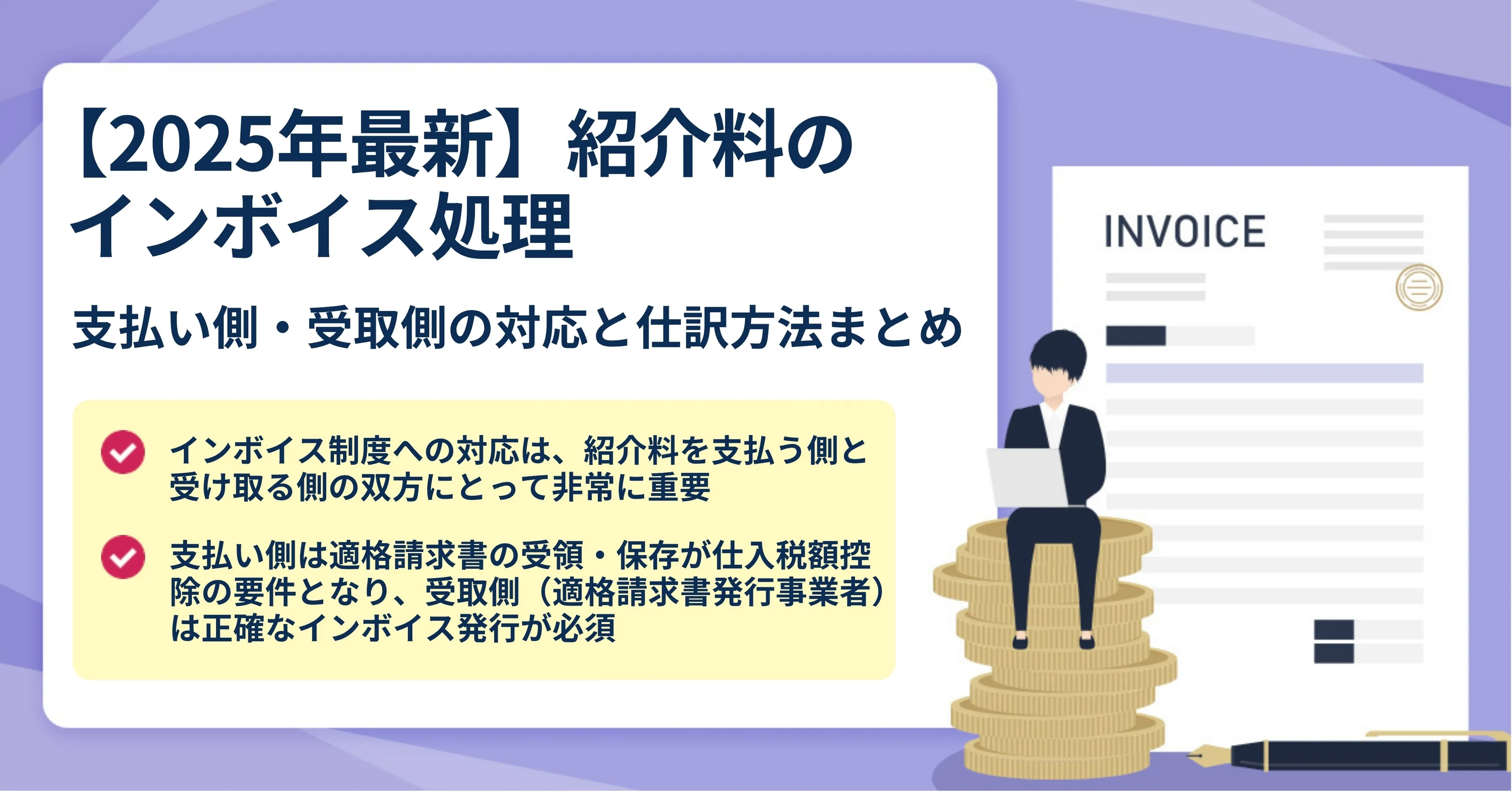
ー 目次 ー
インボイス制度開始で紹介料の経理処理は大きく変わりました。この記事では、2025年最新情報に基づき、紹介料を支払う側・受け取る側双方のインボイス対応と具体的な仕訳方法を徹底解説。適格請求書発行事業者・免税事業者別のケースも網羅し、実務上の疑問を解消、適切な処理へ導きます。
紹介料とインボイス制度の基本を理解する
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、紹介料の取引にも大きな影響を与えます。この章では、まずインボイス制度の基本的な概要と、紹介料の授受においてなぜこの制度が重要になるのか、そして適格請求書(インボイス)に記載すべき必須項目について解説します。
インボイス制度とは何か 概要をわかりやすく解説
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。この制度の下では、買手側(紹介料を支払う側)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として売手側(紹介料を受け取る側で、かつ適格請求書発行事業者)から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。免税事業者は適格請求書を発行できません。この制度の導入により、消費税の納税額計算や経理処理に新たな対応が求められるようになりました。
紹介料におけるインボイス制度の重要性
紹介料は、原則として消費税の課税対象となる取引です。そのため、インボイス制度への対応は、紹介料を支払う側と受け取る側の双方にとって非常に重要です。
紹介料を支払う側にとっては、仕入税額控除を適切に行うために、受け取る請求書が適格請求書の要件を満たしているかを確認する必要があります。もし紹介料の支払先が免税事業者である場合や、受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしていない場合、原則としてその取引にかかる消費税額を仕入税額控除できなくなるため、納税負担が増加する可能性があります。
一方、紹介料を受け取る側が適格請求書発行事業者である場合は、取引先(紹介料の支払い側)の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。免税事業者の場合は適格請求書を発行できないため、取引先から取引条件の見直しを求められたり、取引が敬遠されたりする可能性も考慮しなければなりません。
このように、紹介料の取引においては、インボイス制度が消費税の納税額に直接影響を与えるため、制度を正しく理解し、適切に対応することが不可欠です。
適格請求書(インボイス)の必須記載項目
適格請求書(インボイス)として認められるためには、以下の項目が記載されている必要があります。これらの項目が一つでも欠けていると、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
|
記載項目 |
内容 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
「T」+13桁の法人番号または数字 |
|
取引年月日 |
課税資産の譲渡等を行った年月日 |
|
取引内容 |
課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載) |
|
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
例:10%対象 XXX円、8%対象 YYY円 |
|
税率ごとに区分した消費税額等 |
例:10%対象消費税額 XX円、8%対象消費税額 YY円 |
|
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
紹介料を支払う側の会社名や屋号など |
紹介料の取引においても、これらの記載事項が網羅された請求書を受領または発行することが重要です。
紹介料が発生する場面:インボイス制度との関係
ビジネスにおいて「紹介料(キックバック・謝礼・手数料)」を支払う場面は多々ありますが、これらは原則として消費税の「課税取引」に該当します。
そのため、紹介料を支払う側が「仕入税額控除」を受ける(支払った消費税を経費として引く)ためには、紹介者からインボイス(適格請求書)の発行を受ける必要があります。
人材紹介
採用時に人材紹介会社やヘッドハンターへ支払う手数料です。
- 紹介会社の場合:
ほとんどの法人は課税事業者でありインボイス登録済みですので、発行される請求書を保存すれば問題ありません。 - 個人の場合(リファラル採用など):
知人や社員の紹介で、個人に対して謝礼を支払うケースです。相手が免税事業者(インボイス未登録)である場合、支払う側は消費税分の控除ができません。税負担が増えることを考慮し、謝礼額を調整するかどうか事前に取り決めが必要です。
新規顧客の紹介
「お客様を紹介してくれたら売上の〇%を還元する」といった、販売促進費や支払手数料としての性質を持つ紹介料です。
特に注意が必要なのは、副業の個人やフリーランスに紹介を依頼しているケースです。相手がインボイス未登録であれば、これまで通りに消費税上乗せで支払うと、会社側が「消費税分を多く払っているのに、税額控除できない」という損をする状態になります。
契約更新時に「インボイス登録の有無」を確認し、未登録の場合は「消費税相当額を差し引いた金額に変更する」などの価格交渉が必要になる場合があります。
不動産の紹介
土地や建物の売買情報を紹介してもらった際に支払う紹介料です。
ここで間違いやすいのが「土地の売買自体は非課税だが、紹介料は課税」という点です。
- 土地の代金=非課税(消費税かからない)
- 土地売買の仲介手数料・紹介料=課税(消費税かかる)
不動産取引では金額が大きくなりがちです。紹介料が数百万〜数千万円になる場合、その消費税(10%)が控除できるかどうかはキャッシュフローに多大な影響を与えます。必ず相手方がインボイス発行事業者かどうかを確認しましょう。
紹介料を支払う側のインボイス対応と仕訳
インボイス制度開始後、紹介料を支払う側は、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。取引先が適格請求書発行事業者であるか、免税事業者であるかによって対応が異なりますので、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
適格請求書発行事業者へ紹介料を支払う場合のインボイス処理
紹介料の支払先が適格請求書発行事業者である場合、仕入税額控除を受けるためには、交付された適格請求書を適切に保存する必要があります。受領した適格請求書の内容確認と、正確な経理処理が重要です。
受領する適格請求書の確認ポイント
適格請求書発行事業者から紹介料の請求書を受領した際は、以下の項目が正しく記載されているかを確認しましょう。これらの記載がない場合、仕入税額控除が認められない可能性があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(紹介料である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
特に登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で有効性を確認することができます。
紹介料支払い時の仕訳例 消費税の経理処理
例えば、株式会社A(適格請求書発行事業者)に紹介料として110,000円(うち消費税10,000円)を普通預金から支払った場合の仕訳は以下の通りです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
支払手数料(紹介料) |
100,000円 |
普通預金 |
110,000円 |
|
仮払消費税等 |
10,000円 |
摘要欄には「株式会社A 紹介料」など、取引内容がわかるように記載しておくと管理がしやすくなります。
免税事業者等へ紹介料を支払う場合のインボイス対応
紹介料の支払先が免税事業者や、適格請求書発行事業者以外の事業者(消費者、適格請求書発行事業者以外の事業者など)である場合、原則として仕入税額控除は受けられません。ただし、一定期間は経過措置が設けられています。
仕入税額控除の経過措置と紹介料の取り扱い
免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度開始から一定期間、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。紹介料の支払いもこの対象となります。
|
期間 |
控除割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
この経過措置の適用を受けるためには、免税事業者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除対象、50%控除対象など)を記載した帳簿の保存が必要です。
免税事業者への紹介料支払いと仕訳具体例
例えば、免税事業者である個人B氏に紹介料として55,000円(消費税相当額5,000円を含む)を普通預金から支払い、2025年中に80%の経過措置を適用する場合の仕訳は以下の通りです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
支払手数料(紹介料) |
51,000円 |
普通預金 |
55,000円 |
|
仮払消費税等 |
4,000円 |
※ 消費税相当額5,000円 × 80% = 4,000円が仮払消費税等として計上されます。残りの1,000円は支払手数料に含めて処理します(50,000円 + 1,000円 = 51,000円)。会計ソフトによっては、経過措置に対応した税区分コードが用意されている場合があります。
紹介料支払い側が知っておくべきインボイスQ&A
紹介料を支払う際に生じやすいインボイス制度に関する疑問点をQ&A形式で解説します。
Q1. 請求書に登録番号の記載がありませんでした。どうすればよいですか?
A1. まず、支払先に登録番号の記載された適格請求書の再発行を依頼してください。相手が適格請求書発行事業者でない場合は、経過措置の適用を検討します。意図的に誤った情報を伝える事業者もいる可能性があるため、国税庁の公表サイトで登録状況を確認することも有効です。
Q2. 税込1万円未満の紹介料の支払いでも、インボイスの保存は必要ですか?
A2. 一定規模以下の事業者(基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者)については、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「少額特例」があります(2029年9月30日まで)。この条件に該当する場合、紹介料が税込1万円未満であれば、少額特例の対象となります。
Q3. 紹介料から振込手数料を差し引いて支払いました。インボイスの処理はどうなりますか?
A3. 振込手数料を支払側が負担する場合、その手数料は課税仕入れとなります。紹介料の請求書とは別に、金融機関が発行する利用明細などで振込手数料の金額を確認し、適切に処理します。もし、紹介料の支払先が振込手数料を負担する契約(売手負担)で、支払側が立て替えて支払う場合は、その振込手数料相当額を売上値引や支払手数料のマイナスとして処理するか、立替金精算書などの発行を相手方に依頼し、インボイスの要件を満たすように調整する必要があります。実務上は、振込手数料を差し引いた後の金額で紹介料のインボイスを発行してもらうか、別途、振込手数料相当額の値引きに係る適格返還請求書を発行してもらうなどの対応が考えられます。
紹介料を受け取る側のインボイス対応と仕訳
紹介料を受け取る側も、インボイス制度への適切な対応が求められます。適格請求書発行事業者であるか、免税事業者であるかによって、対応方法や経理処理が異なります。ここでは、それぞれの立場における具体的な対応と仕訳方法について解説します。
適格請求書発行事業者が紹介料を受け取る場合のインボイス処理
適格請求書発行事業者が紹介料を受け取る場合、取引先(支払側)から適格請求書(インボイス)の交付を求められることが一般的です。適切に対応することで、取引先は仕入税額控除を受けることができます。
紹介料の適格請求書発行方法と注意点
適格請求書発行事業者は、紹介料の請求に際して、以下の点に注意して適格請求書を発行する必要があります。
- 必須記載項目の網羅: 適格請求書には、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などの記載が必須です。記載漏れがないよう注意しましょう。
- 登録番号の明記: 税務署から通知された適格請求書発行事業者の登録番号を正確に記載します。
- 交付方法の確認: 取引先が希望する交付方法(紙、電子インボイスなど)を確認し、対応します。電子インボイスで交付する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存する必要があります。
- 写しの保存: 発行した適格請求書の写しを、規定の期間保存する義務があります。
これらの対応を怠ると、取引先が仕入税額控除を受けられず、今後の取引に影響が出る可能性もあるため、正確な処理を心がけましょう。
紹介料受取時の仕訳例 売上と消費税の計上
適格請求書発行事業者が紹介料を受け取った際の仕訳は、売上と消費税額を区分して計上します。例えば、紹介料として110,000円(うち消費税10%相当額10,000円)を現金で受け取った場合の仕訳例は以下の通りです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現金 |
110,000 |
売上 |
100,000 |
|
仮受消費税等 |
10,000 |
消費税の申告時には、この仮受消費税等と、仕入れにかかった仮払消費税等を相殺して納付税額を計算します。
免税事業者が紹介料を受け取る場合のインボイス対応
免税事業者は適格請求書を発行することができません。そのため、インボイス制度開始後は、取引先との関係や自身の事業戦略を踏まえた対応が必要になります。
課税事業者への転換を検討する際のポイント
免税事業者が紹介料の取引を継続・拡大していく上で、課税事業者への転換を検討するケースがあります。主なポイントは以下の通りです。
- 取引先の意向: 主要な取引先が適格請求書の発行を求めている場合、取引継続のために課税事業者への転換が有利になることがあります。
- 価格競争力: 免税事業者のままでは、取引先が仕入税額控除を受けられない分、実質的な負担増となるため、値下げ交渉や取引中止のリスクが生じる可能性があります。
- 事務負担の増加: 課税事業者になると、消費税の申告・納税義務が発生し、経理処理や事務作業が増加します。
- 納税負担の発生: これまで免除されていた消費税の納税が必要になります。
これらの要素を総合的に比較検討し、自社にとって最適な選択をすることが重要です。税理士などの専門家に相談することも有効な手段です。
免税事業者のまま紹介料を受け取る場合のインボイス影響
免税事業者のまま事業を継続する場合、紹介料の取引において以下のような影響が考えられます。
- 適格請求書を発行できない: 取引先は、原則としてその紹介料にかかる消費税額について仕入税額控除ができません。
- 取引条件の見直し: 取引先から、消費税相当額の値引きを要求されたり、取引自体が見直されたりする可能性があります。
- 新規取引の困難性: 新たに課税事業者との取引を開始する際に、適格請求書を発行できないことが不利に働く場合があります。
ただし、取引先が消費者や免税事業者である場合、または簡易課税制度を選択している事業者で、仕入税額控除の計算にインボイスを必要としない場合は、影響が少ないこともあります。
免税事業者の紹介料受取と仕訳具体例
免税事業者は消費税の納税義務がないため、受け取った紹介料は全額を売上として計上します。消費税を区分して経理する必要はありません。例えば、紹介料として50,000円を現金で受け取った場合の仕訳例は以下の通りです。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
現金 |
50,000 |
売上 |
50,000 |
インボイス制度導入後も、免税事業者の会計処理自体に大きな変更はありませんが、取引先との関係性には注意が必要です。
紹介料受取側が知っておくべきインボイスQ&A
紹介料を受け取る側がインボイス制度に関して抱きやすい疑問点をQ&A形式でまとめました。
|
質問 |
回答 |
|
Q1. 適格請求書発行事業者になるためには、どのような手続きが必要ですか? |
A1. 所轄の税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。登録を受けると登録番号が通知されます。e-Taxを利用してオンラインで申請することも可能です。 |
|
Q2. 免税事業者ですが、取引先からインボイスの発行を強く求められています。どうすればよいですか? |
A2. 免税事業者はインボイスを発行できません。取引先との関係を維持するためには、課税事業者への転換を検討するか、取引条件について交渉する必要があります。状況によっては、取引の継続が難しくなる可能性も考慮し、専門家にも相談しながら慎重に判断しましょう。 |
|
Q3. 副業で得た少額の紹介料でも、インボイスの発行は必要になりますか? |
A3. あなたが適格請求書発行事業者である場合、取引先(支払側)から求められれば、紹介料の金額にかかわらずインボイスを発行する義務があります。免税事業者の場合は発行できません。 |
|
Q4. インボイス制度開始後、免税事業者は請求書に何か記載すべきことはありますか? |
A4. 免税事業者は適格請求書を発行できないため、請求書に登録番号を記載することはできません。従来の請求書と同様の形式で発行することになりますが、取引先が誤解しないよう、自身が免税事業者であることを伝えることも有効な場合があります。 |
紹介料のインボイス処理に関するその他の論点
インボイス制度は紹介料の取り扱いにおいて、基本的な支払い・受取の場面以外にも考慮すべき論点が存在します。ここでは、源泉徴収、契約書、海外取引、立替金といった、より具体的なケースにおけるインボイス制度との関連性について解説します。
紹介料と源泉徴収 インボイス制度下での関係
インボイス制度が導入された後も、紹介料にかかる源泉徴収の基本的なルールに変更はありません。しかし、インボイス(適格請求書)の導入により、請求金額の取り扱いに関して注意が必要です。
紹介料が源泉徴収の対象となるのは、主に個人(フリーランスなど)へ支払う場合や、弁護士や税理士など特定の資格を持つ個人事業主への報酬・料金と同様の性質を持つ場合です。法人間での紹介料支払いは、原則として源泉徴収の対象外となります。
源泉徴収を行う際、源泉徴収税額の計算基礎となる金額は、原則として消費税込みの金額です。ただし、請求書等で報酬・料金の額と消費税額が明確に区分されている場合には、消費税抜きの報酬・料金の額を源泉徴収の対象とすることができます。適格請求書では消費税額が明記されるため、税抜金額を基に源泉徴収税額を計算することが一般的になるでしょう。
支払い側は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を国に納付し、支払調書を作成・提出する義務があります。この際、インボイスの保存は仕入税額控除の要件であり、源泉徴収の手続きとは別に適切に行う必要があります。
紹介契約書とインボイス制度 記載すべき事項
インボイス制度の開始に伴い、紹介料に関する契約書の内容も見直し、必要に応じて追記することが推奨されます。契約締結時にインボイスに関する取り決めを明確にしておくことで、後のトラブルを避けることができます。
契約書に盛り込むべき主な項目は以下の通りです。
|
項目 |
記載内容のポイント |
|
紹介料の金額と消費税 |
紹介料の金額を税抜額と税込額の両方、または税抜額と適用税率を明記する。 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
紹介料の受取側が適格請求書発行事業者の場合、その登録番号を記載する。 |
|
適格請求書の交付 |
紹介料の受取側が適格請求書を交付する義務があることを明記し、交付時期や方法(例:電子インボイス)についても定める。 |
|
免税事業者である場合の取り扱い |
紹介料の受取側が免税事業者の場合、その旨と、インボイスが発行されないことを確認する。仕入税額控除の経過措置を適用する場合の合意事項などもあれば記載する。 |
|
契約期間中に適格請求書発行事業者の登録状況に変更があった場合の通知義務 |
免税事業者が課税事業者になった場合や、その逆の場合に速やかに相手方に通知する義務を定める。 |
特に、紹介料の支払いが継続的に発生する場合や、高額な取引になる場合は、契約書でインボイスに関する事項を明確にしておくことが重要です。
海外への紹介料支払いとインボイスの適用範囲
日本のインボイス制度は、国内で行われる商品やサービスの提供(国内取引)に対して適用されます。したがって、海外の事業者へ紹介料を支払う場合、原則として日本の消費税の課税対象外(不課税または国外取引)となり、インボイスの交付を受ける必要はありませんし、相手方も交付義務がありません。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 日本の事業者が海外の事業者に顧客を紹介し、その対価として海外の事業者から紹介料を受け取る場合:これは輸出免税取引に該当する可能性があります。適格請求書の発行は不要ですが、輸出取引であることの証明書類の保存が必要です。
- 日本の事業者が海外の事業者に顧客を紹介してもらい、その対価として海外の事業者に紹介料を支払う場合:これは国外取引として消費税の課税対象外(不課税)となるのが一般的です。したがって、支払い側は仕入税額控除の対象とはならず、インボイスの保存も不要です。
ただし、役務提供の場所がどこであるか(内外判定)によって消費税の取り扱いが異なる場合があります。例えば、非居住者に対する役務提供であっても、その役務提供が国内で行われたと判断される場合は課税対象となることがあります。国際的な取引における紹介料の消費税の取り扱いについては、複雑な場合もあるため、税理士などの専門家に確認することが推奨されます。
立替金や仲介手数料としての紹介料とインボイス
紹介料という名目であっても、その実態が「立替金」なのか、純粋な「仲介手数料」なのかによって、インボイス制度上の取り扱いが異なります。
立替金としての紹介料
紹介に関連して発生した費用(例:広告費、交通費など)を、紹介者(A社)が一時的に立て替え払いし、後日、被紹介者(B社)からその実費を精算してもらうケースです。この場合、A社がB社に対して発行する請求書は、A社自身の役務提供の対価ではないため、原則としてA社がインボイスを発行する必要はありません。
ただし、B社が仕入税額控除を受けるためには、その立て替えられた費用にかかる元の適格請求書(またはそれに類する書類)が必要になります。そのため、A社は支払い先から受領した適格請求書のコピーをB社に渡すか、立替金精算書に元の適格請求書の記載事項(発行者の登録番号など)を転記するなどの対応が求められます。A社が立て替えた金額に利益を上乗せして請求する場合は、その上乗せ分がA社の手数料収入となり、その部分についてはインボイスの発行が必要となる場合があります。
仲介手数料としての紹介料
紹介者が顧客を紹介するという役務提供の対価として受け取るものが、純粋な仲介手数料としての紹介料です。この場合は、紹介者の課税売上に該当し、紹介者が適格請求書発行事業者であれば、取引先(紹介料の支払者)に対して適格請求書を交付する義務があります。支払い側は、受領した適格請求書に基づいて仕入税額控除を行うことができます。
紹介料がどちらの性質を持つのかを契約内容や取引の実態に基づいて判断し、適切なインボイス対応を行うことが重要です。
まとめ
2023年10月開始のインボイス制度は、紹介料の取引にも大きな影響を与えます。支払い側は適格請求書の受領・保存が仕入税額控除の要件となり、受取側(適格請求書発行事業者)は正確なインボイス発行が必須です。免税事業者は取引先との関係や自身の事業規模を考慮し、課税転換も視野に入れる必要があります。制度への適切な対応は、消費税の正確な申告・納税に繋がり、円滑な取引継続のために重要です。不明点は税理士等へ相談しましょう。










