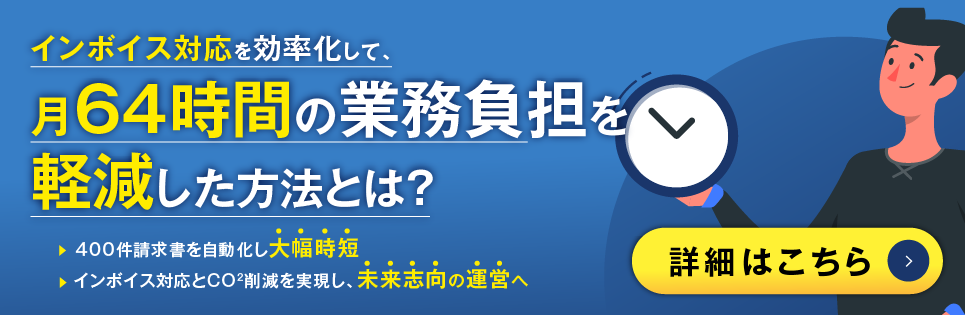3万円以上の旅費にはインボイスが必要?公共交通機関特例・出張旅費特例の概要や違いも解説
更新日:2025.12.06
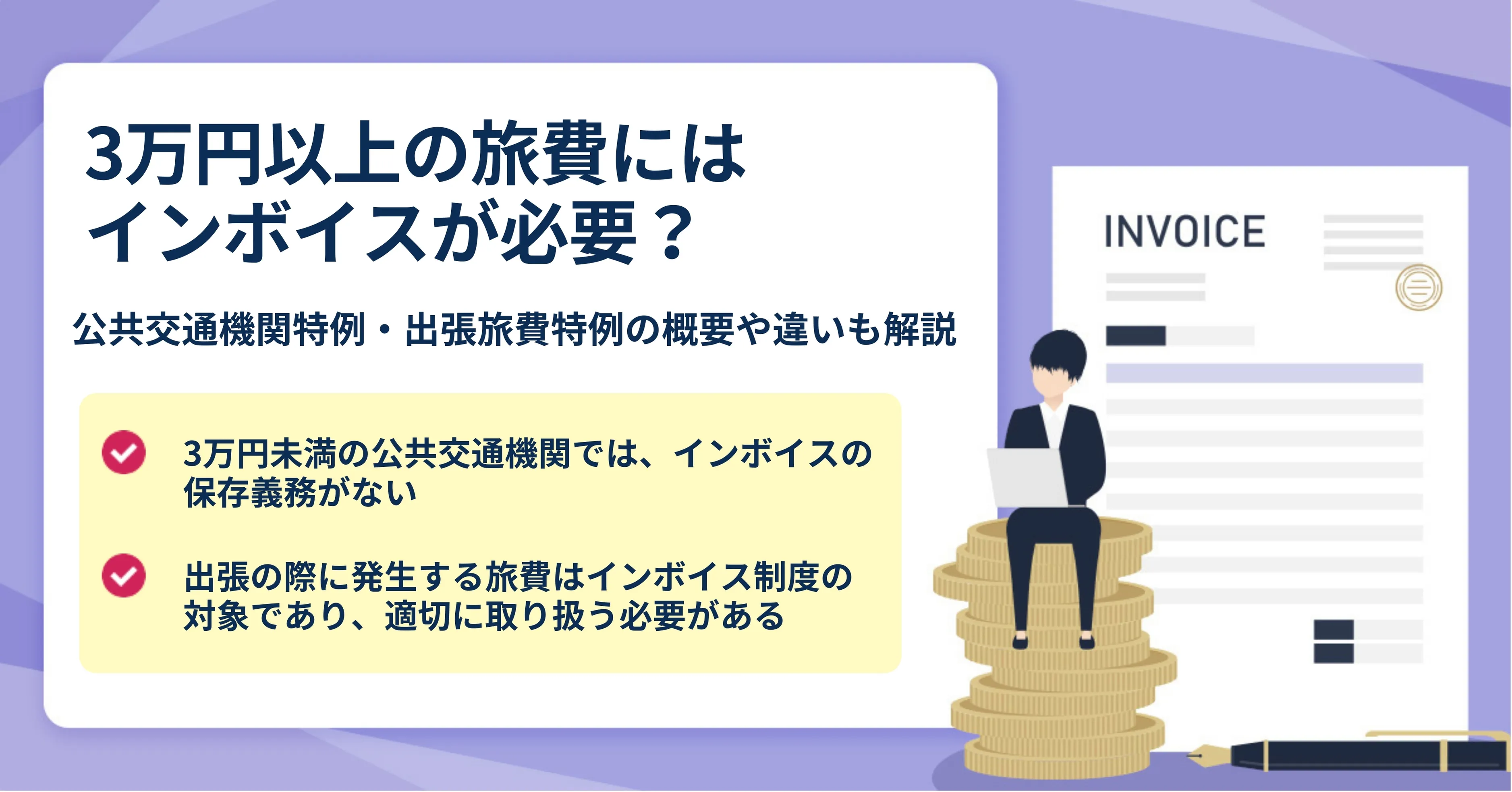
ー 目次 ー
旅費の精算で仕入税額控除を適用するには、インボイス制度への対応が必要です。インボイス(適格請求書)の取扱いを誤ると、仕入税額控除が適用できない可能性があるため注意しなければなりません。
ただし、公共交通機関特例や出張旅費特例を適用することで、インボイスの作成や交付などの対応を簡素化することが可能です。旅費の取り扱いと特例の概要を理解して、スムーズに経理処理を進めましょう。
本記事では、3万円以上の旅費に関するインボイス制度への対応について、公共交通機関特例や出張旅費特例の概要、違いを交えて解説します。
インボイス制度では旅費を2つのケースで取り扱う
旅費の精算では、インボイス(適格請求書)の要否は精算方法によって異なります。それぞれのケースで適切に対応しないと、仕入税額控除を適用できない場合があるため注意しなければなりません。
このようなことから、インボイス制度に対応する際には、旅費の取扱いパターンや対応方法を把握することが重要です。
ここでは、インボイス制度における旅費の取扱いについて解説します。
- 立替払いとして経費精算する
- 出張旅費規程にしたがって精算する
①立替払いとして経費精算する
立替払いとして経費精算する際は、企業が公共交通機関から課税仕入れをおこなったとみなします。そのため、仕入税額控除を適用するにはインボイス(適格請求書)が必要です。
ただし、インボイスの宛名が従業員の名前になっている場合は、立替金精算書の作成により仕入税額控除を適用できます。また、特例として3万円未満の公共交通機関の運賃に関しては、帳簿に明記することでインボイスは必要ありません。
②出張旅費規程にしたがって精算する
出張旅費規程とは、交通費や宿泊費などの出張費を精算する際の基準となる規程のことです。
出張旅費規定にしたがって精算する場合は、企業と従業員の間で取引があったとみなします。そのため、企業から従業員への支給額が仕入税額控除の対象です。
このケースにインボイスは必要なく、帳簿のみの保存で問題ありません。ただし、帳簿には出張旅費特例などと記載が必要です。また、仕入税額控除を適用する金額は、常識的な範囲でなければなりません。
旅費のインボイス制度に関わる2つの特例とその違いとは?
旅費のインボイス制度に関わる特例には、公共交通機関特例と出張旅費特例の2種類があります。どちらの特例を適用するかは、状況によって使い分けなければなりません。
旅費を適切に精算するためには、それぞれの内容をしっかり理解することが重要です。
ここでは、旅費のインボイス制度に関わる特例とその違いについて解説します。
①インボイス制度の公共交通機関特例
税込3万円未満の公共交通機関を利用した場合は、帳簿への保存のみで仕入税額控除を適用できます。公共交通機関特例が存在するのは、公共交通機関を利用する際にインボイス(適格請求書)の交付を受けることが困難なケースがあるためです。
公共交通機関特例では、基本的に1回の取引における税込価額の合計額が3万円未満であるかで適用可否が判断されます。
たとえば、片道14,000円(税込)の乗車券を2人分購入する場合は、公共交通機関特例を適用できます。しかし、3人分の場合は合計額が3万円以上となるため適用できません。
また、公共交通機関特例は、あくまでもインボイスの保存が不要になるものです。法人や個人事業主の経費として計上する際には、取引先や金額、日付がわかる領収書が必要となります。
②インボイス制度の出張旅費特例
従業員に支給する出張旅費や宿泊費、日当などのうち、旅行に必要であると認められる部分の金額は、帳簿への保存のみで仕入税額控除を適用できます。つまり、支給する旅費に関しては、仕入税額控除の適用にインボイス(適格請求書)が不要です。
出張旅費特例において、現金払いやクレジットカード払いなどの支払い方法によって制限を設ける規定はありません。
また、従業員が立て替えた出張旅費については、金額が3万円以上であってもインボイスの保存が不要です。ただし、会社決済型のコーポレートカードで支払った場合は、インボイスの保存が必要となるため注意しましょう。
【違い】公共交通機関特例と出張旅費特例は、適用できる金額が違う!
旅費の精算でインボイス制度に対応するためには、公共交通機関特例と出張旅費特例の違いを把握することが重要です。
公共交通機関特例と出張旅費特例の大きな違いは、特例を適用できる金額に制限が設けられている点です。
公共交通機関特例は合計金額が3万円未満の場合にのみ適用できます。
しかし、出張旅費特例には金額の制限がありません。また、公共交通機関特例で対象外となるタクシーや航空機を利用した場合にも適用できます。
上記を踏まえ、以下に2種類の特例の違いをまとめています。あわせて参考にしてください。
|
公共交通機関特例 |
出張旅費特例 |
|
|
対象費目 |
バスや鉄道などの公共交通機関の利用に限定されている |
とくに費目は限定されていない |
|
金額 |
合計金額が3万円未満の場合にのみ適用できる |
金額の制限は設けられておらず、常識的な範囲内であれば3万円以上でも適用できる |
|
支払者 |
支払者を問わない |
企業が公共交通機関に支払う場合には適用できない |
【記載例あり】特例を適用する際に必要な帳簿の5つの記載事項
インボイス制度における仕入税額控除の特例を適用する場合、インボイス(適格請求書)の保存は不要ですが、帳簿への記載と保存が求められます。そのため、旅費を精算する際には、以下の項目を記載しなければなりません。
- 取引先の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の場合)
- 税率の異なるごとに区分した支払対価の額
- 摘要欄に特例の適用がある旨を記載
基本的には、通常の帳簿記入で記載される項目がほとんどです。特例の適用がある旨を記載する必要がある点にだけ注意しておけば、問題はないでしょう。
特例の適用がある旨を帳簿に記載する際は以下を参考にしてください。
|
||||||||||||||||||
なお、公共交通機関特例の適用については、「公共交通機関特例の適用対象」「入場券」などと記載する場合もあります。
【Q&A】インボイス制度の旅費に関するよくある質問
最後に、インボイス制度の旅費に関するよくある質問を紹介します。
①3万円未満の公共交通機関にインボイスは不要?
3万円未満の公共交通機関を利用した場合には、インボイスの保存義務がありません。公共交通機関特例として認められており、インボイスの手続きを簡素化できます。
②3万円未満の公共交通機関を往復で購入する場合はどうなる?
公共交通機関の乗車券を購入する際に片道分が税込で3万円未満であっても、往復で3万円以上の場合はインボイスが必要です。
公共交通機関特例を適用する際は、1回の取引額が3万円未満であるかで判断しましょう。
③3万円未満でインボイスが不要となる公共交通機関は?
3万円未満の利用でインボイスが不要となる公共交通機関は以下のとおりです。
- 船舶
- バス
- 鉄道
航空機やタクシーは公共交通機関ではないため特例の対象とならず、インボイスが必要です。
まとめ|インボイス制度における旅費の取り扱いを理解してスムーズに精算しよう
本記事では、3万円以上の旅費に関するインボイス制度への対応について、公共交通機関特例や出張旅費特例の概要、違いを交えて解説しました。
出張の際に発生する旅費はインボイス制度の対象であり、適切に取り扱わなければなりません。
ただし、インボイス制度には公共交通機関特例と出張旅費特例が設けられているため、インボイス(適格請求書)の保存が必要ないケースもあります。とくに、公共交通機関特例を適用できるか判断するためのポイントは、旅費が3万円未満であるか3万円以上であるかです。
旅費に関わるインボイス制度の特例について理解し、旅費をスムーズに精算しましょう。