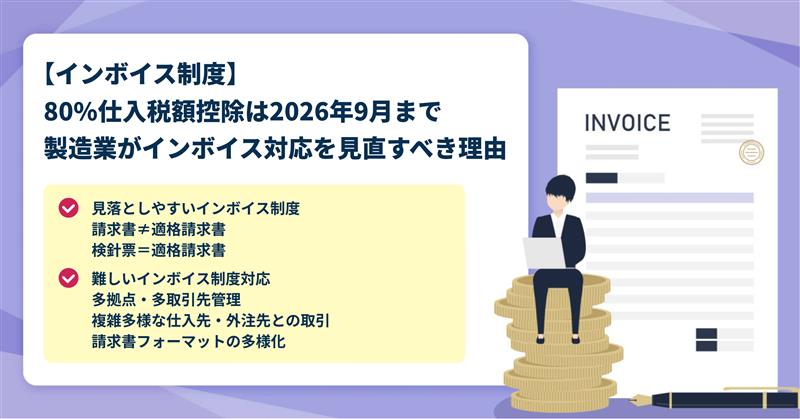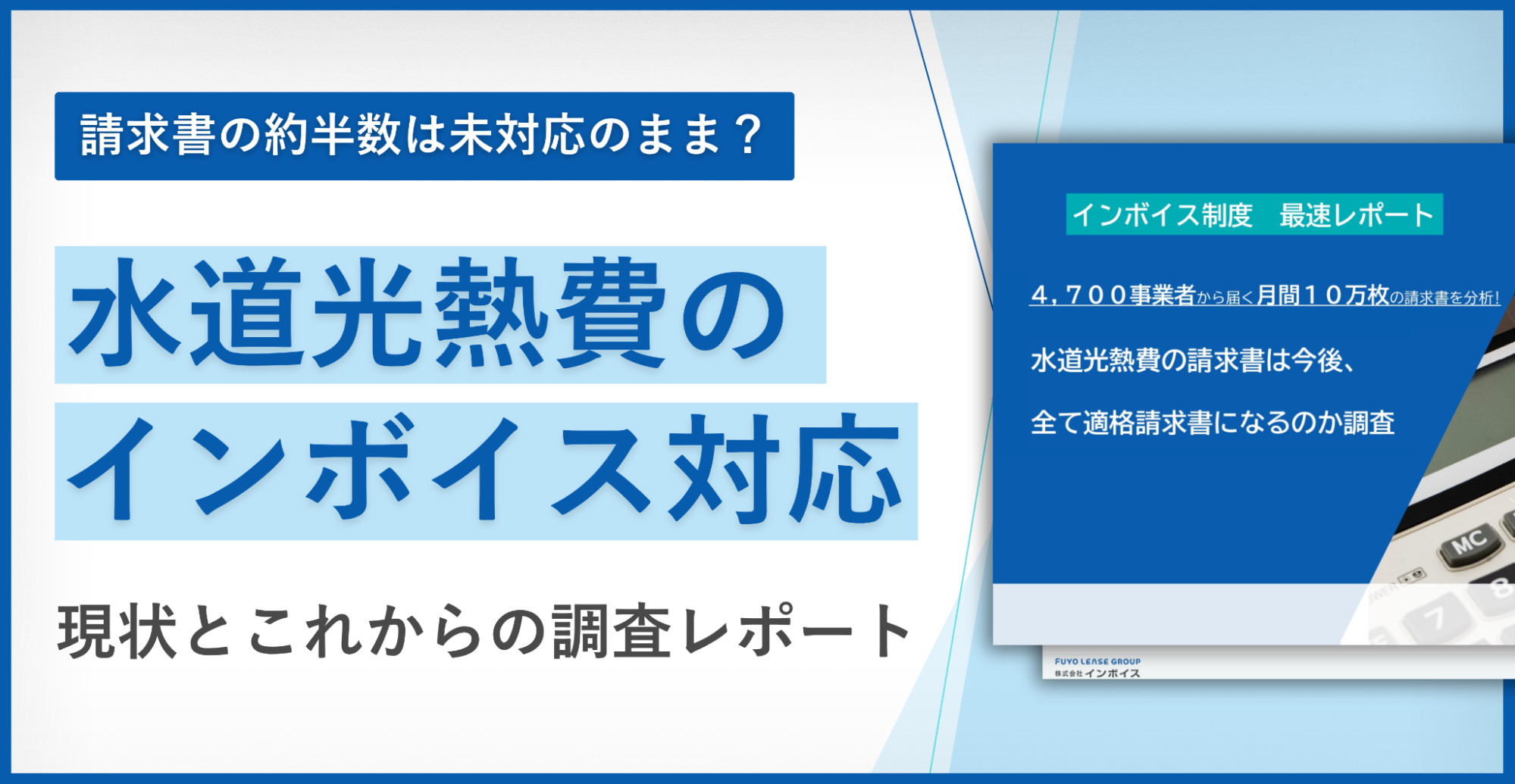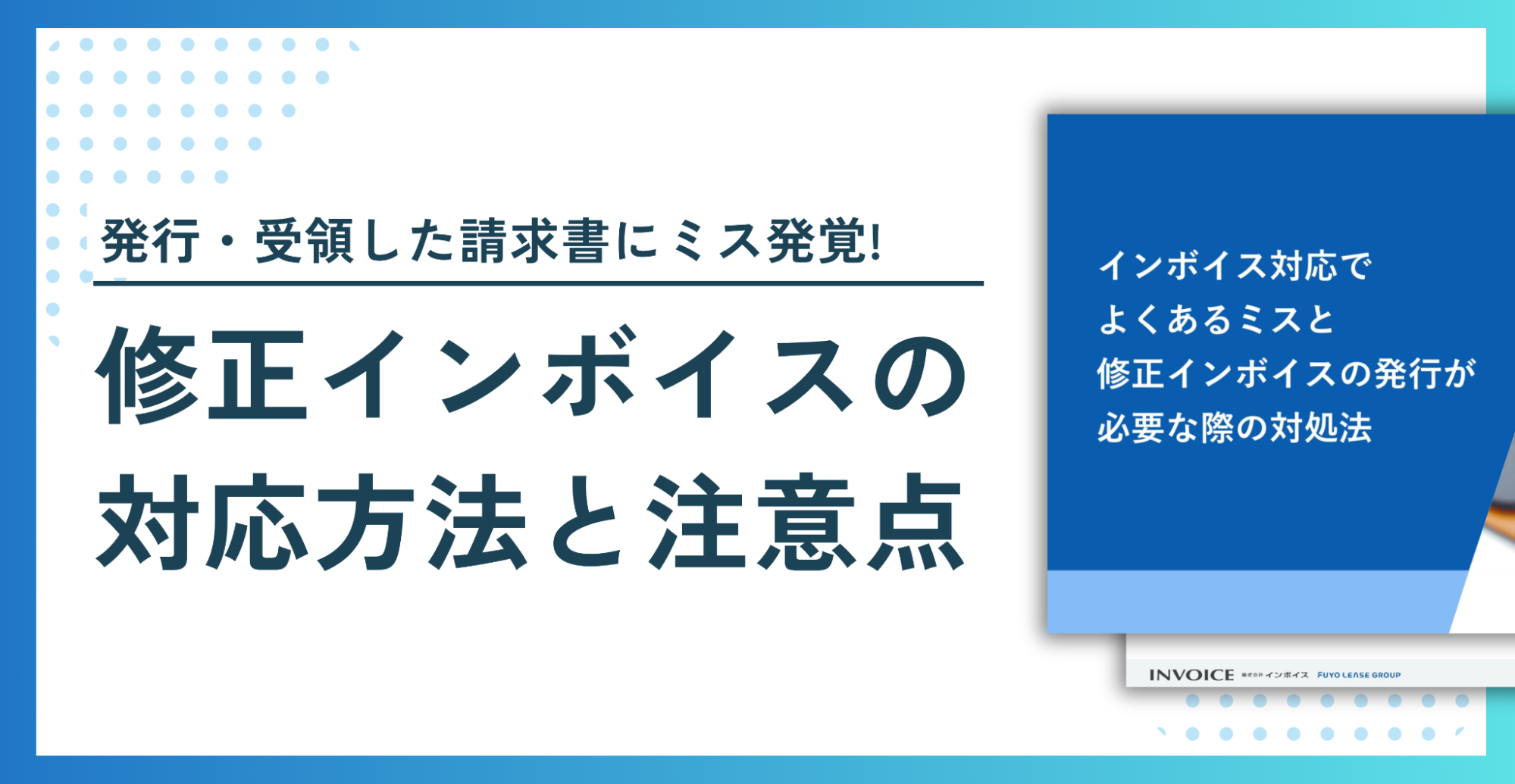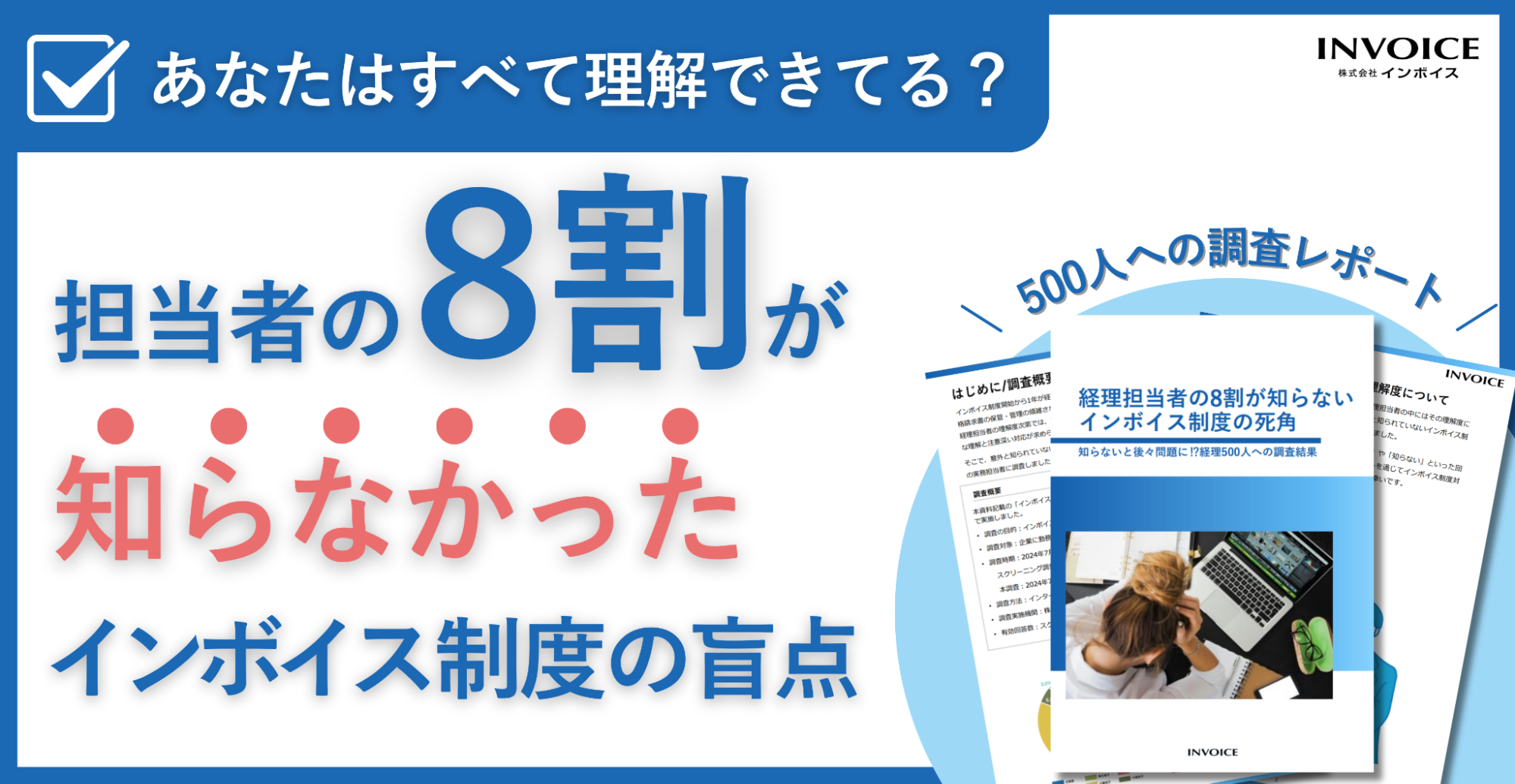インボイス制度で免税業者との取引はどうなる?消費税の扱いや経過措置について解説
更新日:2025.12.06
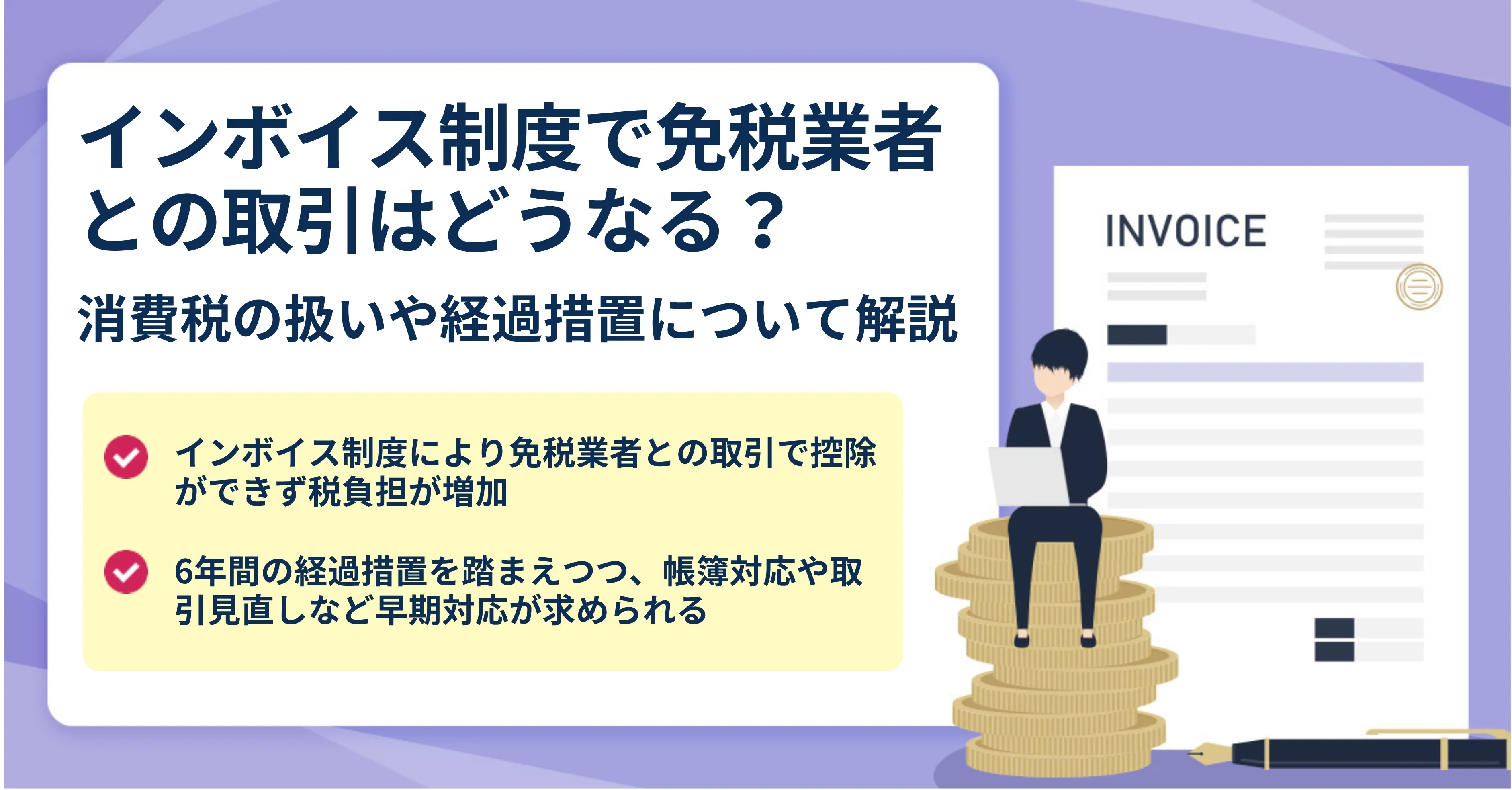
ー 目次 ー
インボイス制度の開始後、免税事業者との取引について、「このまま続けても大丈夫?」と不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、免税事業者との取引で注意すべき消費税の扱いや経過措置の内容、さらに今後の実務対応について丁寧に解説いたします。取引継続の判断や価格交渉の考え方もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度とは?免税業者との取引にどんな影響があるのか解説
2023年10月1日から開始されたインボイス制度は、特に消費税の扱いに大きな変化をもたらしました。この章では、インボイス制度の基本的な仕組みと、免税事業者との取引において具体的に何が変わるのかを分かりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?なんのためか簡単に解説
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。制度の主な目的は、複数税率(標準税率10%と軽減税率8%)に対応し、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。
この制度下では、買い手側が仕入税額控除(※)の適用を受けるために、売り手側から交付された「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になります。
※仕入税額控除:売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引いて、納税する消費税額を計算する仕組みのこと。
インボイス(適格請求書)とは、以下の項目が記載された請求書や領収書などを指します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
このインボイスを発行できるのは、税務署に申請し登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。そして、この登録事業者になれるのは、原則として消費税の課税事業者に限られます。
インボイス制度で免税業者との取引は何が変わる?
インボイス制度の導入により、免税事業者との取引における消費税の扱いが大きく変わりました。免税事業者は適格請求書発行事業者として登録できないため、インボイスを発行することができません。このことが、買い手(発注側)と売り手(受注側)の双方に影響を及ぼします。
具体的に何が変わったのか、買い手(課税事業者)の視点から見てみましょう。
|
制度導入前(~2023年9月30日) |
制度導入後(2023年10月1日~) |
|
|
免税事業者からの請求書 |
免税事業者からの請求書でも、支払った消費税額を仕入税額控除の対象にできた(区分記載請求書等保存方式)。 |
免税事業者はインボイスを発行できないため、原則として仕入税額控除の対象にできなくなった。 |
|
自社の納税額への影響 |
仕入れにかかった消費税分を差し引いて納税できた。 |
控除できる金額が減るため、消費税の納税負担が増加する可能性がある。(※経過措置あり) |
このように、買い手である課税事業者は、免税事業者との取引をこれまで通り続けると、消費税の納税額が増えてしまう可能性があります。そのため、免税事業者である取引先に対して、価格交渉や、課税事業者への転換およびインボイス登録を依頼するなどの対応が必要になるケースが出てきています。
インボイス制度下で免税事業者と取引を続けると消費税はどうなる?
インボイス制度は、特に免税事業者との取引に大きな影響を与えます。具体的にどのような変化があり、納税額にどう影響するのかを詳しく見ていきましょう。
原則として仕入税額控除が適用できなくなる
インボイス制度の導入後、免税事業者との取引で最も大きな変更点は、原則として「仕入税額控除」が適用できなくなることです。
仕入税額控除とは、事業者が消費税を納付する際に、売上にかかる消費税額から仕入れや経費にかかった消費税額を差し引くことができる仕組みです。この控除により、消費税の二重課税を防いでいます。
しかし、インボイス制度下で仕入税額控除を適用するためには、取引相手から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要不可欠です。インボイスを発行できるのは、税務署に登録申請を行った課税事業者(適格請求書発行事業者)のみであり、免税事業者は発行できません。
したがって、免税事業者から仕入れを行った場合、買い手側はインボイスを受け取れないため、その取引で支払った消費税額を仕入税額控除の対象にできなくなります。結果として、買い手側が納める消費税の負担額が増えてしまうのです。
課税事業者の納税額はいくら増えるのかシミュレーション
免税事業者との取引を続けた場合、課税事業者の納税額が具体的にいくら増えるのか、簡単なモデルでシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
- 自社(買い手):課税事業者
- 取引先(売り手):免税事業者
- 自社の課税売上:550万円(うち消費税50万円)
- 取引先からの課税仕入:110万円(うち消費税10万円)
この条件で、インボイス制度の導入前後(経過措置を考慮しない場合)の納税額を比較します。
|
項目 |
インボイス制度導入前 |
インボイス制度導入後(原則) |
|
① 売上にかかる消費税額 |
50万円 |
50万円 |
|
② 仕入にかかる消費税額 |
10万円 |
10万円 |
|
③ 仕入税額控除の適用 |
可能 |
不可 |
|
④ 控除できる消費税額 |
10万円 |
0円 |
|
納税額(① - ④) |
40万円 |
50万円 |
上記シミュレーションの通り、インボイス制度導入前は、免税事業者からの仕入れであっても支払った消費税10万円分を控除でき、納税額は40万円でした。しかし、制度導入後はインボイスがないため仕入税額控除が適用できず、納税額は50万円となります。このケースでは、納税負担が10万円増加することになります。
ただし、この負担を緩和するための「経過措置」が設けられていますので、次章で詳しく解説します。
【知らないと損】インボイス制度と免税事業者との取引に関する経過措置
インボイス制度の開始に伴い、課税事業者の急激な税負担の増加を緩和するため、仕入税額控除に関する特別な「経過措置」が設けられています。経過措置の内容を正しく理解し、適切に活用することで、制度移行期の負担を軽減できます。
ここでは、経過措置の具体的な内容や適用スケジュールについて詳しく解説します。
控除できる割合は何%?経過措置の段階的な縮小スケジュールを解説
インボイス制度開始後、免税事業者からの課税仕入れについては、本来であれば仕入税額控除が一切できなくなります。しかし、経過措置により、制度開始から6年間は、仕入税額相当額の一定割合を控除することが認められています。
控除できる割合は、下の表のように2段階で縮小していきます。
|
期間 |
控除できる割合 |
概要 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
免税事業者への支払対価に含まれる消費税額のうち、8割を仕入税額として控除できます。 |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
控除できる割合が5割に縮小されます。課税事業者の税負担が増加します。 |
この経過措置は、免税事業者や消費者などインボイスを発行できない相手との取引に適用されます。
経過措置を適用するための要件と帳簿の記載事項
この経過措置の適用を受けるためには、特別な申請手続きは不要ですが、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 免税事業者など、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れであること。
- 以下の事項を記載した帳簿および請求書等の保存をしていること。
特に、帳簿への記載事項が重要になります。通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける取引であることを明確に記さなければなりません。
- 取引先の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 対価の額
- 取引先の住所または所在地(※国税庁が定める一定の事業者については省略可)
- 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(例:「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」など)
最後の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が漏れていると、税務調査などで指摘され、控除が認められない可能性があります。経理処理の際は、どの取引が経過措置の対象となるのかを明確に区別し、正確に記帳することが不可欠です。
経過措置が終了するとどうなる?今から備えるべき実務対応とは
6年間の経過措置が完全に終了する2029年10月1日以降は、原則通り、免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除が一切できなくなります。つまり、免税事業者に支払った消費税額分は、すべて自社で負担することになります。
経過措置の終了はまだ先のことと感じるかもしれませんが、今のうちから以下のような実務対応を検討し、準備を進めておくことが重要です。
- 取引先とのコミュニケーション:取引先である免税事業者が、将来的にインボイス登録をする意向があるかを確認し、今後の取引方針について協議を進める。
- 価格・契約の見直し:経過措置の縮小や終了を見据え、取引価格や契約内容の見直しについて交渉を検討する。その際は、下請法や独占禁止法に抵触しないよう注意が必要です。
- 経理体制の整備:経過措置の段階的な縮小(80%→50%→0%)に対応できる経理フローを確立し、社内での周知を徹底する。
- 代替取引先の検討:長期的な視点で、必要に応じてインボイス発行事業者である新規取引先を探すことも選択肢の一つとして検討しておく。
経過措置はあくまで時限的な措置です。終了後の影響を最小限に抑えるためにも、計画的な対応が求められます。
免税事業者との取引を続ける?見直す?インボイス制度下での判断基準
インボイス制度の開始に伴い、多くの課税事業者が「免税事業者との取引を今後どうすべきか」という課題に直面しています。画一的な正解はなく、事業者ごとの状況に応じた判断が求められます。ここでは、取引を継続するか、あるいは見直すかの判断基準を多角的に解説します。
取引を続けるメリットとデメリットは?事業者側の視点での判断ポイント
既存の免税事業者との取引を継続する場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。自社の状況と照らし合わせながら、慎重に検討することが重要です。
|
項目 |
内容 |
|
メリット |
|
|
デメリット |
|
これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、以下のポイントを総合的に考慮して判断しましょう。
- 取引の重要性: その免税事業者との取引は、自社の事業にとってどれほど重要ですか?代替が困難な唯一無二の存在であれば、税負担が増えても取引を継続する価値は高いでしょう。
- コストインパクト: 仕入税額控除が受けられないことによる税負担増は、自社の利益をどの程度圧迫しますか?経過措置を考慮した上で、許容できる範囲内かを見極める必要があります。
- 取引先との関係性: 価格交渉や条件変更について、円滑に話し合いができる関係性が築けているかも重要な要素です。
新たな免税事業者との取引における判断ポイント
これから新たに取引先を探す場合は、既存の取引先とは異なる視点での判断が必要です。基本的には、最初からインボイス(適格請求書)を発行できる課税事業者を選ぶ方が、経理処理の簡素化や税負担の観点からは合理的です。
しかし、免税事業者にしか提供できないサービスや、価格競争力が非常に高い商品がある場合も考えられます。その際は、以下の点を判断基準としましょう。
- 付加価値の大きさ: その免税事業者と取引することで得られるメリット(低価格、高品質、独自性など)が、仕入税額控除を受けられないデメリットを上回るかどうかを比較検討します。
- インボイス登録の意向: 取引開始前に、将来的にインボイス発行事業者として登録する予定があるかを確認することも有効です。
- 条件交渉の余地: こちらの税負担が増える分を考慮した価格設定が可能かなど、契約前に条件を交渉できるかがポイントになります。
契約見直しの場合や価格交渉の考え方
免税事業者との取引を継続するものの、自社の税負担を軽減するために価格交渉や契約内容の見直しを検討するケースも出てきます。その際は、一方的な要求にならないよう、慎重に進める必要があります。
特に注意すべきなのが、独占禁止法や下請法です。自社が優越的な地位にある場合、取引価格を一方的に引き下げたり、インボイス制度に対応しないことを理由に取引を打ち切ったりすると、これらの法律に抵触するおそれがあります。
交渉を進める際は、以下のステップを踏むのが望ましいでしょう。
- 丁寧な情報提供: まず、インボイス制度の概要と、自社の方針について丁寧に説明し、理解を求めます。
- 相手の意向確認: 取引先である免税事業者が、今後課税事業者になる意向があるのか、免税事業者を継続するのかを確認します。
- 協議による着地点の模索: 自社の税負担が増える事実を伝えた上で、取引価格や条件について協議の場を設けます。経過措置による控除額なども考慮に入れ、双方にとって納得できる着地点を探る姿勢が不可欠です。
- 書面での合意: 交渉によって合意した内容は、後のトラブルを避けるためにも、覚書や変更契約書といった書面の形で残しておきましょう。
あくまで「交渉」であり、強制ではないという点を忘れてはいけません。良好な取引関係を維持するためにも、相手の立場を尊重したコミュニケーションを心がけましょう。
Q&A|インボイス制度と免税業者との取引に関するよくある質問
インボイス制度と免税事業者との取引について、実務上で抱きやすい疑問点をQ&A形式で解説します。
免税事業者が「うちは登録申請予定です」と言ってきた。いつまで待つべき?
取引先の免税事業者がインボイス発行事業者への登録を申請中、あるいは申請予定と伝えてきた場合の対応は、多くの事業者が悩むポイントです。明確な期限はありませんが、以下の点を踏まえて対応を検討しましょう。
まず、口頭での約束だけでなく、登録申請の意思を書面やメールなど記録に残る形で確認しておくことが望ましいです。その上で、インボイスの登録番号が通知されるまでの期間を考慮する必要があります。国税庁によると、登録申請から通知までの期間の目安は、e-Taxでの申請で約3週間、書面での申請で約1.5か月とされています(※申請件数により変動します)。
重要なのは、登録が完了するまでの期間に行われた取引については、原則として仕入税額控除が適用できないという点です。登録完了後に取引先からインボイス(適格請求書)を遡って発行してもらえるか、事前に双方で合意しておくことが不可欠です。
もし登録が間に合わない場合、その間の消費税相当額の負担をどうするか、経過措置を適用するのかといった点も話し合っておきましょう。結論として、「いつまで待つか」は事業者間の関係性や取引の重要度によりますが、リスク管理の観点から「〇月〇日までに登録番号をお知らせください」といった形で、目安となる期限を設けておくことをお勧めします。
インボイスが必要ない取引もある?免税業者でも控除できるケースは?
はい、一部の取引においては、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められる特例があります。これらの特例に該当する場合、取引の相手方が免税事業者であっても、買手は仕入税額控除を受けることが可能です。
インボイスの保存が不要となる主なケースは以下の通りです。
|
特例の名称 |
内容 |
具体例 |
|
公共交通機関特例 |
3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送 |
電車やバスの運賃 |
|
自動販売機・自動サービス機 |
3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの商品の購入等 |
自動販売機での飲料購入、コインロッカーの利用料 |
|
郵便切手類による郵便・貨物サービス |
郵便ポストに差し出された郵便・貨物サービス(郵便切手を対価とするもの) |
切手を貼って郵便ポストへ投函する郵便料金 |
|
出張旅費等特例 |
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当 |
従業員に支給する出張の日当や、実費精算する宿泊費 |
|
古物商等の特例 |
古物営業、質屋、宅地建物取引業を営む事業者が、インボイス発行事業者でない者から棚卸資産を仕入れる場合 |
古物商が一般消費者から古物を買い取る場合 |
これらの取引に該当する場合は、インボイスがなくても法定の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除が可能です。ただし、例えば同じ交通費でも、タクシー代や航空券代は3万円未満であってもこの特例の対象外であり、原則としてインボイスが必要となるため注意が必要です。
また、これらとは別に、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者などを対象に、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とする「少額特例」も設けられています。この特例も、取引相手が免税事業者である場合に活用できます。
まとめ
インボイス制度の開始により、免税事業者との取引では原則として仕入税額控除が受けられなくなります。経過措置を活用することで一時的な負担軽減は可能ですが、将来的には免税事業者との取引にかかる消費税をすべて自己負担することになります。取引先との信頼関係を大切にしながら、早めの情報共有や条件調整、経理体制の見直しなどを進めておくことが、スムーズな対応につながります。