インボイスは電子帳簿保存法に基づいた保存が必要?請求書の保存方法や期間を解説
更新日:2026.01.29
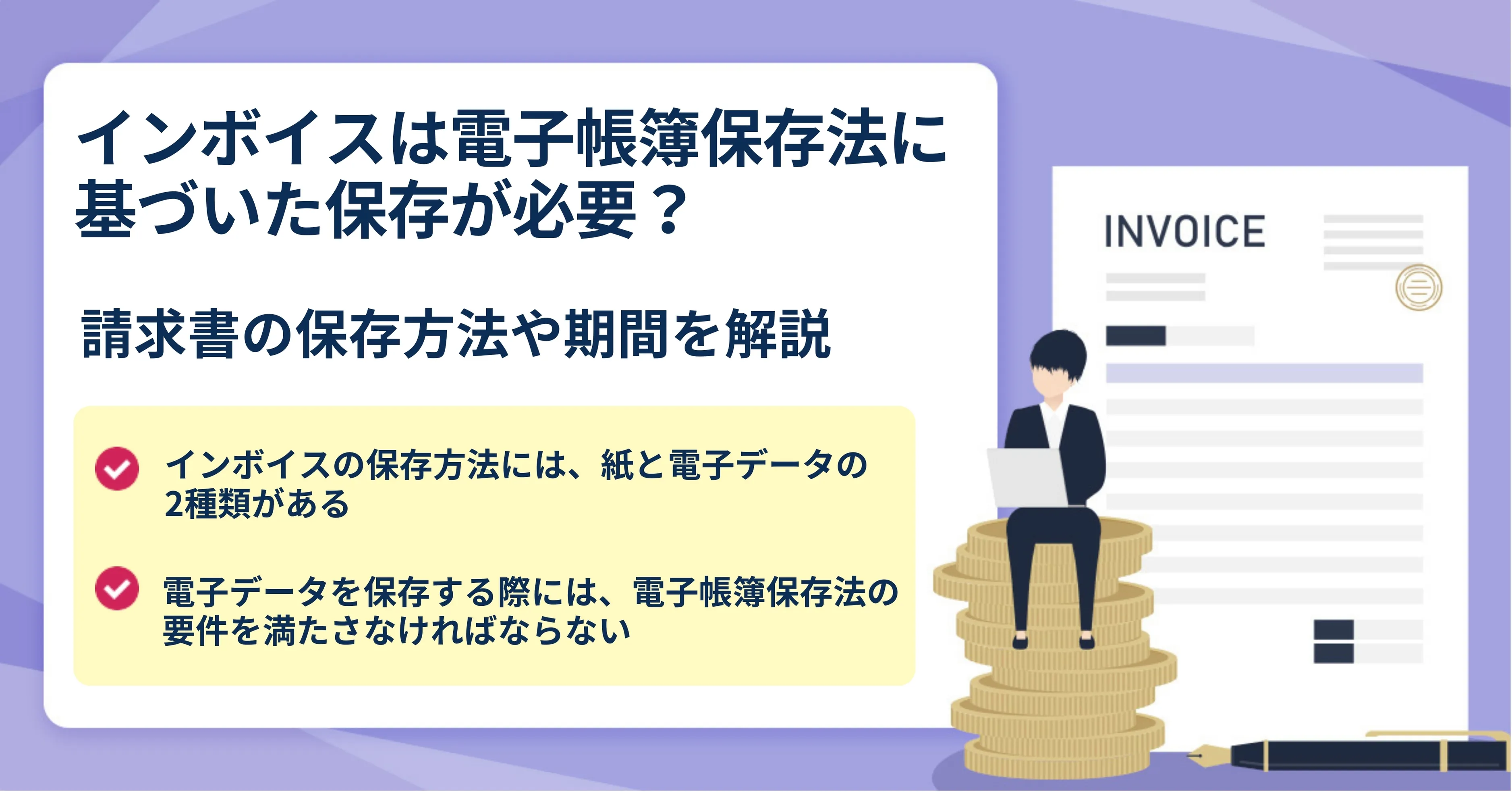
ー 目次 ー
2023年10月1日からインボイス制度が開始され、仕入税額控除を適用するためにはインボイス(適格請求書)の発行・保存が必要となりました。
インボイスの保存方法は、受領した形式によって異なります。とくに、電子データで受領したインボイスは電子帳簿保存法にしたがった保存が必要です。
保存方法を誤った場合は法律違反に該当する可能性があるため、法律の内容と保存方法をよく理解したうえで対応することが重要です。
本記事では、電子帳簿保存法に基づくインボイスの保存方法や保存期間について、インボイス制度と電子帳簿保存法の違いも交えて解説します。
インボイスの保存方法は受領した形式によって異なる
電子帳簿保存法では、受領したインボイスの形式によって保存方法が異なります。保存方法を誤ると、法律違反となる可能性があるため注意しなければなりません。
電子帳簿保存法に適切に対応するためには、各形式の保存方法を正しく理解することが重要です。
ここでは、受領した形式ごとに異なるインボイスの保存方法について解説します。
①電子データで受領したインボイスの保存方法
インボイス制度では、インボイスの保存形式に関する決まりはありません。しかし、電子帳簿保存法で定める電子取引に関しては、インボイスの電子データのままでの保存が義務付けられています。
そのため、PDFなど電子データとしてインボイスを受領した場合、電子帳簿保存法の要件にしたがって電子データのまま保存しなければなりません。
また、自社が電子データとして発行したインボイスの控えについても、保存する際の対応は同様です。
②紙で受領したインボイスの保存方法
紙で発行されたインボイスや控えは、紙のまま保存するか、または電子データで保存するかを選択できます。どちらの形式にも適切に対応するために、保存方法を理解しておくことが重要です。
ここでは、紙で受領したインボイスの保存方法を2パターンに分けて解説します。
紙のまま保存する場合は今までどおりで問題ない
紙で受領したインボイスやその控えは、そのまま紙の状態で保存できます。紙で保存できる請求書や領収書の例は以下のとおりです。
- 郵送したインボイスの控え
- インボイスの要件を満たすレシート
- インボイスの要件を満たす交通機関の領収書
紙のままインボイスを保存する際は日付や取引先ごとに分けて、ファイリングしましょう。
電子データで保存する場合はスキャナ保存の要件を満たす必要がある
インボイスを電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法に対応するためにスキャナ保存の要件を満たす必要があります。スキャナ保存できる書類の例は以下のとおりです。
- 請求書
- 領収書
- 納品書
- 契約書
- 見積書
電子帳簿保存法に対応するためにはスキャナ保存の要件を満たし、書類の内容が正しいことを証明しなければなりません。また、電子データで保存する際は、スキャナ保存に対応した書類保存システムを利用することが一般的です。
インボイス制度と電子帳簿保存法とは?それぞれの概要と違いを紹介
インボイス制度に対応するためには、電子帳簿保存法との関係性を理解することが重要です。
それぞれの概要を正しく理解していないと、インボイスの保存方法が法律違反に該当する可能性があります。そのため、概要と違いを把握して、インボイスを適切に取り扱いましょう。
ここでは、インボイス制度と電子帳簿保存法の概要や、それぞれの違いについて解説します。
インボイス制度では電子データを紙で保存できるケースがある
電子帳簿保存法では、電子取引で受領した書類を電子データのままで保存しなければなりません。そのため、所得税法や法人税法におけるインボイスには、電子データでの保存が求められます。
一方、インボイス制度では、インボイスの保存形式が定められていません。また、消費税法では電子取引において電子データ保存を原則としていますが、紙として出力したデータの保存が認められています。
このように、所得税法や法人税法、消費税法では、電子データの取扱いが異なるため注意しましょう。
電子帳簿保存法では電子取引したデータをそのまま保存する必要がある
電子帳簿保存法では、電子取引によって受領したインボイスに関する書類はすべて電子データ保存が必要です。そのため、法律で定められた要件にしたがって、インボイスを保存しなければなりません。電子帳簿保存法に対応するための要件は以下のとおりです。
- 改ざん防止のための措置をとる
- 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付ける
- 日付・金額・取引先の3要素で検索できるようにする
上記の要件を満たしたうえで、インボイスを保存することが重要です。
インボイス制度における請求書の保存期間とは?
インボイスの保存期間は、個人事業主・法人ともに7年間が原則です。ただし、法人では状況によって、保存期間が10年まで延長される場合があります。
インボイス制度に適切に対応するためには、インボイスの保存期間を正しく理解することが重要です。
ここでは、インボイス制度における請求書の保存期間について解説します。
個人・法人を問わずインボイスの保存期間は7年間
インボイス制度では個人事業主・法人を問わず、受領したインボイスやその控えの保存期間は7年間と定められています。
法律で定められた保存期間は長く、規模の大きい企業では膨大な数のインボイスを保存することになります。
そのため、インボイスを保存する際は、紙ではなく電子データによる保存を検討すべきです。電子データ化すれば管理コストを抑えられるため、経理業務の負担軽減につながります。
【例外】法人で欠損金がある場合、インボイスの保存期間は10年間
法人が欠損金の繰越控除を適用する場合は、インボイスの保存期間が10年間まで延長されます。
欠損金の繰越控除とは、赤字分を次年度に持ち越して節税できる仕組みのことです。繰越控除の適用によって、当期の所得金額の50%を限度に損金算入できます。
また、会社法でも帳簿や計算書類、明細などの保管は10年間と決められています。そのため、会計や税務関係の書類は、基本的に10年間の保管が必要であると覚えておくと良いでしょう。
インボイス制度と電子帳簿保存法に対応できるシステムの導入がおすすめ!
インボイス制度と電子帳簿保存法は、それぞれ異なる制度と法律です。しかし、インボイス制度に基づいて発行されるインボイスは、電子帳簿保存法の対象となります。
経理業務の負担を軽減するためには、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応できるシステムの導入がおすすめです。以下のようなシステムを導入すれば、経理業務を効率化できます。
- OneVoice明細
- 楽々クラウド電子帳簿保存サービスby ClimberCloud
- invox電子帳簿保存
- バクラク電子帳簿保存
- OPTiM 電子帳簿保存
それぞれ利用できる機能が異なるため、必要な機能を整理したうえで自社にあったシステムを選びましょう。
まとめ|インボイスの保存方法と保存期間を理解して、適切に対応しよう
本記事では、電子帳簿保存法に基づくインボイスの保存方法や保存期間について、インボイス制度と電子帳簿保存法の違いも交えて解説しました。
インボイスの保存方法には、紙と電子データの2種類があります。とくに、電子データでインボイスを保存する際には、電子帳簿保存法の要件を満たさなければなりません。
インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応するためには、それぞれの要点を理解することが重要です。要点をおさえて適切に対応すれば、法律違反に該当せずインボイスを保存できます。
本記事を参考にして、インボイスの保存方法と保存期間を正しく理解しましょう。










