副業で年間20万円以下ならインボイス制度は必要?その影響や対応方法を解説
更新日:2025.12.24
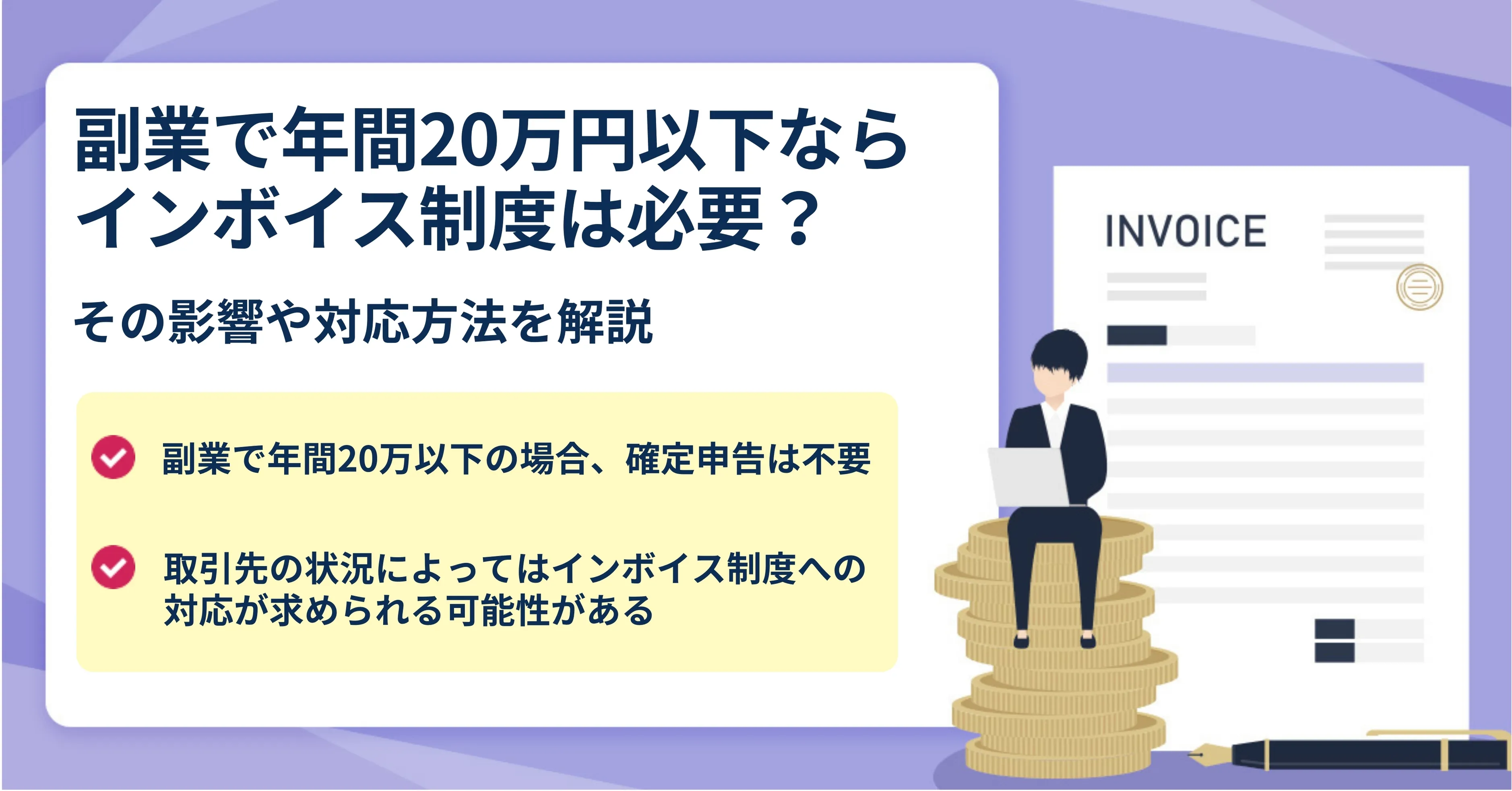
ー 目次 ー
インボイス制度の施行にともない、すべての事業者を対象として消費税に関する対応を求めています。この制度は企業や個人事業主だけに限らず、年間売上高が20万円以下の副業の事業者にも関係します。
インボイス制度に登録していないと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、契約の中断や減額交渉といったリスクも考えられるでしょう。しかし、登録すると消費税の納付義務が発生するなどの影響もあります。
このようなことから、インボイス制度のルールや影響を正しく理解しておくことが必要でしょう。
本記事では、年間20万円以下の副業の方に関係するインボイス制度について、基本的なルールや影響・登録方法を交えて解説します。
【前提】インボイス制度とは消費税に関する計算や請求書作成・保存のルール
インボイス制度とは、取引内容や消費税率・消費税額などの所定の要件を記載した請求書を発行し、保存しておくルールのことです。
適格請求書(インボイス)を発行・保存することで、消費税額が明確になり、取引先の課税事業者は仕入税額控除を受けられます。
インボイスを発行するためには、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。制度のルールにより、発行事業者のみインボイスの発行が許可されているためです。
取引先との関係性によってインボイス制度の必要性が異なるため、状況にあわせてインボイス制度に対応すべきかの検討が必要です。
【重要】インボイス制度に登録したら、副業で年間20万円以下でも申告が必要
副業で年間20万円以下の収入しかない場合、通常は所得税の確定申告が不要となります。しかし、インボイス制度に登録すると課税事業者となるため、収入の金額に関係なく消費税を納める必要があります。
たとえ副業の年間売上が20万円以下でも、インボイス登録をした場合は、消費税の申告と納付の義務が発生します。また、住民税についても同様に申告・納付する義務があります。
申告を怠ると税務署の調査対象になり、後から延滞税が課せられる可能性もあるので注意が必要です。
|
納付が必要な税金 |
納付が不要な税金 |
|
|
副業の事業者が受けるインボイス制度による影響とは?
インボイス制度は、副業の事業者にも大きな影響を与えます。「自分には関係ない」と考えて適切に対応しないと、契約の中断や予期せぬ税負担など、深刻な影響を及ぼす可能性があるでしょう。
トラブルを回避するためには、副業スタイルや取引先の特性を踏まえて、具体的な影響を正確に理解することが必要です。
ここでは、副業の事業者が受けるインボイス制度による影響について解説します。
- 取引が減少する可能性がある
- 事務負担が増える
- 消費税の納付が必要となる
- 登録番号と本名がサイト上に公開される
①取引が減少する可能性がある
適格請求書(インボイス)を発行できないと取引相手に敬遠されるおそれがあります。取引先が「仕入税額控除」を活用するためには、インボイスを受け取る必要があるためです。
インボイスがないと仕入税額控除が活用できないため、取引先から契約の継続を再検討される可能性があります。
また、同業他社がすでにインボイス制度に登録を済ませている場合、契約の比較検討の際に不利になることもあるでしょう。
②事務負担が増える
インボイス制度では、請求書の管理や帳簿の記録方法など、細かいルールが定められています。インボイス制度の施行によって、これまでの作業にくわえて新たに対応することが多くなるため、事務作業の負担が増加します。
対応すべき事務作業は、以下のとおりです。
- インボイスに対応した請求書の作成
- 請求書のフォーマット変更
- 請求書の保存・管理
とくに副業の事業者であれば、本業との両立で時間に余裕がない中で事務作業をこなすのは大変でしょう。
③消費税の納付が必要となる
もともと免税事業者であれば、売上にかかる消費税を納める必要はありませんでした。しかし、発行事業者になると、年間売上がたとえわずかでも消費税を納める義務が発生します。
納付の際に仕入税額控除を受けられますが、免税事業者と比べると税負担が増えてしまうため総体的な事業コストがかかってしまいます。
このようなことから、まだ売上が大きくない事業者の場合は慎重に検討しましょう。
④登録番号と本名がサイト上に公開される
インボイス発行事業者になると、国税庁が運営する公表サイトに事業者の登録番号と本名が掲載されます。副業を密かにやりたい人にとっては心理的ハードルとなるでしょう。
ただし、このサイトは発行番号で検索をかけるため、名前から特定することは困難です。名前で検索しても表示されないため、直接的に副業の存在が発覚する可能性は低いといえるでしょう。
しかし、なにかしらの理由で自身の登録番号が知られた場合には、サイトで確認できてしまうため注意が必要です。
インボイス制度の2つの登録方法と手順は?
インボイス制度に登録する方法は電子と書面の2種類があります。それぞれで登録方法や番号が届く期間が異なります。
適切な登録方法を知らないまま進めると、手続きでミスを起こしたり、準備が間に合わずに取引先の要望に応えられなくなったりするリスクがあります。
インボイス制度の対応に間にあわせるためには、これから正しい手順を理解し、必要な準備をはじめることが重要です。
ここでは、インボイス制度の2つの登録方法と手順を解説します。
①電子申請(e-Tax)での登録手順
電子申請(e-Tax)によるインボイス制度の登録は、以下の手順で進めます。
- e-Taxソフトからログインする
- 利用者識別番号を取得する
- 必要事項を入力する
- 電子署名する
- 通知を確認する
申請にはマイナンバーカード、または通知カードと身元確認書類を用意する必要があります。
電子申請はスマートフォンから手続きができるため、いつでも登録申請が可能です。また、申請から1か月ほどで登録完了となり、書面申請と比べて短いという利点があります。
②書面での登録手順
インボイス制度を書面申請したい場合の手続きは、以下のとおりです。
- 国税庁の公式サイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードする
- 申請書に法人名、所在地、代表者情報など必要事項を記入する
- 記入済みの申請書を、所轄の税務署またはインボイス登録センターに郵送する
- 通常、申請から約1.5か月後に「登録通知書」が郵送されるため保管する
郵送される通知書は再発行できないため、紛失しないよう注意しましょう。
副業が年20万円以下の事業者がインボイス制度に対応する際のよくある質問
最後に、年20万円以下の副業事業者がインボイス制度に対応する際によくある質問について解説します。
①副業の収入が年間20万以下ならインボイスに登録してもばれない?
インボイス制度に登録しても会社に直接的にばれる可能性は低いでしょう。
しかし、登録番号を知られてしまい、国税庁の公式サイトで検索された場合は、副業が発覚する可能性があります。
②副業でもインボイスは必須?
インボイス制度そのものは任意のため、事業者の状況にあわせて検討しましょう。
最終的には自分の副業スタイルと取引相手の要望にあわせて判断することが大切です。
③副業で年間20万以上稼いだ場合、インボイスで支払う税金はいくら?
インボイス制度では、税率の区分によって支払う金額が変動します。まず、売上高を10%と8%の税区分ごとにわけます。標準税率の10%に区分された金額には7.8%、軽減税率の8%に区分された場合には6.24%を掛けて消費税の算出が可能です。
たとえば、IT系の副業で年間20万円を稼いだ場合は、「20万円×7.8%」となり、消費税は15,600円です。(※仕入税額控除を含めない場合)
④インボイス制度に登録した場合、年間20万円以下でも青色申告したほうがいい?
インボイス制度は消費税の納付に関する制度であり、青色申告や白色申告といった所得税に関する確定申告の方式と関連はありません。そのため、インボイス制度に登録したからといって、青色申告する必要はないでしょう
一方で、青色申告には特別控除が受けられるなど税制上のメリットがあるため、青色申告の利用がおすすめです。
まとめ|副業で年20万円以下でも状況によりあわせインボイスの登録が必要
本記事では、年間20万円以下の副業の方に関係するインボイスについて、基本的なルールや影響・登録方法を交えて解説しました。
副業の年間収入が20万円以下であっても、取引先の状況によってはインボイス制度への対応が求められる可能性があります。とくに法人との取引が多い事業者は注意が必要です。
インボイス制度の基本的なルールや影響を正しく理解して、現在の状況にあわせて検討しましょう。










