送料はインボイス対象?消費税の扱いや請求書の書き方まとめ
更新日:2025.12.06
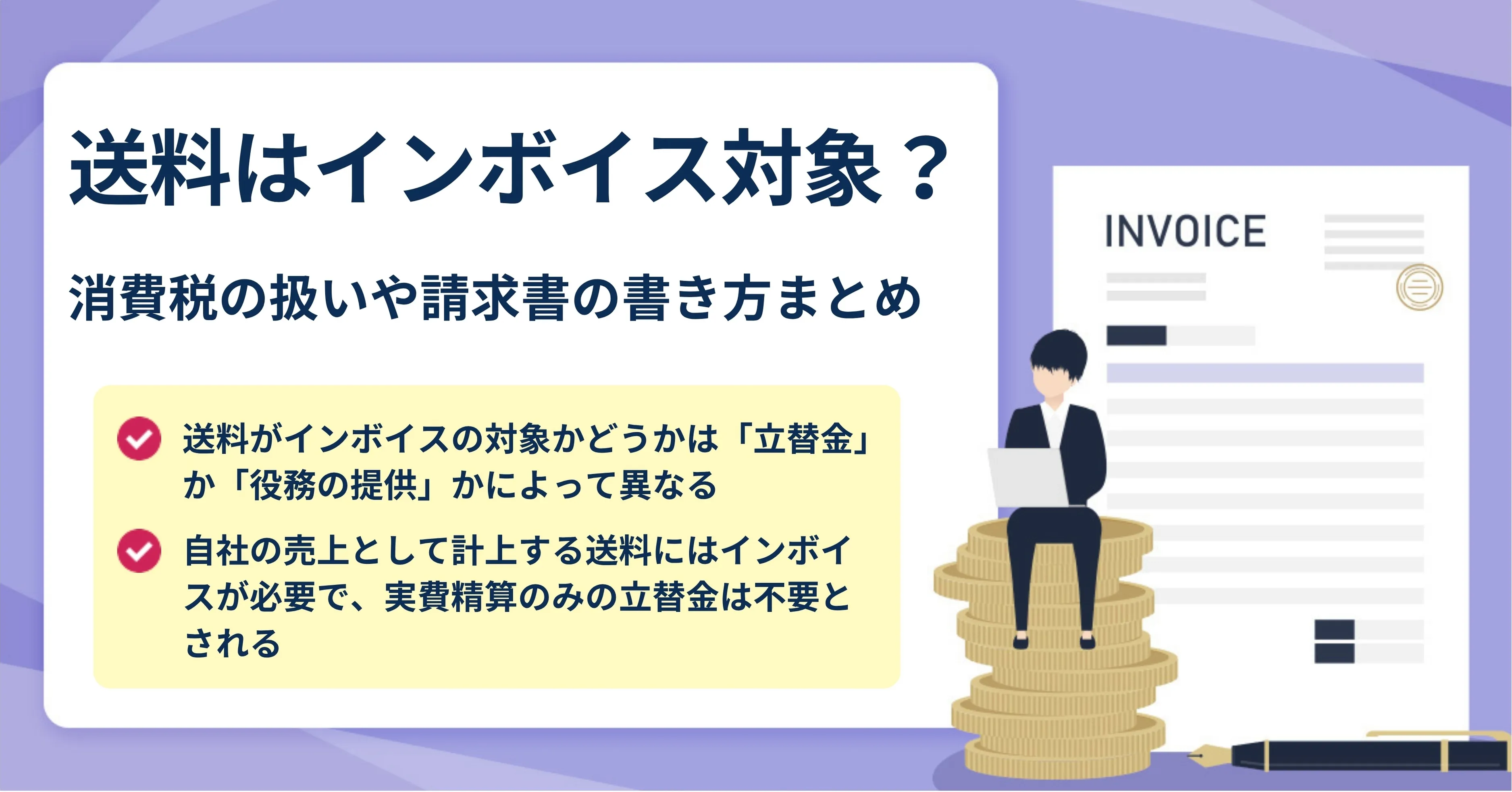
ー 目次 ー
インボイス制度における「送料」の扱いについて、迷われたことはありませんか?請求時の送料が「実費の立替え」なのか、それとも「サービスの一環としての提供」なのかによって、消費税の課税やインボイス発行の必要性が変わってきます。本記事では、この判断のポイントをわかりやすく整理し、売り手の請求書記載方法や、買い手が仕入税額控除を受ける際の注意点についても、具体例を交えて丁寧に解説いたします。
送料まわりのモヤモヤを、すっきり解消していただければ幸いです。
送料はインボイスの対象になる?制度上の基本ルールを整理
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、事業者は請求書や領収書の扱いに多くの変更を求められています。この章では、送料がインボイスの対象となるのか、制度上の基本的なルールと考え方を整理して解説します。
そもそもインボイス制度とは?簡単におさらい
まず、インボイス制度の基本について簡単におさらいしましょう。インボイス制度とは、複数税率(標準税率10%・軽減税率8%)に対応したうえで、買い手が仕入税額控除を受けるための新しい仕組みです。買い手側が消費税の仕入税額控除を適用するには、原則として、売り手である適格請求書発行事業者が交付した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。
|
項目 |
概要 |
|
制度の正式名称 |
適格請求書等保存方式 |
|
目的 |
売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額などを伝えること |
|
適格請求書(インボイス)とは |
登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額など、法律で定められた事項が記載された請求書や領収書などの書類 |
|
買い手の対応 |
原則、インボイスの保存が仕入税額控除の適用要件となる |
送料は場合によっては対象!インボイス制度における送料の基本的な考え方
本題である「送料はインボイスの対象になるか」という問いに対する答えは、「場合による」です。送料が課税取引に該当する場合、インボイスの交付が必要になります。具体的には、売り手が送料をどのように扱うかによって、インボイスの要否が決まります。
ポイントは、送料を「役務の提供の対価」として請求するのか、それとも運送業者に支払った費用をそのまま請求する「立替金」として処理するのか、という点です。自社の売上として計上する送料は課税対象となり、インボイスへの記載が必要になると覚えておきましょう。
|
送料の扱い |
インボイスの要否 |
概要 |
|
役務の提供の対価として請求 |
必要 |
商品代金とは別に、梱包や発送手続きなどのサービス対価として送料を設定する場合。課税売上となる。 |
|
立替金として処理 |
原則不要 |
運送会社に支払った送料の実費を、そのまま買い手に請求する場合。自社の売上には計上しない。 |
このように、送料の扱い方次第で消費税や記載方法が異なるため、次章では具体的なケースに分けて整理します。
送料の消費税は課税?非課税?判断ポイントをわかりやすく解説
インボイス制度において、送料の消費税の扱いは一律ではありません。「自社の売上として送料を請求するのか」、それとも「運送会社に支払った実費を単純に立て替えているだけなのか」によって、課税対象になるかどうかが決まります。ここでは、それぞれのケースについて判断ポイントを詳しく見ていきましょう。
送料が課税となるケース!「役務の提供」として扱う場合とは
販売する商品やサービスとは別に、送料を「荷物を発送する」という自社のサービス(役務の提供)の対価として請求する場合、その送料は消費税の課税対象となります。この場合、送料は商品代金と同様に自社の「課税売上」として計上します。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 実際の送料に梱包手数料などを上乗せして請求する
- 配送地域にかかわらず「全国一律〇〇円」のように、独自の送料を設定している
- 「送料無料」として、商品代金に送料相当額を含めて販売している
これらのケースでは、送料部分も事業者が提供するサービスの対価とみなされるため、消費税がかかります。インボイス発行事業者は、送料を含めた合計金額に対して消費税を計算し、適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。
送料が非課税になるケースは?運送業者の実費をそのまま請求する場合
運送業者(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)へ支払った送料を、そのまま同額で取引先に請求する場合は「立替金」として扱われます。この場合、送料は自社の売上にはならないため、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。
この処理を行うための条件は、以下の通りです。
- 運送業者に支払った実費を、手数料などを上乗せせず同額で請求している
- 立替金であることが契約書や請求書などで明確にされている
この場合、自社が発行する請求書では、送料を消費税の計算対象から除外して記載します。ただし、買い手側がその送料について仕入税額控除を受けるためには、原則として、実際に運送サービスを提供した運送業者が発行したインボイス(またはそのコピー)が必要になる点に注意が必要です。
送料の消費税の扱いをまとめると、以下のようになります。
|
項目 |
課税となるケース(役務の提供) |
非課税となるケース(立替金) |
|
送料の扱い |
自社の売上として請求(手数料上乗せ、一律料金など) |
運送業者に支払った実費をそのまま請求 |
|
消費税 |
課税対象 |
課税対象外(不課税) |
|
経理処理 |
課税売上 |
立替金 |
|
自社発行のインボイス |
送料も消費税計算に含めて記載 |
送料は消費税計算に含めず、「立替金」として別途記載 |
売り手向け!送料を含めたインボイス(適格請求書)の書き方
商品を販売し、送料を請求する場合、売り手はインボイス制度に対応した適格請求書を発行する必要があります。送料をどのように記載すればよいのか、具体的な書き方と注意点を解説します。
送料を請求書に記載する具体的な方法!
送料をインボイスに記載する方法は、主に「商品代金と送料を分けて記載する」方法と「商品代金に送料を含めて記載する」方法の2つがあります。どちらの方法を選択しても問題ありませんが、取引先にとって分かりやすい方法を選ぶことが大切です。それぞれのケースについて見ていきましょう。
商品代金と送料を分けて記載する場合
最も一般的で推奨されるのが、請求書の明細欄で商品代金と送料を別の項目として記載する方法です。この方法のメリットは、買い手側が何にいくらかかったのかを明確に把握できる点にあります。インボイスの要件を満たすためには、送料が課税対象(役務の提供)である場合、その金額と適用税率(通常10%)、消費税額を明記する必要があります。
例えば、「商品A 10,000円」「送料 880円」のように、品目を分けて記載します。これにより、取引の透明性が高まり、買い手側の経理処理もスムーズになります。
商品代金に送料を含めて記載する場合
いわゆる「送料込み」の価格で商品を販売する場合、商品代金に送料を含めて請求書に記載します。この場合、明細には「商品B(送料込み) 10,880円」のように記載するか、あるいは送料の項目自体を設けず、商品代金として合計額を記載します。
注意点として、送料を含めた合計金額に対して適用税率(10%)と消費税額を計算し、インボイスに正しく記載する必要があります。請求書に送料の内訳が記載されないため、事前に取引先と「送料込み」の価格である合意が取れていることが望ましいでしょう。
送料のインボイス書き方!具体的な記載例つき
ここでは、インボイスの要件を満たした、送料の具体的な記載例を紹介します。今回は、最も分かりやすい「商品代金と送料を分けて記載する場合」の例を見ていきましょう。
以下の表は、適格請求書の記載事項のうち、特に取引内容や金額に関する部分を抜粋したものです。
|
内容 |
単価(税抜) |
数量 |
金額(税抜) |
備考 |
|
商品C(※) |
5,000円 |
2 |
10,000円 |
軽減税率対象 |
|
送料 |
1,000円 |
1 |
1,000円 |
|
税率 |
対象金額(税抜) |
消費税額 |
|
10%対象 |
1,000円 |
100円 |
|
8%対象(※) |
10,000円 |
800円 |
ご請求金額(合計): 11,900円
この例のように、インボイスでは以下の点が重要です。
- 軽減税率の対象品目である場合は、その旨(例:「※」印など)を明記する。
- 送料を課税取引として扱う場合、商品代金とは別に項目を立てて記載する。
- 「10%対象」「8%対象」のように、税率ごとに合計した取引金額(税抜または税込)と、それに対する消費税額をそれぞれ記載する。
この形式で作成することで、インボイスの要件を確実に満たすことができます。
買い手向け!送料の仕入税額控除を受けるためのポイント
商品やサービスを購入した際に支払った送料も、インボイス制度における仕入税額控除の対象となります。ここでは、買い手として知っておくべきポイントを解説します。
受け取った請求書の送料部分の確認点
売り手から送料込みの請求書を受け取った場合、その送料部分について仕入税額控除を適用するには、請求書が適格請求書(インボイス)の要件を満たしていることが大前提です。特に送料に関しては、以下の点を確認しましょう。
送料が商品代金とは別に記載されている場合、その送料が課税取引として扱われているかどうかが重要です。売り手が送料を「役務の提供の対価」として課税売上げに計上している場合、その送料は仕入税額控除の対象となります。請求書に送料の消費税率や消費税額が明記されていれば、課税取引と判断できます。
一方、売り手が送料を「立替金」として処理している場合、その送料は売り手の課税売上げにはならず、買い手側も仕入税額控除の対象にすることはできません。ただし、この場合、買い手は運送会社から直接、自身が宛名となるインボイスを受け取ることで控除が可能になるケースがあります。
受け取った請求書で確認すべき具体的な項目は以下の通りです。
|
確認項目 |
チェックする内容 |
|
適格請求書発行事業者の登録番号 |
請求書発行者のTから始まる13桁の登録番号が記載されているか。 |
|
送料の税率区分 |
送料に適用される消費税率(10%)が正しく記載されているか。 |
|
送料にかかる消費税額 |
税率ごとに区分した消費税額等のうちに、送料分の消費税額が含まれているか。または、送料に対しても消費税額が個別に記載されているか。 |
|
取引内容 |
「送料」という品目が明確に記載されているか。(軽減税率の対象品目と混同しないように「※」印などで注記されている場合もあります) |
これらの記載がなければ、仕入税額控除が認められない可能性があります。不明な点があれば、取引先に確認することが重要です。
取引先が免税事業者だった場合の送料の扱い
取引先(売り手)が消費税の免税事業者である場合、その取引先は適格請求書発行事業者として登録できないため、インボイスを発行することができません。したがって、免税事業者から受け取った請求書では、原則として送料にかかる消費税の仕入税額控除は適用できません。
ただし、インボイス制度の導入に伴う急激な変化を緩和するため、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる「経過措置」が設けられています。送料もこの経過措置の対象です。
経過措置の期間と控除可能な割合は以下の通りです。
|
期間 |
控除可能な割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
この経過措置の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 区分記載請求書等と同様の事項(発行者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、受領者の氏名または名称など)が記載された請求書等を保存すること。
- 経過措置の適用を受ける課税仕入れであることを帳簿に記載すること。(例:「80%控除対象」など)
取引先が免税事業者であるかどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索することで確認できます。請求書に登録番号の記載がなければ、免税事業者である可能性が高いと考えられます。
Q&A|インボイスと送料に関するよくある質問
特にお問い合わせの多い質問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
着払いの送料はインボイスの対象になりますか?
商品の代金を着払いで受け取る場合、送料の扱いは売り手と買い手で異なります。結論から言うと、商品の売り手は着払いの送料についてインボイスを発行する必要はありません。
着払いでは、買い手が運送業者へ直接送料を支払います。そのため、送料は売り手の売上にはならず、運送業者の売上となります。したがって、インボイスの発行義務も運送業者にあります。
買い手が送料について仕入税額控除を受けるためには、料金を支払った運送業者が発行するインボイス(またはレシートなどの簡易インボイス)が必要になります。各当事者の対応は以下の通りです。
|
立場 |
対応 |
備考 |
|
商品の売り手 |
送料分のインボイス発行は不要 |
商品代金についてのみインボイスを発行します。 |
|
商品の買い手 |
運送業者からインボイスを受領・保存 |
仕入税額控除を受けるために必要です。運送業者が適格請求書発行事業者であるか確認しましょう。 |
|
運送業者 |
買い手に対してインボイスを発行 |
送料が運送業者の売上となるため、発行義務を負います。 |
送料無料の場合インボイスの記載は必要ですか?
ECサイトなどでよく見られる「送料無料」の場合、インボイスに送料を別途記載する必要はありません。
会計上、「送料無料」は送料が0円なのではなく、「送料を商品代金に含めて請求している」と解釈されるのが一般的です。そのため、売り手は送料を含んだ商品代金の総額をインボイスに記載し、その金額に対応する消費税率と消費税額を明記すれば問題ありません。
請求書の明細欄に「送料 0円」と記載することも可能ですが、インボイスの必須要件ではないため、記載しなくても制度上の問題はありません。商品代金と消費税額が正しく記載されていれば、買い手は仕入税額控除を受けることができます。
海外発送の送料にはインボイスは必要?消費税の課税対象になる?
海外への商品発送にかかる送料は、消費税の「輸出免税」の対象となるため、原則として国内のインボイス制度の対象外です。
インボイス(適格請求書)は、国内の消費税の課税取引において、仕入税額控除を適用するために必要な書類です。一方、輸出として行われる資産の譲渡や役務の提供は、消費税が免除(税率0%)されます。これには、国際郵便や国際宅配便の送料も含まれます。
したがって、海外発送の送料については消費税が課税されないため、売り手はインボイスを発行する義務がありません。ただし、取引の証憑として請求書や納品書は発行するのが一般的です。その際は、摘要欄などに「輸出免税取引」と記載しておくと、取引内容が明確になります。
まとめ
送料が「役務の提供」として扱われる場合は課税対象となり、インボイスへの記載が必要です。一方、運送会社への実費を「立替金」として請求する場合は不課税となります。正しい処理を行うためには、取引の実態を踏まえた対応が大切です。売り手・買い手それぞれの立場で、インボイスの記載内容や確認ポイントを押さえておくことで、制度に対応しつつスムーズな経理処理が可能になります。日々の業務に少しでもお役立ていただければ幸いです。










