家賃の請求書には原則インボイスは不要!ポイントや例外をわかりやすく解説
更新日:2025.12.07
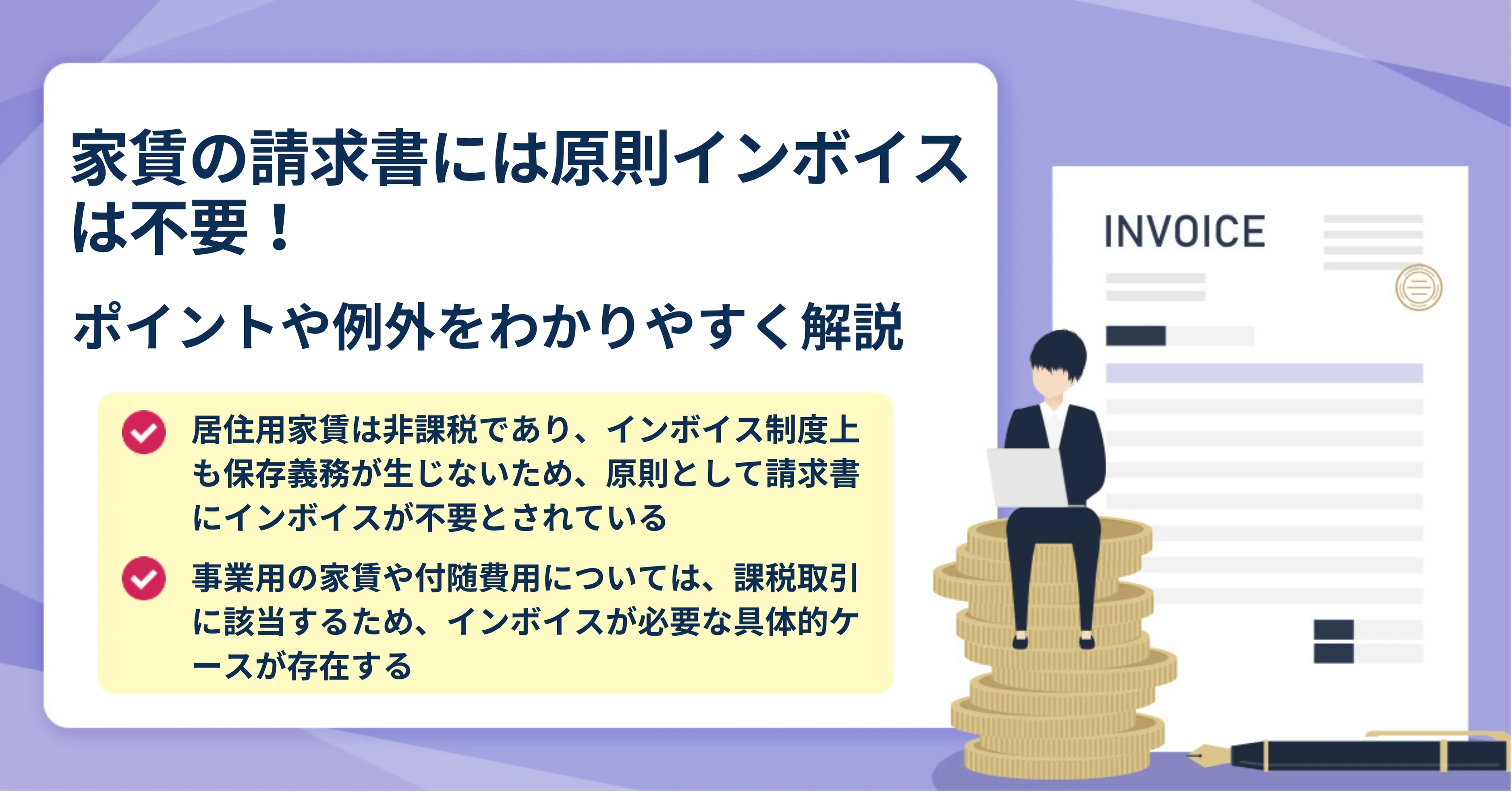
ー 目次 ー
インボイス制度の開始以降、「家賃の請求書にもインボイスが必要なの?」と戸惑われた方も多いのではないでしょうか。実は、家賃の請求書には原則としてインボイスは不要です。ただし、すべてのケースで不要というわけではありません。
本記事では、制度上インボイスが求められる場合や、インボイス制度と家賃の関係を基本から丁寧に解説しつつ、貸主・借主それぞれの立場で知っておくべきポイントや例外も具体的にご紹介します。
家賃とインボイス制度の関係を基本から解説
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、家賃の請求や支払いにも影響を与える可能性があります。まずは、インボイス制度の基本と、家賃における消費税の基本的な考え方について理解を深めましょう。これにより、家賃とインボイス制度がどのように関わってくるのか、その全体像を掴むことができます。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。この制度のもとでは、買手側が仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手側(適格請求書発行事業者)から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。
適格請求書とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類やデータのことです。具体的には、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などの記載が求められます。適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
課税家賃と非課税家賃のちがいを押さえよう
家賃と一口に言っても、その用途によって消費税の取り扱いが異なります。この違いが、インボイス制度への対応を考える上で非常に重要なポイントとなります。主に「居住用家賃」と「事業用家賃」に分けられ、それぞれ消費税の課税対象かどうかが異なります。
|
家賃の種類 |
概要 |
消費税の扱い |
|
居住用家賃 |
アパートやマンションなど、人が住むための物件の家賃。契約期間が1ヶ月未満の場合などを除き、基本的に非課税です。 |
非課税(一部例外あり) |
|
事業用家賃 |
事務所、店舗、工場、倉庫など、事業のために使用される物件の家賃。こちらは消費税の課税対象となります。 |
課税 |
このように、家賃が居住用か事業用かによって消費税の課税関係が異なるため、インボイス(適格請求書)の必要性も変わってきます。この点をしっかり押さえておくことが、インボイス制度への適切な対応の第一歩となります。
家賃の請求書にインボイスは原則不要!その理由とは
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者に影響を与えています。家賃の支払いにおいても、請求書にインボイスが必要なのかどうか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げますと、家賃の請求書には原則としてインボイスは不要です。この章では、その主な理由と関連するポイントをわかりやすく解説します。
居住用家賃は消費税が非課税のためインボイス不要
家賃の請求書にインボイスが原則不要である最大の理由は、居住用家賃が消費税の非課税取引に該当するためです。日本の消費税法では、住宅の貸付は非課税取引と定められています。具体的には、契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
消費税が課税されない取引(非課税取引)については、売手(貸主)はインボイス(適格請求書)を発行する義務がありません。同様に、買手(借主)も、非課税仕入れとなるため仕入税額控除の対象外となり、インボイスの保存は不要です。
したがって、アパートやマンション、戸建てといった個人が住むための物件の家賃に関しては、貸主が課税事業者であっても免税事業者であっても、借主に対してインボイスを発行する必要はありません。借主側も、支払った家賃についてインボイスを求める必要はないのです。
帳簿保存のみで仕入税額控除が可能なケースも
インボイス制度において、一部の取引には帳簿保存だけで仕入税額控除が認められる特例もありますが、家賃取引での適用は限られます。
ただし、家賃取引においてこの特例が適用される場面は限定的です。前述の通り、居住用家賃は非課税取引であるため、そもそも仕入税額控除の対象外であり、この特例を考慮する必要はありません。事業用家賃(事務所や店舗など)は課税取引となるため、原則としてインボイスが必要となります。
参考として、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる主なケースには以下のようなものがあります。
|
対象となる取引の例 |
備考 |
|
3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送 |
例:電車代、バス代など |
|
3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等 |
例:自動販売機での飲料購入など(※インボイス対応の自動販売機を除く) |
|
郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る) |
|
|
従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(通常必要と認められる範囲内の金額) |
社内規程等に基づく実費精算など |
これらの取引で帳簿保存のみで仕入税額控除を受けるためには、帳簿に「取引の相手方の氏名または名称」「取引年月日」「取引内容(軽減税率の対象である旨)」「支払対価の額」に加え、「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨(例:3万円未満の鉄道料金、出張旅費特例など)」を記載する必要があります。
繰り返しになりますが、居住用家賃は非課税取引であるため、これらの特例とは関係なくインボイスは不要です。事業用家賃の場合は、原則としてインボイスの保存が必要となる点を押さえておきましょう。
要注意!家賃関連の請求書でインボイスが必要なケース
原則として居住用家賃にはインボイス(適格請求書)が不要ですが、事業に関連する家賃やそれに付随する費用については、インボイスが必要となる場合があります。借主が仕入税額控除を受けるためには、これらのケースを正しく理解しておくことが重要です。ここでは、特に注意すべき具体的なケースについて詳しく解説します。
事務所家賃 (事務所や店舗)の請求書とインボイス
事業目的で借りている事務所、オフィス、店舗などの家賃は、消費税の課税対象となります。そのため、借主である課税事業者が支払った家賃について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として貸主からインボイスの交付を受ける必要があります。
貸主が適格請求書発行事業者である場合、借主の求めに応じてインボイスを発行する義務があります。このインボイスには、登録番号、適用税率、消費税額などの法定記載事項が明記されていなければなりません。契約書だけではインボイスの要件を満たさない場合が多いため、別途請求書や通知書といった形でインボイスの交付を求めることが一般的です。
もし貸主が免税事業者である場合、インボイスの発行はできません。この場合、借主は原則としてその家賃にかかる消費税額の仕入税額控除を受けることができませんが、インボイス制度開始後の一定期間は、経過措置により一定割合の控除が認められています。詳細は後述の借主向けポイントで解説します。
駐車場代・社宅家賃におけるインボイスの対応
駐車場代や社宅の家賃についても、インボイスの要否は消費税の課税関係によって異なります。それぞれのケースについて具体的に見ていきましょう。
駐車場代のインボイス
事業の用に供するために借りている駐車場の賃料は、原則として消費税の課税対象となります。したがって、借主が仕入税額控除を受けるためには、貸主からのインボイスが必要です。例えば、営業車用の駐車場や、来客用の駐車場などが該当します。
ただし、駐車場であっても以下のような場合は消費税が非課税となるため、インボイスは不要です。
- 住宅の貸付けと一体となっている駐車場代で、1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられるなど、一定の要件を満たす場合。この場合、家賃と同様に非課税扱いとなります。
- 駐車場の設備や管理が伴わない、単なる土地としての貸付け(いわゆる青空駐車場で、地面の整備や区画整理がされていない更地など)の場合。
利用実態や契約内容によって異なるため、不明点は税理士に確認しましょう。
社宅家賃のインボイス
企業が福利厚生の一環として従業員に貸与する社宅の家賃について、企業が貸主(オーナーや不動産会社)へ支払う賃料は、それが住宅の貸付けに該当する限り原則として非課税取引となるため、インボイスは不要です。
企業が従業員から徴収する社宅使用料についても、一定の条件(無償または低廉な家賃でないことなど)を満たせば非課税取引となります。この場合もインボイスは不要です。
ただし、社宅に関連して企業が負担する費用の中で、例えば社宅に付随する駐車場代が別途請求され、それが課税取引に該当する場合や、家具・家電のリース料などが含まれていてそれが課税仕入れに該当する場合には、その部分についてインボイスが必要となることがあります。契約内容を詳細に確認することが求められます。
共益費・管理費など付随費用のインボイスの取扱い
家賃に付随して支払う共益費や管理費なども、その性質や契約内容によってインボイスの要否が異なります。
事務所や店舗などの事業用物件にかかる共益費や管理費は、一般的に共有部分の清掃費、光熱費、警備費、エレベーターの維持管理費など、役務提供の対価として消費税の課税対象となるため、インボイスが必要です。これらの費用が家賃と明確に区分されて請求される場合はもちろん、家賃に含まれて請求される場合でも、その内訳が課税取引であればインボイスの対象となります。
一方、居住用物件の共益費や管理費は、家賃と同様に住宅の貸付けの一部として扱われ、原則として非課税となるためインボイスは不要です。
請求書や契約書で、家賃、共益費、管理費などの内訳がどのように記載されているかを確認し、それぞれの項目が消費税の課税対象なのか非課税対象なのかを明確に把握することが大切です。複数の費用が一括で請求されている場合でも、課税取引に該当する部分についてはインボイスの保存が必要となります。
以下に、家賃に関連する主な費用のインボイス要否について、一般的なケースをまとめました。ただし、個別の契約内容や取引の実態によって取扱いが異なる場合があるため、あくまで参考としてください。
|
費用項目 |
居住用物件の場合のインボイス要否 |
事業用物件の場合のインボイス要否 |
備考 |
|
家賃 |
原則不要(非課税) |
原則必要(課税) |
事業用物件でも、土地の貸付けとみなされる場合は非課税の場合あり。 |
|
共益費・管理費 |
原則不要(非課税) |
原則必要(課税) |
水道光熱費等の実費精算分は、立替金精算書等で対応する場合あり。 |
|
駐車場代 |
条件により異なる |
原則必要(課税) |
居住用で住宅貸付と一体かつ一定要件を満たす場合は非課税。詳細は本文参照。 |
|
仲介手数料 |
必要(課税) |
必要(課税) |
不動産会社へ支払う手数料。 |
|
更新料 |
原則不要(非課税) |
原則必要(課税) |
契約内容により異なる場合あり。 |
|
礼金・権利金(返還されないもの) |
原則不要(非課税) |
原則必要(課税) |
事業用物件の礼金・権利金は資産計上する場合あり。 |
|
敷金・保証金(契約終了時に返還されるもの) |
不要(不課税) |
不要(不課税) |
消費税の対象外。ただし、償却部分は課税の場合あり。 |
※上記の表は一般的な目安です。実際の取引においては、契約書の内容や取引の実態を個別に確認し、不明な点については税理士などの専門家にご相談ください。
貸主向け|家賃とインボイス制度への対応ポイント
インボイス制度の開始は、不動産を賃貸している貸主の皆様にとっても重要な変更点となります。特に事務所や店舗などの事業用物件を貸し出している場合、借主との取引においてインボイス(適格請求書)の取り扱いを理解し、適切に対応する必要があります。この章では、貸主の皆様がインボイス制度に関して押さえておくべき具体的な対応ポイントを解説します。
物件種別(居住用・事業用)と自身の事業者区分を確認
インボイス制度への対応を検討するにあたり、貸主様がまず行うべきことは、ご自身が所有または管理している物件の種別と、ご自身の事業者としての区分を正確に把握することです。これらがインボイス発行の要否を判断する基本となります。
物件種別の確認:
- 居住用物件の家賃:アパート、マンション、戸建て住宅など、人が住むための物件の家賃は、消費税法上「非課税取引」とされています。したがって、居住用家賃については消費税が課されず、貸主は借主に対してインボイスを発行する必要はありません。
- 事業用物件の家賃:事務所、店舗、工場、倉庫、事業用として貸し出す土地など、事業の用に供される物件の家賃は「課税取引」となります。この場合、借主が課税事業者であれば、仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要となるため、貸主側の対応が求められます。
自身の事業者区分の確認:
次に、貸主ご自身が消費税の「課税事業者」であるか「免税事業者」であるかを確認します。さらに、課税事業者の場合は「適格請求書発行事業者」としての登録状況が重要になります。
|
貸主の事業者区分 |
適格請求書発行事業者の登録状況 |
事業用家賃におけるインボイス発行 |
|
課税事業者 |
登録済み |
借主(課税事業者)の求めに応じ、インボイスを発行する義務があります。 |
|
課税事業者 |
未登録 |
インボイスを発行できません。借主が仕入税額控除を受けられないため、登録を検討する必要があります。 |
|
免税事業者 |
登録不可 |
インボイスを発行できません。 |
ご自身の状況を上記に照らし合わせ、必要な対応を検討しましょう。
事業用家賃におけるインボイス(適格請求書)発行の注意点
貸主が課税事業者であり、かつ適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、事業用物件の家賃について借主(課税事業者)からインボイスの交付を求められた際には、これを発行する義務が生じます。インボイスを発行する際には、以下の点に注意が必要です。
インボイス(適格請求書)に必要な記載事項:
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 貸主(発行事業者)の氏名または名称
- 取引年月日(家賃の対象月など)
- 取引内容(例:〇〇ビル 〇階事務所家賃)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率(通常は10%)
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 借主(書類の交付を受ける事業者)の氏名または名称
これらの情報を記載した請求書や、家賃の口座振替通知書などをインボイスとして発行します。賃貸借契約書に上記の全ての情報と「契約書をもって適格請求書とする」旨の記載があれば契約書自体をインボイスとすることも理論上は可能ですが、実務上は毎月の家賃支払いに対して都度、請求書や通知書形式でインボイスを発行するのが一般的です。発行したインボイスの写しは、7年間の保存義務がありますので、適切に管理してください。
免税事業者の貸主が知っておくべき家賃請求の対応
貸主が免税事業者である場合、適格請求書発行事業者として登録することができないため、インボイスを発行することができません。これは、事業用物件の借主(特に課税事業者)にとって、消費税の仕入税額控除の可否に影響を与える重要な点です。
借主への影響と貸主の立場:
免税事業者の貸主から事業用家賃を支払う借主(課税事業者)は、その家賃にかかる消費税額について、原則として仕入税額控除を受けることができません(ただし、インボイス制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合の控除が可能な経過措置が設けられています)。これにより、借主の実質的な税負担が増加する可能性があります。
免税事業者の貸主が検討すべきこと:
- 現状維持(免税事業者のまま):インボイスを発行できないことを借主に伝え、理解を求める必要があります。借主との関係性や交渉次第では、家賃の減額を求められたり、インボイスを発行できる他の物件への移転を検討されたりする可能性も考慮に入れる必要があります。
- 課税事業者への転換検討:多くの借主が課税事業者であり、インボイスの発行を強く希望する場合や、今後の安定的な賃貸経営を考慮し、あえて課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者の登録を受けることも一つの選択肢です。ただし、課税事業者になると消費税の申告・納付義務が発生するため、事務負担や納税資金の確保などを総合的に勘案し、慎重に判断する必要があります。
いずれの選択をするにしても、借主とのコミュニケーションが非常に重要になります。インボイス制度に関するご自身の対応方針を明確にし、特に既存の借主に対しては、事前に丁寧な説明と協議を行うことが、良好な関係を維持するために不可欠です。
借主向け|家賃とインボイス制度への対応ポイント
インボイス制度開始に伴い、家賃を支払う借主側でもいくつかの対応ポイントがあります。物件の種類や貸主の状況によって対応が異なるため、しっかりと確認しておきましょう。
物件種別と貸主のインボイス発行事業者登録状況の確認
まず、借りている物件が「居住用」か「事業用(事務所や店舗など)」かを確認しましょう。居住用家賃は原則として消費税が非課税のため、インボイス(適格請求書)は不要です。
事業用家賃の場合、次に確認すべきは貸主が適格請求書発行事業者であるかどうかです。貸主の登録状況は、賃貸借契約書や請求書に記載された登録番号、または貸主への直接の問い合わせ、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。この情報は、後述する仕入税額控除の可否に直結するため非常に重要です。
事業用家賃の仕入税額控除とインボイス請求書の保存
事業用の事務所や店舗の家賃(課税家賃)について、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として貸主から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要です。インボイスには、貸主の登録番号、適用税率、消費税額などが記載されている必要があります。
受け取ったインボイスは、その課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する義務があります。電子データで受領した場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要がある点にも注意しましょう。適切なインボイスがなければ仕入税額控除が認められないため、確実に受領・保存してください。
貸主が免税事業者の場合の家賃支払いと仕入税額控除(経過措置)
事業用家賃の貸主が免税事業者である場合、貸主は適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、借主は原則としてその家賃にかかる消費税額について仕入税額控除を受けることができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。この経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された請求書(区分記載請求書等と同様の事項)の保存と、経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する必要があります。
|
期間 |
控除可能な割合 |
|
2023年10月1日から2026年9月30日まで |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日から2029年9月30日まで |
仕入税額相当額の50% |
貸主が免税事業者である場合は、家賃の条件について改めて協議するなどの対応も検討する必要が出てくるかもしれません。事前に貸主とコミュニケーションを取り、インボイス制度への対応方針を確認しておくことが推奨されます。
まとめ
家賃の請求書にインボイスが必要かどうかは、「居住用か事業用か」によって大きく異なります。居住用であれば消費税は非課税となるため、原則としてインボイスの発行・保存は不要な一方、事業用の場合は課税対象となり、インボイスの発行や仕入税額控除の対応が求められることになります。
貸主・借主のどちらにとっても、制度の理解と丁寧な対応が信頼関係を築く第一歩になります。ぜひ本記事の内容を参考に、適切な対応を進めてみてください。










