インボイス登録の期間はいつまで?手続き方法と必要書類をわかりやすく解説
更新日:2026.01.14
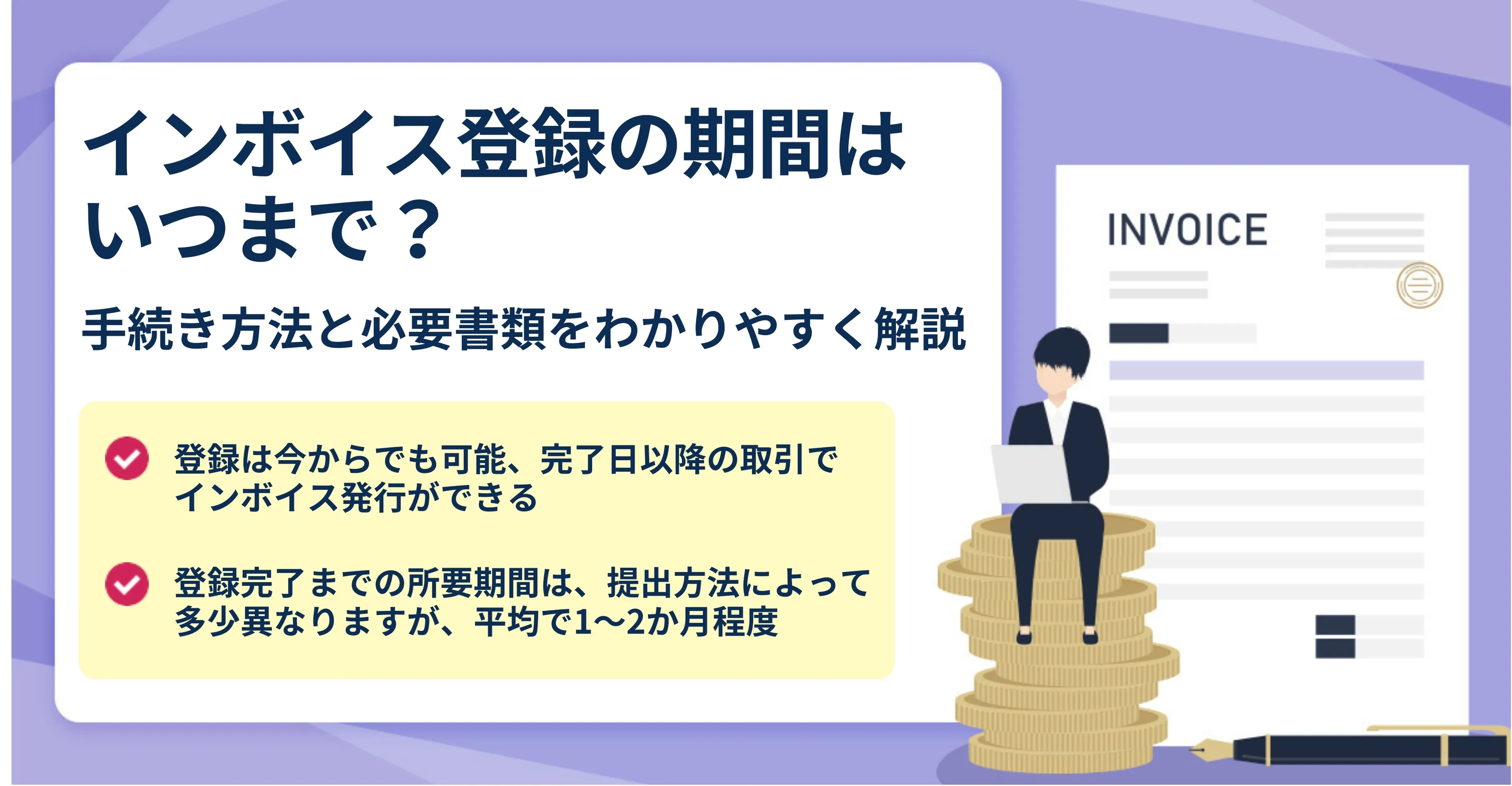
ー 目次 ー
2023年10月に開始されたインボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者としての登録が必要です。本記事では、登録の申請期間や締切、必要書類や手続き方法までを詳しく解説します。この記事を読めば、「いつまでにどのような手続きを行えばよいのか」が明確にわかり、今後の税務対応や取引先との関係構築にも役立てることができます。
インボイス制度とは?
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度で、2023年10月1日から日本で導入された消費税に関する仕組みです。この制度は、消費税の仕入税額控除を適用するためには、仕入れに係る取引について一定の事項が記載された適格請求書(インボイス)を保存する必要があるというルールです。
これまで行われてきた「区分記載請求書等保存方式」とは異なり、より詳細な情報を含んだ請求書が必要になり、発行者は国税庁に登録された「適格請求書発行事業者」でなければなりません。この制度の導入により、消費税制度の透明性が高まり、適正な課税と控除が可能になることを目的としています。
インボイスには、発行者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した消費税額、受領者の氏名または名称など、一定の記載事項が求められます。
適格請求書発行事業者の定義
適格請求書発行事業者とは、所轄の税務署長に申請書を提出し、登録を受けた事業者のことを指します。この登録を受けた事業者のみが、仕入税額控除に対応したインボイスを発行することができます。適格請求書発行事業者は、個人事業主、法人を問わず、課税事業者であることが前提です。
免税事業者は原則としてインボイスを発行することができません。ただし、インボイス制度導入にあたり、免税事業者が課税事業者となって登録することで、適格請求書発行事業者としてインボイスを発行することが可能になります。そのため、現時点で免税事業者である個人事業主やフリーランスも、インボイス制度下での対応を検討する必要があります。
適格請求書発行事業者として登録されると、国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」に、登録番号や名称等が掲載され、取引先がその正当性を確認できるようになります。
|
項目 |
内容 |
|
登録対象者 |
課税事業者(個人事業主または法人) |
|
申請方法 |
所轄税務署に書面またはe-Taxで申請 |
|
有効期間 |
申請し登録された日から取り消し・解散まで |
|
公表内容 |
事業者名、登録番号、所在地など |
なお、インボイス制度導入により、今後は取引先がインボイスに対応しているかどうかが取引先選定の一要素となる可能性が高く、自身が取引先企業から選ばれるためにも、制度に対応した体制整備が不可欠となります。
インボイス登録が必要な理由とは?
課税事業者と免税事業者の違い
インボイス制度において、重要となるのが「課税事業者」と「免税事業者」の違いです。課税事業者は、売上に対して消費税を課して納税する義務を負っている法人や個人事業主を指します。一方、免税事業者は、一定の条件(前々年度の課税売上高が1,000万円以下など)を満たすことで、消費税の納税義務が免除される事業者です。
従来、免税事業者であっても、取引先は仕入税額控除を適用することができましたが、インボイス制度の開始により、適格請求書(インボイス)の発行ができない免税事業者と取引した場合、仕入税額控除ができなくなります。このため、課税事業者との取引を維持するためには、免税事業者もインボイス登録を行う必要性が高まっています。
仕入税額控除の適用要件
仕入税額控除とは、事業者が事業のために購入した商品やサービスにかかった消費税を、納付すべき消費税から差し引く制度です。インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」が発行したインボイスを受け取ることが原則となります。
つまり、たとえ消費税相当額を支払ったとしても、インボイスを受領していない場合には、その消費税は控除の対象とはならず、結果として税負担が増加する可能性があります。このため、取引先企業が今後も仕入税額控除を受けられるよう、自社が適格請求書発行事業者としてインボイスの発行が可能であることが求められます。
登録しない場合の影響
インボイス制度に登録していない場合、以下のような経済的・取引上の不利益が生じる可能性があります。
|
項目 |
登録しない場合の影響 |
|
取引先からの評価 |
インボイスを発行できないため、仕入税額控除が適用されず、取引継続を断られる可能性がある |
|
売上への影響 |
特にBtoB取引の場合、登録済み事業者への発注が優先され、売上減少のリスクがある |
|
取引条件の不利化 |
取引先がインボイスを受け取れないことにより、値下げ交渉など不利な条件を求められることがある |
|
信頼性の低下 |
登録していないことが事業の透明性や信頼性に疑問を抱かせる要因となる |
特に中小事業者や個人事業主の場合、従来は免税事業者として活動していたケースも多く、今回のインボイス制度への適応は大きな転換点となります。登録しない選択肢を取ることも可能ではありますが、実際の取引環境や取引先の意向により、その選択が大きな経済的損失につながる可能性があるため、事前に十分な検討が必要です。
また、今後新規に事業を始めるケースにおいても、開始時点からインボイス発行事業者として登録するかが、取引先との関係構築の鍵となる可能性があるため、戦略的に登録の可否を判断することが求められています。
インボイス登録の期間と申請期限!
登録申請の受付開始日と制度開始日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から施行されました。この制度に対応するためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要です。国税庁では、2021年10月1日より「適格請求書発行事業者の登録申請書」の受付を開始しています。
すなわち、2023年10月1日の制度開始時点で登録を間に合わせるには、前もって申請手続きを済ませておく必要があるということになります。
登録申請の締切日とスケジュール
インボイス制度の開始と同時に登録状態でいるためには、原則として、制度開始の6か月前である2023年3月31日までに登録申請を提出しなければなりません。国税庁がこの日までの申請分については制度施行日に間に合うように審査・登録の処理を行うと明言しています。
それ以降も登録申請の提出は可能ですが、制度開始前の登録には間に合わないため、登録完了後からの対応となります。具体的なスケジュールとしては以下の通りです。
|
日付 |
内容 |
|
2021年10月1日 |
登録申請の受付開始 |
|
2023年3月31日 |
2023年10月1日から登録を希望する場合の申請期限 |
|
2023年10月1日 |
インボイス制度の開始日 |
いつまでに申請すれば対象となるか
インボイス制度に対応するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録完了日以降にインボイスの発行が可能となります。
登録完了までの所要期間は、提出方法によって多少異なりますが、平均で1〜2か月程度とされており、郵送よりもe-Taxを利用した方が処理が早い傾向にあります。よって、早めの手続きが推奨されています。
登録期間の例外と特例措置
制度施行後に事業を開始した場合や、課税事業者となった後にインボイス登録を希望する場合には、一定の要件を満たすことで遡って登録が可能となる特例も設けられています。具体的には、以下のような措置があります。
|
対象者 |
特例内容 |
申請期限 |
|
新たに課税事業者となった者 |
課税事業者の届け出と同時にインボイス登録申請を行えば、届け出の日から登録可 |
課税事業者選択届出書の提出と同時 |
|
免税事業者からの転換者 |
2023年10月以降の期間について、一定期間内の申請で「登録年月日」を遡及適用 |
納税地の所轄税務署に申請 |
|
基準期間のない新規事業者 |
基準期間がないため特例により最初の課税期間から登録可能 |
開始日の前日までに申請 |
特例措置を適用するには、事前に必要な届出書や根拠資料の提出が求められる場合があります。また、遡及適用に関する詳細な条件は国税庁が公表している「インボイス制度 特設サイト」や「適格請求書発行事業者制度に関するQ&A」で確認することが重要です。
なお、インボイス登録を後から取り消すことも可能ですが、その際は要件を満たしたうえで、適切な手続きが必要となるため、登録期間の管理には十分注意が必要です。
インボイス登録に必要な書類は?
個人事業主の場合に必要な書類
インボイス制度において、個人事業主が適格請求書発行事業者として登録する際には、以下の書類が必要です。
|
書類名 |
概要 |
備考 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
インボイス発行事業者として登録するための基本書類。 |
e-Taxまたは紙面で提出可能。 |
|
本人確認書類 |
申請者が本人であることを確認するための書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
e-Taxの場合は省略可能な場合もあります。 |
|
開業届出書(控) |
すでに開業していることの証明。 |
税務署提出済みの控えをスキャンして提出。 |
|
課税事業者選択届出書 |
免税事業者が課税事業者へ切り替える際に提出。 |
インボイス制度では課税事業者であることが前提。 |
個人事業主の場合、特に免税事業者だった人がインボイス登録するには、「課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。また、税務署での処理が完了するまで時間がかかることもあるため、余裕を持った準備が求められます。
法人の場合に必要な書類
法人がインボイス制度に対応するために必要な書類は以下のとおりです。登記された法人情報に基づき、正確な記載と提出が求められます。
|
書類名 |
概要 |
備考 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
法人としてインボイス制度へ登録するための基本書類。 |
法人代表者名義で申請。 |
|
登記事項証明書 |
法人の名称、所在地、代表者情報を証明する書類。 |
提出はコピー可。3ヶ月以内に取得したもの。 |
|
法人番号確認資料 |
国税庁で発行されている法人番号を確認するための資料。 |
法人番号指定通知書など。 |
|
課税事業者選択届出書(必要に応じて) |
今まで免税事業者だった法人が課税事業者へ移行する場合に必要。 |
法人税申告と連動するため、日程に注意。 |
法人はインボイス登録の際、登記内容と申請情報に齟齬がないことが重要です。とくに本店所在地や代表者名の記載ミスは処理遅延の原因になりますので、最新の登記事項証明書で確認しておきましょう。
提出書類の記載ポイント
個人・法人を問わず、インボイス登録における申請書類は正確な記入が求められます。以下に記載時の注意点を示します。
- 税務署に登録された名称を正確に記入すること(略称不可)
- 住所・所在地の記載は住民票や登記簿記載と必ず一致させること
- 誤字・脱字のないよう、丁寧な記入を心がける
- 電子申請の場合はデジタル署名が必要で、事前にマイナンバーカードやICカードリーダーの用意が必要
- 手書き書類の場合はボールペンなど消せない筆記具を使用する
万が一記載に不備があると、税務署から修正の連絡が入り審査に時間がかかる可能性があります。申請内容の確認は提出前に複数の目でチェックすることをおすすめします。
インボイス登録の手続き方法について解説!
登録申請の方法と流れ
インボイス制度において適格請求書発行事業者として登録を受けるには、所定の方法で申請を行う必要があります。登録申請には「電子申請(e-Tax)」と「紙提出(書面申請)」の2つの方法があり、それぞれに応じた手順を踏む必要があります。
e-Taxを使用する場合の手順
電子申請は、国税庁の提供するe-Taxシステムを使って、インターネット上で手続きを完了させる方法です。以下のステップで進めます。
- e-Taxソフトまたはe-Tax Webを利用するための利用者識別番号を取得
- e-Taxにログインし、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を選択
- 申請者情報(氏名・法人番号・取引先情報等)を入力
- 確認・送信し、受領通知を受け取る
e-Taxを使えば、申請状況の確認や登録完了の通知などもオンラインで確認でき、処理もスムーズです。特に法人や定期的な電子申告を行っている事業者には利便性が高い方法と言えます。
紙で提出する場合の流れ
紙で申請する場合は、所轄の税務署へ郵送または持参にて書類を提出する必要があります。以下に主な手順を示します。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を国税庁のホームページからダウンロード
- 必要事項(氏名・法人名・住所・開業日など)を記入
- 捺印のうえ、所轄税務署へ提出(郵送または窓口持参)
- 後日、登録通知が届く
紙申請は必要書類に漏れがないように注意する必要があります。また、処理に時間がかかる場合があるため、早めの提出が推奨されます。
申請後の審査期間と登録通知
登録申請後、税務署によって内容に誤りや不足がないかの審査が行われます。申請方法や混雑状況により審査期間は異なりますが、通常、申請から登録確認通知が届くまでには1か月程度かかるとされています。
電子申請を行った場合は、e-Tax上で結果を確認することができますが、紙による申請の場合は、登録が完了すると以下の書類が郵送されます。
|
通知書名 |
内容 |
|
適格請求書発行事業者の登録通知書 |
登録番号、登録年月日、登録事業者の名称・所在地などが記載 |
|
適格請求書発行事業者公表サイトへの掲載通知 |
登録情報が国税庁の公表サイトに表示される旨の案内 |
登録番号は、インボイス制度における課税仕入れの証明に不可欠となるため、通知書の到着後は速やかに社内システム等へ登録し、管理体制を整えることが重要です。
インボイス登録後の対応と注意点
登録番号の通知と管理方法
インボイス制度に登録された後、国税庁から「適格請求書発行事業者」としての登録番号が付与されます。この登録番号は、適格請求書(インボイス)に必ず記載する必要があり、取引先に対して正確に通知しなければなりません。また、国税庁が公開する「適格請求書発行事業者公表サイト」上でも登録者情報が閲覧可能となります。
登録番号は一度付与されると、基本的には変更されませんが、法人の合併や個人事業主の廃業・再開業などの事情により登録事項が変更される場合には、速やかな変更届出が必要です。そのため、登録番号は契約書・請求書フォーマット・会計ソフトなどに正しく登録し、社内でしっかりと管理することが求められます。
適格請求書の発行義務と記載内容
インボイス制度に登録された事業者は、課税資産の譲渡等を行う際に、「適格請求書」を発行する義務があります。この請求書には、法律で定められた以下の項目を全て記載することが必要です。
|
記載項目 |
説明 |
|
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 |
登録通知で付与される13桁の登録番号を記載 |
|
② 取引年月日 |
取引が行われた具体的な日付を記載 |
|
③ 取引内容 |
品目やサービス内容、数量など具体的な記載 |
|
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込) |
複数税率に対応可能な記載 |
|
⑤ 適用税率 |
標準税率(10%)または軽減税率(8%)を明示 |
|
⑥ 消費税額等 |
税率ごとに分けて税額を記載 |
|
⑦ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(省略可) |
発行側と受領側の関係によっては省略が可能 |
これらの要件を満たさない請求書は、インボイスとして認められず、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。そのため、会計担当者や営業部門に対し、適切な発行フォーマットと記載ルールを周知徹底することが重要です。
会計処理や帳簿の対応の見直し
インボイス制度の開始により、会計処理や帳簿の管理方法も見直す必要があります。特に仕入税額控除を適用するためには、インボイスを保存することが要件の一つとなるため、領収書・請求書の保管方法を電子化するなどの準備が求められます。
加えて、以下の点について体制を整備しておくことが望ましいです。
- 会計ソフトのバージョンアップ:インボイス制度対応の最新バージョンを使用
- 仕入先や外注先のインボイス登録状況の確認:非登録事業者との取引内容の見直し
- 帳簿への記載要件の確認:帳簿に取引日、取引先、金額、インボイス番号等を明示
インボイス制度に対応していないと、消費税申告時に仕入税額控除が認められず、余分な税負担が発生するおそれがあるため、定期的な内部監査や業務フローの点検が推奨されます。
登録事項の変更や取消手続き
インボイス登録後の事業活動に変化が生じた際には、「適格請求書発行事業者」の登録内容を変更、または必要に応じて登録の取消手続きを行うことが必要です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
- 事業者の氏名・名称、住所、法人番号が変更された場合
- 事業を廃止した場合(廃業・法人解散など)
- 適格請求書の交付義務から外れることを希望する場合(任意の登録取消)
変更や取消の手続きは、基幹税務署への「適格請求書発行事業者の変更届出書」または「取消届出書」の提出により行います。紙での提出またはe-Taxでの電子申請が可能です。
なお、登録の取消を希望する際には、原則として取消の効力が生じる3か月前までに届出る必要があるため、スケジュールには十分な余裕を持って対応すべきです。
また、登録を取り消した場合でも、既に発行されたインボイスの記録や保存義務、取引先への通知義務は残るため、関係各所への丁寧な対応が求められます。
まとめ
インボイス制度への登録は、仕入税額控除の適用を受けるために重要な手続きです。登録申請は2023年10月1日の制度開始に向けて早めの対応が求められ、原則として開始の6か月前までに申請する必要があります。e-Taxや紙での申請方法、必要書類も事業形態により異なるため確認が必須です。登録後は、適格請求書の発行義務や帳簿処理の見直しなども発生しますので、登録から運用まで一貫した準備を行いましょう。










