インボイスに対応した領収書テンプレートの作り方!注意点も解説
更新日:2026.01.29
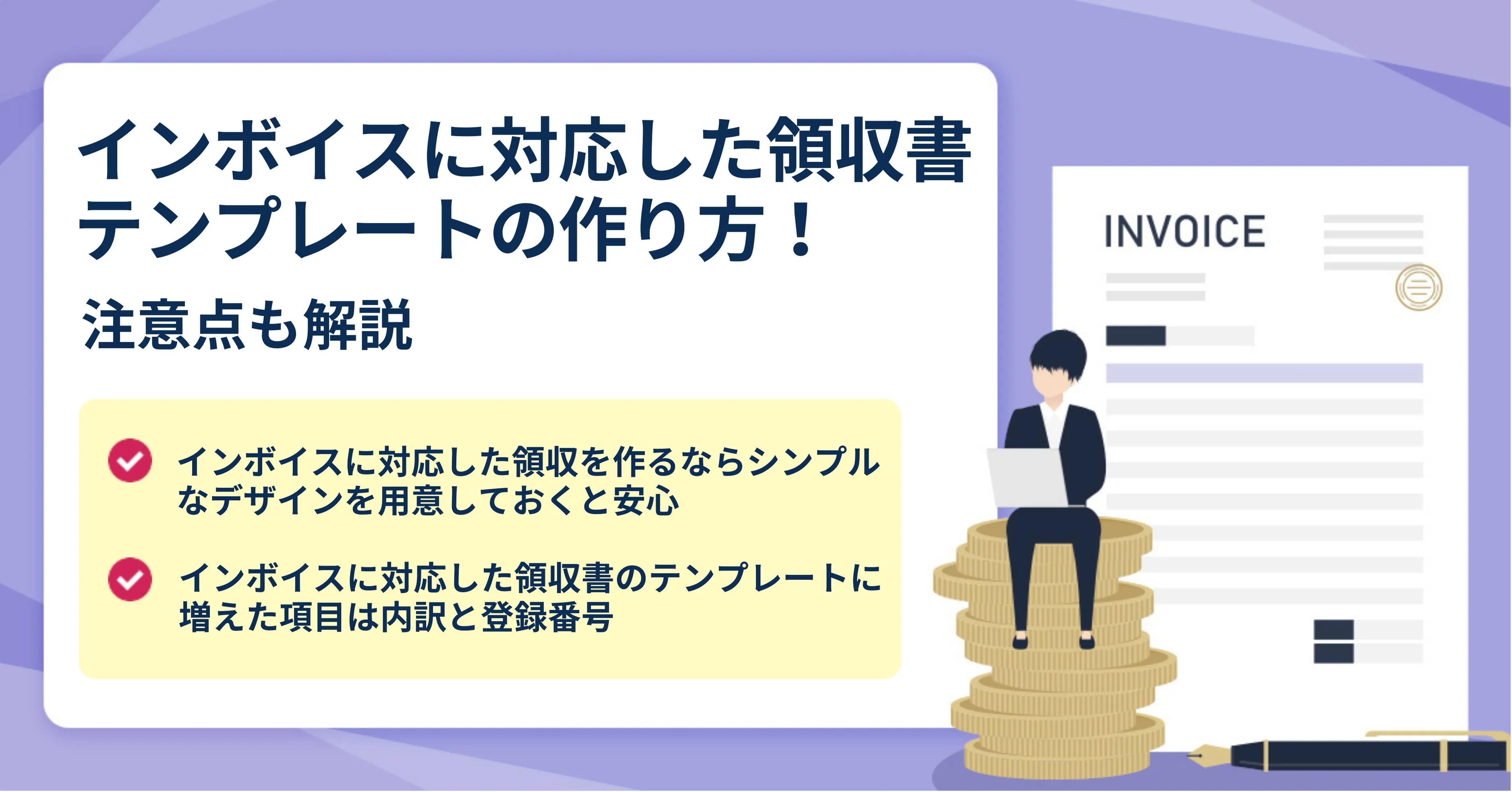
ー 目次 ー
インボイス制度に対応した領収書のテンプレートは、会計ソフトを利用すれば簡単に作成できます。ほかにも、WordやExcelなどのOfficeソフトを利用することで、自社にあったテンプレートの作成も可能です。
テンプレートの作成は、インボイス制度を理解したうえでおこなわないと、取引先が税金の控除を受けられないトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、インボイス制度に対応した領収書の種類や必要な項目を解説します。無料テンプレートを使用して領収書を作るときの注意点も解説するため、ぜひ参考にしてください。
2023年10月開始のインボイス制度。対応はお済みでしょうか?インボイス制度では請求書の作成方法や消費税の計算方法が変わり、対応を誤ると取引先とのトラブルや税務調査で指摘を受ける可能性も。
「インボイス制度に対応した請求書の作成、煩雑で困っている...」
そんな事業者様におすすめなのが、通信費の請求書を1枚にまとめてお届けする「Gi通信」です。「Gi通信」は、請求書の受取から保管までを代行し、経理・総務部門の業務負担を大幅に削減。電子・紙両方の請求書に対応しているため、インボイス制度への対応も容易です。インボイス制度対応にお困りの事業者様は、ぜひ「Gi通信」をご検討ください。
インボイスに対応した領収書は「適格請求書」と「適格簡易請求書」にわかれる
インボイス制度に対応した領収書は、「適格請求書」と「適格簡易請求書」の2つの形式にわかれます。領収書は、下記の項目を記載することでインボイスの交付が可能な適格請求書になります。
- 書類作成者の氏名または名称
- 登録番号
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
他方で「適格簡易請求書」は、小売業や飲食業など一部の業種のみが発行可能であり、記載事項が簡略化されています。適格簡易請求書が発行できる業種は以下のとおりです。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業タクシー業及び駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)
- これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等をおこなう事業
適格簡易請求書の発行が許されている業種は、領収書の発行回数が多く適格請求書(インボイス)の記載要件を満たして書くのが難しいと考えられているため、適格簡易請求書の発行が許可されています。
【テンプレート】インボイスに対応した領収書見本
インボイス制度に対応した領収書を作る場合は、シンプルなデザインを用意しておくことで使用用途に合わせてアレンジができます。
|
領収書 取引先住所 取引先名称 ¥〇〇〇〇- 但 〇〇代として 令和〇年〇月〇日 上記正に領収いたしました (うち10%対象) 〇〇 (うち8%対象) 〇〇 自社名称 自社住所 電話番号 登録番号 |
上記フォーマットを利用して、自社に合ったテンプレートを作成しましょう。
インボイスに対応した領収書のテンプレートに増えた項目は2つ
2023年10月1日よりインボイス制度が施行され、領収書を適格請求書にするためには「税率ごとの合計金額の内訳」や「登録番号」の記載が必要になりました。領収書を発行する前に、テンプレートに加えるべき内容を理解しておきましょう。
ここでは、インボイスに対応した領収書のテンプレートに増えた項目を解説します。
- 内訳
- 登録番号
①内訳
領収書に記載される商品に、軽減税率の対象品目とそれ以外が混在している場合は、税率ごとの合計金額や消費税の金額、適用した税率の記載が必要です。合計金額を記載するときは、税抜・税込どちらでも問題ありません。
なお、適格簡易請求書であれば、税率ごとの消費税額と適用税額のどちらかで要件を満たします。
②登録番号
税務署に適格請求書発行事業者として申請している場合は、Tの後に13桁の番号が続く登録番号が発行されています。領収書でインボイスを交付するためには、登録番号を記載しましょう。登録番号は、適格簡易請求書でも必要な項目です。
登録番号の記載がない領収書を発行した場合、取引先は仕入税額控除を利用できないため、再発行を求められる可能性があります。
インボイス施行前から!基本の領収書のテンプレートに必要な項目
インボイス制度に対応した領収書のテンプレートを作成する前に、従来の領収書に必要な基本的な項目を確認しておきましょう。なかには、適格請求書を発行する際に必要な項目もあるため、漏れないよう注意が必要です。
ここからは、インボイス制度施行前からある基本的な領収書のテンプレートに必要な項目を解説します。
- 取引日
- 宛名
- 但し書き
- 金額
- 発行者
- 収入印紙
①取引日
領収書の取引日は、実際にサービスや商品の対価として代金を支払った日を記載しましょう。取引日は、適格請求書や適格簡易請求書を発行する場合にも必要な項目です。
発行日と金銭の受取日が異なる場合は、金銭のやりとりがあった日を記載する必要があります。取引日を記載する場合、和暦・西暦の決まりはないものの、西暦で記載する場合は「2024年」を「24年」と省略すると、和暦と誤解される可能性もあるため注意が必要です。
②宛名
宛名は、代金を支払った買い手側の会社名や個人事業主の名前を記載しましょう。領収書を適格請求書として扱う場合は、税務署に申請している正式名称の記載が必要です。
ただし、適格簡易請求書の場合は宛名の省略が許されているため、空白や上様の記載でも仕入税額控除を受けられます。
③但し書き
但し書きとは、領収書の代金を支払った代わりに受け取ったサービスや商品の概要を記載します。
領収書を適格請求書としない場合は、「お品代」や「空欄」など、明確に記載されていない可能性があります。一方で、領収書をでインボイスを交付する場合は「食品代」や「飲食代」をはじめとした、製品やサービスを明記しないと取引先が仕入税額控除を受けられません。
但し書きを記載する際は、どのように記載するか確認しておくと安心です。
④金額
領収書の金額を記載するときは、改ざんを防ぐために以下3つのルールが定められています。
- 金額の先頭に「¥」か「金」を記載
- 3桁ごとに「,」
- 金額の最後に「-」「※」「也」
適格請求書の場合は税率ごとの合計金額だけでなく、消費税額の記載が必要です。適格簡易請求書の場合は、8%と10%ごとの合計金額は必要なものの、適用税率と税率ごとの消費税額を分けて記載する必要がなく、どちらかで問題ありません。
⑤発行者
領収書を発行する場合、発行者情報の記載が必要です。発行者情報は、一般的に以下の内容が記載されます。
- 発行者の氏名・会社名
- 住所
- 電話番号
領収書でインボイスを交付する場合は、税務署に申告した正式名称を記載しましょう。その際に、登録番号を発行者情報の付近に記載しておくと取引先が確認しやすくなります。
⑥収入印紙
領収書や契約書などの書類は、印紙税という税金が課せられます。収入印紙は、その税金を支払うために国が発行する証票です。収入印紙は税抜5万円以上の取引で領収書を発行するときに必要となるため、テンプレートを使用する場合でも用意しましょう。
なお、電子領収書の場合は領収書現物の発行がされないため、課税文書を作成したことにはならず、収入印紙の発行が不要になります。
インボイスの領収書テンプレートをWordやExcelで作る注意点
インボイスに対応した領収書は、会計ソフトやOfficeソフトにテンプレートが用意されています。一から作ることが大変であれば、用意されているテンプレートを自社用にアレンジして使用しましょう。
ただし、WordやExcelで作られた無料のテンプレートを使用する場合は記載項目の変え忘れやサイズなどの注意点があるため、事前に理解しておくと安心です。
ここでは、インボイスの領収書のテンプレートをWordやExcelで作るときの注意点を解説します。
①記載項目の変え忘れに注意
WordやExcelを使用して領収書を発行する場合、作成時に前回記載した取引先のデータが残っていないか確認しましょう。
記載項目を変え忘れてしまうと、情報漏洩の懸念があるとされ、取引先からの信用を失うことにつながります。安全な方法は、領収書を作成するときに「上書き保存」ではなく、「名前をつけて保存」をすることで、テンプレートのデータを変えずに済み、取引先の情報が残りません。
また、日付や担当者も変更し忘れてしまう可能性があるため、発行時に見直しておくと安心です。
②ExcelやWordで作成した場合でも印刷する場合は収入印紙が必要
ExcelやWordで利用したテンプレートで作成した領収書は、印刷する場合は収入印紙が必要になる可能性があります。税抜5万円以上の取引の領収書を郵送や手渡しする場合は、収入印紙を用意しましょう。
ただし、作成したデータを取引先でメールを使用して送る場合は収入印紙は必要ありません。
③サイズはA4がおすすめ
WordやExcelを使用して作成された無料の領収書テンプレートは、取引先が印刷したときにサイズがバラバラにならないようA4サイズで作成しましょう。
一度テンプレートを作成してからサイズを変えると、文字の大きさや位置が崩れてしまう可能性があります。サイズ設定をA4にしてから作成を始めると、作り直す手間を減らせるでしょう。
ビジネスで使用する書類はA4サイズが多いため、A4でテンプレートを作成しておくと、取引先が印刷して管理する場合でもサイズ変更の手間をかけません。
まとめ|インボイスに対応した領収書のテンプレートで業務を効率化しよう
本記事では、インボイス制度に対応した領収書の種類や必要な項目を解説しました。
インボイス制度の施行から、領収書を適格請求書にするために必要な記載事項として「内訳」や「登録番号」が追加されました。領収書発行前に自社のフォーマットを作っておくことで、必要なときにすぐに使用できて業務効率を上げられます。
事業内容によっては適格請求書ではなく、適格簡易請求書が発行可能な場合もあるため、本記事を参考に自社が対象になるのか確認してテンプレートを作りましょう。










