インボイスで値下げが話題に...交渉例・違法性・仕訳までやさしく解説
更新日:2025.12.21
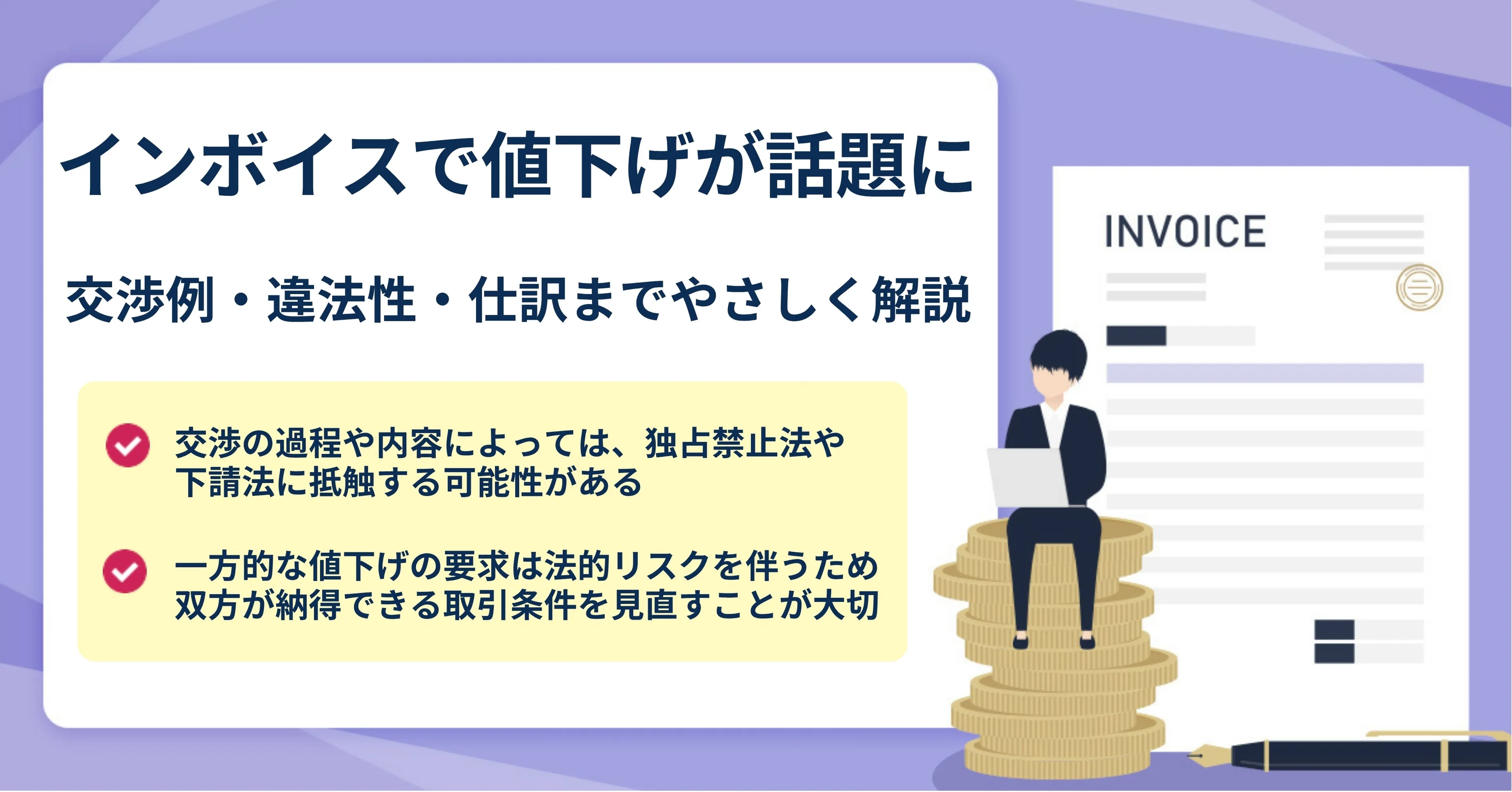
ー 目次 ー
インボイス制度に関連して、最近「値下げ交渉」が話題に上ることが増えました。なぜ値下げが起こるのか、その理由から、交渉の違法性、依頼する側・される側の交渉術や例文、値引き時の仕訳まで実務に役立つ形でわかりやすくご紹介いたします。制度対応にお悩みの方にも、一歩を踏み出していただけるようまとめましたのでぜひ最後までご覧ください。
インボイス制度と値下げが結びつく理由とは?
2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、事業者の消費税処理に大きな変更をもたらしました。この制度変更に伴い、特に免税事業者との取引において「値下げ」が議論されるケースが増えています。なぜインボイス制度が値下げ圧力と結びつくのか、その基本的な理由と背景を解説します。
インボイス制度の基本と値下げの背景
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除を行う制度です。適格請求書には、適用税率や税率ごとの消費税額、登録番号などが記載され、これに基づいて買い手側は仕入れにかかった消費税の控除を受けることができます。
この制度が値下げと関連する背景には、仕入税額控除の仕組みの変更があります。特に、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者との取引において、買い手である課税事業者の税負担が増加する可能性が出てきたため、その負担分を取引価格で調整しようとする動き、すなわち値下げ要求が起こりやすくなっているのです。
免税事業者との取引が値下げにつながる仕組み
インボイス制度導入以前は、免税事業者からの仕入れであっても、買い手である課税事業者は一定の要件を満たせば仕入税額控除を受けることができました(区分記載請求書等保存方式)。しかし、インボイス制度開始後は、原則として適格請求書発行事業者(主に課税事業者)が発行したインボイスがなければ、仕入税額控除が認められなくなりました。
免税事業者は適格請求書発行事業者として登録することができず、インボイスを発行できません。そのため、課税事業者が免税事業者から商品やサービスを仕入れた場合、その仕入れにかかる消費税相当額を控除できず、結果として課税事業者の納税額が増加することになります。
課税事業者が免税事業者との取引において、仕入税額控除がどのように変わるかをまとめると以下のようになります。
|
取引の状況 |
免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除(課税事業者の立場) |
ポイント |
|
インボイス制度導入前 |
可能(区分記載請求書等保存方式) |
帳簿と請求書等の保存により、仕入税額控除が認められていました。 |
|
インボイス制度導入後(原則) |
不可 |
免税事業者はインボイスを発行できないため、買い手は仕入税額控除を受けられません。 |
|
インボイス制度導入後(経過措置期間) |
一定割合可能 |
制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています(例:2023年10月1日から3年間は80%、その後の3年間は50%)。 |
値下げ要求は違法?公正取引委員会の見解と実務上の注意点
インボイス制度の開始に伴い、取引先から値下げを要求されるケースや、逆に値下げを交渉したいと考えるケースが増えています。しかし、その値下げ要求が法的に問題ないのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、インボイス制度に関連する値下げ要求の違法性について、公正取引委員会の見解を踏まえつつ解説します。
値引き要求は独占禁止法に抵触する?公正取引委員会の見解
インボイス制度の導入を契機とした取引価格の引き下げ交渉は、それ自体が直ちに独占禁止法や下請法に違反するものではありません。しかし、交渉の過程や内容によっては、これらの法律に抵触する可能性があります。
公正取引委員会は、インボイス制度に関連して特に注意すべき行為として、以下の点を挙げています。
|
優越的地位の濫用 (独占禁止法) |
取引上優越した地位にある事業者(発注者など)が、その地位を利用して、取引の相手方(受注者など)に対し、インボイス制度への対応を理由に一方的に著しく低い価格を設定したり、不当に不利益を与えたりする行為。 |
|
買いたたき(下請法) |
親事業者が下請事業者に対し、通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。免税事業者であることを理由に、仕入税額控除ができない分を一方的に下請代金から減額する行為などが該当する可能性があります。 |
具体的には、以下のようなケースが問題となる可能性があります。
- 協議なく一方的に取引価格を引き下げる
- インボイス発行事業者になるよう強要し、応じない場合に取引の継続をちらつかせて値下げを迫る
- 控除不可分の税負担をすべて受注者側に転嫁する
- システム対応費用を一方的に差し引く など
公正取引委員会は、インボイス制度に関する相談窓口を設け、事業者からの相談に応じています。不当な値下げ要求を受けたと感じた場合は、これらの窓口に相談することも検討しましょう。
正当な価格交渉との違いはどこにある?境界線を見極めよう
インボイス制度導入に伴う取引条件の見直しが、全て違法となるわけではありません。正当な価格交渉と、違法性を問われる可能性のある一方的な値下げ要求との間には、明確な境界線があります。その境界線を見極めるためには、以下のポイントに注意が必要です。
- 十分な協議の有無
- 正当な価格交渉:双方の当事者が対等な立場で、取引価格や条件について十分に話し合い、合意に基づいて決定される。値下げの理由や根拠が明確に示され、相手方の意見も尊重される。
- 違法な値下げ要求の可能性:一方的な通告のみで、協議の機会が与えられない、または形式的なものに過ぎない。発注者側の都合のみが押し付けられる。
- 値下げの根拠と合理性
- 正当な価格交渉:市場価格の変動、原材料費の変動、発注量の変更、提供される役務内容の変更など、客観的かつ合理的な理由に基づいて価格調整が提案される。インボイス制度への対応に伴うコスト増を考慮し、双方で負担割合を協議する場合も含まれます。
- 違法な値下げ要求の可能性:「免税事業者だから」「インボイスを発行できないから」といった理由のみで、合理的な説明なく大幅な値下げを要求する。仕入税額控除ができないことによる発注者側の負担増を、一方的に受注者側に転嫁しようとする。
- 取引上の地位の利用
- 正当な価格交渉:取引上の力関係に関わらず、公正な取引慣行に則って交渉が行われる。
- 違法な値下げ要求の可能性:発注者側が取引上の優越的な地位を利用し、受注者側が受け入れざるを得ない状況を作り出して値下げを強要する。例えば、「要求に応じなければ今後の取引を停止する」といった圧力をかける。
特に、免税事業者や小規模事業者との取引においては、発注者側がより慎重な対応を求められます。インボイス制度は、あくまで適格請求書の保存・発行に関する制度であり、これを理由とした一方的な不利益の押し付けは避けるべきです。
依頼する側|値下げを交渉する立場で気をつけたいマナーと例文
交渉は相手との良好な関係を維持しつつ、双方にとって納得のいく形で行うことが重要です。本章では、依頼側としてのマナーや伝え方のコツを、例文とともに解説します。
ケース別|取引価格の見直しが妥当とされやすい場面とは?
インボイス制度導入を理由とした値下げ交渉が、常に正当化されるわけではありません。しかし、以下のようなケースでは、取引価格の見直しについて相手方の理解を得やすい可能性があります。
長期的な継続取引がある場合
長年にわたり安定した取引関係が築かれている場合、相互の信頼関係が基盤となります。インボイス制度導入による影響について率直に伝え、今後の取引継続のためにも協力をお願いしたいという姿勢で交渉することで、相手方も検討の余地を見出しやすくなるでしょう。これまでの取引実績への感謝と共に、将来にわたるパートナーシップの重要性を強調することがポイントです。
消費税が価格に反映されていなかった契約の場合
過去の契約において、消費税の取り扱いが曖昧で、実質的に消費税分が価格に十分に転嫁されていなかったケースも考えられます。インボイス制度を機に、適格請求書発行事業者との取引においては消費税額が明確になるため、これを機に取引価格全体を見直し、適正な価格設定について協議を申し入れることは一つの考え方です。ただし、過去の契約経緯を丁寧に説明し、相手方の理解を求める姿勢が不可欠です。
下請けが免税事業者で、仕入税額控除が受けられなくなる場合
取引先である下請事業者が免税事業者であり続ける場合、発注者側は原則としてその取引にかかる消費税の仕入税額控除が受けられなくなります(経過措置あり)。免税事業者にはインボイス発行の義務がないこと、また課税事業者への転換には負担が伴うことを理解し、高圧的な態度や一方的な要求は避けなければなりません。あくまで双方の状況を考慮した上での「相談」という形を取ることが重要です。
印象を損ねない電話での伝え方やメール例文
電話で交渉を持ちかける際は、まず相手の都合を伺い、突然本題に入るのではなく、日頃の感謝を伝えた上で、相談したい旨を切り出すのがマナーです。感情的にならず、冷静に、そして誠実に交渉の理由を説明しましょう。
メールで連絡する場合は、記録が残るメリットがありますが、文面だけではニュアンスが伝わりにくいため、より丁寧な言葉遣いを心がける必要があります。以下にメール例文を示します。
【メール例文】
件名:インボイス制度開始に伴うお取引価格に関するご相談
株式会社〇〇
経理部 △△様
いつも大変お世話になっております。
株式会社□□の◇◇です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日は、昨年10月より開始されましたインボイス制度に関連し、誠に恐縮ながら、お取引価格についてご相談させて頂きたくご連絡いたしました。
ご存知の通り、インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者以外の事業者様とのお取引においては、弊社における仕入税額控除に影響がございます。つきましては、貴社との今後のお取引に関しましても、現行のお取引価格について、一度見直しのご検討を賜れますようお願い申し上げる次第です。
大変申し上げにくいお願いであることは重々承知しておりますが、何卒弊社の状況をご賢察いただき、ご協議の機会をいただければ幸いです。詳細につきましては、改めてお電話にてご説明させていただきたく存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討いただけますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
------------------------------------
株式会社□□
部署名:購買部
氏名:◇◇ ◇◇
電話番号:XXX-XXXX-XXXX
メールアドレス:XXXX@example.com
------------------------------------
上記の例文はあくまで一例です。実際の状況や相手との関係性に応じて、文面は調整してください。重要なのは、一方的な要求ではなく、あくまで「相談」という姿勢を貫き、相手への配慮を忘れないことです。
依頼される側|値下げ交渉を受けたときの対応と判断基準
インボイス制度の開始に伴い、取引先より値下げを要求される状況に直面した際に、対応するためのポイントや判断基準、そしてやむを得ず交渉に応じられない場合の伝え方について解説します。
値下げ交渉を受けたらまず確認すべきポイントとは?
取引先から値下げ交渉の打診があった場合、すぐに回答するのではなく、まずは以下の点を冷静に確認しましょう。これらの情報を整理することで、交渉のテーブルにつくべきか、どのような対応が適切かを見極めることができます。
- 交渉の背景と理由:なぜ値下げを要求しているのか、具体的な理由を確認します。インボイス制度への対応(免税事業者との取引継続、仕入税額控除額の変動など)が主な理由なのか、それとも他の要因があるのかを把握することが重要です。
- 要求されている値下げ幅と期間:どの程度の値下げを、いつからいつまで求めているのか、具体的な数値と期間を確認します。要求が一方的で過度なものでないかを見極める材料となります。
- 対象となる取引の範囲:全ての取引に対してなのか、一部の製品やサービスに限った話なのか、値下げの対象範囲を明確にします。
- 既存の契約内容との整合性:現在の契約期間、価格設定の根拠、価格改定に関する条項などを再確認します。契約に基づいた正当な交渉なのか、あるいは契約内容の変更を求めるものなのかを区別します。
- 公正取引委員会の見解との照らし合わせ:独占禁止法や下請法に抵触するような、一方的な値下げ要求や買いたたきに該当しないか、公正取引委員会が示しているガイドラインなどを参考に確認することも大切です。
値下げに応じるべきかどうかの判断基準
値下げ交渉に応じるか否かは、自社の経営状況や取引先との関係性などを総合的に考慮して慎重に判断する必要があります。以下の表は、判断の際に考慮すべき要素と、それぞれのメリット・デメリットを整理したものです。
|
判断要素 |
値下げに応じる場合の視点 |
値下げに応じない場合の視点 |
|
取引の重要性・継続性 |
主要な取引先であり、長期的な関係維持が自社の利益につながる場合は、一部譲歩も検討。 |
代替可能な取引先が存在し、当該取引が終了しても経営への影響が軽微であれば、無理に応じる必要性は低い。 |
|
自社の利益構造・コスト |
値下げ後も十分な利益が確保できる、あるいはコスト削減の余地がある場合は検討可能。 |
値下げにより採算割れする、または品質維持が困難になる場合は、応じるべきではない。 |
|
交渉相手の状況と誠実さ |
相手方もインボイス制度対応で苦慮しており、双方にとって痛み分けとなる建設的な交渉であれば、協力の余地あり。 |
一方的な要求であり、自社の状況を全く顧みないような場合は、毅然とした対応が必要。 |
|
法的リスク・公正性 |
交渉内容が適法であり、双方合意の上であれば問題なし。 |
独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や下請法違反に該当する可能性のある不当な要求には応じるべきではない。 |
|
今後の取引条件の見直し |
今回の値下げを機に、価格以外の取引条件(発注ロット、支払いサイトなど)で有利な条件を引き出せる可能性も考慮。 |
一度値下げに応じると、将来的にさらなる要求につながる懸念がある場合は慎重に判断。 |
これらの要素を総合的に検討し、自社にとって最善の選択肢は何かを判断します。場合によっては、一部条件付きで応じる、あるいは代替案を提示するといった対応も考えられます。
値下げに応じられない場合の伝え方とやわらかい断る例文
経営状況や採算性を考慮した結果、どうしても値下げ要求に応じられない場合もあります。その際は、相手に不快感を与えず、かつ自社の立場を明確に伝えることが重要です。角を立てずに断るための伝え方と、具体的なメール例文を紹介します。
断る際の基本姿勢:
- 感謝の表明:まずは日頃の取引に対する感謝の気持ちを伝えます。
- 理解と共感:相手の状況や値下げ要求の背景に理解を示し、共感する姿勢を見せることが大切です。
- 明確な理由の説明:なぜ値下げに応じられないのか、具体的な理由(例:原材料費の高騰、品質維持のためのコスト、既にギリギリの価格設定であることなど)を丁寧に説明します。
- 代替案の提示(可能な場合):価格以外の部分で協力できることがあれば提案します(例:納期調整、小ロット対応、情報提供など)。
- 今後の関係維持への配慮:今回の件に関わらず、今後も良好な関係を継続していきたいという意思を伝えます。
メールでの断り例文:
件名:価格改定に関するご相談につきまして
株式会社〇〇
〇〇様
いつも大変お世話になっております。株式会社△△の△△です。
この度は、お取引価格に関するご相談をいただき、誠にありがとうございます。
貴社におかれましても、インボイス制度へのご対応など、様々なご尽力があることと拝察いたします。
早速ではございますが、ご要望いただきました価格改定につきまして、社内で慎重に検討を重ねました結果、誠に恐縮ながら、現状の価格を維持させていただきたく、お願い申し上げる次第でございます。
ご期待に沿えず大変申し訳ございませんが、弊社といたしましても、昨今の原材料費や物流コストの高騰が続いており、現行価格の維持自体が厳しい状況でございます。品質やサービスレベルを維持するためには、現在の価格がギリギリのラインであることを何卒ご理解いただけますと幸いです。
価格面でのご協力は難しい状況ではございますが、例えば〇〇(具体的な代替案や協力できる点)といった形であれば、貴社のお役に立てる部分もあるかと存じます。ご検討いただければ幸いです。
この度の件、誠に恐縮ではございますが、何卒弊社の事情をご賢察いただき、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
株式会社△△
△△
電話で伝える際のポイント:
- 相手の言い分を最後まで丁寧に聞く。
- 即答は避け、一度持ち帰って検討する旨を伝える(時間稼ぎではなく、誠実な対応のため)。
- 感情的にならず、落ち着いたトーンで論理的に説明する。
- 断る理由を明確に、しかし相手を追い詰めるような言い方は避ける。
- 今後の関係性も考慮し、対話の窓口は閉ざさない姿勢を示す。
値下げ交渉は、双方にとってデリケートな問題です。誠意ある対応を心がけ、良好な取引関係の維持に努めましょう。
インボイスで値引きがあったときの仕訳はどうする?会計処理をわかりやすく解説
一度発行したインボイス(適格請求書)の内容に変更が生じる「値引き」があった場合、その仕訳処理は正確に行う必要があります。この章では、インボイス制度下での値引き発生時の会計処理について、具体的な仕訳例を交えながらわかりやすく解説します。
値引きが発生するタイミングと仕訳が必要なケースとは
インボイス制度において値引きが発生し、仕訳が必要となるのは、主に以下のようなケースです。
- 売上値引:提供した商品やサービスに品質不良、数量不足、破損などがあった場合に、売上代金の一部または全部を減額すること。
- 売上割戻:一定期間に多量の商品を購入した得意先や、取引条件を達成した得意先に対して、売上代金の一部を返金または減額すること。
- 売上割引:売掛金の早期回収を目的として、支払期日よりも前に支払いが行われた場合に、一定額を売上代金から差し引くこと。(※本章では主に売上値引・割戻を扱います)
これらの値引きは、インボイス発行後に行われることが一般的です。その場合、売手は買手に対して「適格返還請求書(返還インボイス)」を交付し、会計帳簿にもその内容を正確に反映させるための仕訳処理が必要となります。適格返還請求書には、当初のインボイスの内容と、値引きの対象となった取引年月日、値引きの金額(税抜または税込)、適用税率、消費税額等を記載します。
値引きの事実を会計帳簿に記録することで、正しい売上高や消費税額を把握し、適切な税務申告を行うことができます。
値引きされた場合の具体的な仕訳例【売上側の会計処理】
ここでは、売上側(商品を販売したりサービスを提供したりした側)が値引きを行った場合の具体的な仕訳例を見ていきましょう。消費税率は10%と仮定します。
ケース1:商品販売後に品質不良のため値引きした場合(売上値引)
例:110,000円(税込、うち消費税10,000円)で商品を掛け販売し、適格請求書を発行済み。後日、商品の一部に品質不良が見つかり、買手との合意の上で11,000円(税込、うち消費税1,000円)を値引きし、適格返還請求書を発行した。
当初の販売時の仕訳(参考):
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
摘要 |
|
売掛金 |
110,000 |
売上 |
100,000 |
商品販売(株式会社A) |
|
仮受消費税等 |
10,000 |
値引き発生時の仕訳:
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
摘要 |
|
売上値引 |
10,000 |
売掛金 |
11,000 |
品質不良による値引き(株式会社A) |
|
仮受消費税等 |
1,000 |
この仕訳により、売上高から値引き額が控除され、預かった消費税額も修正されます。売掛金の残高も減少します。
ケース2:一定数量以上の購入のため割戻しを行った場合(売上割戻)
例:得意先である株式会社Bに対し、当期の取引高が一定基準を超えたため、契約に基づき売掛金から22,000円(税込、うち消費税2,000円)を割戻し、適格返還請求書を発行した。
割戻し発生時の仕訳:
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
摘要 |
|
売上割戻 |
20,000 |
売掛金 |
22,000 |
取引高達成による割戻(株式会社B) |
|
仮受消費税等 |
2,000 |
売上割戻勘定を用いて処理します。これにより、実際の売上高が減少し、消費税額も調整されます。買掛金と相殺する場合や、現金で返金する場合は貸方の勘定科目が変わります。
インボイス制度下では、値引きや返品があった際には適格返還請求書の保存が仕入税額控除の要件となるため、売手・買手双方で適切な処理と書類管理が重要です。会計ソフトを利用している場合は、ソフトの指示に従って入力することで、消費税区分なども自動で処理されることが一般的ですが、基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
まとめ
インボイス制度の導入により、特に免税事業者との取引において値下げ交渉が発生しやすくなっています。これは、発注側が仕入税額控除を受けられなくなることが主な理由です。ただし、一方的な値下げの要求は法的リスクを伴う可能性もありますので、双方が納得できる形で取引条件を見直すことが肝要です。本記事が、制度の趣旨をふまえたうえでの適正な価格交渉や、実務上の会計処理にお役立ていただければ幸いです。










