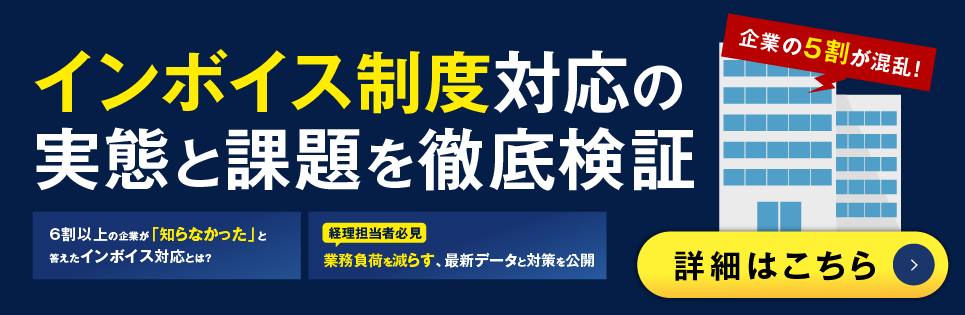インボイス制度で困る人はだれ?関係ない業種や困る人がやりがちな勘違い
更新日:2026.01.15
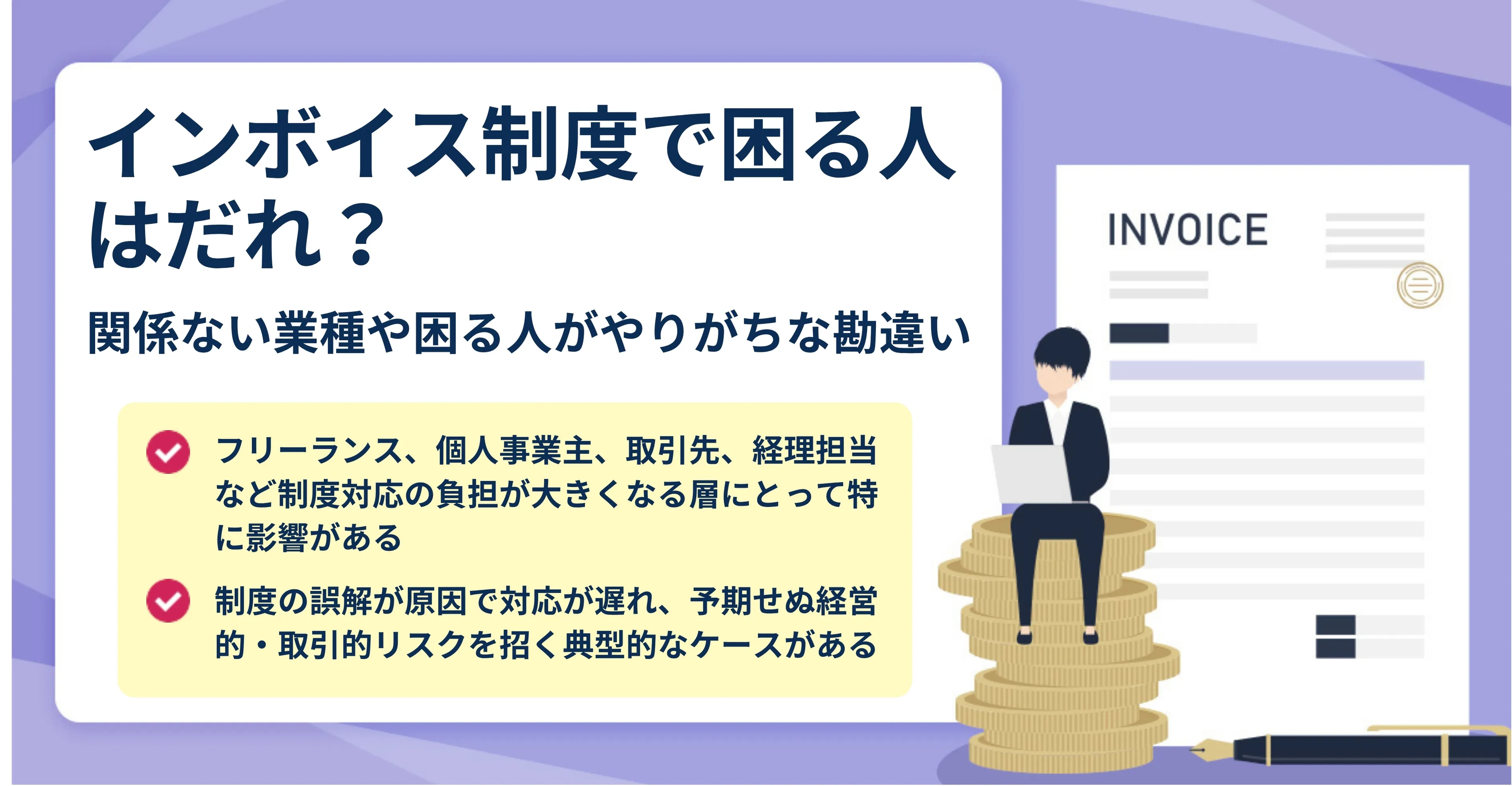
ー 目次 ー
インボイス制度の開始で「誰が困るの?」「自分は大丈夫?」と不安な方も多いでしょう。この記事では、インボイス制度で特に影響を受けるフリーランスなどの免税事業者やその取引先、経理担当者がなぜ困るのか、その具体的な理由と対策を徹底解説。影響が少ない業種や、よくある勘違いも分かります。自身への影響を把握し、適切な準備を進めるための情報が得られます。
インボイス制度の基本をわかりやすく解説!
2023年10月1日から始まったインボイス制度。ニュースや取引先との会話で耳にするけれど、「具体的に何が変わるの?」「自分にはどんな影響があるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。この章では、インボイス制度の基本的な仕組みについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは何か
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式(てきかくせいきゅうしょとうほぞんほうしき)」といいます。これは、複数税率(標準税率10%と軽減税率8%)に対応した消費税の仕入税額控除の新しい方式です。
具体的には、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための「適格請求書(インボイス)」を交付し、双方がその適格請求書を保存することで、買い手は消費税の仕入税額控除を受けることができるようになります。
ここで重要なのが「適格請求書」と「仕入税額控除」です。
- 適格請求書(インボイス):売手が買手に対して発行する請求書や領収書などで、以下の情報が記載されたものを指します。
- 発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- その他、従来の請求書に記載されていた事項(発行者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、対価の額、受領者の氏名または名称)
- 仕入税額控除:事業者が商品やサービスを販売した際に預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて、実際に納める消費税額を計算する仕組みのことです。インボイス制度導入後は、原則としてこの「適格請求書」の保存が仕入税額控除を受けるための要件となります。
なぜインボイス制度が導入されたのか?その目的と影響
インボイス制度が導入された主な目的は、以下の2点です。
- 複数税率への正確な対応
2019年10月に消費税率が10%に引き上げられた際、食料品など一部の品目については軽減税率8%が適用されることになりました。この複数税率の状況下で、取引における正確な適用税率と消費税額を把握し、適正な納税を確保するためにインボイス制度が必要とされました。 - 仕入税額控除の適正化
従来の制度では、免税事業者からの仕入れであっても、一定の要件を満たせば仕入税額控除が可能でした。しかし、これにより、本来国に納付されるべき消費税の一部が事業者の手元に残る「益税」が生じているとの指摘がありました。インボイス制度は、適格請求書発行事業者からの仕入れに限定して仕入税額控除を認めることで、この益税問題の解消を目指しています。
インボイス制度の導入は、特に免税事業者や、免税事業者と取引のある課税事業者に大きな影響を与えます。また、企業の経理業務にも新たな対応が求められることになります。具体的な影響については、後の章で詳しく解説していきます。
インボイス制度の影響が少ない、または関係ない業種や立場の人は?
インボイス制度は多くの事業者に影響を与えますが、中には影響が比較的小さい、あるいは直接的には関係ない業種や立場の人もいます。ここでは、どのようなケースが該当するのか具体的に見ていきましょう。
主に一般消費者向け(BtoC)事業を行っている人
インボイス制度で発行が求められる「適格請求書(インボイス)」は、主に事業者間取引(BtoB)において、買手側が仕入税額控除を受けるために必要となるものです。そのため、商品の販売先やサービスの提供先が一般消費者であるBtoC(Business to Consumer)事業を主軸としている場合、インボイスの発行を求められる場面は限定的です。
例えば、以下のような業種が該当します。
- 小売店(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、アパレルショップなど)
- 飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)
- 美容室、理容室、エステサロン
- 学習塾、習い事教室(個人向け)
- 医療機関(自由診療の一部を除く保険診療など)
これらの事業者は、最終消費者が仕入税額控除を行うことがないため、インボイスの発行を求められるケースは少ないでしょう。ただし、事業者向けに商品やサービスを提供する場合(例えば、企業向けのケータリングや社員研修など)は、インボイスの発行が必要になる可能性があります。
会社員などの給与所得者はインボイス制度と関係ない?
会社員や公務員など、雇用契約に基づいて給与を得ている給与所得者の方々は、基本的にインボイス制度とは直接関係ありません。給与は消費税の課税対象ではないため、インボイスの発行も受領も不要です。
ただし、会社員の方が副業として個人事業を行っており、その事業で課税売上があり、取引先からインボイスの発行を求められる場合は、インボイス制度への対応を検討する必要があります。副業の内容や取引先によって状況が異なるため、自身の状況を確認することが大切です。
その他、インボイス制度の影響を直接受けにくいケース
BtoC事業や給与所得者以外にも、インボイス制度の影響を直接受けにくい、あるいは影響が限定的なケースがあります。主なケースを以下に示します。
|
ケース |
影響が少ない主な理由 |
注意点・補足 |
|
免税事業者との取引がほとんどない課税事業者 |
仕入税額控除の相手先が主に課税事業者(適格請求書発行事業者)であるため、仕入税額控除への影響が小さい。 |
今後、免税事業者との新規取引が発生する可能性も考慮が必要です。 |
|
輸出取引がメインの事業者 |
輸出売上は消費税が免除されるため、売上にかかる消費税の納税はありません。ただし、仕入れにかかる消費税の還付を受ける際には、仕入先からのインボイスが必要になる場合があります。 |
国内での課税仕入れがある場合、その仕入税額控除のためにはインボイスの保存が必要です。 |
|
簡易課税制度を選択している事業者 |
仕入税額控除の計算を、実際の仕入れにかかる消費税額ではなく、課税売上げにかかる消費税額にみなし仕入率を乗じて行うため、インボイスの保存は仕入税額控除の要件ではありません(ただし、帳簿への記載は必要)。 |
簡易課税制度を選択するには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるなどの適用条件があります。また、取引先からインボイスの発行を求められる可能性はあります。 |
|
居住用不動産の賃貸収入が主体の事業者(大家さんなど) |
居住用の家賃収入は消費税が非課税のため、インボイスの発行義務がありません。 |
事務所や店舗など事業用不動産の賃貸収入は課税売上となり、借主が課税事業者であればインボイスの発行を求められることがあります。 |
|
社会福祉事業や医療保険適用の医療を行う事業者 |
提供するサービスの多くが社会政策的配慮から消費税非課税とされているため、インボイスの発行義務が生じる場面が少ないです。 |
医薬品や医療機器の仕入れなど課税仕入れがある場合、その仕入税額控除のためにはインボイスの保存が必要になることがあります。また、自由診療など一部課税取引がある場合は対応が必要です。 |
これらのケースに該当する場合でも、取引内容や取引先の状況によってはインボイス制度への対応が必要になることもあります。自身の事業形態や取引関係を正確に把握し、制度への理解を深めることが重要です。
インボイス制度で特に困る人はこんな人!具体的なケースを紹介
インボイス制度の導入により、特定の立場や状況にある事業者は、業務や経営に大きな影響を受ける可能性があります。ここでは、特に影響が大きいと考えられる具体的なケースを見ていきましょう。
免税事業者のフリーランスや個人事業主が困る理由
インボイス制度で最も大きな影響を受けると言われているのが、売上1,000万円以下の免税事業者であるフリーランスや個人事業主の方々です。主な理由は以下の通りです。
- 取引先からの値下げ圧力や取引打ち切りのリスク: 前述のように免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先である課税事業者は、免税事業者からの仕入れにかかる消費税額を仕入税額控除できなくなります。結果として、取引先から消費税相当額の値下げを要求されたり、インボイスを発行できる他の事業者との取引を優先され、契約を打ち切られたりする可能性があります。
- 課税事業者になるかの選択と負担増: 取引を維持するために適格請求書発行事業者の登録を受け、課税事業者になる選択肢があります。しかし、課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の申告・納税義務が発生し、経理処理の負担も増加します。小規模な事業者にとっては、この事務負担や納税負担が経営を圧迫する要因となり得ます。
- 競争力の低下: 同業の事業者が課税事業者としてインボイスを発行できる場合、免税事業者のままでは価格競争や取引先の選択において不利になる可能性があります。
免税事業者と取引のある課税事業者が困る理由
免税事業者との取引が多い課税事業者も、インボイス制度によって以下のような点で困ることが予想されます。
- 仕入税額控除の制限による納税額の増加: 免税事業者や、適格請求書発行事業者として登録していない課税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除が適用できなくなります。これにより、消費税の納税額が増加する可能性があります。ただし、制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
|
期間 |
免税事業者からの仕入れに係る控除割合 |
|
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
|
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
|
2029年10月1日以降 |
控除不可 |
- 取引先の見直しや交渉の必要性: 仕入税額控除を維持するためには、取引先の免税事業者に適格請求書発行事業者への登録を依頼するか、インボイスを発行できる他の事業者へ取引を切り替えることを検討する必要が出てきます。これには、交渉の手間や新たな取引先を探すコストが発生します。
- 経理処理の複雑化: 受け取った請求書が適格請求書であるかを確認し、そうでない場合は仕入税額控除の対象外として処理するなど、経理処理が煩雑になります。
企業の経理担当者が困る業務負担の増加とシステム対応
企業の規模に関わらず、経理担当者の業務負担はインボイス制度によって増加する可能性が高いです。具体的には以下のような点が挙げられます。
- 請求書の確認・管理業務の増加:
- 受け取った請求書が適格請求書の要件(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額など)を満たしているか、一枚一枚確認する作業が発生します。
- 適格請求書とそれ以外の請求書を区別して保存・管理する必要があります。
- 消費税の計算・申告業務の複雑化:
- 仕入税額控除の計算がより複雑になります。特に、免税事業者からの仕入れや、経過措置の適用がある取引が含まれる場合は注意が必要です。
- 売上税額の計算方法として、割戻し計算だけでなく、インボイスに記載された消費税額を積み上げて計算する方法も認められるようになり、どちらを採用するか、あるいは併用するかの検討も必要です。
- 会計システムや販売管理システムの対応:
- インボイス制度に対応した会計ソフトや販売管理システムへのアップデート、場合によってはシステムの改修や新規導入が必要になります。これにはコストや導入・移行期間も考慮しなければなりません。
- 電子インボイス(デジタルインボイス)の導入を検討する場合、新たな業務フローの構築やシステム連携も課題となります。
以下に、経理担当者が新たに対応を迫られる可能性のある業務内容をまとめます。
|
業務区分 |
具体的な対応内容・負担 |
|
受取請求書の処理 |
適格請求書の記載要件確認、登録番号の照合、請求書の仕分け・保存方法の見直し。 |
|
発行請求書の処理 |
適格請求書発行事業者である場合、自社が発行する請求書のフォーマット変更、記載事項の追加。 |
|
消費税申告業務 |
仕入税額控除の計算ルールの変更への対応、経過措置の適用判断、税額計算の複雑化。 |
|
システム関連 |
会計システム・販売管理システムのインボイス制度対応(アップデート、改修、新規導入)、電子インボイス対応検討。 |
|
取引先との連携 |
取引先へのインボイス対応状況の確認、免税事業者である取引先への対応方針検討。 |
インボイス制度で困る人がやりがちな勘違いワースト3
インボイス制度の導入により、制度を誤解したまま気づかないうちに不利な状況に陥ってしまうケースも少なくありません。ここでは、インボイス制度で困る人が特にやりがちな勘違いを3つピックアップし、それぞれ詳しく解説します。
勘違い1「自分は免税事業者だからインボイスは関係ない」という誤解
「自分は売上1,000万円以下の免税事業者だから、インボイス制度は関係ない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。確かに、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行する義務はありません。しかし、これは大きな誤解です。
あなたの取引先が課税事業者である場合、その取引先はあなたからの仕入れについて仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要になります。あなたがインボイスを発行できない免税事業者であると、取引先は消費税分の負担が増えることになりかねません。その結果、取引先から値下げを要求されたり、最悪の場合、取引自体を見直されたりする可能性があるのです。
勘違い2「課税事業者になればインボイスの問題は全て解決する」という思い込み
「インボイス制度で困らないためには、適格請求書発行事業者として登録し、課税事業者になれば良い」と考えるのは、一見すると正しいように思えます。確かに、課税事業者になればインボイスを発行できるようになり、取引先との関係も維持しやすくなるでしょう。
しかし、課税事業者になるということは、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生することを意味します。売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた額を国に納める必要があり、経理処理も複雑になります。また、インボイスに対応した請求書の発行や保存、消費税申告のための準備など、新たな業務負担も増えます。
課税事業者になることで解決する問題もありますが、同時に新たな課題も生じます。自身の事業規模や取引先の状況、そして利用できる負担軽減措置(例:2割特例など)を総合的に比較検討し、最適な選択をすることが重要です。「課税事業者になれば全て解決」という思い込みは避けましょう。
勘違い3「インボイス制度の対応はまだしなくて大丈夫」という油断
インボイス制度開始後も「まだ本格的な対応は先で大丈夫だろう」と油断している方もいるかもしれません。しかし、この油断が後々大きな問題を引き起こす可能性があります。
例えば、適格請求書発行事業者の登録申請は、申請から登録通知を受け取るまでに一定の期間を要します。また、取引先との間でインボイスに関する取り決めや価格交渉が必要になる場合、それには相応の時間が必要です。経理システムの見直しや新しい会計ソフトの導入、従業員への周知徹底なども、すぐに完了するものではありません。早め早めの対策を講じることが、スムーズな制度移行の鍵となります。
インボイス制度で困る人が今すぐ確認し対策すべきこと
インボイス制度の開始により、影響を受ける可能性がある方は、早めの確認と対策が不可欠です。具体的にどのような点を確認し、どのような対策を講じるべきかを見ていきましょう。
自身の事業状況とインボイス制度への影響を正確に把握する
まず、ご自身の事業がインボイス制度によってどのような影響を受けるのかを正確に把握することが第一歩です。以下の表を参考に、現状を整理してみましょう。
|
確認ポイント |
具体的な確認内容 |
|
現在の事業者区分 |
ご自身が免税事業者なのか、それとも課税事業者なのかを確認します。 |
|
主な取引先の状況 |
主な取引先が課税事業者なのか、免税事業者(または一般消費者)なのかを把握します。特にBtoB取引が多い場合は注意が必要です。 |
|
取引先からの要請 |
既に取引先から適格請求書(インボイス)の発行について問い合わせや要請があるか、今後求められる可能性が高いかを確認します。 |
|
課税事業者になった場合の影響試算 |
免税事業者が課税事業者になる場合、消費税の納税負担がどの程度増えるのか、また経理処理の変更に伴う事務負担やコスト(会計ソフトの導入・更新など)を試算します。 |
これらの情報を基に、インボイス制度への対応方針を検討する必要があります。
取引先との早めの情報共有とインボイス対応に関する協議
インボイス制度への対応は、自社だけで完結するものではなく、取引先との連携が非常に重要です。特に免税事業者の方は、今後の取引条件について取引先と早めに話し合うことをおすすめします。
具体的には、以下のような点を協議・確認しましょう。
- 適格請求書発行事業者になる予定があるか、またはならないか。
- ならない場合、取引価格や取引条件に変更が生じる可能性があるか。
- 取引先が適格請求書発行事業者でない場合、自社の仕入税額控除にどのような影響があるか。
お互いの状況を理解し、円滑な取引継続のために対話を進めることが大切です。
税理士など専門家への相談でインボイスの疑問を解消
インボイス制度は複雑であり、個々の事業状況によって最適な対応策は異なります。判断に迷う場合や、より詳細なアドバイスが必要な場合は、税理士や税務署、商工会議所などの専門機関に相談することを強く推奨します。
専門家からは、以下のようなサポートが期待できます。
- 制度内容の正確な理解と、自社の状況に合わせた具体的な影響の分析。
- 課税事業者への転換シミュレーションや、節税対策に関するアドバイス。
- 適格請求書発行事業者の登録申請手続きのサポート。
- 利用可能な補助金や支援制度の情報提供。
専門家の知見を活用し、疑問点を解消して適切な判断を下しましょう。
必要に応じた適格請求書発行事業者の登録準備
取引先との関係や事業戦略を踏まえ、適格請求書発行事業者になることを決めた場合は、速やかに登録準備を進める必要があります。登録は任意ですが、課税期間の初日から登録を受けるためには、原則としてその課税期間の初日の15日前(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、当該課税期間の初日)までに申請が必要です。
登録準備の主なステップは以下の通りです。
|
準備段階 |
具体的な内容 |
|
登録申請の検討・判断 |
自社の事業への影響、取引先の意向などを総合的に考慮し、登録するか否かを最終判断します。 |
|
申請手続きの確認と実施 |
国税庁のウェブサイト(e-Taxソフト(WEB版・SP版)または書面)で申請方法を確認し、必要な情報を準備して申請手続きを行います。マイナンバーカードと電子証明書があるとオンラインでスムーズに申請できます。 |
|
登録番号の管理と通知 |
登録が完了すると、税務署から登録番号が通知されます。この登録番号は適格請求書に記載する必要があるため、正確に管理し、取引先にも適切に通知します。 |
|
請求書フォーマットの変更 |
適格請求書の記載要件(登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等)を満たした請求書や領収書のフォーマットを準備します。会計ソフトや請求書発行システムを利用している場合は、対応状況を確認し、必要に応じてアップデートや設定変更を行います。 |
制度開始直前は申請が集中する可能性もあるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。
まとめ
インボイス制度は、特に免税事業者やその取引先となる課税事業者、さらには経理業務を担当される方々に大きな影響を与える制度です。「自分には関係ない」と思っていた方も、取引先や副業などを通じて間接的に影響を受ける可能性は少なくありません。
ご自身の立場や事業環境を見直し、必要な準備を早めに進めておくことが、トラブルを避けるカギとなります。もし不安や疑問がある場合は、税理士など専門家に相談することもご検討ください。制度を正しく理解し、落ち着いて対応していくことが大切です。