インボイス制度後の発注書・注文書はどうなる?記載項目やテンプレートを解説
更新日:2026.01.13
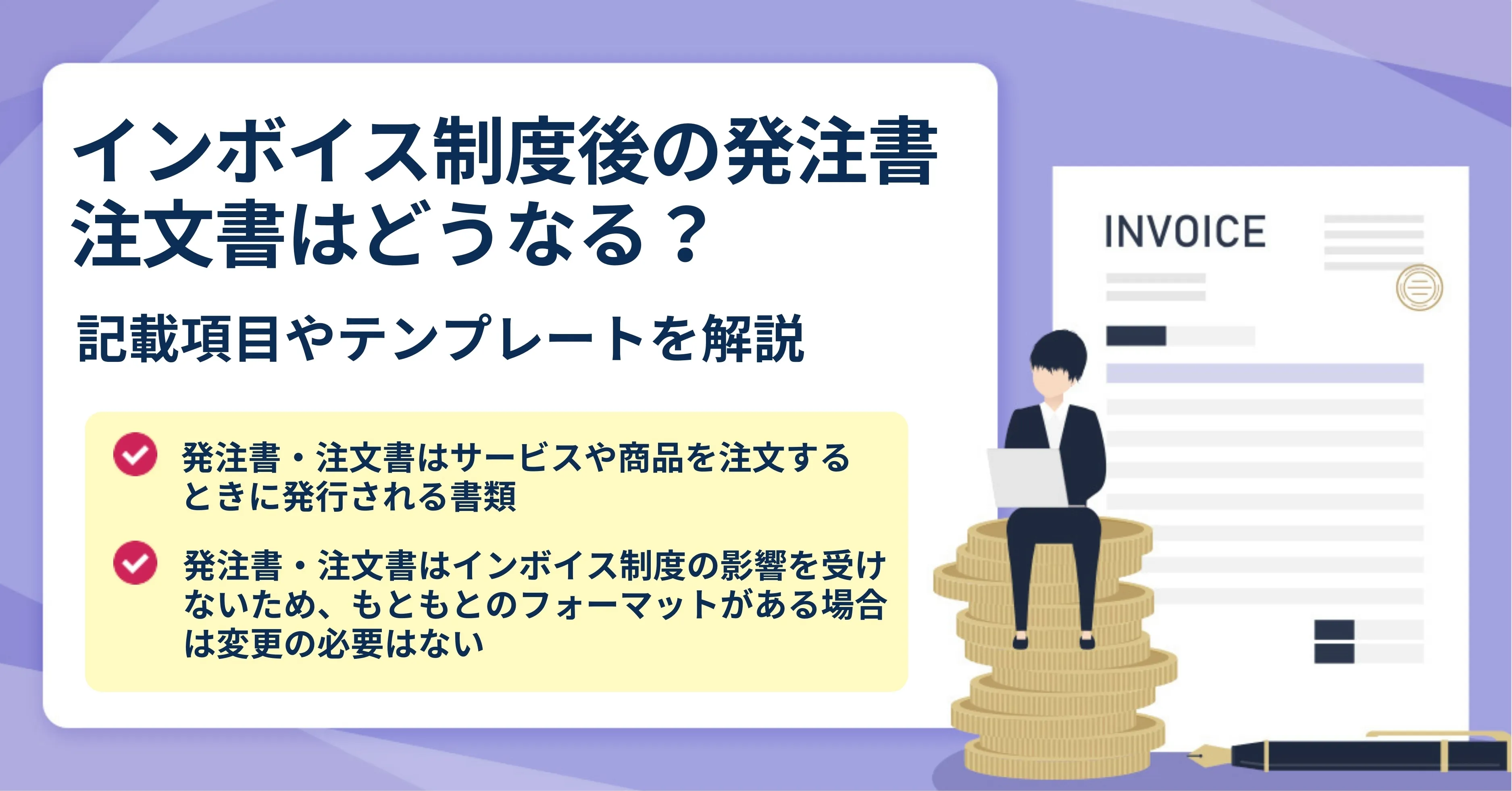
ー 目次 ー
インボイス制度の施行により、請求書や領収書、納品書などの書類はテンプレートの変更が必要になりました。特に、多くの取引先を抱える企業は、インボイス制度の影響を受ける書類を理解しておくことで、書類作成時の混乱を避けられるでしょう。
本記事では、発注書・注文書の基本情報やインボイス制度での対応方法を解説します。そのまま使用できるテンプレートも紹介するため、自社に合わせて発注書・注文書を作成したい場合もぜひ参考にしてください。
インボイス制度の前に!発注書・注文書の基本情報
ビジネスシーンでは利用する書類の種類が多いため、発注書・注文書を発行する前に、書類の基本情報を理解しておくことで用途を誤る心配がありません。似ている用語との違いも解説するため、あわせて内容を理解しておきましょう。
ここでは、発注書・注文書の基本情報を解説します。
発注書・注文書は商品やサービスを注文するときに発行する書類
発注書・注文書は、サービスや商品を注文するときに発行される書類です。
発注書・注文書は、下請法が適用される取引である製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の場合は発行が義務付けられています。ただし、下請取引と見なされる範囲は、取引内容や取引当事者の資本金の区分によっても異なるため、取引前に確認しておくと安心です。
なお、発注書・注文書が義務ではない取引でも、発行しておくことで認識の齟齬を防げる可能性があります。
発注書・注文書と発注請書の違い
発注書・注文書はどちらも商品やサービスを注文するときに発行する書類のため、明確な違いはありません。取引先にあわせた言葉を使用すると、齟齬が防げます。
一方で、発注請書は商品やサービスを提供する側が、発注者に対して発注を受けたことを伝える目的で発行する書類です。発注書・注文書と発注請書では発行者が異なるため、誤って言葉を使用しないよう注意しましょう。
発注書・注文書を発行するまでの流れ
発注書・注文書や発注請書を発行する場合は、以下の流れで取引が進みます。
- 発注者が商品・サービスの提供側に見積りを依頼する
- 提供側が見積書を発行する
- 発注側が見積書の内容を確認し、納得したら発注書・注文書を発行する
- 提供側が発注請書を発行する
取引が開始する流れは企業によって異なるため、必ずしも上記の通りに進むとは限りません。不明な点があれば取引前に確認しておき、不安のない状態で取引を開始しましょう。
【結論】発注書・注文書はインボイス制度の影響を受けない
発注書・注文書は商品・サービスを提供する前に発行される書類のため、インボイス制度の影響を受けません。すでに自社のフォーマットがある場合は、変更せず使用できます。
インボイス制度の影響を受ける書類は、請求書や領収書、納品書が一般的です。
なお、発注書・注文書をインボイス制度に合わせて対応する場合は、書類に登録番号の記載事項を追加しておくことがおすすめです。登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録した際に通知されるTから始まる13桁の数字を指します。発注書に記載することで、取引先が登録番号を確認する手間を減らせます。
一般的な発注書・注文書の記載項目
新しく発注書・注文書のテンプレートを作る場合は、記載項目を理解しておくことでスムーズに作業が進められます。項目を理解しないまま作業を始めると、漏れやミスにつながり信頼関係を失う原因になりかねません。
ここでは、一般的な発注書・注文書の記載項目を解説します。
- 発行日・発行番号
- 交付先
- 発行者情報
- 取引内容
- 納期・支払条件
①発行日・発行番号
発注書・注文書には、発行日と発行番号を記載しましょう。発行日は、発注書・注文書を作成した日を記載します。
発行番号は必須ではないものの、記載しておくことで同月に同じ取引先と複数の書類をやりとりする際に、別の取引だと判断しやすくなります。
②交付先
発注書・注文書の交付先は、商品やサービスを提供する企業や個人事業主の名称を記載しましょう。
記載する名称は、取引先に直接確認しておくことでミスを減らせます。書類の交付先には、名称のあとに個人の場合は「様」、法人の場合は「御中」を記載します。
③発行者情報
発注書・注文書を作成する場合は、取引先が管理しやすいように自社の名称や連絡先などを記載しておきましょう。
連絡先には住所・電話番号・担当者を記載しておくことで、取引先が問い合わせるときに担当者を調べる手間を減らせます。
④取引内容
発注書・注文書の取引内容は、商品名・合計金額・数量・単価・消費税などを記載しましょう。商品名を記載するときは、正式名称や型番を明記しておくことで齟齬の可能性を減らせます。
合計金額を、税込・税抜のどちらで記載するかは法律上の決まりはありません。しかし、税込の金額を記載しておくことで企業が最終的に支払う金額が明確になり、わかりやすい発注書・注文書になります。
⑤納期・支払条件
発注書・注文書には、認識の齟齬を避けるために納期や支払条件も記載しておきましょう。
納期や支払条件は、取引先と相談したうえで決定することでトラブルを防げます。納期や支払条件に不安がある場合は、取引が確定する前に取引先に再度確認しておくと安心です。
インボイス制度後も使用可能な発注書・注文書のテンプレート
インボイス制度にあわせて発注書・注文書のテンプレートを変更する必要はありません。まだ自社のテンプレートがない場合は、事前に作成しておくことで発注書・注文書の作成がスムーズになります。
|
発注書 発注日:〇年〇月〇日 株式会社〇〇 御中 自社の企業名 下記の通り、発注いたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インボイス制度と発注書・注文書にまつわるよくある質問2選
ここからは、インボイス制度と発注書・注文書にまつわるよくある質問に回答します。
インボイス制度後の発注書・注文書には登録番号が必要?
インボイス制度導入後も発注書・注文書には登録番号の記載は必要ありません。
ただし、登録番号を記載しておくことで、企業が確認したいときに問い合わせる手間を減らせます。適格請求書発行事業者との取引が多い場合は、テンプレートへの追加を検討しましょう。
インボイス制度後の発注書・注文書の保存期間は?
発注書・注文書は国税関係書類に該当するため、法人の場合は確定申告書の提出期限の翌日から7年間、個人事業主の場合は5年間の保存が義務付けられています。
保存しなかった場合は、ペナルティとして青色申告者の承認を取り消される可能性があるため注意しましょう。
まとめ|インボイス施行後も自社に合わせた発注書・注文書を発行しよう
本記事では、発注書・注文書の基本情報やインボイス制度での対応方法を解説しました。
発注書・注文書はインボイス制度の影響を受けないため、自社のテンプレートを変更する必要はありません。新しく発注書・注文書のテンプレートを作成する場合は、適格請求書発行事業者の登録番号を記載しておくことで、取引先が確認する手間を減らせます。
発注書・注文書の作り方に悩んだときは、本記事を参考に自社に合ったテンプレートを作成しましょう。










