インボイス制度では振込手数料の相殺に注意!知らないと損する会計ルール
更新日:2025.12.07
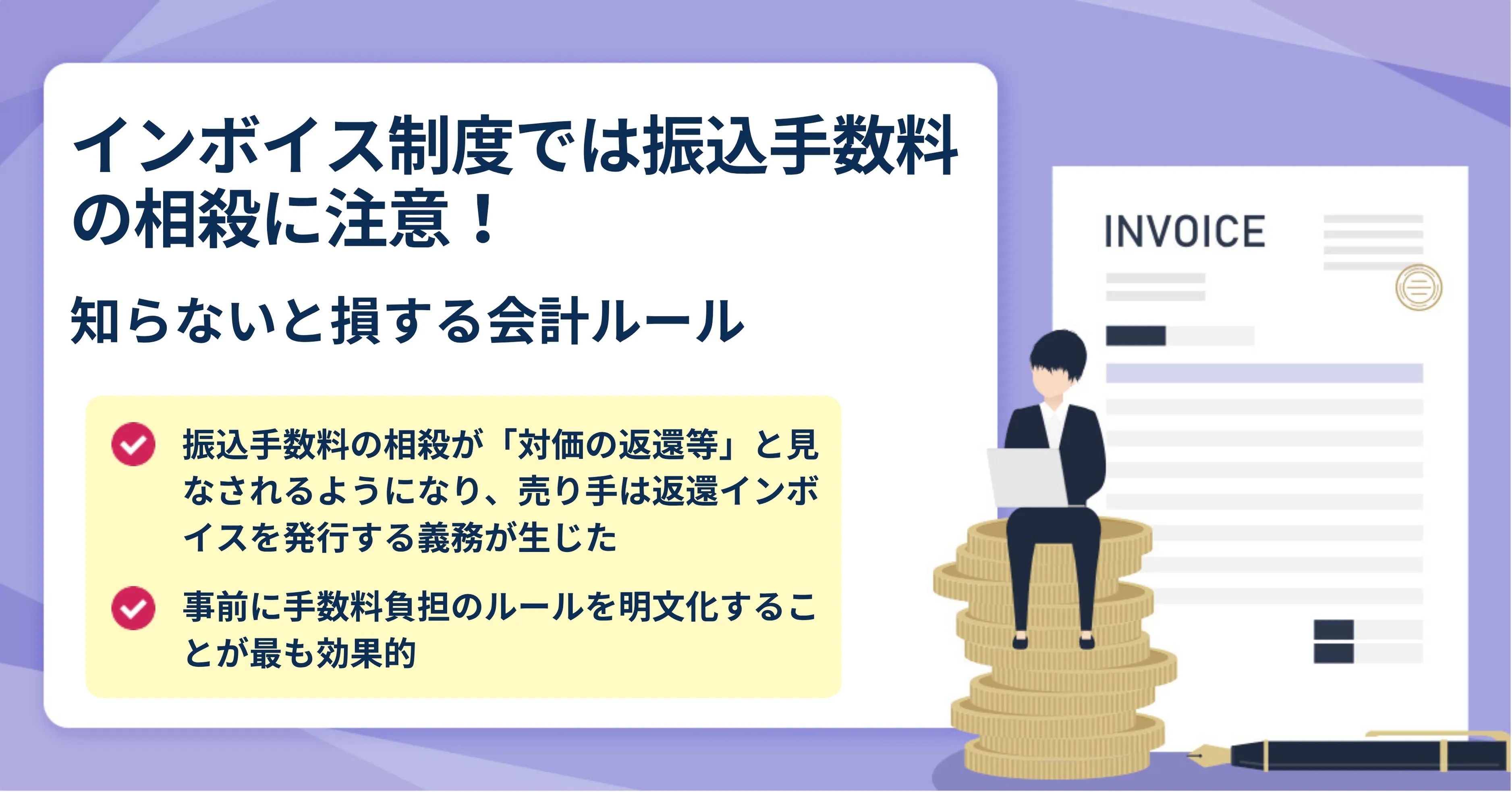
ー 目次 ー
インボイス制度の導入により、振込手数料の相殺処理について注意すべき点が増えました。従来は慣習的に行われていた処理でも、新制度下では「売上値引き」と見なされ、売り手側に返還インボイスの発行義務が生じるケースがあります。対応を誤ると、買い手が仕入税額控除を受けられなくなるなど、予期せぬ不利益につながる可能性も。この記事では、こうしたリスクを避けるために必要な売り手・買い手双方の実務対応や仕訳例、少額特例の扱いまで、分かりやすく解説いたします。
インボイス制度と振込手数料の相殺、どこが問題なの?
2023年10月1日から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、多くの事業者の経理業務に影響を与えています。特に、取引で慣習的に行われてきた「振込手数料の相殺」について、新たな会計処理や書類発行の手間が発生し、知らないと思わぬ損をする可能性があります。
これまで、買い手(支払側)が売上代金から振込手数料を差し引いて支払うことは、双方の合意があれば特に問題視されませんでした。しかし、インボイス制度下では、この「相殺」という行為が消費税の計算に大きく関わるため、注意が必要です。本章では、なぜ振込手数料の相殺が問題視されるようになったのか、その根本的な原因と、売り手・買い手双方に求められる対応の概要を解説します。
仕入税額控除のルール変更が根本的な原因
インボイス制度で振込手数料の相殺が問題となる根本的な原因は、消費税の「仕入税額控除」のルールが厳格化されたことにあります。仕入税額控除とは、課税事業者が納める消費税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引く仕組みのことです。
インボイス制度開始後は、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ、この仕入税額控除が受けられなくなりました。そして、振込手数料の相殺は、税務上「売上にかかる対価の返還等」とみなされます。これは、売り手が受け取るはずだった代金の一部を、振込手数料という形で買い手に返還した(値引きした)と解釈されるためです。
この「対価の返還等」を行った売り手には、その事実を証明する「適格返還請求書(返還インボイス)」を買い手に交付する義務が生じます。つまり、制度開始前と後では、下表のように取り扱いが大きく変わりました。
|
インボイス制度 開始前 |
インボイス制度 開始後 |
|
|
振込手数料相殺の解釈 |
当事者間の合意に基づく商慣習 |
売上にかかる対価の返還等(売上値引) |
|
仕入税額控除の要件 |
帳簿および請求書等の保存 |
原則として適格請求書(インボイス)の保存 |
|
売り手の義務 |
特になし(当事者間の合意による) |
適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務が発生 |
このように、これまで当たり前だった振込手数料の相殺が、インボイス制度によって消費税の仕入税額控除と密接に結びつき、新たな書類発行の義務を伴うようになったのです。
売り手と買い手双方で新たな対応が必要に
振込手数料の相殺に関するルール変更は、取引を行う売り手と買い手の双方に影響を及ぼし、それぞれで新たな対応が求められます。
【買い手(支払側)の対応】
買い手が振込手数料を相殺した場合、その手数料分について仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手から「返還インボイス」を交付してもらう必要があります。もし返還インボイスがなければ、その手数料にかかる消費税額を控除できず、結果的に納税額が増えてしまう可能性があります。そのため、取引先に返還インボイスの発行を依頼するか、後述する別の方法を検討するなど、事務処理が従来よりも煩雑になります。
【売り手(受取側)の対応】
一方、売り手は買い手から振込手数料を相殺された場合、それは「売上値引」にあたるため、買い手に対して返還インボイスを交付する義務が生じます。数百円程度の振込手数料のために、わざわざ返還インボイスを作成・送付する手間が発生することになります。特に取引先が多い場合、この事務負担は無視できません。
|
立場 |
インボイス制度下での主な課題 |
|
買い手(支払側) |
仕入税額控除を受けるために、売り手から返還インボイスを取得する必要がある。 |
|
売り手(受取側) |
手数料を相殺された場合、買い手へ返還インボイスを交付する義務が生じる。 |
このように、振込手数料の相殺は、インボイス制度をきっかけに売り手・買い手双方にとって見過ごせない経理上の論点となったのです。後の章では、この問題に対する具体的な会計処理や実務対策を詳しく解説していきます。
そもそも振込手数料の負担はどちら?国税庁の見解
インボイス制度の導入により、振込手数料の相殺処理が複雑になりました。しかし、その前に「そもそも振込手数料は売り手と買い手のどちらが負担すべきなのか」という根本的な疑問があります。この点について、国税庁も参照する法律上の原則と、特定の取引形態における注意点を解説します。
結論から言うと、振込手数料の負担者について法律で一律に定められているわけではなく、当事者間の契約や合意が最も優先されます。合意がない場合に、法律の原則が適用されることになります。
民法における原則的な考え方
当事者間で振込手数料の負担について特に取り決めがない場合、民法の原則に従うことになります。民法第484条では、弁済(代金の支払いなど)にかかる費用は、原則として債務者(代金を支払う側・買い手)が負担すると定められています。
これは「持参債務の原則」という考え方に基づいています。代金の支払いは、本来であれば債権者(代金を受け取る側・売り手)の住所に持参して行うのが原則であり、その際にかかる交通費などは債務者(買い手)が負担すべき、という考え方です。銀行振込は、この「持参」に代わる手段と解釈されるため、その際に発生する振込手数料も債務者(買い手)が負担するのが原則となります。
ただし、これはあくまで双方の合意がない場合の原則です。契約書などで「振込手数料は売り手負担とする」といった特約があれば、その合意が優先されます。
下請法が適用される場合の注意点
取引が「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の適用対象となる場合は、民法の原則よりも下請法が優先されるため、特に注意が必要です。
下請法では、親事業者(発注者・買い手)が下請事業者(受注者・売り手)の責めに帰すべき理由なく、発注した物品等の代金を減額することを禁止しています(下請代金の減額の禁止)。親事業者が一方的に振込手数料を下請代金から差し引いて支払う行為は、この「下請代金の減額」に該当し、下請法違反となるおそれがあります。
ただし、下請事業者との間で「振込手数料は下請事業者の負担とする」という旨を事前に書面等で合意している場合は、例外的に問題ないとされています。
|
ケース |
下請法違反の可能性 |
|
親事業者が、下請事業者との合意なく一方的に振込手数料を差し引いて支払った。 |
違反となる可能性が非常に高いです。 |
|
事前に書面などで、振込手数料を下請事業者が負担することについて双方が合意している。 |
原則として違反にはなりません。 |
このように、インボイス制度への対応を考える以前に、自社の取引が下請法に該当するかどうかを確認し、手数料負担のルールを取引先と明確に合意しておくことが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
【買い手・支払側】インボイス制度での振込手数料相殺の会計処理
インボイス制度の開始後、買い手(支払側)が売買代金から振込手数料を相殺して支払う場合、消費税の仕入税額控除を正しく受けるために、原則として新たな対応が必要になりました。これは、振込手数料の相殺が消費税法上の「対価の返還等」に該当するためです。具体的にどのような処理が必要になるのか、3つの方法と仕訳例を解説します。
特例もアリ!税込1万円未満の振込手数料相殺は返還インボイス不要
実務上の負担を軽減するため、振込手数料のように少額な対価の返還等については特例が設けられています。具体的には、相殺する振込手数料の金額が税込1万円未満である場合、「少額な返還インボイスの交付義務免除」の特例が適用されます。
この特例により、買い手は売り手から返還インボイスを交付してもらう必要がありません。その代わり、以下の事項を記載した帳簿を保存するだけで、仕入税額控除の調整(控除額を減らす処理)を行うことが認められます。
- 対価の返還等を受けた相手方の氏名または名称
- 対価の返還等を受けた年月日
- 取引内容(「〇月〇日仕入の振込手数料」など)
- 対価の返還等を受けた金額
- この特例の適用を受ける旨(例:「少額特例」など)
多くの企業の振込手数料は税込1万円未満に収まるため、この特例を適用することで、経理業務の煩雑化を防ぐことができます。
売り手から返還インボイスを発行してもらう
相殺する振込手数料が税込1万円以上の場合や、特例を適用しない場合の原則的な方法が、売り手から「返還インボイス(適格返還請求書)」を発行してもらうことです。
買い手は、代金を支払う際に振込手数料を相殺する旨を売り手に伝え、返還インボイスの交付を依頼します。そして、受け取った返還インボイスを、もともとの請求書(インボイス)と一緒に保存しておく必要があります。この2つの書類を保存することで、対価の返還等があった事実と、それに基づき仕入税額控除額を正しく調整したことを証明できます。
買い手が仕入明細書を作成し相手の確認を受ける
売り手に返還インボイスの発行を依頼する代わりに、買い手側で処理を完結させる方法もあります。それが「仕入明細書」を活用する方法です。
この場合、買い手は仕入明細書を作成し、通常の記載事項に加えて「振込手数料相当額を値引きした」という対価の返還等に関する内容を明記します。そして、その仕入明細書を売り手に送付し、内容に誤りがないか「確認を受ける」必要があります。
相手方の確認を受けた仕入明細書は、返還インボイスと同様の効力を持ちます。これにより、買い手は仕入税額控除の調整が可能となります。この方法は、特に継続的な取引がある場合に、双方の事務負担を軽減する有効な手段となり得ます。
振込手数料の相殺は「対価の返還等」に該当する
インボイス制度では、課税事業者が対価の返還等を行った場合、原則として相手方に返還インボイスを交付する義務があります。買い手は、この返還インボイスを受け取ることではじめて、支払った消費税額から値引き分の消費税額を減額する調整(仕入税額控除の調整)が法的に認められるのです。
ケース別|買い手側の仕訳例
実際に振込手数料を相殺した場合の会計処理(仕訳)を見ていきましょう。ここでは、110,000円(うち消費税10,000円)の買掛金を支払う際に、振込手数料550円(うち消費税50円)を相殺したケースを想定します。この場合、買い手は売り手から550円分の値引き(対価の返還)を受けたと解釈します。
会計処理上、この値引き分は「支払手数料」勘定のマイナスとして処理し、仕入税額控除額を減額するのが最も整合性のとれた方法です。
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
摘要 |
|
買掛金 |
110,000円 |
普通預金 |
109,450円 |
A社への仕入代金支払 |
|
支払手数料 |
500円 |
振込手数料相殺による値引 |
||
|
仮払消費税等 |
50円 |
振込手数料相殺による値引 |
この仕訳により、買掛金110,000円が全額消去されると同時に、実際に支払った預金額109,450円との差額550円が、支払手数料とそれにかかる消費税のマイナスとして正しく計上されます。これにより、仕入税額控除の対象となる消費税額が適切に50円減額調整されます。
【売り手・受取側】振込手数料を相殺された場合の会計処理
インボイス制度の開始後、取引先から売上代金が振り込まれる際に、振込手数料を差し引かれて(相殺されて)入金されるケースが増えています。この場合、売り手(代金受取側)は会計処理と消費税の申告において、インボイス制度に対応した適切な処理が求められます。ここでは、売り手側の具体的な会計処理と、新たに発生する「返還インボイス」の交付義務について詳しく解説します。
会計処理は「売上値引」か「支払手数料」の2択
買い手負担の振込手数料を売り手が事実上負担する形(相殺)になった場合、その手数料相当額の会計処理には主に2つの方法があります。それは「売上値引」として売上から直接減額する方法と、「支払手数料」として費用計上する方法です。どちらの勘定科目で処理するかは企業の会計方針によりますが、消費税の扱いに違いが生じるため、その点を理解しておくことが重要です。
売上値引として処理する場合
振込手数料相当額を「売上値引」として処理する方法は、消費税法上の「対価の返還等」という考え方に最も近い会計処理です。売上高から直接値引額を差し引くため、課税売上高が減少し、結果として納付する消費税額も減ります。
【仕訳例】110,000円(税込)の売掛金に対し、振込手数料550円(税込)を相殺され、109,450円が入金された場合
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
普通預金 |
109,450円 |
売掛金 |
110,000円 |
|
売上値引 |
550円 |
この処理により、損益計算書上の売上高は値引き後の金額で計上されます。
支払手数料として処理する場合
振込手数料相当額を「支払手数料」という販売費及び一般管理費(経費)で処理する方法です。この場合、売上高の総額は変わらず、経費として手数料を計上します。
【仕訳例】110,000円(税込)の売掛金に対し、振込手数料550円(税込)を相殺され、109,450円が入金された場合
|
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
|
普通預金 |
109,450円 |
売掛金 |
110,000円 |
|
支払手数料 |
550円 |
会計上は費用として処理しますが、前述の通り、消費税法上では「対価の返還等」に該当します。そのため、課税売上から控除して消費税額を計算する必要があり、返還インボイスの交付義務も生じます。会計処理と税務処理が異なる点に注意が必要です。
返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務とは
インボイス制度では、返品や値引き、割戻しなど、売上にかかる「対価の返還等」を行った事業者は、取引の相手方に対して「返還インボイス(適格返還請求書)」を交付する義務があります。
国税庁の見解では、買い手が負担すべき振込手数料を売り手が負担する(代金から相殺する)ことは、この「対価の返還等」に該当するとされています。したがって、振込手数料を相殺された売り手は、原則としてその手数料相当額について返還インボイスを買い手に交付しなければなりません。
ただし、買い手側には「税込1万円未満の対価の返還等については、返還インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる」という特例があります。
返還インボイスの書き方と記載例
返還インボイスには、通常のインボイスと同様に定められた事項を記載する必要があります。振込手数料の相殺に関する返還インボイスは、以下の項目を網羅して作成します。
- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 対価の返還等を行う年月日
- ③ 対価の返還等の基となった取引を行った年月日(※元の請求書で特定できる場合は省略可)
- ④ 対価の返還等に係る資産又は役務の内容(「振込手数料相当額」など)
- ⑤ 対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
- ⑥ 対価の返還等に係る消費税額等又は適用税率
以下に、振込手数料550円(10%対象)の返還インボイスの記載例を示します。
【返還インボイス(適格返還請求書)の記載例】
|
宛名 |
株式会社〇〇 御中 |
|
発行日 |
202X年X月X日 |
|
発行者 |
株式会社△△ 東京都千代田区... 登録番号:T1234567890123 |
|
件名 |
適格返還請求書 |
|
内容 |
202X年X月X日付ご請求分(請求書番号:INV-001)に係る振込手数料相当額として |
|
値引額 |
10%対象 値引額(税抜): 500円 消費税額等(10%): 50円 合計値引額: 550円 |
このように、元の取引を特定できる情報と、値引きの対象額、消費税額などを明記します。取引先との合意があれば、複数の取引の振込手数料をまとめて1枚の返還インボイスとして発行することも可能です。
振込手数料相殺でトラブルを防ぐために知っておきたい実務対策!
インボイス制度の開始により、振込手数料の相殺処理は以前よりも複雑になりました。手間や認識の齟齬から生じるトラブルを未然に防ぐためには、事前の対策が極めて重要です。ここでは、実務上有効な対策を具体的に解説します。
取引先と手数料負担のルールを事前に決めておく
最も効果的で根本的な対策は、取引先との間で振込手数料をどちらが負担するのか、事前に明確なルールを取り決めておくことです。商習慣として売り手負担が定着しているケースも多いですが、インボイス制度を機に双方の事務負担を考慮し、改めて協議することをおすすめします。
契約書や覚書で明確に合意する
口頭での確認だけでなく、必ず書面で合意内容を残しましょう。これにより、「言った・言わない」といった将来のトラブルを確実に防ぐことができます。
新規で取引を開始する場合は、契約書の条項に振込手数料の負担に関する項目を必ず盛り込みます。既存の取引先については、新たに「振込手数料に関する覚書」を締結するか、基本取引契約書の内容を見直すといった対応が考えられます。合意する際は、単にどちらが負担するかだけでなく、売り手負担の場合の処理方法(売上値引とするか、支払手数料とするか)についても明確にしておくと、その後の会計処理がスムーズになります。
振込手数料を売り手負担にする場合の代替案
取引の関係上、引き続き売り手が振込手数料を負担せざるを得ないケースもあるでしょう。その場合でも、インボイス制度下での事務負担を軽減するための代替案がいくつか存在します。自社の状況に合わせて最適な方法を検討してみてください。
以下に、代表的な代替案とそのメリット・デメリットをまとめました。
|
代替案 |
概要とメリット |
デメリット・注意点 |
|
請求書発行時に値引き処理する |
あらかじめ振込手数料相当額を売上から値引いた金額で適格請求書を発行する方法です。相殺処理そのものがなくなるため、返還インボイスの交付は不要になり、売り手・買い手双方の事務負担を大幅に削減できます。 |
どの取引で値引きを適用するか、事前に双方で合意形成が必要です。また、金融機関によって振込手数料が異なるため、どの金額を基準に値引くかを決めておく必要があります。 |
|
インターネットバンキングを利用する |
買い手(支払側)に、窓口やATMより手数料が安いインターネットバンキングからの振込を依頼する方法です。売り手が負担する手数料の金額を低く抑えることができます。 |
取引先がインターネットバンキングを利用していることが前提となります。強制はできないため、あくまで協力をお願いする形になります。 |
|
キャッシュレス決済を導入する |
クレジットカード決済や口座振替などを導入し、銀行振込以外の決済手段を用意する方法です。振込手数料の問題そのものを解消できます。 |
決済システム導入の初期費用や、売上に応じた決済手数料が別途発生します。手数料率と事務負担の軽減効果を比較検討する必要があります。 |
まとめ
インボイス制度のもとでは、振込手数料を売上代金から差し引く処理に対して、これまで以上に慎重な対応が求められます。特に、「対価の返還等」としての位置づけから、売り手に返還インボイスの発行義務が生じる点は見落とせません。もっとも、税込1万円未満であれば帳簿保存のみで対応できる特例もあり、状況に応じた柔軟な判断が可能です。今後のトラブルを防ぐためにも、振込手数料の取り扱いについては、事前に取引先としっかり取り決めておくことをおすすめいたします。










