インボイス対応!相殺領収書の記載例や注意点を徹底解説
更新日:2025.12.06
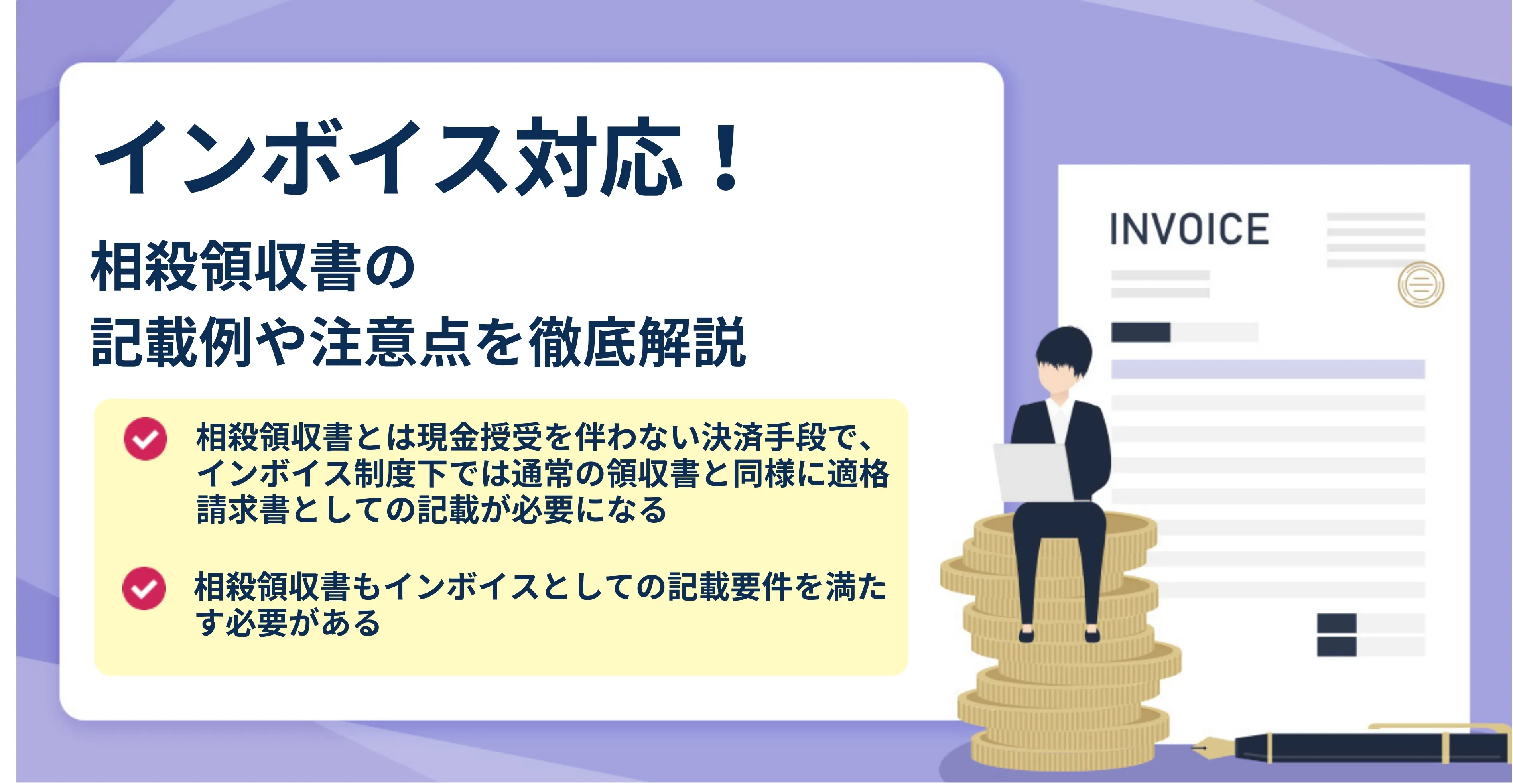
ー 目次 ー
インボイス制度の開始により、「相殺領収書」の正確な対応が必須となりました。本記事では、相殺領収書の基本からインボイス対応の具体的な書き方、税務上の注意点まで、実務で失敗しないための最新知識とポイントをわかりやすく解説します。
インボイス制度と相殺領収書の基礎知識!
インボイス制度とは何か
2023年10月から日本国内で導入された「インボイス制度」は、消費税の仕入税額控除に関する新たな制度です。消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者が発行した「インボイス(適格請求書)」を保存することが義務付けられています。
相殺領収書の意味と用途
「相殺領収書」は、双方が債権・債務を持つ取引において、お金の受け払いではなく相殺金額で決済を行ったことを証明する書類です。相殺とは「自社の売掛金」と「仕入先に対する買掛金」が発生している場合など、双方の債権債務を互いに消しあい、残額だけをやり取りする決済方法です。通常の現金での入金・支払いの代替手段として利用され、特に法人間でよく用いられます。会計処理上の証憑書類として、また取引におけるトレーサビリティ確保のためにも重要です。
一般的な領収書との違い
一般的な「領収書」は、現金や振込などで実際に金銭を受け取った際に発行される受領証です。一方で相殺領収書は、「代金の受け取り」を行わず、別の債務と相殺する形で決済を完了した場合に発行されます。
|
領収書の種類 |
発行タイミング |
証明内容 |
消費税の扱い |
|
一般的な領収書 |
現金での受領時、銀行振込などでの入金確認後 |
現金や預金の受領証明 |
受け取った金額に応じた消費税を記載 |
|
相殺領収書 |
相殺処理(債権債務の消し合い)確定時 |
債権・債務の相殺処理を証明 |
相殺対象の税込金額や消費税を記載(インボイス対応必須) |
このように、相殺領収書は「実際の入金を伴わない」決済方法に特化しており、昨今のインボイス制度下では、相殺処理の場合もインボイスとしての記載要件を満たした発行が必須となります。適切に発行・保存しなければ、仕入税額控除が認められない場合がある点に留意が必要です。
インボイス対応が求められる相殺領収書とは?
適格請求書発行事業者と相殺領収書
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、消費税の仕入税額控除を行うために、取引の証憑として「適格請求書(インボイス)」の保存が必須となります。したがって、売掛金や買掛金などの相殺取引における領収書も、発行者が適格請求書発行事業者でなければなりません。
仕入先や得意先との間で金銭を直接授受せず、債権債務の帳消し(相殺)による決済が行われても、相殺額についてインボイス要件を満たす証票の発行・受領が求められます。
インボイス記載事項と相殺取引のポイント
相殺領収書でも、インボイス制度に準拠した記載が無い場合、仕入税額控除を認めてもらえません。相殺取引特有の注意点を押さえ、以下の各事項が漏れなく記載されているか確認しましょう。
|
必要な記載事項 |
相殺領収書での具体的対応 |
|
発行者の氏名(名称)および登録番号 |
適格請求書発行事業者名とインボイス登録番号を必ず記載 |
|
取引年月日 |
実際に相殺が行われた日付を明記 |
|
取引内容 |
「売掛金と買掛金の相殺」といった具体的な内容・取引区分を明記 |
|
適用税率ごとの取引金額(税込または税抜表示) |
10%課税分、8%軽減税率分など、税率ごとに区分して記載 |
|
適用税率 |
10%、8%など税率ごとに明示 |
|
消費税額等 |
税率ごとの消費税額(1円未満切捨て)を明確に記載 |
|
相手方の氏名(名称) |
相手先法人名・担当者名などを記載 |
相殺取引では「振込」や「現金受領」ではなく、「債権債務の消込(相殺)」という決済手段になるため、相手方との合意を文書にし、証憑として両社で保存することが重要です。インボイス対応相殺領収書は、そのまま税務調査時の証拠書類となります。
また、電子帳簿保存法対応や会計ソフトとの連携を考える場合も、これらインボイス要件を確実に満たすレイアウトが推奨されます。
このように、相殺領収書であってもインボイス制度の下では、通常の領収書と同様、適格請求書レベルの記載事項・管理が必要となります。発行・受領双方で注意し、仕入税額控除要件を欠かさないよう徹底しましょう。
相殺領収書の正しい書き方を記載例で解説!
必要な情報とレイアウト例
相殺領収書のフォーマットは自由ですが、上記の必須事項が抜け漏れなく、かつ相殺の内容が明確に分かる書式にしましょう。誤解やトラブルを避けるため、下記の要素も盛り込んでおくことをおすすめします。
- 「相殺」を明記し、双方の債権・債務金額を対比して記載
- 取引の明細や内訳欄を設ける
- 相殺後の残高があればその金額も明示
- 発行者の押印または電子署名(必要に応じて)
以下に、インボイス対応の相殺領収書レイアウト例を示します。
|
項目 |
具体例 |
|
書類名称 |
相殺領収書 |
|
発行日 |
2024年6月10日 |
|
発行者名・登録番号 |
株式会社〇〇商事 登録番号:T1234567890123 |
|
受取人名 |
株式会社△△産業 |
|
取引内容 |
|
|
消費税額 |
各取引ごとに本体・消費税額を明示 |
|
相殺後の残高 |
0円 |
|
発行者印 |
〇〇商事代表取締役 印 |
【記載例:文言サンプル】
株式会社△△産業殿
下記債権債務について、相殺により領収いたしました。
記
商品A納品代金 110,000円(うち消費税10,000円)
商品B仕入代金 110,000円(うち消費税10,000円)
上記の通り相殺したことを証明いたします。
2024年6月10日
株式会社〇〇商事
登録番号:T1234567890123
代表取締役 〇〇〇〇 印
消費税や登録番号の記載方法
インボイス制度では「消費税額等」の明示と、発行事業者の「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が絶対条件です。特に相殺領収書では、相殺されるそれぞれの取引ごとに本体金額と消費税額を区分して記載しましょう。また、8%と10%など税率が混在する場合は、必ず税率ごとに区分記載してください。
- 登録番号は、発行者情報の欄または書類の余白に必ず記載
- 「消費税(10%)」や「消費税(8%)」など税率を併記
- 課税・非課税取引が混在の場合、課税・非課税の区分も明示
例:
商品A納品代金 本体100,000円 + 消費税10,000円(10%対象)
商品B仕入代金 本体100,000円 + 消費税10,000円(10%対象)
登録番号記載例:
登録番号:T1234567890123
これらの情報を明確に記載し、社内でひな形を統一すると、相殺領収書についてのトラブルを防止できます。
相殺領収書の発行時に注意すべき実務ポイント
金額が一致しない場合の対応
取引先との売掛金と買掛金を相殺する際、相殺金額と実際の取引金額が一致しないケースは少なくありません。例えば、売掛と買掛のどちらかが多い場合、差額は別途入金や支払が必要となります。その際、相殺領収書には相殺額・差額それぞれについて明確に記載し、どの請求や支払いに充当するかを特定できるようにします。
さらに、消費税の取り扱いも要注意です。消費税を含む総額で相殺する場合は、双方で課税関係がズレないよう消費税区分(課税・非課税・免税)を明確に記載することがインボイス制度上求められます。
|
項目 |
注意点 |
具体例 |
|
相殺金額 |
相殺に充てる請求書や明細を明記 |
「2024年6月分売掛金相殺」 |
|
差額 |
現金支払・入金の場合、通常の領収書や請求書も発行 |
「相殺差額2,200円 別途入金」 |
|
消費税の明示 |
消費税課税・非課税取引の明確な区分表記 |
「本相殺金額のうち消費税200円含む」 |
また、実際の相殺処理に関して、取引明細や合意内容を両社で保管することが重要です。不一致の場合は速やかな修正や、訂正仕訳、訂正インボイス(修正後の適格請求書)を発行する対応が必要となります。
記帳・保存方法と電子帳簿保存法対応
インボイス制度の施行により、相殺領収書も仕訳帳や帳簿へ適切に記録することが義務付けられます。帳簿上は「売掛金の消込」「買掛金の消込」として、取引内容・相手先情報・インボイス登録番号・相殺額・消費税額等を正確に記載し、相殺領収書(または相殺処理に係る適格請求書)を証憑として保存します。
電子帳簿保存法に対応する場合、次の点に注意が必要です。
- 電子データで発行・受領した相殺領収書は、電子保存要件(タイムスタンプ付与・検索機能確保・改ざん防止処置等)を満たす形で保管します。
- 紙書類の場合もスキャン保存が認められていますが、要件を満たす必要があります。
- 自社の会計ソフトやクラウドサービスが電子帳簿保存法に対応しているか事前確認しましょう。
|
保存区分 |
必要な対応 |
備考 |
|
電子データ |
タイムスタンプ、検索機能、電磁的記録保存 |
会計ソフト等の活用が有効 |
|
紙書類 |
スキャナ保存要件に基づき保存 |
訂正・削除履歴の管理が必要 |
インボイス制度開始後は、相殺領収書であっても「保存義務のある書類」として、税務調査に備えることが求められます。
仕入税額控除の可否とリスク
相殺領収書が適格請求書(インボイス)の要件を満たしていない場合、仕入税額控除の適用が受けられないリスクがあります。
仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者の登録番号」「取引年月日」「取引内容」「税率ごとの合計対価額」「消費税額または適用税率」等、インボイスの必須記載事項を全て網羅している必要があります。
また、相殺領収書であっても「摘要欄」に領収書発行の趣旨や取引の相殺経緯・対象取引を正確に記載していない場合、税務署で否認される事例があります。
|
判定ポイント |
内容 |
リスク・注意点 |
|
インボイス記載要件 |
登録番号、日付、取引詳細、消費税情報の全記載 |
1つでも欠落があると控除不可 |
|
控除期間 |
相殺領収書と実際の棚卸日・仕入計上日が一致しているか |
記載日付のズレによる否認リスク |
|
証憑保存 |
相殺の経緯が分かる関連書類の保存 |
証憑不備で追加納税となる恐れ |
会計処理・消費税申告書作成時には、単に相殺計算だけでなく、適格請求書等保存方式の要件充足状況を必ずチェックしましょう。また、「適格簡易請求書」では相殺領収書では対応できない場合が多いため、相殺取引イコール仕入税額控除の対象とは限らない点にも十分注意が必要です。
Q&A|相殺領収書に関するよくある質問と最新動向
相殺領収書とインボイス(適格請求書)は何が違うのですか?
相殺領収書とは、通常の現金支払いではなく、売掛金や買掛金などの相殺取引を行った場合に、取引内容を証明するために発行される領収書です。インボイス(適格請求書)は、2023年10月に開始されたインボイス制度に対応するための、消費税額や登録番号など所定の要件を満たした請求書を指します。
相殺領収書も事実上「支払い証明書」として機能しますが、インボイス制度下では、消費税の仕入税額控除を適用するために、インボイス要件を満たした記載でなければなりません。
相殺領収書にもインボイスの記載事項は必要ですか?
はい、必要です。インボイス制度開始後は、現金支払い・振込だけでなく、売買代金の相殺を行った場合も「適格請求書」としての記載事項(登録番号、取引内容、消費税額、相手方の氏名・名称など)がなければ、仕入税額控除が認められません。そのため、従来の簡易な相殺証憑ではなく、インボイス要件を満たした様式で発行する必要があります。
電子取引や会計ソフトでの相殺領収書発行はできますか?
近年は多くの会計ソフトが、インボイス制度への対応を進めており、電子帳簿保存法にも適合した形で相殺領収書や適格請求書を電子発行・保存できる機能を備えています。ただし、発行時に必要なインボイス記載要件を自社でしっかりチェックし、電子データの適切な保存も行う必要があります。
国税庁の見解やガイドラインはありますか?
国税庁のインボイス制度Q&A(適格請求書等保存方式に関するQ&A)では、「取引内容や消費税額等が明記された書類であれば、領収書でも相殺領収書でもインボイスとして認められる」と示された事例があります。つまり、様式名にはこだわらず、インボイスの記載事項が網羅されていれば、相殺領収書も受領・保存の対象となります。
インボイス制度Q&A 該当事項(国税庁)
|
Q番号 |
内容 |
ポイント |
|
問29 |
金銭授受がない相殺や現物供与でも、適正な様式であればインボイスと見なす。 |
取引証憑は状況に応じて柔軟運用可能。 |
|
問36 |
相殺領収書にインボイス必要項目が記載されていれば、保存要件を満たす。 |
領収書名称は不問、記載内容が重視される。 |
相殺金額が消費税端数処理等で一致しない場合のインボイス上の注意点は?
消費税額や端数処理が原因で、相殺金額と取引明細上の請求・支払金額が完全に一致しないケースもあります。その際は索引明細書や付帯資料への説明記載、またインボイス記載の消費税額等の計算根拠を明確にし、仕入税額控除の要件を満たすか確認することが重要です。
仕入税額控除が認められないケースがあるのはどんな場合ですか?
インボイスにおける仕入税額控除の要件は厳格化されています。以下のような場合、控除が否認されるリスクがあります。
|
ケース |
控除の可否 |
対応策 |
|
インボイス記載事項の記入漏れ |
不可 |
再発行や書類補正で対応 |
|
適格請求書発行事業者でない相手方との取引 |
不可 |
相手の登録番号確認と記載を求める |
|
証憑の保存期限切れや電子保存要件不備 |
不可 |
電子帳簿保存法に基づき適切保存する |
今後の制度改正や実務対応の動向について教えてください
インボイス制度施行から期間が経過し、数々の質疑応答や国税庁のQ&A掲載内容、会計ソフトメーカーの機能更新情報が発信されています。一方、2024年度税制改正により一部の記載省略や保存方法の緩和など、実務負担を軽減するための見直しも検討されています。
相殺取引に関しては「証憑様式フリー化」が一般化しつつあり、会計実務の現場では、適切な証憑作成と保存体制の継続的な見直しが求められています。
電子帳簿保存法との関係について具体的に教えてください
相殺領収書やインボイスの電子保存は、2024年1月以降、すべての法人・個人事業主に義務化されました。電子取引に関する証憑は、電子帳簿保存法に基づき、PDFデータや会計ソフト上で適格請求書の記載項目が保存できる形で保管する必要があります。ファイル名や検索条件付与など、保存要件についても適切に管理しましょう。
まとめ
インボイス制度下では、相殺領収書についても適格請求書の記載要件を満たすことが求められます。登録番号や取引内容、消費税額など正しく記載し、記帳や保存も電子帳簿保存法に対応しておくことで、仕入税額控除の適用を確実に行うことが重要です。今後も国税庁や会計ソフトの最新情報に注意しましょう。










