インボイス登録して確定申告してないのはNG?ペナルティと今すぐやるべきこと
更新日:2025.12.21
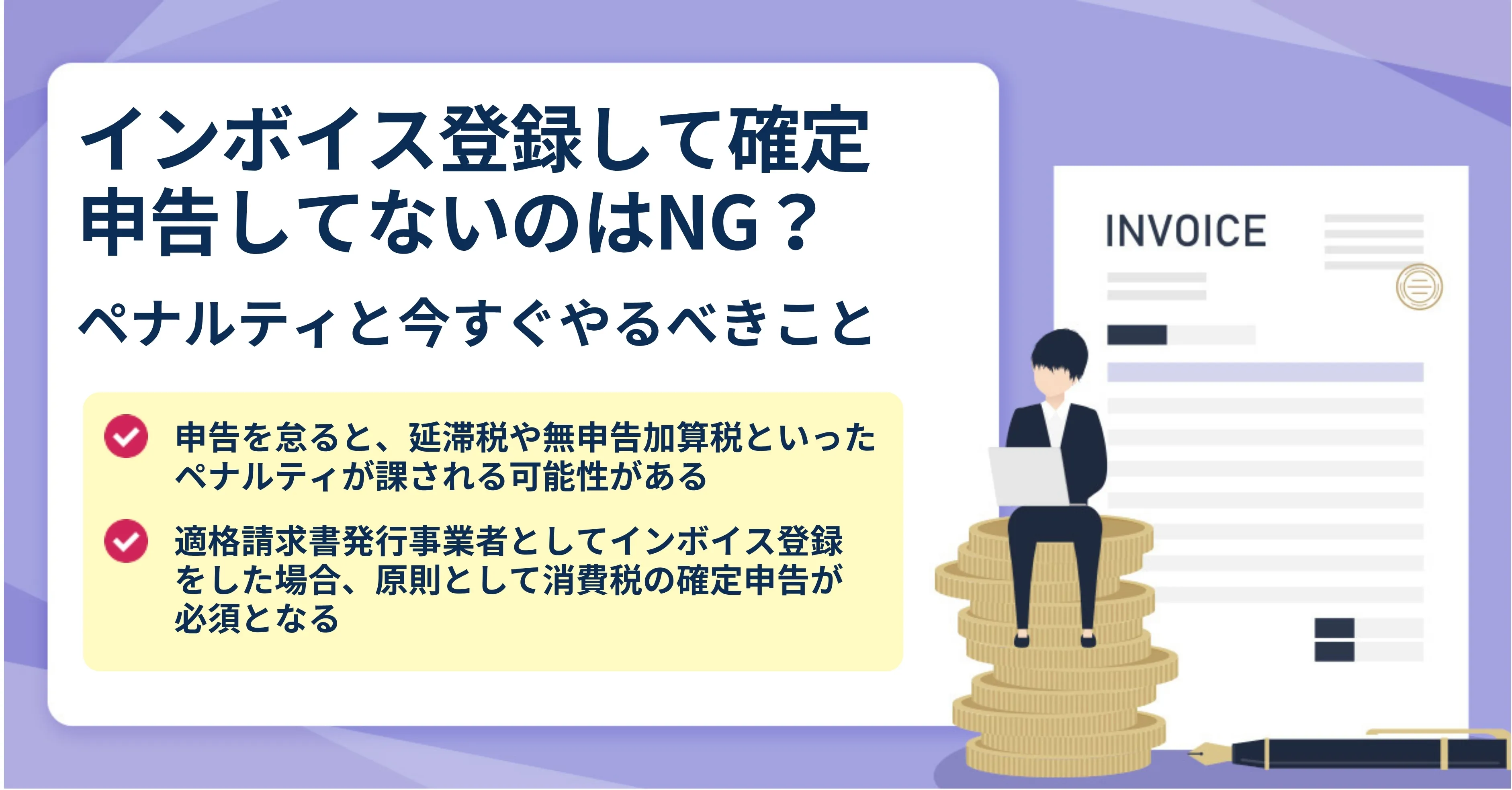
ー 目次 ー
「インボイス登録はしたけれど、確定申告はまだ...」そんな状態のままにしていませんか? 実はそのまま放置していると、消費税や所得税の申告漏れと見なされ、ペナルティのリスクがあります。この記事では、インボイス登録後に申告していない場合の影響や、今からでも間に合う対応策をわかりやすくご紹介します。
インボイス登録と確定申告 基本的な関係を理解しよう
インボイス制度の開始に伴い、多くの事業者の方が確定申告との関係について疑問をお持ちのことでしょう。特に「インボイス登録をしたが、確定申告をしていない」という状況は、法的に問題が生じる可能性があります。この章では、インボイス登録と確定申告の基本的な関係性について、わかりやすく解説します。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除に関する新しい制度です。この制度の導入により、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となりました。
インボイス制度の主なポイントは以下の通りです。
|
項目 |
内容 |
|
制度開始日 |
2023年10月1日 |
|
目的 |
複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の適正化 |
|
適格請求書(インボイス) |
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書や領収書などです。具体的には、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などの記載が求められます。 |
|
適格請求書発行事業者 |
インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。この登録を受けることができるのは、消費税の課税事業者のみです。 |
この制度は、消費税の納税義務がある課税事業者はもちろん、これまで免税事業者であった方や、買い手側の事業者にとっても重要な変更点を含んでいます。
インボイス登録したら確定申告は必須?
結論から申し上げますと、適格請求書発行事業者としてインボイス登録をした場合、原則として消費税の確定申告が必須となります。
これまで消費税の納税義務が免除されていた免税事業者がインボイス登録を行った場合、その登録をもって課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。具体的には、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額(インボイスに基づいて計算)を差し引いた差額を国に納付するための手続き、つまり消費税の確定申告が必要になるのです。
一方で、所得税(個人事業主)や法人税(法人)の確定申告は、インボイス登録の有無にかかわらず、事業所得があれば原則として必要です。インボイス登録をしたからといって、これらの所得に関する税金の申告が不要になるわけではありません。
インボイス登録と確定申告の関係を整理すると、以下のようになります。
|
税の種類 |
インボイス登録事業者 |
インボイス未登録の事業者(免税事業者の場合) |
|
消費税の確定申告 |
原則として必須(課税事業者となるため) |
原則として不要 (ただし、任意で課税事業者を選択している場合は必要) |
|
所得税・法人税の確定申告 |
事業所得があれば原則として必須 |
事業所得があれば原則として必須 |
つまり、「インボイス登録をしたけれど確定申告をしていない」という状況は、多くの場合、消費税の申告義務を果たしていないことを意味し、後述するようなペナルティのリスクを伴うことになります。
インボイス登録後に確定申告してないとどうなる?考えられるリスクとペナルティ
インボイス制度の登録を受け、適格請求書発行事業者となったにもかかわらず、確定申告を怠ると、さまざまなリスクやペナルティが発生する可能性があります。ここでは、具体的にどのような事態が想定されるのかを解説します。
消費税の申告漏れによるペナルティ
インボイス発行事業者は、原則として消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。確定申告をしないということは、この消費税の申告義務を果たしていないことになり、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
|
ペナルティの種類 |
内容 |
税率(主なケース) |
|
無申告加算税 |
法定申告期限までに申告しなかった場合に課されます。 |
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%。税務調査の通知前に自主的に申告した場合は5%に軽減されることがあります。 |
|
過少申告加算税 |
期限内に申告したものの、申告額が本来納めるべき税額より少なかった場合に課されます。 |
新たに納めることになった税額の10%。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。税務調査の通知前に自主的に修正申告した場合は課されません。 |
|
重加算税 |
仮装や隠蔽など、悪質な不正行為によって税金を免れようとした場合に課されます。 |
無申告の場合は納付すべき税額の40%、過少申告の場合は追加本税の35%。 |
|
延滞税 |
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課されます。 |
納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは原則として年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は原則として年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。(割合は変動します) |
これらのペナルティは、本来納めるべき消費税額に加えて支払う必要があるため、資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。特に、意図的な申告漏れと判断された場合の重加算税は非常に重いペナルティです。
所得税の申告漏れにも注意
インボイス登録をした個人事業主やフリーランスの方は、消費税だけでなく、所得税の確定申告も必要です。売上から経費を差し引いた所得に対して所得税が課されますが、この申告を怠った場合も、消費税と同様のペナルティ(無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、延滞税)が課される可能性があります。
特に、これまで免税事業者で所得税の確定申告のみを行っていた方が、インボイス登録を機に課税事業者になった場合、消費税の申告・納税が新たに発生することを認識し、忘れずに対応する必要があります。所得税の申告と消費税の申告はそれぞれ独立した手続きですので、両方の申告漏れがないように注意が必要です。
インボイス登録への影響は?
確定申告を怠ったからといって、直ちにインボイス発行事業者としての登録が取り消されるわけではありません。しかし、税務署からの指導や督促に応じず、悪質な申告漏れや納税義務の不履行が長期間続いた場合には、登録取り消しのリスクもあります。
それ以上に現実的なリスクとして考えられるのは、取引先からの信用失墜です。適格請求書を発行する事業者が税務申告を適切に行っていないという事実は、取引の継続において大きな不安材料となり得ます。コンプライアンス意識の低い事業者と見なされ、取引停止に至るケースも考えられます。インボイス制度は、事業者間の信頼関係の上に成り立つ制度であることを理解しておく必要があります。
インボイス登録済みで確定申告してない人が今すぐやるべきこと!
インボイス発行事業者として登録したにもかかわらず、確定申告をまだ行っていない方は、速やかな対応が必要です。放置してしまうと、ペナルティが課される可能性があります。この章では、今すぐやるべきことを具体的に解説します。
まずは状況を確認、確定申告の対象とは?
インボイス登録事業者は、原則として消費税の確定申告が必要です。ご自身の事業年度の課税売上高や、インボイス制度開始に伴う影響を確認し、申告義務の有無を正確に把握しましょう。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、課税売上高にかかわらず消費税の申告義務が生じます。
また、消費税だけでなく、所得税の確定申告も必要かどうかを確認してください。個人事業主であれば、事業所得について所得税の確定申告が通常必要となります。
期限後申告の手続きと必要書類
確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、「期限後申告」として手続きを行うことになります。ペナルティを最小限に抑えるためにも、気づいた時点ですぐに申告準備を始めましょう。
申告には以下の書類などが必要となります。状況によって追加の書類が必要になる場合もありますので、国税庁のウェブサイトや税務署で確認してください。
|
申告の種類 |
主な必要書類・準備物 |
|
消費税及び地方消費税の申告 |
|
|
所得税の申告 |
|
これらの書類を準備し、期限後申告の手続きを進めます。
確定申告書の作成と提出方法
確定申告書作成のポイント
確定申告書は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで比較的簡単に作成できます。会計ソフトを利用している場合は、ソフトの機能で申告書を作成できることが多いです。
インボイス制度開始後の消費税申告では、適格請求書発行事業者としての売上や、仕入税額控除の計算が重要になります。発行・受領したインボイスに基づいて正確に集計し、記帳するようにしましょう。
提出方法と注意点
作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で税務署に提出します。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードと対応するスマートフォンまたはICカードリーダライタがあれば、自宅からオンラインで提出できます。
- 郵送:管轄の税務署宛に郵送します。信書便で送付し、提出日を証明するために控えに受付印を押してもらい返送してもらう場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封しましょう。
- 税務署の窓口へ持参:管轄の税務署の窓口に直接提出します。時間外収受箱が設置されている税務署もあります。
提出した申告書の控えは、後日の確認や証明のために必ず保管しておきましょう。
納税方法について
期限後申告により納付すべき税額が確定したら、速やかに納税する必要があります。主な納税方法は以下の通りです。
- 振替納税:事前に税務署に依頼書を提出しておくことで、指定した預貯金口座から自動的に引き落とされる方法です。期限後申告の場合は利用できないことがありますので、税務署にご確認ください。
- ダイレクト納付(e-Taxによる納付):e-Taxを利用して、預貯金口座から即時または期日を指定して電子納税する方法です。事前に税務署への届出が必要です。
- クレジットカード納付:「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、クレジットカードで納付する方法です。納付税額に応じた決済手数料がかかります。
- コンビニ納付:税務署から発行されるバーコード付きの納付書を使って、コンビニエンスストアの窓口で納付する方法です。納付できる金額には上限があります。
- 金融機関または所轄税務署の窓口での現金納付:納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)または税務署の窓口で現金で納付する方法です。
納期限を過ぎて納税する場合、延滞税が課されることがあります。延滞税は納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されますので、1日でも早く納税することが大切です。
Q&A|確定申告してない場合のよくある質問と注意点
インボイス登録と確定申告に関して、多くの方が疑問に思う点や注意すべき点をQ&A形式でまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
確定申告の期限はいつまでだった?
確定申告の期限は、申告する税金の種類によって異なります。主なものの期限は以下の通りです。インボイス制度に関連が深い消費税の申告期限は特に注意が必要です。
|
税金の種類 |
申告対象期間 |
原則的な申告・納付期限 |
|
所得税及び復興特別所得税 |
毎年1月1日から12月31日まで |
翌年3月15日 |
|
消費税及び地方消費税(個人事業者) |
毎年1月1日から12月31日まで |
翌年3月31日 |
これらの期限は、土日祝日と重なる場合は翌平日になることがあります。正確な情報は国税庁のウェブサイトなどで確認しましょう。
過去の確定申告も遡って必要?
はい、原則として過去に申告すべきであった確定申告は、遡って行う必要があります。これを期限後申告といいます。
申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。自主的に期限後申告を行うことで、ペナルティが軽減される場合もありますので、気づいた時点で速やかに対処することが重要です。
なお、税金の時効(除斥期間)は原則として法定申告期限から5年ですが、悪質なケースと判断されると7年となることもあります。ただし、時効を待つのではなく、速やかに正しい申告を行うようにしましょう。
確定申告してないとインボイス発行事業者としての登録は取り消される?
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録自体が、確定申告をしていないことだけを直接的な理由として、直ちに取り消されるわけではありません。
しかし、適格請求書発行事業者は、消費税の納税義務者であることが前提となっています。確定申告を長期間怠っていると、税務調査の対象となったり、税務署からの指導が入ったりする可能性があります。その過程で、事業の実態や納税義務の履行状況に問題があると判断された場合、登録の維持が難しくなるケースも考えられます。
また、取引先からの信頼を損なう可能性も否定できません。適格請求書発行事業者として、納税義務をきちんと果たすことは非常に重要です。
税理士に相談するメリットとは?
インボイス制度開始後の確定申告は、特に免税事業者から課税事業者になった方にとっては複雑に感じられることが多いでしょう。確定申告をしていない状況であればなおさら、税理士に相談することには多くのメリットがあります。
- 正確な申告ができる: 複雑な税法やインボイス制度の規定に基づき、ミスなく正確な申告書を作成してもらえます。これにより、追徴課税や加算税のリスクを軽減できます。
- 節税に関するアドバイスが受けられる: 適用可能な控除や経費の計上について専門的なアドバイスを受けられ、合法的な範囲での節税につながることがあります。
- 手間と時間を大幅に削減できる: 煩雑な書類作成や計算作業を専門家に任せることで、ご自身の事業に専念する時間を確保できます。
- 税務調査への対応: 万が一、税務調査が入った場合でも、代理人として対応してもらえるため、精神的な負担が軽減されます。
- 期限後申告や納税計画の相談: 確定申告をしていない場合の期限後申告の手続きや、納税資金に関する相談にも乗ってもらえます。
税理士への相談費用はかかりますが、それ以上のメリットを得られる場合も少なくありません。特に、インボイス制度への対応や確定申告に不安がある方は、一度相談してみることをお勧めします。
まとめ
インボイス登録事業者は、原則として消費税の確定申告が必須です。申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。もしインボイス登録後に確定申告をしていない場合は、速やかに状況を確認し、期限後申告の手続きを進めましょう。不安がある方は、税理士など専門家に相談して、確実に対応していくことが重要です。










