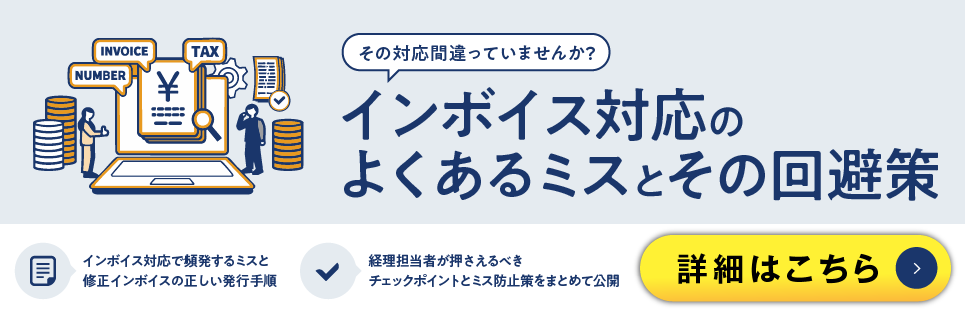インボイスは雑所得でも必要?副業や一時収入との関係をわかりやすく解説
更新日:2026.01.15
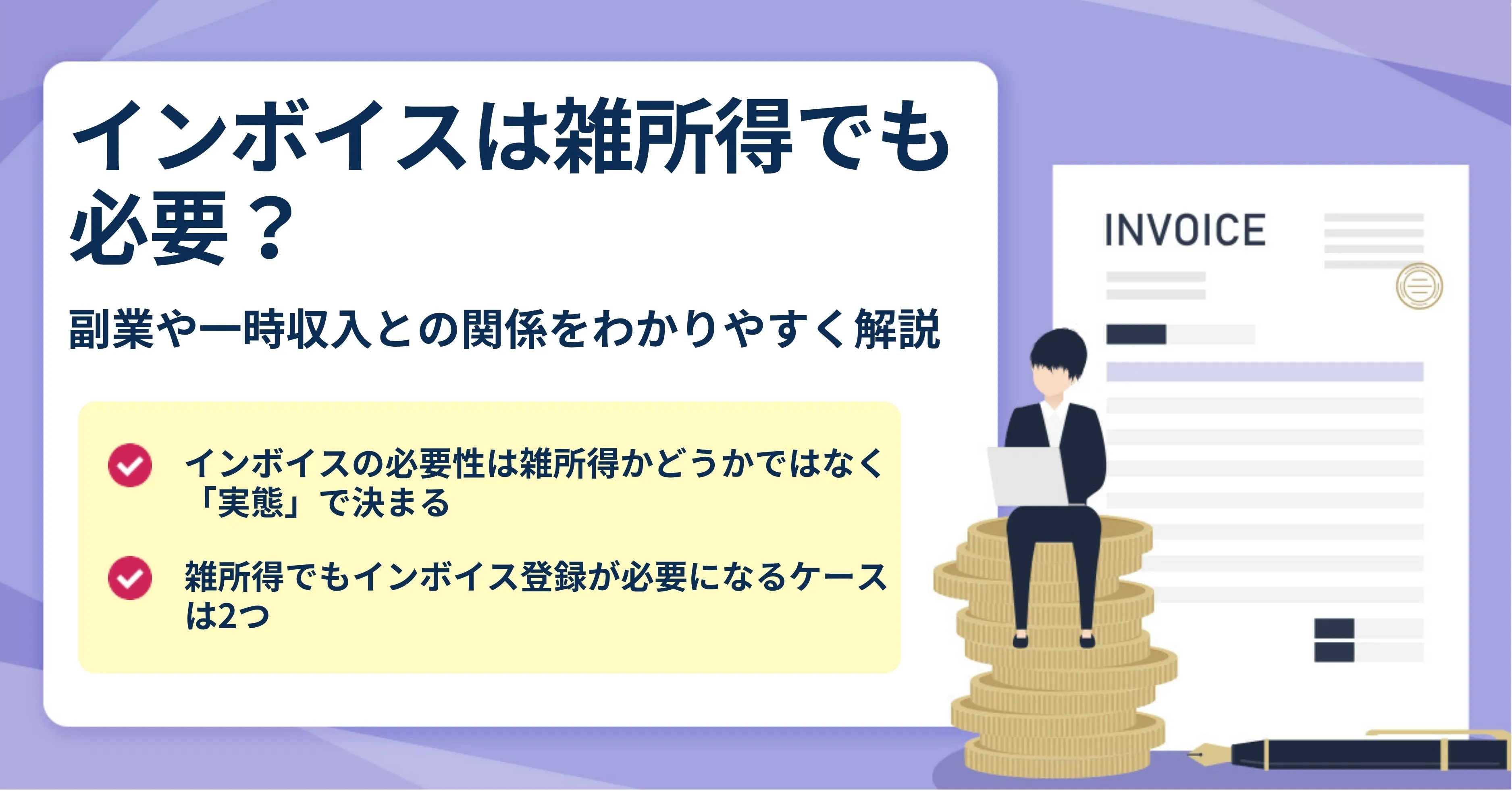
ー 目次 ー
「副業の収入は雑所得だから、インボイス登録は必要ない」とお考えの方も多いかもしれません。しかし、インボイスの要否は所得の種類ではなく、取引の実態や相手先の状況によって異なります。本記事では、会社員の副業収入や一時的な講演料、フリマアプリの売上など、雑所得に該当するケースを中心に、インボイス登録が必要かどうかをわかりやすく解説していきます。
インボイス制度と雑所得について簡単におさらい
2023年10月から始まったインボイス制度。フリーランスや個人事業主だけでなく、副業で収入を得ている会社員など、多くの方に関係する制度です。ここでは、インボイス制度と深く関わる「雑所得」の基本と、制度の概要についてわかりやすく解説します。
雑所得とは?副業・一時収入との関係
所得税法では、個人の所得を10種類に分類しています。そのうち「雑所得」とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)のいずれにも当てはまらない所得を指します。
具体的には、会社員の方の副業収入(原稿料、アフィリエイト収入、Webデザインの報酬など)や、公的年金などが雑所得に該当します。ただし、副業であっても継続性や規模によっては「事業所得」として扱われる場合もあり、その判断は収入の実態によって行われます。
|
所得区分 |
概要と具体例 |
|
事業所得 |
農業、製造業、サービス業など、事業として継続的・安定的に行っている活動から得られる所得。 例:フリーランスのエンジニアやデザイナーとしての収入、個人商店の売上など。 |
|
雑所得 |
他の9種類の所得に分類されない、事業とはいえない規模の所得。 例:副業の原稿料、講演料、アフィリエイト収入、公的年金など。 |
|
一時所得 |
営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の一時的な所得。 例:懸賞の賞金品、競馬の払戻金(一定の場合)、生命保険の一時金など。 |
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。消費税の仕入税額控除を受けるための新しいルールです。
事業者が納める消費税は、「売上で預かった消費税」から「仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いて計算します。この差し引く行為を「仕入税額控除」と呼びます。
インボイス制度の開始後は、原則として、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」が発行する「インボイス(適格請求書)」がなければ、買い手側は仕入税額控除を受けられなくなりました。そのため、事業者間の取引ではインボイスの発行を求められるケースが増えています。
インボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者として登録した「適格請求書発行事業者」のみです。これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者(前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者)も、取引先からインボイスの発行を求められた場合は、課税事業者となりインボイス登録をするかどうかの判断が必要になります。
【結論】インボイスの必要性は雑所得かどうかではなく「実態」で決まる
「自分の収入は雑所得だからインボイスは関係ない」と考えている方もいるかもしれませんが、それは正確ではありません。ここでは、インボイス登録の必要性を判断するための本質的なポイントを解説します。
インボイスの必要性を左右するのは"形式"ではなく"実態"
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は消費税に関する制度です。そのため、登録が必要かどうかを考える上での大前提は「あなたが消費税の課税事業者であるかどうか」になります。
所得税法における「雑所得」や「事業所得」といった所得区分は、インボイス登録の要否を直接決定するものではありません。たとえ確定申告で雑所得として申告していても、消費税の課税事業者であれば、インボイス(適格請求書)を発行する義務が生じます。
課税事業者とは、原則として基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。この基準に該当しない事業者は「免税事業者」となり、消費税の納税やインボイス発行の義務はありません。
しかし、免税事業者であっても、後述する取引の「実態」によっては、インボイス登録を検討すべきケースが出てきます。
取引先が課税事業者かどうかも重要な判断ポイント!
インボイス制度の核心は、買い手側(取引先)の「仕入税額控除」にあります。仕入税額控除とは、課税事業者が納める消費税額を計算する際に、仕入れにかかった消費税額を差し引くことができる仕組みです。
インボイス制度の開始後、買い手側がこの仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売り手側から発行されたインボイスの保存が必要になります。つまり、あなたの取引先が課税事業者である場合、その取引先はあなたにインボイスの発行を求める可能性が高いのです。
ご自身の状況を以下の表に当てはめて、インボイス登録を検討する必要があるか確認してみましょう。
|
主な取引先の状況 |
インボイス登録の検討ポイント |
|
企業などの課税事業者 |
取引先が仕入税額控除を受けられるよう、インボイスの発行を求められる可能性が高いです。取引を継続するためには、インボイス登録を検討する必要が出てきます。 |
|
一般消費者や免税事業者 |
取引先は仕入税額控除を必要としないため、インボイスの発行を求められる可能性は低いです。この場合、インボイス登録の必要性は低いと言えます。 |
このように、たとえあなたの収入が雑所得で、かつ売上1,000万円以下の免税事業者であっても、取引先との関係性という「実態」によって、インボイス登録(適格請求書発行事業者への登録)を迫られるケースがあることを理解しておくことが重要です。
雑所得でもインボイス登録が必要になる2つのケース
原則として、所得の種類が「雑所得」であること自体が、インボイス登録の要否を直接決定するわけではありません。しかし、所得区分に関わらず、実質的にインボイス登録が必要、あるいは登録を検討すべき状況が存在します。ここでは、特に注意すべき2つのケースについて具体的に解説します。
ケース① 課税売上高が1,000万円を超えている
まず、インボイス制度の登録以前の問題として、消費税の納税義務があるかどうかを確認する必要があります。所得の種類が事業所得か雑所得かにかかわらず、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その翌々年から消費税の「課税事業者」になる義務が生じます。
課税事業者になると、取引先に消費税を請求し、受け取った消費税を国に納めなければなりません。このとき、取引先(買い手)が仕入税額控除を受けるためには、売り手であるあなたが発行するインボイス(適格請求書)が必要です。そのため、課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になった場合は、取引を円滑に進めるためにインボイス登録が実質的に必須となります。
|
期間 |
内容 |
|
基準期間 |
個人事業主の場合、原則として前々年の1月1日から12月31日までの期間を指します。 |
|
特定期間 |
前年の1月1日から6月30日までの期間を指します。基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となります。(給与所得との合算も考慮) |
ご自身の課税売上高を正確に把握し、納税義務の有無を確認することが最初のステップです。
ケース② 取引先からインボイスの発行を求められている
自身の課税売上高が1,000万円以下で免税事業者であったとしても、インボイス登録を検討すべきもう一つの重要なケースが、「取引先からインボイスの発行を求められた場合」です。
あなたの取引先が課税事業者である場合、その取引先はあなたに支払った代金に含まれる消費税分を、自社が納める消費税額から差し引く「仕入税額控除」という仕組みを利用しています。しかし、インボイス制度開始後は、原則としてインボイスがなければこの仕入税額控除が適用できません(経過措置あり)。
そのため、取引先としては、仕入税額控除を適用するために、あなたにインボイスの発行を依頼してくる可能性があります。もしあなたがインボイス登録をせず、発行できない場合、取引先は税負担が増えることになります。その結果、消費税相当額の値引きを要求されたり、最悪のケースではインボイスを発行できる他の事業者との取引に切り替えられてしまったりするリスクが考えられます。
これは法律上の義務ではありませんが、取引関係を継続するためのビジネス上の判断として、インボイス登録(適格請求書発行事業者への登録)を検討する必要があるでしょう。
【状況別】副業や一時収入とインボイスの関係
雑所得と一言でいっても、その収入源はさまざまです。ここでは「会社員の副業」「フリマアプリでの収入」「単発の講演料」といった具体的な状況別に、インボイス登録の必要性について詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
会社員の副業収入が雑所得の場合
会社員の方がWebライターやWebデザイン、コンサルティングなどの副業で得た収入を雑所得として申告するケースはよくあります。この場合、インボイス登録を検討すべき可能性が高いと言えます。
なぜなら、副業の取引先の多くは法人などの課税事業者だからです。取引先は、あなたに支払った報酬にかかる消費税を「仕入税額控除」として自身の納税額から差し引くために、インボイス(適格請求書)を必要とします。
もしあなたがインボイスを発行できない免税事業者のままだと、取引先は仕入税額控除が受けられず、税負担が増えてしまいます。その結果、取引の継続が難しくなったり、消費税分の値下げを交渉されたりする可能性があるのです。
会社員の副業でインボイス登録をするかどうかの判断材料として、メリット・デメリットを以下の表にまとめました。
|
インボイス登録をする場合 |
インボイス登録をしない場合 |
|
|
メリット |
課税事業者である取引先との取引を継続・拡大しやすい。 |
消費税の申告・納税義務がないため、事務負担や税負担が増えない。 |
|
デメリット |
消費税の申告・納税義務が発生し、手取りが減る可能性がある。確定申告の事務負担が増える。 |
取引先から値下げを要求されたり、契約を打ち切られたりするリスクがある。 |
副業が軌道に乗り、継続的に課税事業者と取引していくのであれば、インボイス登録を前向きに検討することをおすすめします。
メルカリなどフリマアプリでの収入の場合
メルカリやラクマといったフリマアプリで得た収入については、原則としてインボイス登録は不要です。
その理由は主に2つあります。
- 取引相手が一般消費者であること
フリマアプリの購入者は、ほとんどが事業者ではない一般消費者です。消費者は仕入税額控除を行う必要がないため、インボイスを求められることはありません。 - 生活用動産の売却は非課税であること
ご家庭にある洋服や家具、本といった生活用の不用品(生活用動産)を売却して得た利益は、そもそも消費税の課税対象外(不課税取引)です。そのため、インボイス制度とは関係ありません。
ただし、ハンドメイド作品を制作して販売するなど、営利目的で継続的にフリマアプリを利用している場合は注意が必要です。この場合、売上は課税対象となりますが、購入者が一般消費者である限りは、インボイスの発行を求められるケースは稀でしょう。
単発の講演料や原稿料など一時的な雑所得の場合
一度きりの講演や、単発で依頼された原稿の執筆などで得た報酬も雑所得に該当します。この場合も、インボイスの必要性は「取引先がインボイスを必要としているか」で決まります。
講演や原稿執筆の依頼元は、出版社やイベント会社といった課税事業者であることが大半です。そのため、報酬を支払う側として、仕入税額控除のためにインボイスの発行を求めてくる可能性が高いでしょう。
もしインボイス登録をしない場合、以下のような状況が考えられます。
- 取引先が消費税分の負担を考慮し、報酬額の引き下げを交渉してくる
- インボイスを発行できる他の人に依頼先が変更されてしまう
- 経過措置を適用して一部を控除するが、事務処理が煩雑になるため敬遠される
単発の取引だからといって、必ずしもインボイスが不要とは限りません。依頼を受けた際に、取引先に対してインボイスの発行が必要かどうかを事前に確認しておくことが最も確実な方法です。
Q&A|インボイスと雑所得に関するよくある質問
ここでは、インボイス制度と雑所得に関して、特に疑問に思われることが多い点についてQ&A形式で解説します。
雑所得か事業所得か自分で判断できない場合はどうする?
所得税法上、雑所得と事業所得の区分には明確な数値基準がなく、実態に応じて総合的に判断されます。一般的には、その収入を得るための活動が「継続的・反復的」に行われ、「営利性・有償性」があり、客観的に見て「事業」として社会的に認知される程度のものであれば事業所得に該当する可能性が高まります。
しかし、この判断は非常に専門的で難しいのが実情です。もしご自身での判断に迷う場合は、安易に決めずに以下の専門機関に相談することをおすすめします。
- 税理士に相談する
個別の事情を詳しくヒアリングした上で、最も適切な所得区分をアドバイスしてもらえます。確定申告の代行や節税対策の相談も可能です。 - 所轄の税務署に相談する
税務署の窓口や電話相談センターで、一般的な見解や判断基準について質問することができます。相談は無料ですが、個別の事情に対する最終的な判断を下す場所ではない点に注意が必要です。
誤った所得区分で申告を続けると、後から税務調査で指摘され、追徴課税や延滞税が発生するリスクがあります。不安な場合は、必ず専門家へ相談しましょう。
インボイス登録による税負担を軽くする方法はある?
インボイス発行事業者として登録すると、これまで免税事業者だった方も消費税の納税義務が生じます。この急激な税負担を緩和するため、いくつかの特例措置が設けられています。代表的なものが「2割特例」と「簡易課税制度」です。
|
制度名 |
概要 |
主な対象者 |
注意点 |
|
2割特例 |
売上にかかる消費税額の2割を納税額とする制度。 |
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方。 |
2026年9月30日の属する課税期間までの期間限定。事前の届出は不要で、確定申告時に選択可能。 |
|
簡易課税制度 |
売上にかかる消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額を計算する制度。 |
基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の方。 |
適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要。 |
どちらの制度が有利になるかは、実際の経費(仕入)の割合や業種によって異なります。例えば、経費が少ないフリーランスのライターやデザイナーなどは、2割特例のほうが税負担を抑えられるケースが多いです。ご自身の事業内容に合わせてシミュレーションを行い、最適な制度を選択することが重要です。
雑所得で申告したけど、取引先から「インボイスがないと困る」と言われたらどうする?
雑所得として申告している状況で取引先からインボイスの発行を求められた場合、いくつかの対応が考えられます。まずは慌てずに、取引先との関係性や今後の取引の見通しを考慮して慎重に判断しましょう。
主な対応方法は以下の通りです。
- インボイス発行事業者になる
今後の取引を継続するために、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、課税事業者になる選択です。登録が完了すれば、取引先にインボイスを発行できます。その代わり、消費税の申告・納税義務が発生します。 - 取引先と価格交渉をする
インボイスを発行できない(免税事業者のままでいる)代わりに、取引先が負担することになる消費税相当額を値引きする交渉です。ただし、取引先がこれに応じるかは分からず、交渉が決裂して取引が終了となるリスクもあります。 - 所得区分を見直す
そもそも、その収入が実態として「事業所得」に該当しないか再検討する機会でもあります。もし事業所得として認められるのであれば、インボイス登録を機に青色申告の承認申請を行い、青色申告特別控除などのメリットを受けることも視野に入れられます。
どの選択をするにしても、まずは取引先に対して「現在、免税事業者であるためインボイスは発行できないが、対応を検討している」といった形で誠実にコミュニケーションを取ることが大切です。
まとめ
雑所得であっても、インボイス登録が必要になるケースは珍しくありません。登録の判断は「形式」ではなく、売上の規模や取引先の属性といった「実態」に基づいて行う必要があります。特に、企業との継続的な取引がある副業や、報酬を得る単発案件などがある場合は、インボイスの発行可否が今後の契約に影響することも。ご自身の状況を整理し、取引先とも相談しながら、最適な判断をしていきましょう。